| 『韓非子』の中に「亡徴」という章がある。「亡国のきざし」の意味である。日本にはいま亡国のきざしが顕著になっている。いくつか、日本の現状に合う言葉を紹介してみたい。森首相ら政府与党とその支持組織のリーダーの顔を思い浮かべながら読んでほしいと思う。(以下、徳間書店刊『中国の思想・韓非子』西野広祥・市川宏訳より引用)
(1)「緩心(かんしん)にして成なく、柔茹(じゅうじょ)にして断寡(すくな)く、好悪決するなくして定立するところなきものは亡ぶべきなり」(君主がぼんくらで無能、何事につけ優柔不断で、人まかせにして自分の考えというものがない。このようなとき、国は亡びるであろう)
(2)「浅薄にして見(あら)われ易く、漏泄(ろうせつ)して蔵(かく)すなく、周密なる能わずして、群臣の語を通ずるものは、亡ぶべきなり」(君主の人物が薄っぺらで簡単に本心を見すかされ、またオシャベリで秘密が守れず、臣下の進言内容を外にもらす。このようなとき、国は亡びるであろう)
(3)「狠剛(こんごう)にして和せず、諌(いさめ)に愎(もと)りて勝つを好み、社稷(しゃしょく)を顧みずして、軽(かるがる)しくなして自ら信ずるものは、亡ぶべきなり」(独善的で協調性がなく、諌言されればむきになる。国家全体のことを考えずに軽率に動き、しかも自信満々である。このようなとき、国は亡びるであろう)
(4)「大心にして悔ゆるなく、国乱れてみずから多とし、境内の資を料(はか)らずして、その鄰敵(りんてき)を易(あなど)るものは、亡ぶべきなり」(君主がずぼらで、およそ反省ということをせず、どんなに国が乱れていても自信満々で、自国の経済力を考えずに、隣の敵国を組みやすしとする。このようなとき、国は亡びるであろう)
(5)「好みて智をもって法を矯(た)め、時に私をもって公を雑(まじ)え、法禁変易し、号令しばしば下るものは、亡ぶべきなり」(都合が悪ければ理屈をつけて法をまげ、何かにつけて公事に私情をさしはさむ。その結果は朝令暮改、次から次へと新しい法令が発せられる。このようなとき、国は亡びるであろう)
(6)「大臣はなはだ貴く、偏党(へんとう)衆強、主断を壅塞(ようさく)して重く、国を擅(ほしいまま)にするものは、亡ぶべきなり」(大臣があまりに尊ばれ、強力な派閥を形成して、裁決を君主に仰がず、思いのままに国政を動かす。このようなとき、国は亡びるであろう)〈「大臣」を、「自民・公明・保守三与党の大幹部または自民党の派閥の実力者」の意味と解すれば、日本の現実にあてはまる〉
(7)「公家(こうか)虚(むなし)くして大臣実(み)ち、正戸(せいこ)貧しくして寄寓富み、耕戦の士困(くる)しみて、末作(まっさく)の民利するものは、亡ぶべきなり」(国家の財政が底をついているのに、大臣の家には金がうなっている。戸籍のある正規の人民、農民や兵士が恵まれず、利益を追って流れ歩く商人や末梢的な仕事にたずさわるものが利益を得ている。このようなとき、国は亡びるであろう)
いま、日本は第二次大戦後最大にして最悪の危機に直面している。国政を自公保連立政権にまかせつづけるならば、日本という国が滅亡するおそれが高い。政権交代を実現しなければ、わが国は亡びるだろう。 韓非は「亡徴」章の最後で「亡徴とは必ず亡ぶと曰(い)うにあたらず、その亡ぶべきを言うなり」と述べている。これは「亡国のきざし――亡徴とは、それがあらわれたからといって、必ず亡びるという意味ではない。亡びる可能性があるということである」という意味である。日本がいま政治の出直しを実現すれば、再生は可能だ。すべてはこの夏の参院選における国民の投票行動にかかっているのである。
|


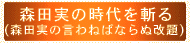 )転載。
)転載。
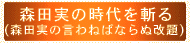 )転載。
)転載。
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)