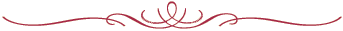
| 四文字熟語集2(カ行)(4.5、6文字) |
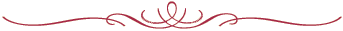
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のカ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| カ | ||
| 火牛之計 | かぎゅうのけい | 牛の角に刃をしばり、尾に火のついた葦束を結んで敵陣へ突っ込ませる戦術。 |
| 加持祈祷 | かじきとう | 仏の力とその加護を祈念すること。加持は仏が不可思議な力をもって衆生を護る意。祈祷は、祈り、またはその儀式の作法をいう。護摩を焚いたりして、仏に感応するために行う祈り。 |
| 花言巧語 | かげんこうご | 口先だけのうまい言葉、美辞麗句。花のように美しく飾って言い、巧みに語ること。 |
| 花鳥諷詠 | かちょうふうえい | 自然とそれにまつわる人事を無心に客観的に詠ずること。 |
| 花鳥風月 | かちょうふうげつ | 天地自然の美しい風景。また、それらを鑑賞することや、題材にした詩歌・絵画をたしなむ風雅の道をいう。 |
| 花天月地 | かてんげっち | 空には花が咲き、地には月影がみちわたっている。花咲く陽春のころの月夜のけしきをいう。 |
| 瓜田李下 | かでんりか | ひとに疑われるようなことはするなというたとえ。疑いを受けるような状況に身を置いてはならないという教え。 |
| 河図洛書 | かとらくしょ | 得難い図書のたとえ。一般に用いられる「図書」の語源でもある。 |
| 和氏之璧 | かしのへき(たま) | 中国の春秋時代・戦国時代の故事にあらわれた名玉。韓非子(和氏篇十三)および史記に記される。連城の璧(れんじょうのへき)とも称する。楚の国にいた そののち、宝玉は趙の恵文王の手にわたり、秦の昭襄王が自領にある15の城と交換に入手しようと持ちかけられた。しかし、秦が信用できるかどうか悩んだ恵文王は藺相如を秦に送った。命をかけた藺相如の働きにより、約束を守る気の無かった昭襄王から璧を無事に持ち帰ることができ、「 |
|
夏炉冬扇 |
カロトウセン | 夏の火鉢と冬の扇のように役に立たない人物や意見と物。時期はずれで無用であること。 |
| 佳人才子 | かじんさいし | 才能ある男性と美しい女性。理想的な男女の組み合わせのこと。 |
| 佳人薄命 | かじんはくめい | 美人は運命に恵まれずとかく不幸になりがちであるの意味。佳人=美しい女性。 |
| 華燭之典 | かしょくのてん | 結婚式。他人の結婚式や婚礼のこと。 |
| 科挙圧巻 | かきょあっかん | 試験で最優秀の成績を収めること。「科挙」で、一番の合格者の答案を他の合格者の答案の上に乗せたことから出た言葉で、「圧巻」の語源。 |
| 家宅捜索 | かたくそうさく | 捜査機関などが、職権によって人の住居に入り、証拠物件などを捜し求めること。 |
| 家内安全 | かないあんぜん | 家庭はじめ家の中全部が安全なこと。 |
| 下意上達 | かいじょうたつ | 一般大衆の心情、しもじもの考えが上の人や上司などに通じること。 |
| 下学上達 | かがくじょうたつ | 日常の身近なところから学び始めて、次第に深い学問の奥儀、高邁な哲理や真理にまで進み至ること。【説】訓読では「下学して上達す」と読む。【典】『論語』 |
| 下筆成章 | かひつせいしょう | 文才に恵まれていて、詩文を書き上げるのがきわめて速いこと。「筆を下せば章を成す」。 |
| 下里巴人 | かりはじん | 通俗的な音楽や文芸作品のたとえ。大衆受けのする歌謡曲、演歌、大衆小説、娯楽小説のたぐい。 |
| 過大評価 | かだいひょうか | 物事を実際よりも高く見積もったり評価したりすること。「実力を―する」 |
| 禍福無門 | かふくむもん | 偶然ともとれる災いや幸せも、自分自身で招き寄せるものだというたとえ。 |
| 寡見少聞 | かけんしょうぶん | 見聞が少なく知識に乏しいこと。 |
| 苛斂誅求 | かれんちゅうきゅう | 税金を厳しく取り立てる酷政のたとえ。「斂」は絞るようにして集めるの意。 |
| 呵々大笑 | カカタイショウ | 声高く大いに笑うこと。おおごえでわらうこと。「呵々」は、からからという笑い声のこと。 |
| 蝸角之争 | かかくのあらそい | きわめて小さくつまらない争い。かたつむりの角の上にある二国が争ったこと。かたつむりの左の角の上に触氏、右の角に蛮氏がそれぞれ国を持っていたが、あるとき戦って死者数万、逃げるのを追って、それも十五日でけりがついたというたとえ話。 |
| 蝸牛角上 | かぎゅうかくじょう | 取るに足らない争い。小競り合いのたとえ。かたつむりの左右の角の上で戦争したという寓話による。 |
| 迦陵頻伽 | かりょうびんが | 声の大変美しいもののたとえ。声の美しさをたたえるときに使う。ヒマラヤ山中に住むとも、極楽浄土に住むともいわれる幻の鳥の名。その美しい声は、仏の声の形容とも言われる。 |
| 我田引水 | ガデンインスイ | 物事を自分の都合のいいように取りはからったりすること。わが田へ水を引く。自分の都合のいいように、物事をこじつけること。自分の田にだけ水を引き入れるような、利益のために道理の合わない言動をとることを言う。「我が田に水を引く」という。 |
| 我利我利 | がりがり | 自分に利益のあることだけをする。道理に合わない無理なことをする。 |
| 画蛇添足 | がだてんそく 蛇を画いて足を添う |
戦国策(せんごくさく)(戦国時代の諸国の物語)に見える故事。楚の国の祭りで、係りの者に酒が振舞われた。「数人で飲むには足りないが、一人で飲むには十分だ。地面に蛇の絵を描いて早くできた者が一人で飲もう」ということになった。最初に描けた者が酒を取り、余裕で足まで描いた。すると2番目に描けた者が「蛇には足はないぞ」と言い、酒を奪って飲んだ。「蛇足」を描いたために蛇ではなくなりしくじったという、転じてしなくても良い余計なことをすることの戒め。 |
| 画竜点睛 | ガリョウテンセイ | わずかなことであるが、それを加えることによって物事が完成、成就することのたとえ。最後の仕上げ。最後にもっとも大切な部分に手を加えて全体を完成させること。「竜を画(えが)いて睛(ひとみ)を点ず」とよむ。 |
| 臥薪嘗胆 | ガシンショウタン がしんしょうたん |
薪の上に寝たり苦い胆を嘗めたりするように常に自らに試練を課して苦しみ努力すること。史記。薪の上に寝たり苦い胆を嘗めたりするように常に自らに試練を課して苦しみ努力すること。将来の成功を期して長い間苦しみに耐えること。「臥薪」は、薪の上に寝ること。「嘗胆」は、苦い胆をなめること。 |
| 臥龍鳳雛 | がりょうほうすう | 将来大活躍する英雄をたとえる。臥龍は「伏龍」(ふくりょう)ともいう。諸葛孔明(しょかつこうめい)(名は亮(りょう))のこと。龍は漢音でリョウ、呉音でル、慣用でリュウと読んでいる。三国志によると、徐庶(じょしょ)という人物が、蜀(しょく)の先主(せんしゅ)劉備に「諸葛孔明は臥龍だから、是非会いに行きなさい」と勧めた。孔明は隠棲(いんせい)していたのだが、いずれ風雲に乗じて大きな働きをする人物だという意味。そこで劉備は「三顧之礼」をもって孔明を招き、孔明は蜀のために尽くす。鳳雛は、おおとりのひな。将来有望な若者を意味し、こちらは龍士元(ほうしげん)(名は統(とう))のこと。劉備の参謀となって活躍し、若くして戦死する。麒麟児(きりんじ)という語に近い。ともに三国時代の英雄だ。 |
| 餓狼之口 | がろうのくち | 危難のあることのたとえ。 |
| 改易蟄居 | かいえきちっきょ | 武士の家禄を没収して士籍から除く刑罰と、表門を閉めさせ一室で謹慎させる刑。最も重い刑は「切腹」。 |
| 会稽之恥 | かいけいのはじ | 敗戦して命乞いをするような恥辱のたとえ。 |
| 開眼供養 | かいげんくよう | 新しく仏像・仏画が出来上がって安置する時行う仏眼を開く儀式法要。この供養を経て魂が入るとされている。 |
| 開口一番 | カイコウイチバン | 口を開くとまず最初に~~~。話を始めるやいなや~~。口を開けると同時にいうこと。また行うこと。話し始める最初の言葉。「開口」は、ものを言い始めること。「かいこ」とも読む。口を開くやいなやのさま。 |
| 外交辞令 | がいこうじれい | 交渉をなごやかに進めるための外交上の応対話。口先だけのお世辞、社交辞令。リップサービス。 |
| 懐古趣味 | かいこしゅみ | 昔を懐かしみ、古い情緒にひたること。 |
| 解語之花 | かいごのはな | 「言葉を理解する花」の意で、美人のこと。 |
| 開山祖師 | かいざんそし | 寺院を開いた開祖。転じて、ある物事を初めて行った先覚者、草分け、創始者のこと。 |
| 鎧袖一触 | がいしゅういっしょく | 弱い敵にほんの少しの武勇を示す意。敵を問題にしない形容。敵がとるに足らないほど弱いこと。簡単に相手をやっつけること。 |
| 外柔内剛 | ガイジュウナイゴウ | 表面は柔和で穏やかそうに見えるが、実は、意志が強くてしっかりしていること。うわべはやさしく(弱々しく)見えながら、心の中ではしっかりしてること。 |
| 外剛内柔 | がいごうないじゅう | うわべはしっかりしているように見えながら、実は弱々しいこと。 |
| 海内無双 | かいだいむそう | 天下に並ぶものがない。天下第一。 |
| 街談巷語 | がいだんこうご | まちの話。世間のうわさ。 |
| 街談巷説 | がいだんこうせつ | 世間のつまらない噂。風聞。 |
| 海底撈月 | かいていろうげつ | 海に映った月を見て本物と思い、海底から月をすくい取ろうとする。無駄なことをするたとえ。 |
| 回天事業 | かいてんのじぎょう |
天地を動かすほどの大事業。
|
| 怪力乱神 | カイリョクランシン | 人間の理性で説明のつかないような不思議な現象、事物のたとえ。カイリキ~とも読む。 |
| 快刀乱麻 | カイトウランマ | もつれた麻を刀で断ち切るように、複雑にこじれて紛糾していることを見事に処理するようすのたとえ。物事を敏速に手際よく解決すること。乱れた糸を刀で断ち切るように、込み入った物事を明快に解決すること。 |
| 傀儡政権 | かいらいせいけん | ある国の思いのままに操られる政権のこと。 |
| 偕老同穴 | カイロウドウケツ かいろうどうけつ |
夫婦がともに老い、同じ墓に葬られること。夫婦の仲が睦まじく幸福な結婚生活。夫婦が非常に仲の良いこと。偕老はともに年老いるまで連れ添うという意味。「詩経」 |
| 各自為政 | かくじいせい | それぞれが勝手に事を処理する。大局を顧みないで、自分勝手に振る舞うこと。縄張り根性のセクト主義のたとえ。 |
| 各人各様 | かくじんかくよう | 一人一人それぞれちがいがあること。 |
| 拡大解釈 | かくだいかいしゃく | 言葉や文章の意味を、自分に都合のいいように広げて解釈すること。「契約書を勝手に―する」 |
| 格物致知 | カクブツチチ かくぶつちち |
事物の道理をきわめ、学問・知識を高めること。 |
| 鶴髪鶏皮 | かくはつけいひ | 白髪(しらが)としわの多い肌。老人の形容。鶴の羽のような髪の毛とにわとりの皮のような肌を指す。言葉は洒落(しゃれ)ているが、内容は厳しいことを言う。逆に言えば、老醜のさまを風雅に表現していることになる。「鶴髪鶏皮」は、六朝の詩人〓信(ゆしん)(6世紀)の句に見える。また古く「台背(たいはい)」という語も見える。フグの背中のようなしみをいう。 |
| 鶴鳴之士 | かくめいのし | 多くの人から信頼される人物。また、登用されずに冷遇されている賢人のたとえ。 |
| 廓然大公 | かくぜんたいこう | さっぱりとして物事にこだわらず、公平なこと。廓は「くるわ」の意から、がらんと中空になった広いさまをいう。 |
| 確固不抜 | かっこふばつ | しっかりして、動かないこと。「確固」は、しっかりして堅いさま。いかなる状況にもかかわらず、信念を守る、不変なさまをいう。 |
| 活殺自在 | カツサツジザイ | 生かすも殺すも思いのままに、~他を自分の思うがままに取り扱うこと。意のままに人を動かすこと。生かすも殺すも思いのままであること。 |
| 刮目相待 | かつもくそうたい | 目をこすってよく見る。人の進歩、成功の著しいのを待望するたとえ。 |
| 割鶏牛刀 | かっけいぎゅうとう | 小さいことを処理するのに大きな道具を用いる必要はない。転じて、小事を処理するのに大人物の手を借りる必要はない、ということ。 |
| 豁然大悟 | かつぜんたいご | 迷いや疑いが解けて真理を悟ること。 |
| 豁達大度 | かったつたいど | 心が広く度量の大きいこと。 |
| 隔靴掻痒 | かっかそうよう | 靴の裏から痒い所をかくように、思うようにならなくて非常にもどかしいという意味。 |
| 闊達自在 | かったつじざい | 思いのままにのびのびとしている様。「闊達」は、心が広く物事にこだわらないさま。「闊達」は、「豁達」とも書く。 |
| 赫赫之名 | かっかくのな | 盛んに現れる名誉。 |
| 合従連衡 | ガッショウレンコウ | その時々の利害に応じて、結合したり離れたりすることをいう。一つの強国に対する同盟。中国の戦国時代の六国が、秦に対抗するか(合従)服従するか(連衡)の二案に、前者をとったこと。 |
| 鼎の軽重 | かなえのけいちょう | 楚の荘王が周を軽んじ、周室に伝わる宝器である九鼎 (きゅうてい) の大小・軽重を問うたという春秋左伝宣公三年の故事から。統治者を軽んじ、これを滅ぼして天下を取ろうとする。権威ある人の能力・力量を疑い、その地位から落とそうとする。 |
| 唐草模様 | からくさもよう | つる草のはいまわる様子をかいた模様。 |
| 甘酸辛苦 | かんさんしんく | 人の味覚のこと。この順番に味覚は発達する。 |
| 完全無欠 | かんぜんむけつ | どの点から見ても、まったく欠点・不足がなく完璧であること。 |
| 官民格差 | かんみんかくさ | 官吏と民間人の間に差や開きがあること。 |
| 官尊民卑 | かんそんみんぴ | 政府や官吏に関連する事業などを尊いとし、一般の民間人や民間の事業などを卑しむこと。また、その気風。 |
| 関東八州 | かんとうはっしゅう | 相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・上野・下野の8カ国の総称。 |
| 感慨無量 | カンガイムリョウ かんがいむりょう |
感慨がはかり知れないほどである。胸いっぱいにしみじみ感じること。何もいえないほど胸がいっぱいになる様。無量は、無限の意。身にしみて感動が心を占めること。 |
| 歓欣鼓舞 | かんきんこぶ | 踊り上がって喜ぶさま。にぎやかに、息をはずませ、鼓をたたいて歓喜するようす。 |
| 勧善懲悪 | かんぜんちょうあく | 善行を勧め励まし、悪事を懲らしめること。 |
| 換骨奪胎 | かんこつだったい | 骨をとりかえ、子宮を取って使う意で、古いものに新しい工夫をこらして再生することにいう。 |
| 緩急自在 | 物事を自由自在に操ること。速度などその場その場に応じて自由自在に調節すること。「緩急」は、ゆるやかなことときびしいこと。また、遅いことと早いこと。 | |
| 汗牛充棟 | カンギュウジョウトウ かんぎゅうじゅうとう |
蔵書が多いこと。「牛に(運ばせれば)汗し、(積めば)棟に充つほどの多さ」の所有している本が非常に多いこと。 |
| 汗馬之労 | かんばのろう | 戦陣での働き。武功のたとえ。騎馬で戦場を駆け巡り、馬に汗をかかせた骨折りやそれによって得た手柄のこと。 |
| 簡潔明瞭 | かんけつめいりょう | 「簡潔」は短く簡単で分かりやすいことをあらわし、「明瞭」は見やすくはっきりしていることをさす言葉です。「簡潔明瞭」とは、単純で理解しやすく、はっきりとしていることを意味する四字熟語。 |
| 簡明直截 | かんめいちょくせつ | すとんと落ちるように、分かりやすいこと。まどろっこしい物言いをせず、はっきり言うことです。「簡明」には、非常に分かりやすいという意味がある。難しい言葉を並べ立てるのではなく「ひと言でストレートに伝える」という訳が込められている。「直截」は、ためらいがないこと。「まわりくどい言い方をせずに、ズバッと言う」。 |
| 閑雲野鶴 | かんうんやかく | 世俗に拘束されず、自由にのんびりと暮らすたとえ。また、自適の生活を送る隠士の心境のたとえ。大空にゆったりと浮かぶ雲と、広い野にいる野生のつるの意から。▽「閑雲」は大空にゆったりと浮かぶ雲。「野鶴」は野に気ままに遊ぶつる。何ものにもしばられない自由な生活のたとえ。「閑」は「間」とも書く。 |
| 閑人閑話 | かんじんかんわ | これという用のない閑人(ひまじん)の無駄話。 |
| 閑話休題 | カンワキュウダイ かんわきゅうだい |
むだばなしや前置きを打ち切って、話の本題に入ること。本筋からそれている話をもとに戻す時に使う言葉。「それはさておき~」。それはさておき、さて。無駄話はやめて、話を本筋に戻すときの言い出しに用いる言葉。「閑話」はむだばなしの意味。「閑話」は、「間話」とも書く。 |
| 邯鄲之歩 | かんたんのほ | むやみに自分の本文を捨てて他の行為をまねるのは失敗に終わるということのたとえ。昔、燕の国の寿陵の少年が趙の都、邯鄲に行き、その都人の歩きぶりをまねたが、まだ十分に学ばないうちに燕に帰ったので、都風の歩き方もできず、自分の歩き方も忘れて這って帰ったという故事。 |
| 換骨奪胎 | かんこつだったい | 他人の作品を表現や筋立てを少し変えて、自分の作品にすること。 |
| 冠婚葬祭 | カンコンソウサイ | 元服・婚礼・葬儀・祖先の祭祀の、四つの重要な礼式。慶弔の儀式。人の一生のうち大事な儀式。成人式(昔の元服)、婚礼、葬式、および祖先の祭典。 |
| 勧善懲悪 | カンゼンチョウアク | 善行を勧め励まし、悪事を懲らしめること。善を進め悪を懲らすこと。 |
| 旱天慈雨 | かんてんじう | 苦境の時の援助や救い。 |
|
肝胆相照 |
かんたんそうしょう |
互いに心の底まで打ち明け、親しく付き合うこと。【説】「肝胆」は肝臓と胆嚢(たんのう)。転じて「心」の意。訓読では「肝胆相(あい)照らす」と読む。 |
| 奸智術策 | かんちじゅっさく | 腹黒い策謀。悪知恵と陰謀。また、よこしまで邪悪な考え。 |
|
邯鄲之夢 |
かんたんのゆめ |
邯鄲(かんたん)の枕(まくら)。盧生(ろせい)という青年が、邯鄲で道士呂翁から枕を借りて眠ったところ、富貴を極めた五十余年を送る夢を見たが、目覚めてみると、炊きかけの黄粱(=大粟)もまだ炊き上がっていないわずかな時間であったという「枕中記」の故事。人生の栄枯盛衰のはかないことのたとえ。一炊(いっすい)の夢。盧生の夢。邯鄲の夢。出世を望んで邯鄲に来た青年盧生(ろせい)は、栄華が思いのままになるという枕を道士から借りて仮寝をし、栄枯盛衰の50年の人生を夢に見たが、覚めれば注文した黄粱(こうりよう)の粥(かゆ)がまだ炊き上がらぬ束の間の事であったという沈既済「枕中記」の故事より栄枯盛衰のはかないことのたとえ。邯鄲の枕。邯鄲夢の枕。盧生の夢。黄粱一炊の夢。黄粱の夢。一炊の夢。 |
| 艱難辛苦 | カンナンシンク | 困難な状況や辛い場面に出会い、苦しみ悩むような大変な苦労。耐え難い苦労をすること。困難にあって苦しみ悩むことで「艱」も「難」もつらく苦しいこと。 |
| 艱難多事 | かんなんたじ | 難儀で、面倒なことの多いこと。 |
| 管鮑之交 | かんぽうのまじわり | きわめて友情のあつい関係。 親密な友情のたとえ。 |
| 侃侃諤諤 | かんかんがくがく | 遠慮することなく、言いたいことを言い盛んに議論するさま。(正しいことを)遠慮なしにどしどし言うこと。 |
| 頑固一徹 | ガンコイッテツ | 自分の考えや態度を少しも曲げようとしないで押し通すさま。また、そういう性格。 |
| 頑迷固陋 | がんめいころう | 頑固で、道理に暗く、見識のせまいこと。また、そのような人。「頑迷」は、自分の考えに固執して他の忠告など受け入れないこと。「固陋」は、融通性がなく頑固なこと。 |
| 顔厚忸怩 | がんこうじくじ | 恥知らずのものがさすがに恥ずかしく、きまりの悪い思いをすること。「顔厚にして忸怩たる有り」の略。 |
| 顔面蒼白 | がんめんそうはく | 恐怖やけがなどのために、顔色が青ざめて見えるさま。 |
| 眼光炯炯 | ガンコウケイケイ | 眼が鋭く光り輝くさま。視察力の優れていること。眼が輝き鋭くひかる様。「眼光」には、観察力、洞察力、眼識の意もある。「炯」は、あきらか、「炯々」は、光り輝くさま。 |
| 眼光紙背 | がんこうしはい | 読解力が鋭いことのたとえ。読書の字句の奥にある深い意味を読み取ること。【説】鋭い眼の光が紙の裏まで貫くという意から。「眼光紙背に徹す」という形で用いる。 |
| 眼高手低 | がんこうしゅてい | いたずらに理想だけ高く実行力のないこと。ものを見る目は高いが、ものを作りだす手は低いの意で、目は肥えているが腕は下手ということ。 |
| 眼中之釘 | がんちゅうのてい | 邪魔者のたとえ。「眼中の釘を抜く」といい、一人の悪人を除き去ること。 |
| 眼中無人 | がんちゅうむじん | 何物も恐れるもののないさま。おごりたかぶって人を人とも思わず、まったく問題にしないさま。(= 傍若無人) |
| キ | ||
| 気韻生動 | きいんせいどう | 芸術作品に気高い風格や気品が生き生きと表現されていること。また、絵画や他の芸術作品などに、生き生きとした生命感や迫力があり、情趣にあふれていること。▽「気韻」は書画など芸術作品にある気高い趣。気品。「生動」は生き生きとしているさま。また、生き生きとして真に迫ること。中国六朝時代、南斉の人物画の名手謝赫(しゃかく)が、古画品録の中で画の六法の第一に挙げたのに始まるといわれる。 |
| 気宇壮大 | キウソウダイ | 度量・構想などが並外れて大きいさま。「気宇」は心の広さ、心がまえ、器量の意。度量や構想が大きいさま。「気宇」は、気構え、心の広さの意。「壮大」は、さかんで大きいの意。 |
| 気炎万丈 | きえんばんじょう | 意気込みのさかんなこと。意気が、一万丈(丈は、長さの単位)にまで立ち上る様子から。「気炎」は話しぶりなどにあらわれる盛んな勢い。 |
| 気随気儘 | きずいきまま | わがまま勝手に振舞うこと。 |
| 気息奄奄 | キソクエンエン | 息が絶え絶えになり余命が幾ばくもないようす。今にも滅亡しそうである。息が絶え絶えで、今にも死にそうなさま。「奄々」は、息も絶え絶えなさま。虫の息の意。国家や家、思想が今にも滅びそうな状態にも使う。 |
| 危機一髪 | キキイッパツ | 非常にあぶない瀬戸際。ほんのわずかな違いで今にも危険なことがおこりそうなこと。非常に危険な状態。(髪の毛一本ほどの違いで)危機に陥るような状態のこと。一本の髪の毛で重いものを引いて、いまにも切れてしまいそうな状態から出た言葉。 |
| 危急存亡 | キキュウソンボウ | 危機が迫っていること。生き残るか亡びるかの瀬戸際のような状態。生きるか死ぬかの境の意で、生き残るか滅びるかにかかわる、重大な瀬戸際。「危急存亡の秋(とき)」と使い、個人より組織や集団の存亡にいうことが多い。 |
| 奇貨可居 | きかおくべし | 好機はうまくとらえて、利用しなければならないというたとえ。珍しい値打ちのある物は貯えておいて、将来値が上がってから売ること。▽「奇貨」は珍しい価値のあるもの。転じて、絶好の機会のたとえ。「居」はたくわえる、手元に置く意。 |
| 奇奇怪怪 | キキカイカイ | 常識では理解できないような不思議な出来事。あるいは容認できないようなけしからぬこと。非常に奇妙な様子。奇怪をつよめた形。 |
| 奇想天外 | キソウテンガイ | 誰にも思いもよらないような奇抜なこと。また、そのようす。あっといわせるほど思いつきが変わっている様子。奇(優れた)想(着想)が、天外(思いもよらないところ)から、ふってわくこと。 |
| 希少価値 | きしょうかち | 非常にまれな価値のあるもの(または、こと)。 |
| 器用貧乏 | キヨウビンボウ | 器用であるがために、他人に利用されたり、かえってひとつのことに集中できずに損ばかりしていること。 |
| 喜色満面 | キショクマンメン | 顔中に喜びの表情が満ちるようす。うれしそうな表情を顔いっぱいに見せるようす。喜びが顔いっぱいにあふれている様子。喜びを心の中に隠しきれず嬉しそうな表情が顔全体に広がっている状態。 |
| 喜怒哀楽 | キドアイラク | 喜び・怒り・哀しみ・楽しみなど~人間の持っている様々な感情。喜び、怒り、悲しみ、楽しみ(の感情) |
| 木戸御免 | きどごめん | 芝居、見せ物などにただで入れること。 |
| 切り盛り | きりもり | 料理用語。料理の盛り付けから転じて、何かを手際よく処理することを意味するようになった。 |
| 器用貧乏 | キヨウビンボウ | 器用な人は一応何でも上手にこなすために、かえって一事に集中・徹底できず、結局は大成できないということ。 |
| 帰属意識 | きぞくいしき | 特定のところに所属して落ち着く気持ち。 |
| 帰命頂礼 | キミョウチョウライ | 仏に対して心から帰依すること。神仏に対しての唱え文句としても用いられる。 |
| 鬼神敬遠 | きじんけいえん | 敬遠のフォアボールと同じ。尊敬はするけれど、あまり近寄らない、という心構え。転じて、敬うように見せかけ、実は嫌って寄せつけないこと。 |
| 鬼畜米英 | きちくべいえい | |
| 鬼面仏心 | きめんぶっしん | 外見の恐ろしさに似ず、優しい仏のような心を持っていること。またそういう人。「鬼面」は、怖そうな外見をいう。 |
| 起死回生 | キシカイセイ | 死に瀕したもの、滅びかかっているものを再び生き返らせること。もとに戻すこと。死にかかっているところを生き返らせること。だめになるところを立ち直らせること。 |
| 起承転結 | キショウテンケツ | 「起」で始まり「承」で受け、「転」で変化を出し「結」で終結させる構成方法。広く一般の事柄の展開にも比喩的に用いられる。漢詩、ことに絶句の組み立て方。初めの句(起句)でおこし、次の句(承句)でうけ、第三の句(転句)で一転し、最後の句(結句)で全体を結ぶ。 |
| 旗幟鮮明 | キシセンメイ | 旗の色が鮮やかなように、主義・主張・態度などがはっきりしているようす。主義主張や立場、態度などがはっきりしていること。 |
| 機会均等 | きかいきんとう | すべての人に平等な権利や活動の場をあたえること。 |
| 機知縦横 | きちじゅうおう | 時に応じて、適切な知恵を自在にめぐらすこと。 |
| 機略縦横 | キリャクジュウオウ | 臨機応変の計略が自在に考案・運用できること。 |
| 既成概念 | きせいがいねん | すでに認められ広く通用している意味合いや考え方。 |
| 既成事実 | きせいじじつ | すでにできあがっている周知の事実。 |
| 規矩準縄 | きくじゅんじょう | 物事や行為の標準・基準になるもののこと。手本。きまり。▽「規」はコンパス。円を描くのに用いる。「矩」は方形を描くさしがね(直角に曲がったものさし)。定規。「準」は水平を測るための水盛(みずもり)水準器。「縄」は直線を引くための墨縄(すみなわ)。転じて、物事の基準や法則をいう。 |
| 規行矩歩 | きこうくほ | 規則、規準に沿って行動する。転じて、古い規範にこだわって融通のきかないたとえ。 |
| 規制緩和 | きせいかんわ | 自由な経済活動を縛る制限を緩めること。 |
| 亀甲獣骨 | きこうじゅうこつ | 亀のこうらと獣の骨。殷時代これに文字を刻んで占いに使った。これを甲骨文字といい、現存する中国最古の文字。 |
| 亀文鳥跡 | きぶんきょうせき | 亀の甲の模様と鳥の足跡。ともに文字の起源。 |
| 騎虎之勢 | きこのいきおい | 虎にまたがって走り出したら、途中で降りることはできないので、行く所まで行かなければならない。そのような勢いをいう。物事の成りゆき上、中止できないこと。 |
| 毀誉褒貶 | きよほうへん | ほめたりけなしたりの評判。悪口を言ったり、ほめたりで世間の評判のこと。 |
| 葵花向日 | きかこうじつ | 「ひまわりの花、日に向かう」。夏の点景を、熱い太陽に向かって咲き誇るひまわりの姿に託した言葉。 |
| 箕裘之業 | ききゅうのぎょう | 祖父から受け継いだ仕事のこと。「箕」はふるい、「裘」は皮の上着のこと。弓作りの職人の子は箕を作ることからはじめ、鍛冶屋の職人の子は裘を作ることからはじめ、祖父の家業を受け継ぐ準備をするという故事から。 |
| 義理人情 | ぎりにんじょう | 人付き合いで大事な日本的なモラルのこと。 |
| 議論百出 | ぎろんひゃくしゅつ | さまざまに議論が戦わされること。多くの意見が出ること。 |
| 疑心暗鬼 | ギシンアンキ | 心に疑いをもってると、暗がりの中に鬼の幻影をみたような気がすることが有る。一度疑い出すと、何でもないことまで疑わしく思われてきて、見る物すべてが恐ろしくなりびくびくしたり不安になる。 |
| 吉凶禍福 | きっきょうかふく | 吉事と凶事。「吉・福」はめでたく幸せなこと。「凶・禍」は不吉やわざわい。運や縁起が良いか悪いかということ。 |
| 橘中之楽 | きっちゅうのたのしみ | 囲碁の楽しみをいう。橘の実の中でふたりの老人が向い合って碁を打つており、いかにも楽しそうであったという昔話から。 |
| 脚下照顧 | きゃっかしょうこ | 身近なことに十分気をつけること。「脚下」は、足もと。「照顧」は、照らしかえりみるの意。 |
| 九牛一毛 | きゅうぎゅうのいちもう | |
| 九死一生 | きゅうしいっしょう | 死にそうなあぶないところをやっと助かること。全く絶望的な状態のこと。また、そこから助かること。「死」が九分、「生」が一分の状態のこと。ほとんど助かるとは思えないほどの危険な状態のことで、そこから奇跡的に助かることを「九死に一生を得る」という。 |
| 九鼎大呂 | きゅうていたいりょ | 貴重なもの、重い地位、名望などのたとえ。 |
| 旧態依然 | キュウタイイゼン | 昔からの状態、体制が古いままで少しも変化・進歩のないさま。昔の状態がそのまま続き、少しも変わりばえしないこと。 |
| 旧敵宿怨 | きゅうてんしゅくえん | 以前からの敵に対する積もり積もった恨み、怨念。 |
| 旧套墨守 | きゅうとうぼくしゅ | 古くさい形式や方法にこだわって、融通がきかないこと。「旧套」は、古い形式、ありふれた方法。「墨守」は、自分の考えを堅く守って改めないこと。 |
| 弓箭之士 | きゅうせんのし | 弓矢を持った兵士。 |
| 急転直下 | きゅうてんちょっか | 急に形勢が変わって解決に向かうこと。 |
| 救世済民 | きゅうせいさいみん | 世の中を救い、人民の難儀を助ける。 |
| 窮鼠噛猫 | きゅうそねこをかむ きゅうそこうびょう |
窮地に陥れば、弱い者も必死になって強者に刃向かうということ。 |
| 窮鳥入懐 | きゅうちょうにゅうかい | 「窮鳥、ふところに入れば、仁人の憐れむところなり。」困窮して頼ってくる者があればどんな理由があっても助けてやろうという意味。 |
| 窮余一策 | きゅうよいっさく | 困りきったあげくの果てに思い付いたひとつの手段・計略。 |
| 牛飲馬食 | ぎゅういんばしょく | やたらたくさん飲み食いすること。(牛や馬のように) |
| 挙措進退 | きょそしんたい | 日常のちょっとした動作。立ち居振る舞い。 |
| 挙措動作 | きょそどうさ | 立ち居振る舞い。からだの動かし方。「挙措」は、あげることとおくこと。 |
| 挙動不審 | きょどうふしん | 動作・様子が疑わしいこと。「挙動」は、人の立ち居振る舞い。尋問の理由に使うことが多い。 |
| 虚虚実実 | キョキョジツジツ きょきょじつじつ |
互いに策略を尽くし、相手のすきをねらって必死で戦うさま。敵の油断をねらい一生懸命に戦うこと。 |
| 虚心坦懐 | きょしんたんかい | 心にわだかまりを持たず、素直でさっぱりした気持ち。無心で平静な心境。 |
| 虚心平易 | きょしんへいい | 愛憎の念がなく公平な態度。 |
| 虚心平気 | きょしんへいき | 平静で、心にわだかまりをもたないこと。また、その心。気を平らかにして、心を虚(むな)しくする意。「平気」は気を静め落ち着ける意。「虚心」は心にわだかまりをもたないこと。「虚」はむなしくする、からにする、雑念をなくす意。 |
| 虚脱状態 | きょだつじょうたい | 心身が衰え、気力が抜けて何も出来ないさま。 |
| 漁夫の利 | ぎょふのり | 両者が争う隙につけこみ、第三者が労せずして利益を横取りすること。 |
| 共存共栄 | きょうぞんきょうえい | 共に助け合い、共に栄えること。 |
| 共同一致 | きょうどういっち | 二人以上が力や心を合わせること。 |
| 協力一致 | きょうりょくいっち | 同じ目的のために大勢の人が心を一つにし、事を行なうこと。また、人々が力を合わせ、助け合っていくこと。 |
| 興味津津 | きょうみしんしん | 興味が次々とわいて、つきないさま。「津々」は、絶えずあふれ出るさま。 |
| 恐悦至極 | きょうえつしごく | 相手の厚意に大変喜び感謝すること。「恐悦」は、かしこまって喜ぶ意。「至極」は、程度が甚だしいさま。 |
| 恐恐謹言 | きょうきょうきんげん | 気づかい恐れて、謹んで申し上げる。手紙の終わりに添える言葉。 |
| 恐惶謹言 | きょうこうきんげん | 「おそれながら、謹んで申し上げる」。 |
| 教唆煽動 | きょうさせんどう | 人をおしえそそのかして行動させること。「教唆」は、暗示を与えてそそのかす。「煽動」は、あおりうごかす。 |
| 拱手傍観 | きょうしゅぼうかん | そばで眺めているだけで何もしないさま。関心はあっても協力しないときなどに使う。 |
| 驚天動地 | きょうてんどうち | 世の中を大いに驚かすこと。天を驚かし地を動かすの意で、世間の人を大いに驚かすこと。 |
| 強迫観念 | きょうはくかんねん | 払いのけようとしても強く浮かんでくるいやな考え。 |
| 狂喜乱舞 | きょうきらんぶ | 非常に喜ぶさま。 |
| 狂言綺語 | きょうげんきご | 道理に合わない言葉と表面だけを飾った言葉。転じて、小説や物語の類いをいやしめて言う語。 |
| 狂風暴雨 | きょうふうぼうう | 吹き荒れる風、激しく降る雨。きわめて手のつけられぬ状況や境遇のこと。 また勢力が抑制できぬほど盛んなことや、態度が粗暴なことにも用いる語句。 |
| 狂乱怒濤 | きょうらんどとう | 物事が乱れて大荒れの状態。荒れ狂う波の様子から転じて言う。 |
| 胸襟担白 | きょうきんたんぱく | 気持ちが率直で、あっさりしていること。態度に表裏がないようす。 |
| 鏡花水月 | 鏡に映った花、水に映る月。美しいが、ただ見るだけで捉えることができない。実体がなく、掴みどころのないもののたとえ。幻影。また、芸術作品の理屈を越えた情趣の高尚さをいう。 | |
| 鏡花風月 | きょうかふうげつ | 見えるだけで手に取れないもの、直感で感じ取ったり、悟ったりして把握するもののたとえ。鏡に映った花と水に映った月は、ともに見えるだけで、実際にてをすることにできないものである。また、小説・詩歌など、感知できてもことばでいいつくせない優れた趣のたとえにも使われる。 |
| 叫喚地獄 | きょうかんじごく | ひどい苦しみに泣き叫ぶこと。仏教語で、八大地獄の第四番目。 |
| 矯角殺牛 | きょうかくさつぎゅう | 牛の角を安全のために斧で矯正しようとして、ついに牛を殺してしまうこと。枝葉末節のことにこだわり、それを直そうとして全体を台無しにし、元も子もなくしてしまうこと。 |
| 行住坐臥 | ぎょうじゅうざが | 日常の立ち居振る舞い、起居動作。「行」は行く(歩く)こと、「住」は止まること、「坐」は座ること、「臥」はふせる(寝る)こと。この4つが一切の行動の基本になるため、仏教ではこれを「四威儀」とよんで、特に規律を定めた。 |
| 局外中立 | きょくがいちゅうりつ | 戦争をしている国のどちらの見方にもならず、援助もしないこと。 |
| 曲水流觴 | きょくすいりゅうしょう | 屈曲した小川の流れに杯を浮かべ、それが自分の前を流れ過ぎてしまわないうちに詩歌を作り、杯の酒を飲むという風雅な遊び。もと陰暦三月三日(また、上巳(じょうし)の日)に行われた風習。▽「曲水」は曲折した小川の流れ。「觴」は杯の意。中国晋代、王羲之が、ので文人を集めて催したものが有名。「流觴曲水」ともいう。 |
| 曲学阿世 | きょくがくあせい | 学問の正しい態度を曲げて世の中におもねり、迎合すること。 |
| 旭日昇天 | きょくじつしょうてん | 朝日が天空に昇ること。また勢いが盛んなようすのたとえ。 |
| 玉石混交 | ギョクセキコンコウ ぎょくせきこんこう |
良いものと悪いもの、優れたものとつまらぬものが入り混じっていること。優れたものとつまらないものが雑然と混じり合っていること。 |
| 旭日昇天 | キョクジツショウテン | 朝日が天空に昇ること。また勢いが盛んなようすのたとえ。上に向かう勢いが非常に盛んなこと。(朝日が天に昇るように)。 |
| 金科玉条 | キンカギョクジョウ |
金や玉のように尊い大事な法律、規則。ぜひとも守るべき大切な法律、きまり、よりどころ。その人にとって一番大事な法則(規定)。 |
| 金言名句 | きんげんめいく | 珠玉のいい言葉、名文句など。 |
| 金口木舌 | きんこうぼくぜつ | 優れた言論・出版などを通じ、社会を教え導く人のたとえ。 |
| 金城鉄壁 | きんじょうてっぺき | 非常に堅固な城壁。 |
| 金城湯池 | きんじょうとうち | 防備の堅固な城壁と、熱湯の沸きたぎる濠(堀)。他から侵略されない極めて堅固な備えをいう。きわめて守りの堅い城のこと。ゆるがぬ地盤。金で造った城、熱湯の沸き立つ堀。 |
| 金声玉振 | きんせいぎょくしん | |
| 金襴緞子 | きんらんどんす | ぜいたくで高価な美しい織物。「金襴」は錦地で模様を織り込んだもの。「緞子」は厚手の絹に模様を織り込んだもの。 |
| 欣喜雀躍 | きんきじゃくやく | 雀が飛び跳ねるように非常に喜ぶこと。小躍りして喜ぶ。有頂天になること。大喜びすること。雀がぴょんぴょんはねるようにこおどりして喜ぶさま。 |
| 勤倹貯蓄 | きんけんちょちく | よく働いて倹約し、お金をためること。 |
| 勤倹力行 | キンケンリッコウ | 仕事・事業に励み、倹約し努力して物事を行うこと。勤勉で倹約な行いに、たえまなく力をつくし励むこと。 |
| 勤王攘夷 | きんのうじょうい | 天皇を尊び、外異を撃ち払って入国させないこと。「勤王」は、「勤皇」とも書く。「尊王攘夷・尊皇攘夷(そんのうじょうい)」ともいう。 |
| 謹厳実直 | キンゲンジッチョク | 慎み深く、誠実・正直なさま。まじめな人間のようす。慎み深く慎重で正直、律儀なさま。融通のきかないさまをからかって言うこともある。 |
| 謹言慎行 | きんげんしんこう | 言動を特別慎重にすること。「謹」はつつしむ、こまやかに気を配る。「慎」はつつしむ、念を入れる意。 |
|
緊褌一番 |
きんこんいちばん |
気持ちを大いに引き締めて、物事に当たること。【説】「緊褌」は褌(ふんどし)を引き締めること。「一番」はここ一番の大事なときの意。 |
| 緊張緩和 | きんちょうかんわ | ひきしまった心が緩むこと。 |
| 琴瑟相和 | きんしつちょうわ きんしつあいわす |
夫婦が仲睦まじいことのたとえ。兄弟、友人の仲がよいこと。【説】「瑟」は大型の琴。琴と瑟を合奏すると音がよく調和し、美しい調べを生ずることから。【類】琴瑟調和 きんしつちょうわ |
| 琴瑟相和 | きんしつあいわす | |
| 琴瑟調和 | きんしつちょうわ | 夫婦の仲がむつまじいこと。琴と瑟(おおごと)とを合奏していてその音がよく調和する様子にたとえた。 |
| 欣喜雀躍 | きんきじゃくやく | 雀が飛び跳ねるように非常に喜ぶこと。小躍りして喜ぶ。有頂天になること。 |
| 筋骨隆隆 | きんこつりゅうりゅう | 体がぎっしりしていて筋肉が盛り上がって見える形容。 |
| 禽獣夷狄 | きんじゅういてき | 鳥と獣と野蛮人。恩義や道理を知らぬ人々を罵っていう言葉。犬畜生といった感じ。「夷狄」は中国からみた異民族の地域。 |
| 槿花一朝 | きんかいっちょう | 槿(むくげ)の花は、朝開いてその夕べにはしぼんでしまう。はかないことのたとえ。「槿花一日(いちじつ~」ともいう。栄耀栄華を謳(おう)歌していても、たちまち失敗、元の木阿弥(もくあみ)になる。これを「槿花一朝の夢」という。白楽天の詩にある「槿花一日自(おのず)から栄を為(な)す」が最初の用例のようだ。その詩では、「松樹千年終(つい)に是(こ)れ朽(く)つ」(千年の松の木でもついには枯れる)と対句になっていて、槿の花のようにはかないものでも、一日の間は栄える、という用い方になっている。また、「小人(しょうじん)槿花の心」(孟郊の詩)と、変わりやすい心をたとえるのもある。いずれにせよ、得意満面時めいていても長くは続かない。槿花一朝、冷たい風が身にしみるようになる。 |
| ク | ||
| 九識十名 | くしきじゅうみょう | 摂論宗の祖真諦の立てた人間の心のあり方の分類。眼、耳、鼻、舌、身、末那、阿頼耶の八識に阿摩羅を加えたもの。第九菴摩羅識に,真識・無相識・法性識・仏性真識・実際識・法身識・自性清浄識・阿摩羅識(無垢識)・真如識、不可名識の十識をいう。 |
| 九尺二間 | くしゃくにけん | 間口が九尺、奥行きが二間の家。狭くてみすぼらしい家のこと。 |
| 九寸五分 | くすんごぶ | 長さが九寸五分(約30センチメートル)あるところから短刀・あいくちのこと。二尺八寸が刀。 |
| 九損一得 | くそんいっとく | 十回のうち徳になるのは一回ということ。費用ばかりかかってほとんど益のないこと。 |
| 九分九厘 | くぶくりん | 十分のうち一厘をを残すだけの意。ほぼ確実であること。 |
| 九分十分 | くぶじゅうぶ | たいした違いはないこと。大同小異。五十歩百歩。 |
| 口先三寸 | くちさきさんずん | おしゃべりの巧みさで人をだますこと。 |
| 口伝耳受 | くでんじじゅ | 口で伝えられたことを耳で聞く。 |
| 苦海十年 | くかいじゅうねん | 年季で縛られていた遊女が十年で自由になれた。この十年のこと。 |
| 苦学力行 | くがくりっこう | 苦心して勉学に励むこと。 |
| 苦心惨憺 | クシンサンタン | 心を砕いて苦労を重ね、困りながらも、あれこれと工夫を凝らすこと。非常な苦心をすること。あれこれ心を砕いて苦労を重ねること。 |
| 苦肉之計 | くにくのけい | 苦し紛れに考えた手段。 |
| 苦肉之策 | くにくのさく | 「苦肉」とは“敵をあざむくため、自分の身をくるしめること”。「苦い肉」ではないのです。よってこの四字熟語のいみは、苦労してひねり出した計画のこと。 |
| 具眼の士 | ぐがんのし | 物事の是非・善悪を判断し、ものの本質を見抜く見識をもっていること。 |
| 愚公移山 | ぐこういざん | 「愚公、山を移す」。根気よく努力し続ければ、ついには成功するというたとえ。 |
| 愚者一得 | ぐしゃいっとく | 愚か者でも、たまに名案を出すことがある。愚者の考えも、よく聞くことが大事だ。 |
| 愚夫愚婦 | ぐふぐふ | 愚かな男や女。愚民。 |
| 虞美人草 | ぐびじんそう | ひなげしの別名。楚の項羽に殉じた虞美人の墓の上に生えた草に名づけられたという伝説がある。 |
| 愚問愚答 | ぐもんぐとう | ばかげた質問と回答。 |
| 空々漠々 | くうくうばくばく | 何もなくて広々としている様子。 |
| 空前絶後 | クウゼンゼツゴ | これまでにも一度も経験がなく、今後も絶対にありえないと思われるような珍しくて貴重なこと。過去、将来にわたって、例のないこと。 |
| 空即是色 | くうそくぜしき | 万物の真の姿は「空(実体がない)」だが、それは虚無ではなく、真の実在であるという考え方。 |
| 空中楼閣 | クウチュウロウカク | 空想的で現実性の乏しい考えや議論。やってもできそうにない無理な空論。根拠のないことから空想的な議論や、文章のこと。空中に現れる高殿。蜃気楼のこと。 |
| 空理空論 | クウリクウロン | 理屈は通っていても現実から懸け離れていて、実際には役立ちそうもない理論や議論。 |
| 薬九層倍 | くすりくそうばい | 暴利をむさぼること。薬の値段が原価に比べて極めて高いことから。 |
| 求聞持法 | グモンジホウ | 虚空蔵求聞持法の略。虚空蔵菩薩を本尊として修行することで、頭脳を明快にし、記憶力を増大するものとされる。空海が入唐前に勤操から授かって修行したとされる妙法。 |
| 桑原桑原 | くわばらくわばら | 雷鳴の時、落雷を避ける呪文として用いる語。また、一般に忌まわしいことを避けるためにも言う。 |
| 君子三楽 | くんしさんらく | 君子の持つ3つの楽しみのこと。「孟子」では君子(学徳の高い人)の楽しみは、第一には父母が健在で兄弟も無事なこと、第二には天や人に恥じる後ろめたい点がないこと、第三には天下の英才を集めて教育すること。この3つである。別に「列子」では、この世に生まれてきた3つの楽しみとして、人間として生まれ、男子とした生まれ、長生きしていることをいう。 |
| 君子豹変 | クンシヒョウヘン | 道徳的に立派な人が豹のまだらがくっきり変化するように、変わり身が早く、無節操なさまをいう。思想や行動、態度が急変する、変わり身の早さをいう。君子は間違いを改め善に移るのが早いこと。俗に、態度が急に悪く変わることに使われる。君子=人格者、徳の高い人。 |
| 君臣水魚 | くんしんすいぎょ | 水と魚との関係のように君臣の間の親密なこと。蜀の劉備と諸葛亮の親密な交わり。 |
| 君側之悪 | くんそくのあく | 君主のそばにいる悪人。悪だくみを抱く側近の家来をいう。 |
| 群集心理 | ぐんしゅうしんり | 多くの人々の言動に同調する心の状態。 |
| 群盲評象 | ぐんもうひょうぞう | 凡人が大人物や大事業を批評しても、その一部分だけにとどまって、全体の把握、理解ができないということ。 |
| 群雄割拠 | グンユウカッキョ | 多くの実力者が各地でそれぞれに勢力をふるい、対立しあうこと。戦国時代に多くの英雄が各地に本拠を構え、対立していたことからいう。群雄が各地を地盤として勢いをふるい対立すること。 |
| ケ | ||
| 戯作三昧 | げさくざんまい | 小説を書くのに夢中であること。 |
| 兄弟之国 | けいていのくに | 親しみの深い国。祖先が兄弟同士の国。また、婚姻関係による親類の国。 |
| 蛍火乱飛 | けいからんぴ | ほたるが乱れ飛ぶこと。 |
| 蛍雪之功 | けいせつのこう | 苦労して学問に励むこと。螢の光や雪明かりで貧乏に耐えながら勉学する。 |
| 軽求肥馬 | けいきゅうひば | 身分が高く財産がある人の服装。または、常にとても富貴な様子。「軽裘」は軽くて高級で丈夫な皮ごろも。「肥馬」は肥え太った立派な馬。「肥馬軽裘」ともいう。 |
| 軽挙妄動 | けいきょもうどう | 事の是非を考えずに、でたらめな感じで軽々しく行動すること。向こう見ずな振る舞いを言う。 |
| 軽佻浮薄 | けいちょうふはく | 軽はずみで、行動がしっかりしていないこと。考えが浅く、上すべりで移り気な感じ。 |
| 軽薄短小 | けいはくたんしょう | 軽い、薄い、短い、小さい。 |
| 軽妙洒脱 | けいみょうしゃだつ | 気がきいていて、さっぱりとしていること。軽快で妙味があり、気がきいて味があること。 |
| 経国大業 | けいこくたいぎょう | 立派な文章、著作をほめていう言葉。また、国家を治めるための大きな仕事を指す。 |
| 経文緯武 | けいぶんいぶ | 文を縦とし武を横とする。文武両道を兼ね備える。 |
| 慶雲之瑞 | けいうんのずい | めでたい雲のしるしの五色。太平のまえぶれ。 |
| 敬天愛人 | けいてんあいじん | 天をおそれ敬い人民を慈しむこと。 |
| 形影一如 | けいえいいちにょ | 影と影がいつも一緒であるように夫婦の仲が良い状態であることの意。「一如」は同じということ。 |
| 傾危之士 | けいきのし | 巧みに弁舌を弄して、国家の命運を危うくする人。危険人物のたとえ。 |
| 傾国傾城 | けいこくけいせい | 絶世の美女をいう。「国を傾け城を傾く」と読む。「傾城傾国」も同じ。国と城は同義でくにを意味する。 漢の李延年(りえんねん)の「佳人の歌」に、「一顧すれば人の城を傾け、再顧すれば人の国を傾く」(1度振り返ると城を滅(ほろ)ぼし、二度振り返ると国を滅ぼしてしまう)と詠うのがこの語の出所だ。この歌は自分の妹を武帝に売りこむために作ったといわれる。夢中になり国を滅ぼすかもしれないほどの美人ですよ、と。その結果、妹は李夫人と呼ばれ武帝の寵愛(ちょうあい)を得ることになる。白楽天の「長恨歌(ちょうごんか)」にも「漢皇(実は唐の玄宗(げんそう))色を重んじて傾国を思う」と楊貴妃(ようきひ)寵愛のことを詠う。なお、わが国では江戸時代、歌舞をする遊女(おいらん)を傾城とよんだ。 |
| 傾城傾国 | けいせいけいこく | その美しさゆえに国を滅ぼすほどの美女。 |
| 警鐘乱打 | けいしょうらんだ | ① 急を知らせる鐘。戦いや火災、大水など、危険な事態を知らせるために打ちならす合図の鐘。また、その鐘の音。早鐘。② (比喩的に用いられて) 警告となるもの。いましめ。③ 初期の市街電車の運転台の下にあった装置で、前方の人に電車が近づくことを知らせた鐘。 |
| 桂冠詩人 | けいかんしじん | イギリス王室に参与する名誉の詩人。古代ギリシアの名誉ある詩人に月桂冠を授けたのでいう。 |
| 鶏群一鶴 | けいぐんのいっかく | 凡庸な人の中で、一人だけ際立って優れた人。鶏(にわとり)の群(むれ)の中に一羽の鶴(つる)がいるように、目立つ存在のこと。「群鶏の一鶴」ともいう。 晋(しん)の紹(けいしょう)の故事。けい紹は竹林の七賢の領袖けい康(けいこう)の子。『晋書(しんじょ)』(晋代の歴史)によると、けい紹が初めて都・洛陽(らくよう)へ上った時、ある人がけい紹を見て「ちゅう人の中にこう然(ぜん)として野鶴(やかく)の鶏群(けいぐん)に在るが如(ごと)し」(多くの人の中で意気高く野の鶴が鶏の群にいるようだ)と言ったと。 けい紹は後(のち)に晋の恵(けい)帝の侍中(じちゅう)(側近の大臣)となり、戦乱の際、恵帝をかばって戦死した。その時けい紹の血が帝の衣についたが、帝は「けい侍中の血である」と言って洗わせなかったという。けい紹の父の康(こう)も優れた人物。「青眼白眼」の話が有名。 |
| 鶏口牛後 | ケイコウギュウゴ | 大きな組織に付き従って軽んぜられるよりも、小さな組織の長となって重んぜられるほうがよいということ。大きなものの後ろにつくよりは小さいものの頭になった方がいいと言うこと。小国の王にはなっても大国の臣下にはなるなの意。 |
| 鶏鳴狗盗 | けいめいくとう | 人を欺いたり、物を盗んだりする卑しい者。また、そのようなことしかできない者。戦国時代、斉の孟嘗君が、鶏の鳴き真似のうまい男と、犬のまねをする盗人を利用して難を逃れた故事に基づく。 |
| 閨閤之臣 | けいこうのしん | 君主の側近の臣。奥方づきの家来のこと。 |
| 閨秀作家 | けいしゅうさっか | 女流作家。学問、才能に秀でた才媛のこと。 |
| 潔白清廉 | けっぱくせいれん | 潔くて欲が少ない。 |
| 月下推敲 | げっかすいこう | 詩文の字句を工夫し、練り上げt\ること。【説】詩作中に門を「推(お)す」とするか、「敲(たた)く」とするか、月の下で思案するという意。 |
| 月下氷人 | げっかひょうじん | 男女の縁をとりもつ人。媒酌人。なこうど。 月下老人の伝説。ある青年が見合いのために寺に行くと、月の光の下で、老人が本を読んでいた。不審に思って尋ねると、老人は結婚を司る幽界の人だと言う。袋の中には、縁結びの赤い縄が入っていた。老人は、青年の結婚相手は別にいると告げる。それは三歳の少女だった。結局、青年は後に、成長したその相手と結婚する。これは「続幽怪録」という書物の中の「定婚店」という話です。 もうひとつは占い師の話。ある人が氷の上に立ち、氷の下にいる人と話す夢を見た。占い師に聞くと、「それはあなたが仲人を務めるという夢だ」と告げられた。そして結局、そのとおりになったという。こちらは「晋書」に載っている話である。 「月下老人」「氷人」が混同されて「月下氷人」となった。「月」「氷」というきれいな語句を並べたくなる、無意識の心が働いたのかもしれない。 |
| 月下美人 | げっかびじん | サボテン科の熱帯植物。六月頃の夜、白くて大きい花を開き数時間でしぼむ。媒酌人。 |
| 犬馬之心 | けんばのこころ | 臣下や子が、主君や親のために尽くすことを、犬や馬が主人のために働くことにたとえた言葉。 |
| 犬馬之労 | けんばのろう | 犬や馬程度の働き。主人や他人のために力を尽くして奔走することを謙遜していう語。 |
| 見性成仏 | けんしょうじょうぶつ | 自分に執着し、外物に執着する自己の心を徹底的に掘りさげ、自己の本性として見るべきものは何もないと見極めたとき、その身はそのまま仏に他ならないと悟り得られるという禅宗の根本主張。 |
| 乾坤一擲 | けんこんいってき | 自分の運命をかけて、のるかそるかの大勝負をする。もと、天下をかけた大ばくちの意。思い切ったかけをすること。乾坤は、天地、宇宙。擲はなげる。天地をさいころのひとふりに賭ける。 |
| 権限委譲 | けんげんいじょう | 自らの権限を他にまかせ、譲ること。 |
| 権謀術数 | けんぼうじゅっすう | 種々の計略をめぐらすこと。人をあざむくためのはかりごと。たくらみ。人を欺くはかりごと。(術数=たくらみ) |
| 堅忍不抜 | けんにんふばつ | 一生懸命我慢してたゆまない様子。蘇軾の文に「才能だけでは大事な志を遂げることはできないのであって、堅忍不抜の志が必要である」とある。 |
| 捲土重来 | けんどちょうらい | 一度は衰えたり失敗したものが新たにやり直し、土煙をまき上げるような勢いで再び勢いを盛り返し反攻すること。「じゅうらい~」とも。 |
|
牽強付会 |
ケンキョウフカイ | 道理に合わないことを無理にこじつけ、理屈づけること。道理に合わないことを、自分の都合のいいようにこじつけること。(議論で)こじつけて、都合良くつなぎ合わせること。こじつけ。「牽強」も「付会」も、こじつけるの意。 |
| 狷介固陋 | けんかいころう | 自己の狭い見聞をかたくなにまもって人と相容れないこと。 |
| 狷介孤高 | けんかいここう | 自分の意志を固く守って、人々から離れ品格を高く保っていること。俗世に超然としていること。 |
| 喧喧囂囂 | けんけんがくがく けんけんごうごう |
多くの人が口やかましく騒ぐさま。また、やかましく騒ぎ立てて収拾がつかないさま。▽「」「」はともに、やかましいさま。騒がしいさま。 |
| 拳拳服膺 | けんけんふくよう |
心に銘記して決して忘れないこと。【説】「拳拳」は両手で大切に捧げ持つこと、「服膺」は胸につけること。「膺」は胸の意。 |
| 絢爛華麗 | けんらんかれい | 華やかで美しく、きらびやかに輝くさまをいう。美的な感覚が多分に含まれており、ゴージャスで価値のある雰囲気を演出することができる言葉でもある。 |
| 絢爛豪華 | けんらんごうか | きらびやかに輝き、華やかで美しいさま。▽「豪華」はぜいたくで華やかなさま。「絢爛」はきらびやかで美しいさま。「絢爛豪華」ともいう。 |
| 元気溌剌 | げんきはつらつ | 気力があふれ、生き生きとしていること。「溌剌」は、魚が勢いよく飛び跳ねるさま。 |
| 言行一致 | げんこういっち | 言うことと行うことが、一致していること。言葉と行いが、食い違うことなく一つになること。また、同じにすること。 |
| 言行齟齬 | げんこうそご | 政治の世界では、言行の逆が画策されるという現象が見られる。例えば、「増税をしない」と言い出したら、やがて増税が実施されることを意味しているという按配である。つまり、云うこと(建前)と行うこと(本音)が逆で、それがぬけぬけとまかり通り不自然を感じないという現象がある。 |
| 元軽白俗 | げんけいはくぞく |
北宋時代の詩人/蘇軾(そしょく)が、唐の時代の詩風を酷評した言葉。元稹(げんしん)の詩は軽々しくて重厚さがなく、白居易の詩は卑俗で品がないという意味。 |
| コ | ||
| 古往今来 | こおうこんらい | 昔から今に至るまで、古今。昔から。 |
| 古今東西 | ここんとうざい | 昔から今まで、あらゆる場所で。いつでもどこでも。▽「古今」は昔と今。昔から今まで。「古今」は時間の流れ、「東西」は空間の広がり。「東西古今」ともいう。 |
| 古今無双 | ここんむそう | 古から今まで並ぶものがないこと。 |
| 古今無比 | ここんむひ | 古今にわたって比べるものがないこと。 |
| 古色蒼然 | こしょくそうぜん | 長い年月を経て古びている様。「蒼然」は、ものの古びた様子。古さが現れていること。 |
| 小糠三合 | こぬかさんごう | わずかな財産のことをたとえていう。 |
| 小春日和 | こはるびより | 11月~12月にかけての良く晴れたひより。 |
| 固定観念 | こていかんねん | かたくかたまった、一定の考え方。 |
| 孤影蕭然 | こえいしょうぜん | 一人で寂しげなさま。しょんぼりと寂しい姿。「孤影悄然」とも書く。「孤影」は、たった一人でいる姿。「影」はかげ、ではなく姿の意。六朝・宋の謝霊運の詩に「孤影与ともに爰わするる莫なし」(孤独な姿を忘れさせてくれるものはない)という句がある。たとえば、事業に失敗し、誰も助けてくれず(孤立無援)、また親兄弟もいない(天涯孤独)で、しょんぼりした姿が「孤影蕭然」だ。 |
| 狐疑逡巡 | こぎしゅんじゅん | 迷って決心がつかずぐずぐずしていること。「逡巡」は、ぐずぐずとためらって実行しようとしないこと。狐は疑い深い動物であるということから。 |
| 孤軍奮闘 | こぐんふんとう | 援軍がなく、周囲から孤立した小数の軍勢でよく戦うこと。 |
| 孤掌難鳴 | 相手がなければ何事もできないこと。 | |
| 孤城落日 | こじょうらくじつ | 昔の勢いを失い、助けるものもなく、ひたすら没落に向かう状態。 |
| 孤独地獄 | こどくじごく | |
| 孤立無援 | こりつむえん | ひとりぼっちで助けがないこと。 |
| 虎穴虎子 | こけつこじ | 「虎穴に入らずんば虎子を得ず」。「虎の子」を得るためには、危険を承知で冒険しなければ実現しない、という意味。 |
| 虎視眈眈 | こしたんたん | 虎が獲物を狙って鋭い眼でじっと見下ろすようす。野望を遂げようとして機会をじっと狙う。 |
| 故事来歴 | 由緒とそれから後の経過。 | |
| 誇大妄想 | こだいもうそう | 自分の現在の状態を大げさに空想すること。 |
| 姑息之政 | こそくのまつりごと | 一時のがれの政治。その場の間に合わせの政治。 |
| 胡蝶之夢 | こちょうのゆめ | 人生ははかない、ということ。《荘子が夢の中で胡蝶になり、自分が胡蝶か、胡蝶が自分か区別がつかなくなったという「荘子」斉物論の故事に基づく》自分と物との区別のつかない物我一体の境地、または現実と夢とが区別できないことのたとえ。 荘子が、蝶となり百年を花上に遊んだと夢に見て目覚めたが、自分が夢で蝶となったのか、蝶が夢見て今自分になっているのかと疑ったという「荘子(斉物論)」の故事による[1] 夢と現実との境が判然としないたとえ。この世の生のはかないたとえ。 |
| 鼓腹撃壌 | こふくげきじょう | 太平の世の形容。太平で安楽な生活を喜び楽しむさま。善政が行われ、人々が平和な生活を送るさま。満腹で腹つづみをうち、足で地面をたたいて拍子をとる意から。▽「鼓腹」は腹つづみをうつこと。「壌」は土・地面。「撃壌」は地面をたたいて拍子をとること。 |
| 鼓舞激励 | こぶげきれい | ひとを励まし元気を出させること。ひとを奮い立たせはげますこと。 |
| 股肱之臣 | ここうのしん | 最も頼りになる部下。 |
| 壺中之天 | こちゅうのてん | 別世界、別天地のこと。また、酒を飲んで俗世間を忘れることのたとえ。「壺中」は、壺の中。「壺中天地」ともいう。 故事/中国後漢の時代、汝南じょなん(河南省の地名)に費長房ひちょうぼうという者がいた。市場の役人をしていたとき、薬を売る老人が商売を終えると、店先につるしていた壺の中に飛び込むのを見た。費長房は老人に仙人の術を教えてくれるように頼み壺の中に入れてもらったところ、中には立派な建物があり、美酒とおいしい料理がずらりと並んでいた。費長房は老人と一緒にそれを飲み食いして、壺から出てきたという。 |
| 五畿七道 | ごきしちどう | 畿内の五カ国(山城・大和・河内・和泉・摂津)と東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海の七道。 |
| 五公五民 | ごこうごみん | 収穫の五割を年貢として官に納め、残りの五割を農民のものとする年貢率。 |
| 五十歩百歩 | ごじっぽひゃっぽ | 戦場で50歩逃げた(後退した)者が100歩逃げた者を見て 「意気地なし、臆病者」と笑ったという孟子の説話からでた格言で、どっちもどっち、 似たり寄ったりだ、たいして差のないことを言います。 |
| 五十二類 | ごじゅうにるい | 釈迦が入滅するときに集まって悲しんだという五十二種類の生き物、人間から禽獣・蟲・魚をいう。五十二衆ともいう。 |
| 五臓六腑 | ごぞうろっぷ | 腹の中、からだ全体のこと。五臓(肺、心臓、脾臓、肝臓、腎臓)と六腑(大腸、小腸、胆、胃、三焦(不明)、膀胱)のこと。六腑は、中が空になっている内臓。 |
| 五人囃子 | ごにんばやし | 雛人形の一種。地謡・笛・太鼓・大鼓・小鼓などの五人。 |
| 五百羅漢 | ごひゃくらかん | 釈迦の弟子である五百人の聖者、諸国に木造や石造の像があるまたその場所。 |
| 五分五分 | ごぶごぶ | 双方に優劣の差のないこと。お互いに同等であること。力や勢いが互角であるさま。 |
| 五風十雨 | ごふうじゅう | 五日に一度風が吹き、十日に一度のわりあいで雨が降る。農作において望ましい天候のことで、世の中が平穏無事で天下泰平なことのたとえ。 |
| 五里霧中 | ごりむちゅう | 霧が深くて方角がわからないように、物事の手がかりがつかめず困惑している状態のたとえ。 物事に迷って、手がかりがなく方針が定まらず当惑すること。 |
| 呉越同舟 | ゴエツドウシュウ | 仲の悪い者同士が、同じ場所にいたり行動を共にしたりすること。 |
| 呉越之争 | ごえつのあらそい | 春秋時代、呉王夫差が父の仇を討つため臥薪(たきぎの上で寝る)し、前494年越王勾践を破って会稽に走らせたが、勾践もまたその恥をそそぐため嘗胆(きもをなめる)すること20年で呉を破った。 |
| 呉下阿蒙 | ごかのあもう | いつまで経っても進歩しない人のことを指す言葉。旧態依然と通底している。基本的には悪い意味合いで使われているが、あとに「~にあらず」を付け加え、よく進歩する人という意味に変えて、褒め言葉として利用することもできる。また、「阿」は「~ちゃん」といった感じの意味合い(阿Q正伝を参照)で、「蒙」は道理に暗いの意味合いも存在する。したがって「阿蒙」の部分は「おバカちゃん」という意味も同時に含んでいて、この一語だけで「おバカな蒙ちゃん」という意味を表している。この言葉の由来となった呂蒙という武将は武勇一点張りだったので、呉主孫権は彼に「武勇ばかりではなく学問も修めたほうがよい」と助言した。すると彼は、孫権の意に応えるために猛勉強を始め、高い教養を身につけていった。それからしばらくしたある日、彼は参謀の魯粛と対談したのだが、魯粛は彼の高い見識と知識に大いに驚いて「すでに武略のみの呉の蒙君ではなくなったな」といったという。またこのとき彼は魯粛に「士別れて三日ならば、即ち更に刮目して相待つべし」といった。この言葉も有名でありその意味は、日々努力しているものは三日も会わなければ目を見張るほど進歩しているということである。この後彼は三国志の表舞台に登場することができた。後世では、毛沢東がこの故事をプロパガンダに用いている。彼が羅瑞卿に語った言葉では「呂蒙は行伍の出身にして教養を持っていなかったため、不利であった。その後孫権が彼に読書を勧めると、彼は勧めを受け入れて勤学苦読し、後に東呉の統帥に出世した。今、我々の高級軍官のうち八割九割は行伍の出身で、革命に参加した後にやっと教養を学んでいる者たちだ。彼らは『三国志』と『呂蒙伝』を読まないわけにはいかない」とある(張貽玖『毛沢東読史』当代中国出版社 2005)。 |
| 呉牛喘月 | ごぎゅうつきにあえぐ | 過度におびえ恐れることのたとえ。また、疑いの心があると、何でもないものにまで恐れや疑いの気持ちをもつたとえ。暑い呉の地方の牛は月を見ても暑い太陽だと思い、喘あえぐ意から。▽「呉」は江南一帯の地。「喘」は息が切れて苦しそうに呼吸すること。 |
| 御前会議 | ごぜんかいぎ | 国家の重大事について、元老・重臣たちが天皇の御前で開いた会議。 |
| 後生大事 | ごしょうだいじ | ものを非常に大切にすること。もともと、仏教語で来世を考えて信心を忘れない意であったが、後生(来世)の安楽を願うことが大事という本来の意味から離れ一般に、大切に扱うの意に転じた。 |
| 胡麻すり | ごますり | 実際の胡麻すりに由来しており、四苦八苦して嫌なことをすることから転化して、上役におべっか使いする行為とか人に使われるようになった。 |
| 梧桐一葉 | ごどういちよう | ものの衰えのきざしの意。あおぎりの一葉が落ちたことで秋の到来を知ることができるという意から。また、些細な出来事から、全体の動きを予知することの例え。 |
| 口耳之学 | こうじのがく | 底の浅い、受け売りの学問、聞きかじりの学問のこと。【説】耳から入って口から出る学問の意で、人の言葉を鵜呑みにして、すぐに話すこと。【典】『荀子』 【類】道聴塗説 どうちょうとせつ |
| 口舌の徒 | ||
| 口誅筆伐 | こうちゅうひつばつ | 言葉と文章で激しく批判、攻撃すること。現代で言うと、ある事件、人物に対しマスコミ・報道機関が容赦なく批判を浴びせるたとえ。 |
| 口頭試問 | こうとうしもん | その場で口頭で答えを述べる試験。 |
| 光風霽月 | こうふうせいげつ | 心がさっぱりと澄み切ってわだかまりがなく、さわやかなことの形容。日の光の中を吹き渡るさわやかな風と、雨上がりの澄み切った空の月の意から。また、世の中がよく治まっていることの形容に用いられることもある。▽「霽」は晴れる意。 |
| 光芒一閃 | こうぼういっせん | 光が一瞬、ぴかりと光るさま。白刃がひらめく、電光がきらめくさま。転じて、英雄の華々しくも短い、あっという間の人生。 |
| 光芒万丈 | こうぼうばんじょう | 遠く四方に光を放ち、あたり一面に輝きわたるさま。聖人君主の出現、また偉人の功績をたたえる言葉。 |
| 光明磊落 | こうみょうらいらく | 胸にわだかまりがなく、公明正大であるさま。大らかでさっぱりしている状態。 |
| 広大無辺 | コウダイムヘン | とてつもなく広くて大きく、きわまりがないこと。 |
| 広範多岐 | こうはんたき | 範囲が広く多方面にわたること。 |
| 公私混同 | こうしこんどう | 公の立場と私の立場をごっちゃにすること。 |
| 公序良俗 | コウジョリョウゾク | 一般社会の秩序と善良な習慣、ならわし。 |
| 公武合体 | こうぶがったい | 江戸幕府の末期、朝廷と幕府の和合を図って国政に当たろうとした一派の議論。 |
| 公平無私 | コウヘイムシ | 行動、判断などが公平で、私的な感情や利益などに左右されないさま。 |
| 公明正大 | コウメイセイダイ | 心がはっきりと明らかで、正しく大きいさま。心が公明で正しくて立派な様子。 |
| 甲論乙駁 | こうろんおつばく | 議論がまとまらないこと。(甲がある説を論じると乙が反対するという様子。) |
| 興亡治乱 | こうぼうちらん | 国が興りまた滅び、世の中が治まり、また乱れること。 |
| 交淡如水 | こうたんじょすい | 「まじわりは淡き水のごとし」。君子の交際は、目先の利害にこだわらず、お互いの人格を重んずるので水のように淡白である。 |
| 行雲渭樹 | こううんいじゅ | 遠くにいる友人を気遣うこと。「江雲」は長江の空に浮かぶ雲。「渭樹」は長安郊外を流れる川、渭水のほとりの樹木。渭水の北の地にいる杜甫が、長江にいる李白を思って詩を作ったということから。 |
|
行雲流水 |
コウウンリュウスイ | 空を行く雲と流れる水と。そのように自然のままに行動することや物事にとらわれず事に従うという平静な心境のたとえ。気楽になりゆきにまかせ(て行動す)ること。空を行く雲と、川を流れる水のように。 |
| 効果覿面 | コウカテキメン | ある事柄のききめや報いがすぐに現れること。すぐにはっきりとした結果や効果が出る。即座にはっきりとききめが現れること。 |
| 厚顔無恥 | コウガンムチ | あつかましく、恥知らずでずうずうしいこと。つらの皮の厚いこと。きわめて厚かましく、恥知らずなこと。人のことなどいっさい気にせず、図々しく自分のことだけ考えて主義主張を押し通していく態度。 |
| 綱紀粛正 | コウキシュクセイ | 国家の規律・政治の方針や、政治家・役人の態度を正すこと。また、一般に規律を正すことをいう。公務員の守るべき秩序を厳しく取り締まり不正をのぞき去ること。 |
| 巧言令色 | こうげんれいしょく | 口先だけで真心にかけること。言葉巧みにものを言い、顔色をやわらげているのは、たいてい人間の徳である仁の心に欠けているものだの意。「令色」は、へつらう顔つき。孔子の言葉「巧言令色鮮(すくな)し仁」から。 |
| 好機到来 | こうきとうらい | またとない、よい機会がめぐってくること。絶好の機会に恵まれること。▽「好機」はちょうどよい機会、またとない機会のこと。「到来」は時機・機会の来ること。 |
| 高圧手段 | こうあつしゅだん | ある強い力で押さえつけて、他の者を自分に従わせるやり方。あたまごなし。 |
| 高歌放吟 | こうかほうぎん | あたりかまわず大声で歌い吟ずること。 |
| 高山流水 | こうざんりゅうすい | すぐれて巧みな音楽、絶妙な演奏のたとえ 。また、自分を理解してくれる真の友人の たとえ。清らかな自然の意に用いられること もある。 『列子』湯問(とうもん) 中国春秋時代、琴の名手の伯牙はくがが、高い山を思いながら演奏したところ、友人の鍾子期しょうしきは「まるであの高い泰山が目前にあるようだ」と評し、川の流れを思いうかべながら演奏したところ、「まるで滔々と流れる大河が目前にあるようだ」と評した故事から。鍾子期が死ぬと、伯牙は琴を打ち割り弦を断ち切って、終身琴を弾かなかったという。 |
| 高論卓説 | こうろんたくせつ | 程度の高い論議。すぐれた意見。立派な理論など。 |
| 恒久平和 | こうきゅうへいわ | 永久平和 |
| 恒産恒心 | こうさんこうしん | 定職のない者には、定まった心もない。一定した生業を持たない者は、安定した良心を持ち得ないということ。孟子が人々の生活安定を政治の基本として、その必要を強調した言葉。 |
| 後顧之憂 | こうこのうれい | 物事をやり終わった後に残る気がかり。のちのちの心配。 |
| 後生可畏 | こうせいおそるべし | |
| 恍然自失 | こうぜんじしつ | ぼんやりとして気抜けしたようになる。 |
|
浩然之気 |
こうぜんのき |
自分が正しい行いをし、天地に恥じることがないときに感じる大きく強い道徳的精神。転じて、何事にもこだわらないゆったりとした心。【説】「浩然」は、広くゆったりとしたさま。 【典】孟子 【類】正大之気 せいだいのき |
| 荒唐無稽 | コウトウムケイ | 言葉や説明に根拠がなく、ばかげていること。でたらめであること。言うことにとりとめが無くて、根拠がないこと。でたらめ。「荒」(何もなく広い)に「唐」(大きい)を重ねて、大げさで何の根拠もないことをいう。 |
| 好事多魔 | こうじたま | 好いことはとかく邪魔が入りやすい。いいことがあっても、有頂天になっていると、思い掛けない支障や妨害が入ってくるものだ。 |
| 黄髪垂髫 | こうはつすいちょう | 老人と子どものこと。「黄髪」は黄色がかった白髪ということから、老人のたとえ。「垂髫」は子どものおさげ髪ということから、子どものたとえ。 |
| 黄粱一炊 | こうりょういっすい | 一炊之夢に同じ。 |
| 紅毛碧眼 | コウモウヘキガン | 赤茶色の髪の毛と青緑色の眼。すなわち西洋人のこと。 |
| 皓月千里 | こうげつせんり | 月が明るく遠くまで輝き渡るさま。 |
| 鴻鵠之志 | こうこくのこころざし | おおとりや、くぐいなどの大鳥の気持。大人物や英雄の心にたとえる。遠大なこころざし。 |
| 蛟竜雲雨 | こうりょううんう | 「蛟竜雲雨を得」と読む。竜の子の蛟竜は、天上に雨雲が出ると、一気に天に奔け上ってゆく。 風雲児が好機に恵まれ、勢いに乗じて大きな飛躍を遂げること。「校意悔いあり」は栄達を極めた者に対する警告のことば。 |
| 豪華絢爛 | ゴウカケンラン | 「豪華」は派手ではなやかな、「絢爛」は彩り豊かで美しいさま。すなわちはなやかに豊かで、光り輝くように美しいさま。華やかで贅沢、美しく輝くばかりに立派であるさま。また、修飾の多い見事な詩文などにも使う。 |
| 豪放磊落 | ゴウホウライラク | 気持ちが大らかで、神経が太く、小さなことにこだわらないさま。度量が大きく、細かなことに気をかけないこと。「豪放」は、気性が大きい、「磊落」は、小事にこだわらない、落ち着いているさま。 |
| 剛毅果断 | ごうきかだん | 強い意志を持ち、物事にひるまず思い切って事を行うさま。 |
| 剛毅木訥 | ごうきぼくとつ | 強い心と毅然たる態度で、しかも飾り気のない木訥とした人物は、本当にえらいということ。 |
| 傲岸不遜 | ゴウガンフソン | 「傲岸」はおごりたかぶるさま。「不遜」は思い上がってへりくだらないこと。つまり、人を見下すような態度を取ること。おごり高ぶって、謙虚さのないこと。人を見下し、思い上がって屈することのないさま。 |
| 傲然屹立 | ごうぜんきつりつ | 誇らし気にそびえ立つさま。また、堅固で揺るぎないさまをいう。堂々として山が険しくそびえ立つさま。 |
| 傲慢無礼 | ごうまんぶれい | 威張って他人を見下し、他人に従わないさま。 |
| 告朔餼羊 | こくさくのきよう | (餼は食と氣の合わせ文字) |
| 国威発揚 | こくいはつよう | 国の威光を輝かせ、高くあらわすこと。 |
| 国士無双 | コクシムソウ こくしむそう |
国の中で他と比べる者のないようなすぐれた大人物、偉大な人材のことをいう。 |
| 国家柱石 | こっかのちゅうせき | 国家の重い責任を負う大臣や武将。 |
| 国利民福 | こくりみんぷく | 国家の利益と民衆の幸福。 |
| 黒衣宰相 | こくいのさいしょう | 僧侶の身分で天下の政治に参画する人のたとえ。徳川家康の政治顧問として活躍した天海僧正がその典型。黒衣は僧侶の衣装からその身分をあらわす。 |
| 刻舟求剣 | こくしゅうきゅうけん 舟に刻きざみて剣を求む |
時代の変化を知らずに、古い方法や慣習などに固執することのたとえ。 中国春秋時代、楚の人が舟で川を渡ったとき、剣を水中に落としてしまった。そこで後で探すために剣が落ちたところの船べりに印を刻み、向こう岸に着いてから、その印を刻んだところから水中に入って剣を探したが、見つからなかったという説話から。 |
| 骨肉相食 | こつにくそうしょく | 肉親同士が争うこと。 |
| 骨肉之親 | こつにくのしん | 親子・兄弟など血をわけた身内の者をいう。肉と骨とが離れられないような深いつながり。親族。 |
| 告朔餼羊 | こくさくのきよう | 魯ろの国で告朔の儀式がすたれ、羊を供える形式だけが残っていた。「それでは無意味だから餼羊をやめるべきです」と子貢しこうが言うと、孔子は儀式がすたれるのを惜しんだという。出典は論語の八佾はちいつ。(餼は食と氣の合わせ文字) |
| 克己復礼 | こっきふくれい | 私欲にうち勝ち、社会の規範・礼儀に従って行動すること。 |
| 刻苦精励 | こっくせいれい | 非常に苦労して、努力し励むこと。 |
| 刻苦勉学 | こっくべんがく | 非常に努力して、勉学に励むこと。 |
| 刻苦勉励 | こっくべんれい | 心身を苦しめるほどに、ひたすら努力を積み重ねること。力を尽くし、つとめはげむ。 |
| 酷寒猛暑 | こっかんもうしょ | 厳しい寒さと激しい暑さ。 |
| 滑稽千万 | こっけいせんばん | おどけていて面白いこと。また、その様子。馬鹿馬鹿しくて下らないこと。また、その様子。「―千万」 |
| 極悪非道 | ごくあくひどう | この上なく悪く、人の道にはずれている・こと(さま)。 |
| 極悪無道 | ごくあくむどう | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 極楽往生 | ごくらくおうじょう | 極楽浄土に行って生まれ変わること。楽に死ぬこと。 |
| 極楽浄土 | ごくらくじょうど | 仏教でこの世でよいことをした人が死後行くところ。また非常に清らかで楽しいところ。 |
| 極楽蜻蛉 | ごくらくとんぼ | 何もしなくて気楽な人。(極楽にいるトンボのように)。 |
| 今来古往 | こんらいこおう | いにしえから今に至るまで。 |
| 金剛不壊 | こんごうふえ | きわめて堅固で決して壊れないこと。志を堅く守ってかえないこと。金剛石(ダイヤモンド)の様に堅固で、用意に壊れないことから。 |
| 困苦欠乏 | こんくけつぼう | 物資の不足などからくる困難な状況に苦しむこと。 |
| 渾然一体 | こんぜんいったい | 別々のもの、いくつかの物が溶け合って一体となっているさま。 |
| 懇切丁寧 | こんせつていねい | 親切でこまかく気配りのあること。 |
| 蒟蒻問答 | こんにゃくもんどう | とんちんかんな会話。意味をなさない話のやりとり。 |
| 言語道断 | ごんごどうだん | とんでもないこと。もってのほか。「言語の道断えたり」と訓読みする。 |
| 欣求浄土 | ごんぐじょうど | 極楽浄土に往生することを願い求めること。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)