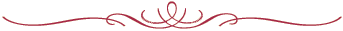
| 四文字熟語集1(ア行)(4.5、6文字) |
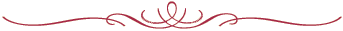
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のア行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
| ア | ||
| 合縁奇縁 | アイエンキエン | 人と人の気持ちのつながりの不思議さは仏教でいう因縁によるもの。不思議な巡り合わせの縁。人と人の気が合うのも合わないものも不思議な縁のはたらきによるということ。 |
| 相(愛)碁井目 | アイゴセイモク | 何事につけても人の実力は上下様々、バラエティーに富んで巧拙の差が甚だしいピンキリの様を云う。相碁とは実力が相等しいもの同士で打つ碁のこと。井目とは碁盤にしるされた九つの黒い点のこと。 |
| 哀訴嘆願 | あいそたんがん | なりふりかまわず、心の底から願い出ること。 |
| 哀悼痛惜 | あいとうつうせき | 人の死を悲しみ惜しむ気持ちの伝統的な表現。 |
| 愛別離苦 | アイベツリク | 親子・兄弟・夫婦など愛する者と生別・死別する苦しみ。別れのつらさをいう。父子、兄弟、夫婦など愛している人との離別の苦しみ。生き別れ、死に別れ共に使われる仏教語。仏教で八種の苦悩の一つ。 |
| 曖昧模糊 | あいまいもこ | 物事の本質や実体が、ぼんやりして何かはっきりしない様子。あやふやではっきりしない様子。 |
| 阿吽の呼吸 | ||
| 青息吐息 | あおいきといき | 非常に困ったときに出す元気のないため息。「青色吐息」とも云う。 |
|
悪因悪果
|
あくいんあっか | 悪いおこないが原因となって悪い結果の生ずること。悪いことをすれば悪い報いがある、との戒めの言葉。 |
| 悪逆非道 | あくぎゃくひどう | 比類のないほどのひどい行い。道徳に背く残酷な行為。「悪行無道」とも云う。 |
| 悪逆無道 | アクギャクムドウ | 道理にはずれたひどい悪事を行うこと。道徳にそむく残酷な行為。 |
| 悪事千里 | アクジセンリ | 悪いことはどんなに隠してもたちまち評判になり、世間に知れ渡ってしまうということ。悪いことはすぐに世間にしれわたるということ。 |
| 悪戦苦闘 | アクセンクトウ | 死にものぐるいの苦しい戦い。困難な状況の中で苦しみながら努力すること。困難な状態の中で苦しみ努力すること。非常に苦しんで戦うことや、かなり不利な状況下で苦しみながらも努力を続けること。 |
| 悪人正機 | アクニンショウキ | 人間は如来の本願にすがってこそ救われる。自分を悪人と思う人は、まさに本願他力の正しい機会を得ているという意味。 |
| 悪婦破家 | アクフハカ | 悪妻は夫の一生をだいなしにし、家庭を壊すということ。悪妻は百年の不作。 |
| 阿衡之佐 | アコウノサ | 天子を補佐する賢臣、名宰相のたとえ。阿衡とは総理大臣のことで、それを助ける者。 |
| 浅瀬仇波 | あさせあだなみ | 思慮の浅い人は、とかくとるにたりない小さなことにも大さわぎすることのたとえ。深い淵より浅い瀬の方がはげしく波立つ意。 |
| 浅茅生宿 | あさぢがやど | 荒れ果ててちがやが茂っている宿。 |
| 葦花赤毛 | あしばなあかげ | 馬の毛色の名前。少し赤ばんだ葦花毛。葦花毛:黄色を帯びた葦毛。 |
| 阿修羅道 | アシュラドウ | 強い闘争心と猜疑、嫉妬、執着の心をいう。地獄、餓鬼、畜生、人間、天上と並んで六道のひとつとされる修羅道の世界。 |
| 可惜身命 | あたらしんみょう | 体や命を大切にすること。 |
| 悪口雑言 | あっこうぞうげん | 口にまかせて様々に悪口をいいまくることをいう。口からでまかせにいろいろと悪口を言うこと。さんざんののしること。「雑言」は、本来は「ぞうげん」と読む。 |
| 阿鼻叫喚 | あびきょうかん | 非常な苦しみに落ち込んで、救いを叫び求める甚だしい惨状の様子。「阿鼻」は、八大地獄の中で最下最苦のところ。 |
| 阿鼻驚嘆 | あびきょうたん | 地獄の苦しみに絶えきれないで、わめき叫ぶこと。「阿鼻地獄」は仏教で言う八大地獄の一つ。 |
| 阿鼻地獄 | あびじごく | 地獄の8つの形相をいう八大地獄の第八。五逆と謗法 (ほうぼう) の大悪を犯した者が落ちる所。八熱地獄ともいう。諸地獄を一としてその一千倍の責め苦を受けるという。無間 (むけん) 地獄。阿鼻獄。阿鼻。 |
| 阿附迎合 | あふげいごう | 相手の機嫌をとって気に入られるように努めること。 |
| 阿付雷同 | あふらいどう | 自分の定見がなく、みだりに他人の説に同意して、へつらい従うこと。(「阿付迎合」「付和雷同」と同意) |
| 雨栗日和 | あまぐりひがき | 雨天続きの年は栗の実りがよく、天気の好い年は柿が豊作であるという関西方面での言い伝え。 |
| 蛙鳴蝉噪 | アメイセンソウ | カエルや蝉がやかましく鳴き立てるように、ただやかましく騒ぐこと。騒がしいばかりで役に立たない議論や文章のたとえ。やかましく騒ぐ様子。蛙や蝉がやかましく鳴くことから。 |
| 阿諛追従 | あゆついしょう | こびへつらうこと。相手に気に入られようとしてこびること。 |
| 阿諛便佞 | あゆべんねい | 口先でへつらって、ずるがしこく人の気に入るように立ちふるまうこと。「阿諛」は、おもねりへつらう。「便佞」は、口先はうまいが、心はねじけているさま。 |
| 暗雲低迷 | アンウンテイメイ |
今にも雨が降り出しそうな場合のように危険なよくないことが起こりそうな気配。不穏な情勢。 |
| 安居楽業 | あんきょらくぎょう | 居所、地位も安定し楽しく仕事をしているさま。居に安んじ業を楽しむ。 |
| 晏子之御 | アンシノギョ | 低い地位に満足して得意がる小人物。また、主人の権威を笠にきて威張ることのたとえ。虎の威をかる狐のような人物。 |
| 安心立命 | アンシンリツメイ |
天命に身を任せて心を動かさず、煩悶もないこと。いかなる場合にも心が落ち着いていること。信仰によって天命を悟り、心を安らかにして悩まないこと。 |
| 安宅正路 | アンタクセイロ |
仁と義のこと。仁は人の安全な住居であり、義は人の正しい通路であるという孟子の言葉。 |
| 暗中飛躍 | あんちゅうひやく | 人に知られないように秘密のうちに策動・活躍すること。 |
| 暗中模索 | アンチュウモサク | 闇の中を、手探りで物を捜し求めるという意味で、手がかりのないものをいろいろと探ってみるようすをいう。むやみやたらに探し求めること。暗闇の中で、手探りでものを探すこと。手がかりもなく手探りの状態。 |
| 安如泰山 | あんにょたいざん | 泰山は山東省にある名山。泰山のように微動だにしない安定したさまをいう。 |
| 安穏無事 | あんのんぶじ | 穏やかで、事件や事故などがないこと。 |
| 安寧秩序 | アンネイチツジョ | 世の中が平穏で公共の安全や社会の秩序が保たれていること。やすらかな状態。世の中が平穏で、公共の安全や社会の秩序が、やすらかに保たれていること。 |
| 安楽浄土 | アンラクジョウド |
現実の世界のような苦悩はなく、一切の心配やけがれなどもなく、安心して楽しく生活できる清浄な国土。 |
| イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部金吉 | いしべけんきち | 石と金と二つの堅いものを並べた擬人名。道徳的に堅固で、金銭や女色に心を迷わされない人。また、物堅くきまじめ過ぎて、融通のきかない人。男女間の情愛などを解しない人。かたぞう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逸失利益 | いっしつりえき | 事故に遭わなければ、手に入れていたはずの収入や利益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因果応報 | インガオウホウ | よい行いをした人には良い報い、悪い行いをした人には悪い報いがある。過去および前世の因業に応じて果報があるという意。一つの行いにはそれにふさわしい報いが必ずあるということ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因果関係 | いんがかんけい | 結果と原因の間に何らかの関係があること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因機説法 | いんきせっぽう | その場その場に対応して仏法の真理を悟らせようとする説法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因循守旧 | いんじゅんしゅきゅう | 旧習を守って改めようとしないこと。しきたりどおりにして改めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因小失大 | いんしょうしつだい | 目先の小利をむさぼって大利を失う。小に因(よ)りて大を失う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因循姑息 | いんじゅんこそく | 古い習慣にしたがって改めず、また、一時しのぎに間に合わせのやりかたをすること。また、消極的でぐずぐず迷っている様子。保守的で消極的なこと。古い習慣にとらわれたりなどして、その場しのぎのけちなやり方でことを運ぼうとすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 員淵方井 | いんえんほうせい | 四角い天井に丸い淵を描く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰々滅々 | いんいんめつめつ | 非常に暗くて陰気な様子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰徳陽報 | イントクヨウホウ | 人知れず善行を積めば、必ずよい報いとなって現れてくるという意味。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰謀詭計 | インボウキケイ | 密かにたくらむ悪だくみと人をあざむく計略策謀。「詭」はいつわりあざむく意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠晦曲折 | いんかいきょくせつ | 言い方が遠回しではっきりしない。回りくどくて、わかりにくい言い方、表現のたとえ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠姓埋名 | いんせいまいめい | 姓名を隠し、偽名を使って世渡りすること。また、改名したりして他郷に逃亡するたとえ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠忍自重 | いんにんじちょう | 我慢して軽々しい行動をしないこと。よくいえば慎重、悪くいえば引っ込み思案。ひたすら堪え忍んで軽々しい行動を慎むこと。慎重であること。「隠忍」は、「おんにん」とも読み、じっと我慢すること。「自重」は、自分の行動を慎むこと。別に自分の体を大切にする意味に使われる場合もある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允文允武 | いんぶんいんぶ | まことに文、まことに武の意味で、天子に文武の徳が兼ね備わっていることを褒め称える言葉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲灰洗胃 | いんかいせんい | 胃袋の中の汚いものを灰で洗い清めるように、自分の過去を悔い、心を改めて出直すこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲河之願 | いんかのねがい | 自分の願望が少ないこと。自分の分に安んじることをいう。もぐらが黄河の水を飲もうと思っても、腹がふくれる程度にしか飲むことができないということ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲河満腹 | いんがまんぷく | 自分の身分をわきまえ、安らかに暮らすさま。どぶねずみは広大な黄河の水を飲んでも腹をいっぱいにする以上は飲めない。人には、それぞれ定まった分があるのだから、それに満足しなければいけないという例え。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲水思源 | いんすいしげん | 水を飲んで“ああ美味かった”とその流れの水源に思いをはせるように、いつも物事の根本を忘れぬこと。 今の幸いを考え、恩人に感謝すること。“水を飲みて源を知る”ともいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引据剪裁 | いんきょせんさい | 古人の文章を切り取ってつなぎあわせること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引喩失義 | いんゆしつぎ | つまらない前例やたとえを引いて正しい本来の意義を見失うこと。良くない先例をひいて正しい道を踏み外す意にも用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽喉之地 | いんこうのち | 戦略的に見て、国の一番重要な土地をいう。人間の体でいう急所「のど、くび」にたとえた言葉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婬虐暴戻 | いんぎゃくぼうれい | 女色に溺れ、暴虐で人倫を乱すこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韻鏡十年 | いんきょうじゅうねん | 漢字、漢文の音韻学は非常にむずかしく、音韻の研究書「韻鏡」を十年引いても難解ということ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殷鑑不遠 | いんかんふえん いんかんとおからず |
いんかんとおからず。鑑(かんが)みる戒めは、すぐ手近にあるというたとえ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慇懃無礼 | インギンブレイ |
言葉や物腰が丁寧すぎて、かえって礼儀にはずれていること。丁寧な態度に反して尊大。丁寧すぎてかえって無礼になること。丁寧なようで実は無礼なこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | ||
| 有為転変 | ウイテンペン |
仏教の教えで、この世の現象はすべてとどまることなく移り変わっていくものだということ。無常ではかないこと。世の中のうつろいやすいことをいう。世の中は常に変化し、ひとところにとどまるものはないこと。 |
| 有為無常 | ういむじょう | この世の現象は因縁によって生じたものであるから、常に移り変わるものだ。 |
| 有卦七年 | うけしちねん | 幸運の年まわり。有卦に入ること。ついていて調子のいいたとえ。有卦に入れば吉が7年、無卦に入ると凶が5年続くという。 |
| 有相執著 | うそうしゅうじゃく | 形ある現象の姿にとらわれる心。それらが一切皆空であることを悟らないで執着心を起こすこと。 |
| 有象無象 | うぞうむぞう | つまらない人のことを賎しむ語。世の中の様々なくだらないもののこと。すべてのもの。またたくさん集まった人たち。 |
| 有智高才 | うちこうさい | 生まれつき頭の働きがよく、学習によって得た才能も優秀なさま。またはその人。 |
| 有頂天外 | うちょうてんがい | 有頂天を極め、さらにその上の状態。 |
| 右往左往 | うおうさおう | 右へ行ったり左へ行ったりするように、うろたえ、混乱する様子。混乱している状態のこと。大勢が右に行ったり左に行ったりすること。 |
| 如魚得水 | うおのみずをえたるがごとし | 水を得た魚のように、自分がかねて考えていた理想の人に会う、またふさわしい環境を得て、思うようにはつらつと活躍すること。 |
| 魚游釜中 | うおふちゅうにおよぐ | 釜の中で泳いでいる魚がまもなく煮られ死ぬことも知らないでいる。最悪の事態も知らぬこと。 |
| 羽化登仙 | うかとうせん | 酒などに酔い、良い気分になることのたとえ。人間に羽が生え、仙人となって天に昇ること。中国の古い信仰による。 |
| 羽翼既成 | うよくきせい | 物事の組織や基礎ができあがり、いまさら動かしようのないさまをいう。 |
| 浮草稼業 | うきぐさかぎょう | 軽がると場所を変えて、落ち着かない職業。または生活。 |
| 右顧左眄 | うこさべん |
右か左か決めかねて迷うように、人の思惑などまわりのことばかり気にして決断をためらうこと。なかなか決心のつかないこと。(右を見たり左を見たりして)。=左顧右眄 |
| 禹行舜趨 | うこうしゅんすう | 夏の禹王や虞舜のような聖人の動作だけを見習って、その聖人である実質、すなわち学問・人格のないことをいう。趨は小走りに走ること。 |
| 烏焉魯魚 | うえんろぎょ | 文字の書き誤り |
| 烏獲之力 | うかくのちから | 大力をいう。烏獲は秦の武王に仕えた勇士の名で、よく千鈞の重さを持ち上げたという。 |
| 烏合之衆 | うごうのしゅう | カラスの群れ、集まりのように、規律も統制もない大勢の人の寄り集まり。また、そのような軍隊や、群衆。 |
| 烏集之交 | うしゅうのまじわり | 偽りが多く、真実のない交わり。 |
| 烏孫公主 | うそんこうしゅ | 政略結婚の犠牲、またそれによって悲運に泣く女のこと。 |
| 烏鳥私情 | うちょうのしじょう | 親孝行をしたいという気持ちをへりくだっていう言葉。カラスはひなの時に養われた恩を成長してから返す親孝行な鳥とされている。 |
| 烏兔怱怱 烏兎匆匆 |
うとそうそう | 月日が流れるのは早いということ。 |
| 烏白馬角 | うはくばかく | カラスの頭が白くなり、馬に角が生じるというような、全くありえないこと。 |
| 烏飛兔走 | うひとそう | 歳月がたつのが、あわただしく速いこと。烏は太陽、兔は月。 =兔走烏飛 |
| 烏有先生 | うゆうせんせい | 実在しない架空の人物。前漢の文人司馬相如がその文中で仮に設けた人名。 |
| 雨過天晴 | うかてんせい | うっとうしい雨が止んで青空が広がる。悪い状況が好転するたとえ。 |
| 雨奇晴好 | うきせいこう | 晴れても雨でも、どちらも素晴らしい景色で、趣があるという意。晴好雨奇とも書く。 |
| 雨後春筍 | うごしゅんじゅん | ひと雨降った後に沢山生え出るタケノコのように数が多いこと。事物が増えるのが速くて勢いが盛んなたとえ。 |
| 雨絲煙柳 | うしえんりゅう | 春雨に霞む柳、しとしとと降り続く春雨に、柳も煙って見える。春の風情を語った成句。 |
| 雨絲風片 | うしふうへん | 糸のように細かな春の雨に、かすかな風。春のさかりに霞む天地のたゝずまいはまるで秋の終りのような情景である。「十日の雨の糸、風片の裏、濃春の煙景は残秋に似たり」と、春を詠んだ七言絶句の一節からとった語句。 |
| 雨笠煙蓑 | うりゅうえんさ | 煙雨を帯びた笠とみの。漁父などの形容。 |
| 雨鈴鈴曲 | うりんれいきょく | 亡き妻をしのぶ曲。唐の玄宗が愛する楊貴妃をやむなく殺したのち、楊貴妃を悼んで作った楽曲。 |
| 雨露霜雪 | うろそうせつ | 日常生活における様々な困難や苦労。 |
| 内股膏薬 | うちまたこうやく | 自分の考えがはっきりせず、どっちつかずの人のこと。内股についた膏薬はあちこちについて困ることから。「うちまたごうやく」とも読む。 |
| 迂直之計 | うちょくのけい | 実際的でないように見えて、実は最も現実的で効果のある計略のこと。わざと迂回して敵を安心させ、妨害のないのに乗じ先に到着する戦法。 |
| 鵜目鷹目 | うのめたかのめ | 鵜が魚をあさり、鷹が獲物をさがすように、人が熱心に物を探し出そうとするさま。 |
| 孟方水方 | うほうすいほう | 四角な容器に水を入れると、水も四角になる。このように上に立つ人の行いを下の人もまねることのたとえ。 「孟」は飲み物を入れる碗、器、「方」は方形。君を孟に、民を水にたとえたことば。 |
| 海千山千 | うみせんやません | 「海に千年、山に千年住んだヘビは天に上って竜になる」に由来し、一筋縄ではいかない経験豊富でしたたかなやりかた。あらゆる経験をしてきた、わるがしこい人を言う言葉。 |
| 梅木分限 | うめのきぶげん | 梅ノ木は成長が早いが大木にならないことから、成り上がりの金持ち。にわか長者のことをいう。 |
| 有耶無耶 | うやむや | あるのかないのかはっきりしないこと。いいかげんなこと。どちらつかずではっきりしないさま。いいかげんではっきりしないこと。 |
| 紆余曲折 | うよきょくせつ | 経てきた事情などが、ひとことで言えないほど曲がりくねっていて複雑で厄介なこと。物事が、結果に至るまでにこみいって変化の多い経過をたどること。 |
| 雲煙過眼 | うんえんかがん | 雲や霞がたちまち目の前を通り過ぎるように、その場限りで、心にとめないこと。 |
| 雲煙変態 | うんえんへんたい | 雲やかすみが千変万化して趣をなすこと。 |
| 雲烟飛動 | うんえんひどう | 雲やかすみが飛動するように筆勢が躍動する文字のたとえ。書道でいう「草書」の自由自在な筆の運びにたとえる。 |
| 雲外蒼天 | うんがいそうてん | 困難を乗り越え、努力して克服すれば快い青空が望めるという意味。絶望してはいけないという激励の言葉。 |
| 雲行雨施 | うんこううし | 「雲行き雨施す」。空は雲が悠々と流れ、やがて散じて雨となり、地方万物に恩思を施す意。 |
| 雲合霧集 | うんごうむしゅう | 雲や霧があっという間にたちこめるさま。多くのものが一時にどっと群れ集まること。 |
| 雲散鳥没 | うんさんちょうぼつ | 雲のように散って鳥のように跡形もなく姿を消すこと。 |
| 雲消霧散 | うんしょうむさん | 雲のように消え霧のように散りうせる。跡形もなく消えうせることの形容。 |
| 雲散霧消 | うんさんむしょう | 雲や霧が消え去るように、物事が跡形もなく消えてしまうこと。ちりじりに消えてしまうこと。 |
| 雲集霧散 | うんしゅうむさん | 雲が集まり、霧が晴れるように、集まったものが消えてしまうこと。 |
| 雲蒸龍変 | うんじょうりゅうへん | 雲がわきあがり、龍がそれに乗って不思議な働きをする。英雄・豪傑が機会を得て世に出て、活躍するたとえ。 |
| 雲心月性 | うんしんげっせい | 無私無欲の例え。物にとらわれない雲のような心と、澄みきった月のような本性。名誉や利益を求めることなく超然としていること。 |
| 雲水飛動 | うんすいひどう | 雲や水の飛び動く意味で、山水画の妙を窮め真に迫ることをいう。 |
| 雲中白鶴 | うんちゅうはっかく | 雲間を優美な姿で飛翔する白鶴のイメージから、品性の優れた高尚な人物、婦人をさす言葉。 |
| 雲泥之差 | うんでいのさ | 天の雲と地の泥の差。極めてかけ離れていること。 |
| 雲泥万里 | うんでいばんり | 天と地が遠く隔たっているほどに、二つのものの差が大きいこと。極端に違うもののたとえ。 |
| 雲竜風虎 | うんりゅうふうこ | 雲は龍に従い、風は虎に従う。 |
| 運斤成風 | うんきんせいふう | 大工の凄腕。転じて、見事な工作。他人に詩文の添削を頼むこと。 |
| 運否天賦 | うんぷてんぷ | 人の幸運や不運は、天によって定められ、与えられること。また、運を天に任せること。運を天にまかせること。運命のよしあしは天が決めるということ。「運否」は、幸運と不運。「天賦」は、天が与えるという意。 |
| エ | ||
| 栄位勢利 | えいいせいり | 名誉と地位と権力と利益。 |
| 盈盈一水 | えいえいいっすい | 愛する人と直接に会えないつらさ、清々とあふれる川の水に隔てられて再会できない彦星と織姫伝説による。 |
| 永永無窮 | えいえいむきゅう | 長く続いてきわまりないこと。 |
| 永遠不変 | えいえんふへん | いつまでも変わらないこと。 |
| 永遠不滅 | えいえんふめつ | いつまでも滅びないこと。 |
| 永遠無窮 | えいえんむきゅう | いつまでも続いて、極まりがないこと。 |
| 影駭響震 | えいがいきょうしん | 影を見ただけで驚き、ひびきを聞いただけでふるえる。ちょっとしたものにも驚く。(= 風声鶴唳) |
| 栄華之夢 | えいがのゆめ | 華やかに世を過ごしている自分を見た夢。また、栄華の儚さを、夢に喩えて言う。 |
| 英華発外 | えいかはつがい | 物事のすぐれた美しさが表面に現れること。すぐれた詩や文章、名誉、ほまれの意。 |
| 栄枯窮達 | えいこきゅうたつ | 栄えることと衰えること、また困窮することと栄達すること。 |
| 栄枯盛衰 | エイコセイスイ えいこせいすい |
人や組織の隆盛と衰退は必ず交互にやってくるものだ~~~という、 歴史的に実証された事実。栄えたり衰えたりすること。また、今栄えているものでも、いつかは衰えるときがくる、という人生の無常を表すときにも用いる。人や組織の隆盛と衰退は必ず交互にやってくるものという意。 |
| 栄耀栄華 | エイヨウエイガ えいようえいが |
富や地位を得て、繁栄し得意になること。転じて驕り・贅沢を尽くすこと。華やかで贅沢なこと。また、おごりたかぶること。「栄耀」は、「えよう」とも読み、権力を得て富み栄えるもの。「栄華」も、財力や権力を得て華やかに栄えること。 |
| 永劫回帰 | えいごうかいき | 宇宙は永遠に循環運動を繰り返すものであるから、人間は今の一瞬一瞬を大切に生きるべきだ、とするドイツの哲学者ニーチェの根本思想。物事は永遠に同じ事の繰り返しである、ということ。 |
| 英姿颯爽 | えいしさっそう | きりっと引き締まって、いかにもりりしく勇ましいさま。きびきびとして勢いのある様子。 |
| 英俊豪傑 | えいしゅんごうけつ | 多くの人にすぐれている人物。英雄。豪傑。 |
| 英明果敢 | えいめいかかん | 才知に優れ、道理に明るくしかも思い切りのいいこと。 |
| 英雄豪傑 | えいゆうごうけつ | 優れてえらく強い人のこと。 |
| 英雄好色 | えいゆうこうしょく | 英雄は女性を好む性向にある。女性を好むことの弁護としても用いる。 |
| 郢書燕説 | えいしょえんせつ | 理屈に合わないことをそれらしく説明すること。 |
| 詠雪之才 | えいせつのさい | 文才のある女性を褒め称えて言う言葉。 |
| 盈満之咎 | えいまんのとが | 満ちれば欠ける。何事も満ち溢れるほどになるとかえって禍いを招くという戒め。 |
| 益者三楽 | えきしゃさんごう | 有益な三つの楽しみ。第一に礼楽に親しみ調和のとれた暮らし。第二に人の美点を話題にする。第三は立派な友を多く持つこと。 |
| 益者三友 | えきしゃさんゆう | 真の友人とは、剛直、誠実、教養である。→損者三友。 |
| 易姓革命 | エキセイカクメイ | 王朝がかわることをいう。 |
| 役夫之夢 | えきふのゆめ | 人生の栄華は夢のようにはかないものというたとえ。転じて、欲求不満を夢で補うこと。 |
| 廻向発願 | エコウホツガン |
自らが積んだ功徳(善行)を人々や他のものに振りむけて、浄土に生まれようと願う心を起こすこと。仏事法要を営んでその功徳が死者の安穏をもたらすように期待すること。 |
| 依怙贔屓 | えこひいき | 一方だけにひいきすること。不公平。 |
| 会者定離 | エシャジョウリ | 会う者はかならず、離れる。人の世の無常をいう言葉。別れは必ずくるということ。この世で出会ったものには生別、死別を問わず、必ず分かれるときがくる定めであるということ。 |
| 越俎之罪 | えっそのつみ | 自分の職分を超えて他人の仕事に干渉する罪。 |
| 越鳥南枝 | えっちょうなんし | 南から来た越の国の鳥は少しでも故郷に近い南側の枝に巣を作るように、鳥でも故郷を忘れがたいというたとえ。 |
| 得手勝手 | えてかって | わがままなこと。他人の気持ちや立場を尊重しないで、自分だけに都合のいいように行動すること。「得手」は、勝手気ままなこと。 |
| 烏帽子親 | エボシオヤ |
武家の男子の元服の祝儀で、親に代わって烏帽子をかぶらせ、烏帽子名をつける有力者。 |
| 援護射撃 | えんごしゃげき | ①敵の攻撃から味方を守るために行う射撃。 ②当事者でない者が、他の人の言動を助けるために発言したり行動したりすること。 |
| 縁木求魚 | エンボクキュウギョ |
「木に縁(よ)って魚を求む」~誤った手段では目的が達成できない。不可能なたとえ。 |
| 円滑洒脱 | えんかつしゃだつ | 物事の進行をそつなくこなす様子。 |
| 円転滑脱 | エンテンカツダツ | 人と争わずにうまく物事を運ぶ。かどが立たない。人と衝突しないようにうまくやる様子。 |
| 円熟無礙 | えんじゅくむげ | 人格・知識・技術などが、これ以上ないほどに熟達していること。 |
| 円満具足 | エンマングソク | 充分に満ち足りて不足のないこと。転じて人柄に欠点がなく温厚な様子を言う。 |
| 遠交近攻 | えんこうきんこう | 遠くの国とは親しくして、近くの国を攻める。 |
| 燕雀鴻鵠 | えんじゃくこうこく | 小人物には大人物の遠大な心がわからないこと。もとは、燕や雀のような小鳥には鴻や鵠という大きな鳥の遠大な心はわからないという意。「鴻鵠」は、おおとりとくぐい。どちらも大きな鳥のこと。 |
| 燕雀相賀 | えんじゃくそうが | 新居の落成を祝う言葉。燕と雀は人家に巣を作るので新しい家が完成すると、ともに喜ぶということ。 |
| 猿猴取月 | えんこうしゅげつ | 猿たちが樹下の井戸の水に映った月をとろうと、手や尻尾を繋いでぶら下がったところ、 木の枝が折れて溺れ死んだという故事。実現不可能なことをして身を滅ぼすたとえ。「猿猴月を捉う」ともいう。=猿狗捉月(えんこうそくげつ) |
| 遠水近火 | えんすいきんか | 遠い所にあるものは急場の役には立たないということ。「遠水、近火を救わず」 |
| 遠走高飛 | えんそうこうひ | 高飛びする。遠方へ逃げること。苦境を脱して明るい道を求める意味もある。 |
| 猿臂之勢 | えんぴのいきおい | 軍の進退攻守を自由にすること。 |
| 縁木求魚 | えんぼくきゅうぎょ | 「木に縁(よ)って魚を求む」。誤った手段では目的が達成できない。不可能なたとえ。 |
| 延喜之治 | えんぎのち | 醍醐天皇の時代。延喜はその年号。よく治まったので善政の模範としていう。 |
| 延頸鶴望 | えんけいかくぼう | 首を鶴のように長く伸ばして相手を待ち望むさま。切実に待望する気持ち。今か今かと待つ。 |
| 延命息災 | えんみょうそくさい | 寿命を延ばし、災いを除くこと。「息災」は、災難や病魔を仏の力で退散させること。また、元気なこと。「延命」は、「えんめい」とも読む。 |
| 鳶目兎耳 | えんもくとじ | トビの目のようによく見える目とウサギの耳のようによく聞こえる耳 |
| 遠慮会釈 | えんりょえしゃく | 相手に対する思いやりのこと。他人に対して態度を慎みその心を思いやること。「会釈」は、他人の気持ちを思いやることで、斟酌(しんしゃく)のこと。 |
| 遠慮近憂 | エンリョキンユウ |
よく先のことまで考えて行動しないと、必ず急な心配事が起こって苦しむことになるという孔子の言葉。行き当たりばったりの行動を慎しみなさいということ。先のことを考えた対策を立てずに方針のない暮らしをしていると早晩困ることになるということ。「遠慮」は遠い将来を見通す思慮を持つこと。「遠き慮(おもんぱか)り無ければ、必ず近き憂い有り」という孔子の言葉に基づく。 |
| 鴛鴦之契 | えんおうのちぎり | 夫婦が仲睦まじいこと。永遠に付き合うという約束。 |
| オ | ||
| 桜花爛漫 | おうからんまん |
桜の花が満開になって咲き乱れているようす。
|
| 奥義秘伝 | おうぎひでん |
学芸・武術などで、容易には人に伝えない奥深くて最も大切な事柄。
|
| 応急措置 | おうきゅうそち |
急を要する時に、間に合わせとして行うさしあたっての処置。
|
| 応急手当 | おうきゅうてあて | 緊急の場合に、さしあたって行う処置。 |
| 横行闊歩 | おうこうかっぽ | いばって歩き回る。思いのままに振る舞う。 |
| 横行覇道 | おうこうはどう | 権勢をたのんで横暴な振る舞いをする。力づくで無理を通し、のさばりかえること。 |
| 王侯将相 | おうこうしょうしょう | 勢力のある人々をいう。本来は「王侯将相、寧ぞ(いずくんぞ)種あらんや」で、王侯や将軍・大臣となるのは、家系や血統によるのではないから、どんな人でも努力や運によって栄達できる意で用いられる。「王侯」は、王と諸侯のこと。「将相」は、将軍と大臣のこと。 |
| 王公大人 | おうこうたいじん | 身分の尊い人。 |
| 王佐之材 | おうさのざい | 帝王を助けることのできる才能。 |
|
王政復古 |
おうせいふっこ | 武家政治や共和制が廃止されて、もとの君主政治にもどること。明治維新がその例。 |
| 王道楽土 | おうどうらくど | 王道によって治められる、楽しく平和な国土。 |
| 黄金時代 | おうごんじだい | 理想的な最良の時代。また、最も盛んな時代。 |
| 黄金分割 | おうごんぶんかつ | 小部分と大部分の比例が、大部分と全体の比に等しくなるように分割すること。大と小の比率は1.618 対 1。 |
| 懊悩煩悶 | おうのうはんもん | 悩みもだえて苦しむこと。煩悶懊悩(はんのうおうもん)。 |
| 大盤振舞 | おおばんぶるまい | 気前よく盛大に人に物を与えたり、ご馳走をふるまったりすること。盛大にもてなすこと。気前よく人に食事や金品をふるまうこと。「大盤」は当て字で、椀盤(おうばん)と書く。(要注意:椀盤は「おお」ではなく、「おう」とよむ。)「わんはん」が転じたもので、椀にもった飯から、人をもてなす為の食膳の意となった。 |
| 応病与薬 | おうびょうよやく | 病気の種類に応じて最も適した薬を与えること。人に応じて法を説くたとえ。 |
| 大風呂敷 | おおぶろしき | 誇張していうこと。~を広げる=ほらをふくこと。 |
| 横目之民 | おうもくのたみ | 人民。人の目は横になっているからいう。 |
| 岡目八目 | おかめはちもく | 碁を見物していると、対局者よりもずっと先の手まで見越して形勢が読める。転じて、傍観者のほうが当事者よりもかえって物事の状況がよくわかることを言う。当事者よりも第三者の方が事の善し悪しなどがよく見えて正確な判断が出来ることのたとえ。傍目は、岡目とも書く。 |
|
屋上架屋 |
おくじょうかおく |
屋根の上にまた屋根を作るという意で、重複して意味のないことを繰り返すたとえ。 |
| 億万長者 | おくまんちょうじゃ | 非常に多くの金や財産を持っている人。大金持ち。 |
| お墨付き | おすみつき | 封建時代の君主が家臣や家来に与えた黒印付きの文書に由来している。これを貰えば記述のことが必ず保証されるという有り難い証書。 |
| 小田原評定 | おだわらひょうじょう | 戦後時代の北条家の家臣団が豊臣秀吉の軍勢に対処する為に小田原城で繰り広げた「いつまでもまとまらない相談」のことから由来。 |
| 鬼に金棒 | おににかなぼう | ただでさえ強い鬼に、強力な武器である金棒を持たせると、さらに強くなる。もともと強い者に何かが加わって、さらに強力な者になることのたとえ。また、すぐれた者に似つかわしいものが加わって一段と引き立つことのたとえ。 |
|
汚名返上 |
おめいへんじょう | 以前の失敗などで受けた不名誉を、自分の力で取り除くこと。 |
|
温厚質実 |
おんこうしつじつ | 穏やかで優しく、飾り気がなくて誠実なこと。 |
|
温厚篤実 |
おんこうとくじつ | 性格が穏やかで情に厚く、誠実であるようす。やさしくて人情に厚くまじめなこと。「篤実」は、人情に厚く、物事に忠実で正直な意。 |
| 温故知新 | おんこちしん | 古きを温め、新しきを知る。経験のない新しいことを進めるにも、過去を充分学ぶことから知恵を得ようということ。前に学んだことを復習、研究して新しい知識を得ること。故(ふる)を温(たず)ね新しきを知ると読む。英訳・He that would know what shall be must consider what has been. 将来の事態を知りたいものは、過去の歴史を考察しなければならない という意味。 |
| 温柔敦厚 | おんじゅうとんこう | 穏やかでやさしく、情が深いこと。もと、孔子が儒教の基本的な古典で、中国最古の詩集である詩経(しきょう)の教化の力を評した語。詩経の詩篇は古代の純朴な民情が素直に歌われたもので、人を感動させ、教化する力をもっていると説いたもの。「温柔」は穏やかで柔和なこと。「敦厚」はねんごろで人情深いこと。 |
|
音信不通 |
おんしんふつう | 便りや連絡が絶え、まったく様子がわからないこと。便りがないこと。交際や訪れが途絶えていること。「音信」は、「いんしん」とも読む。「音」も「信」も便りのこと。 |
|
音吐朗朗 |
おんとろうろう | 音声が明瞭、声量が豊かで響きわたるようす。音量がゆたかでさわやかなさま。「音吐」は声の出し方。詩歌を吟じたり詩や文章を朗読したりする声。 |
| 乳母日傘 | おんぼひがさ | 乳母が抱き、日傘をさしかけるように大切に、恵まれた環境で子供を育てること。 |
|
厭離穢土 |
おんりえど | 煩悩に汚れた、悪の多いこの世を嫌い、離れてしまうこと。この世を煩悩に汚れたものとして嫌い、はなれること。 |
|
怨霊怪異 |
おんりょうかいい |
怨みを抱いて死んだ者の霊が、それをはらそうとして引き起こす怪奇な現象。また、その霊が化け物となったものをいう。
|
![]()