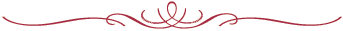一族とともに生きた北条氏の長老軍師〜北条幻庵
天正十七年(1589年)11月1日、戦国時代の関東に君臨した北条氏の長老&ご意見番、北条幻庵が97歳で亡くなりました。
・・・・・・・・・・・
戦国時代、約100年に渡って関東を牛耳る北条氏(ほうじょうし=鎌倉時代の北条氏と区別するため後北条氏とも)・・・その祖となる北条早雲(ほうじょうそううん)こと伊勢盛時(いせもりとき)の末っ子=四男として明応二年(1493年)に誕生した(誕生年には諸説あり)とされる北条幻庵(ほうじょうげんあん)は諱(いみな=実名)を長綱(ながつな)、法名を宗哲(しゅうてつ)と言いますが、隠居後に名乗った幻庵の名前が有名なので、本日は幻庵さんと呼ばせていただきます。
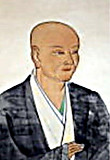 そんな幻庵は、幼くして近江(おうみ=滋賀県)の三井寺(みいでら=滋賀県大津市)に入寺し、大永四年(1524年)に出家し、箱根権現(はこねごんげん=神奈川県)を祀る箱根権現社(後の箱根神社)の別当寺(べっとうじ=神社を管理するための寺)である金剛王院(こんごうほういん)に入りました。
そんな幻庵は、幼くして近江(おうみ=滋賀県)の三井寺(みいでら=滋賀県大津市)に入寺し、大永四年(1524年)に出家し、箱根権現(はこねごんげん=神奈川県)を祀る箱根権現社(後の箱根神社)の別当寺(べっとうじ=神社を管理するための寺)である金剛王院(こんごうほういん)に入りました。
なんせ、この箱根権現は山岳信仰の中心的存在で、あの源頼朝(みなもとのよりとも)以来関東武士の守り神として崇められていて、大きな力も持ってますから、そこに息子を送り込んでおけば何かと有利・・・なので、当然ですが幻庵本人ではなく、父親の思惑ドップリの出家だったわけですが、そのおかげで、幻庵は、他の兄弟たちとは・・・いや、多くの戦国武将の中でも、かなり特異な立場の人物となるのです。
それは北条一門の武将でありながら箱根権現別当金剛王院の院主(いんじゅ=住職・寺の主)=僧侶であるという事・・・
もちろん、武将ですから、馬術や弓にも長け、合戦の記録も複数あるわけですが、何と言っても他者を寄せ付けないほどトップクラスだったのは和歌や連歌、茶道に築庭、さらに、見事な鞍を作ったり、石工や弓細工などなどの芸術的才能です。
中でも、連歌師の宗牧(そうぼく)とは三井寺での修行時代からの友人で、彼が小田原(おだわら=神奈川県小田原市)にやって来た時には国境まで出迎えて歓待し、連歌会を催したりしています。
そう・・・こういう芸術的お付き合いが非常に重要なんです。
連歌師という人は、歌を作るだけでなく、その指導もするわけで、指導する相手には武将もいれば公家もいる・・・それも全国各地に・・・
宗牧の場合など、公家の三条西実隆(さんじょうにしさねたか)の邸宅や摂関家の近衛家(このえけ)にも出入りし、第105代・後奈良天皇(ごならてんのう)と尾張(おわり=愛知県西部)の織田信秀(おだのぶひで=信長の父)の間を取り持った記録も残っています。
このような独自の人脈を持つ連歌師は、複数の公家や戦国武将の間を自由に行き来し、近隣の情報を得て来てくれるわけです。
もちろん、それは情報を得ると同時に発信する事も可能・・・
たとえば、越前(えちぜん=福井県東部)の朝倉宗滴(そうてき)の回顧録には
「『北条早雲は、普段はめっちゃケチで金を使おうととせんけど、合戦の時には惜しみなく戦費を投入するらしい』という事を連歌師の柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)から聞いた」
という話が登場しますが、この宗長という人は宗牧の師匠にあたる人・・・なので、情報は、「北条は強いんやゾ!なめんなよ」てな、けん制の意味を込めて、おそらくは意図的に幻庵から宗牧&宗長を通じて朝倉へと流された物?
しかも幻庵は、推定97歳という長寿を全うした事により、結果的に、初代の北条早雲から氏綱(うじつな=早雲の長男)→氏康(うじやす=氏綱の長男)→氏政(うじまさ=氏康の次男)→氏直(うじなお=氏政の長男)の北条5代(【北条五代の年表】参照>>)に仕える事になりますから、まさに北条家の諜報機関のトップ・・・半分武将で半分僧侶という立場で様々な情報を得て、その情報で以って北条家を支えていたわけです。
逆に、他家へ嫁ぐ娘に贈るために書いた『幻庵覚書(幻庵おほへ書)』では、女性としての礼儀作法や心得とともに
「僧侶や芸能関係者をむやみやたらに近付けたらアカンぞ!」
と、いかにも自分がアブナイ事やって来たからこそのアドバイス感満載な事を言っちゃってます。
(若い時に暴れまくってたヤンキー父ちゃんも、娘には、そんなヤツに引っかからんといて欲しいみたいな?www)
ちなみに、長男を早くに、次男&三男を武田(たけだ)との合戦で亡くした幻庵は、もう一人の娘に氏康の三男を婿養子に迎えて、自身の後継者としていましたが、北条と上杉の同盟のためにその三男は越後(えちご=新潟県)へと行く事になり、娘さんとは離縁・・・その彼が御館(おたて)の乱で自害する上杉景虎(うえすぎかげとら)です(3月17日参照>>)。
とにもかくにも、その稀にみる才能で芸術家や公家との交流し、情報を集め、その情報を北条家の戦略に活かしていく・・・一見穏やかに芸術を楽しんでいるように見えるその姿は、ある意味、一騎当千の荒武者より怖い存在だった事でしょう。
現に、約100年に渡って関東に君臨した北条は、彼の死から半年余りで滅亡する事となります。
幻庵が亡くなったのは天正十七年(1589年)11月1日・・・享年97。
そのわずか23日後に北条が起こした真田とのトラブル(10月23日参照>>)を理由に、豊臣秀吉(とよとみひでよし)が宣戦布告(11月24日参照>>)し、あの小田原征伐(おだわらせいばつ)が開始されるのです(12月10日参照>>)。
やはり幻庵の死によって、北条の「何かが外れた感」が否めませんね〜
ただ、冒頭にも書かせていただいたように、幻庵さんの誕生年も諸説ありますし、亡くなった日付も現在では疑問視する声も出てきていますので、そうなると享年の97歳ってのもあやしくなって来るのですが、初代の早雲の息子でありながら、天正八年(1580年)に5代目の氏直が当主になってから後も、しっかりと活躍している記録が残っていますので、97歳でないとしても、かなりの長寿であった事は間違いなさそう・・・まさに、北条家とともに生き、北条家とともに去っていったと言えますね。
・‥…━━━☆
ところで、ここからは、
この幻庵さんの97歳という年齢に関連して、私個人が少々気になっている事。
幻庵さん以外にも、
先ほどの朝倉宗滴が79歳(8月13日参照>>)、
他にも、
毛利元就(もうりもとなり)=75歳(11月25日参照>>)、
細川幽斎(ほそかわゆうさい=藤孝):77歳(8月20日参照>>)、
藤堂高虎(とうどうたかとら)=75歳(6月11日参照>>)、
本多正信(ほんだまさのぶ)=79歳(9月5日参照>>)、
大久保彦左衛門(おおくぼひこざえもん)=80歳(2月1日参照>>)
などなど、ご高齢で活躍された方がけっこういてはります。
確かな統計が無いので、あくまで予想の範囲=「そうのように考えられている」というデータではありますが、戦国時代の平均寿命は37歳くらいだったとされています。
で、この方たちが話の中に出て来ると、よく言われるのは、
「平均寿命が37歳くらいの頃に80代や90代なんて、かなりのご長寿」
てな事。
もちろん、80代&90代なら、今現在でもご長寿なのですから、これに関しては正解なのですが、気をつけねばならないのは、
「平均寿命が37歳なら、50代くらいでお年寄り=お爺ちゃんの部類に入るんじゃないの?」
あるいは、
「平均寿命が37歳なら、そんくらいで死んでしまう人がたくさんいたのでは?」
という解釈をしてしまう場合がある事です。
ご存じのように、現在の日本人の平均寿命は男性=81歳、女性=87歳で、街中を歩いていても、そのくらいのお年寄りが元気に闊歩しておられますから、「平均寿命」という言葉を聞いて、その言葉通り「普通にしていたらそんくらいまで生きられる年齢」と思ってしまいますが、
実はコレ、「新生児&子供の死亡率が激減した現在」の感覚です。
ほんの少し前(太平洋戦争の頃)でも、未だ乳幼児の死亡率が高く、平均寿命は50歳くらいだったと言われていますが、だからといって50歳でお年寄りだったわけではなく、まだまだ現役でバリバリ働いてますよね。
(ただし、栄養状態が今ほど良くない時代では年齢より老けて見えるという事はあるかも知れませんが…今の50代は若いww)
以前、【七五三の由来】>>のところで、江戸時代には「七歳までは神のうち」という考え方があって、7歳の時に霊的な試練があり、そこを踏み越えれば大人の階段を上る事ができるというような言い伝えがあった・・・てな事を書かせていただきましたが、
それは、それまでに死んでしまうお子様が数多くいた=生まれた赤ちゃんが、無事に大人になる確率が低かったという事で、そのために平均寿命が、今よりグンと下がってしまうというわけです。
もちろん戦国時代は、病気以外の危険も多かったですから、幻庵の場合は、半分僧侶であった事で、特に晩年は、ほとんど戦場に出て無かったおかげで、無事に長寿を全うできたという事なのでしょうけど・・・
.