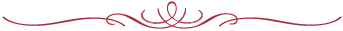
| 123 | 修養名言録 |
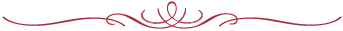
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年.3.29日
| 2005.3月号の「諸君」の矢崎科学技術振興記念財団理事長・尾崎護・氏の「孫のための『おじいちゃんの素読』私塾」を参考にしつつ「基礎修養録」を作成する。 2005.3.13日 れんだいこ拝 |
| 孟子曰く、人恒の言あり。皆曰く、天下国家と。天下の本は国にあり。国の本は家にあり。家の本は身に在り。 |
| 少年老い易く、学成り難し(朱子) |
| 一寸の光陰、軽んぜられるべからず(朱子) |
| 子曰く、学びて時に之を習う。亦(また)、説(よろこ)ばしからずや |
| 朋(とも)有り。遠方より来る。亦、楽しからずや |
| 子曰く、故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る。以って師と為るべし。 |
| 春眠暁を覚えず。処処(しょしょ)啼鳥(ていちょう)を聞く(孟浩然もうこうねん) |
| 朱に交われば赤くなる(いろはかるた) 朱に近づけば赤く、墨(ぼく)に近づけばかならず黒し |
| 身体髪膚(はっぷ)之を父母に受く。敢えて毀傷(きしょう)せざるは、孝の始め也 |
| 玉琢(みが)かざれば器を成さず、人学ばざれば道を知らず |
| 千里の行(こう)も足下に始まる。(老子) |
| 国破れて山河在り。城春にして草木(そうぼく)深し。時に感じては花にも涙をそそぎ、別れを恨んでは鳥にも心を驚かす。(杜甫とほ) |
| 子曰く、己の欲せざる所(ところ)、人に施す勿れ。(論語) |
| 春宵(しゅんしょう)一刻値千金、花に清香(せいこう)あり、月に陰あり。(蘇しょくの「春夜詩」) |
| 子曰く、仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼(おそ)れず。 |
| 豹(ひょう)は死して皮を留(とど)め、人は死して名を留む。(王げん章) |
| その疾(はや)きこと風の如く、その除(しず)かなること林の如く、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如し。(孫子「軍争篇」) |
| 「干支」(えと)、「十二支(じゅうにし)」 「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)。 |
| 男児、志を立てて郷関(きょうかん)を出ず。学若(も)し成る無くんば復(また)還(かえ)らず。骨を埋むること何ぞ墳墓の地を期せん。(釈月性)。 |
| 君が代は、千代に八千代に。巌(いわお)となりて、苔(こけ)のむすまで。(日本国家「君が代」) |
| 子曰く、吾(われ)十有五にして学を志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順(したが)う。七十にして心の欲する所に従いて、矩(のり)を越えず。 15歳ー志学、30歳ー而立(じりつ)、40歳ー不惑、50歳ー知命、60歳ー耳順(じじゅん)、70歳ー古希(こき)、人生七十古来稀なり(杜甫)。 |
(解説) |
(解説) 昔、中国の北方に塞翁という人が居り、飼っていた馬に逃げられ悲しんでいた。ところがやがてその馬は立派な別の馬を連れて帰ってきた。二頭の馬に良馬が生まれ、老人の子がこの馬に乗って遊んでいるうちに、馬から落ちて骨を折った。駆けつけた人々はそれに同情していた。やがて戦争となり、若者達は戦って十人中九人まで死んだが、足を折った老人の子は不具の為に闘わず、無事だった。このように、人間の幸不幸はめまぐるしく変わるものだという話。 |
(解説) |
(解説)このことわざの意味は、物事は急がず、無理をせず、こつこつと真面目に努力すれば必ず希望通りの事が成し遂げられるというたとえ。 昔、中国に愚公という老人がいた。この人は家族と共に二つの山を越えた所に住んでいたが、年齢も90に近いのでこの山歩きが辛くなった。そこで家族を集めて「この二つの山をどこかに移そう」と相談した。家族の中に知者といわれる老人がいて、「あなたの年齢と体力でそのようなことは到底不可能だ」と止めたところ、愚公は「私には子もあり、孫もある。そして、子や孫もやがて子や孫を作るから、子々孫々この仕事を受け継いでいけばよい。山はいつまでも今のままで、大きくはなるまい」と言った。時の天帝は愚公の根強さに感心し、山を他に移してやったという。このようないわれのことわざのようです。 |
(解説)このことわざの意味は、悪いことは誰も知るまいと思っても自然と現れるものであって決して隠し仰せるものでない。中国で王密という人が高官であった揚震の家を深夜密かに訪れて賄賂を送ろうとしたとき揚震はこういって断った。「天知る地知る我知る人知る」というもので、後年、「四知の戒め」として尊ばれている。「今あなたが行おうとしている悪いことは、私とあなたの他に天地の神々と、やがて他の人が知ることになりましょう。 悪いことや不正は隠そうとしても、必ず現れるものです」。このような意味合いのことわざです。 |
| 四面楚歌 |
(解説)
このことわざの意味は、四方皆敵の孤立無援の窮地をあらわしている。楚の項羽が漢の高祖にガイ下(がいか)で包囲された。夜、項羽は自陣の四方に、楚歌を聞き、楚人が皆、漢に味方してしまったと驚いた故事から、孤立無援のことを四面楚歌といった。(「史記」)
| 三顧の礼 |
| 先んずれば人を制す |
| 背水の陣 |
| 『論語』 |
| 孔子曰く、君子に三畏有り。天命を畏れ、大人を畏れ、聖人の言を畏る。小人は天命を知らずして、畏れざるなり。大人に狎れ、聖人の言を侮る。 |
| 「天は自ら助くる者を助く」
Heaven(God) helps those who help themselves. |
|
| 「天罰は遅くとも必ず来る」 | (天罰はゆっくりでも、必ずある、Heaven's vengeance is slow but sure) |
| 「天網恢恢疎にして漏らさず」 | (天の作った法の網の目は大まかだが悪人の行為を決して見逃さない)天の法網は広大で目が粗いようであるが、すくいもらすことはない。悪人は必ず捕らえられ、天罰を下されるということ。 |
![]() (私論.私見)
(私論.私見)