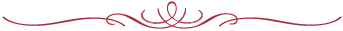
| その4、世の中、社会考察 |
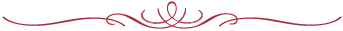
(最支那見直し2006.5.23日)
| 菜根譚の一節 | |
(解説) 悪も暴かれて世に現われるようなものは、それほどの悪ではなく、その罪は浅いが、隠れた悪はその根が深く恐ろしい。 |
夏目漱石の「草枕」の一節
(解説) 日本人は、昔からこの発想で生きてきた。向こう三軒両隣りの仲間意識の上に立って、他人の立場と心情をも思いやり、気を配って生きるという人間関係を結んできた。そこに義理と人情がからみ、詩が生まれている。これが基礎となって道徳と法律が生まれてきた。ここに日本社会の特質が有る。 |
| 近代物理学の鬼才スティーヴン・ホーキング | |
|
| 佐賀藩士山本常朝(つねとも)の「葉隠れ」 | |
|
| 民法学者・末弘厳太郎「嘘の効用」 | |
(解説) 「嘘は泥棒の始まり」と「嘘も方便」との間に世の生態があるというべき。 |
| E.カーペンター(英:詩人) | |
|
| リリー・ピンカス | |
|
| 新渡戸稲造「武士道―日本の魂」 | |
(解説) 新渡戸稲造(1862〜1933)は、農業経済学者、教育者。名著「武士道―日本の魂」で、日本の武士階級の人生観を著作し、欧米で評価を得た。 |
| 野村克哉監督 | ||
|
| 木村愛二「碁盤外の岡目八目の方が疑い過ぎ」 | |
木村説を「陰謀史観」と批判的姿勢を取る者に対して次ぎのように述べている。
|
| 夏目漱石「草枕」の書き出し | |
|
| 福沢諭吉「学問の勧め」 | |
|
|
| ガリレオの「新科学対話」 | |
|
|
|
| フルシチョフの「忙しい怠け者」 | |
第20回大会でのフルシチョフ報告の1節。
|
|
|
これは、アヘン戦争により列強に引き裂かれ租界を作られてしまった清国や、防備を怠り列強の侵攻が恣に行われた李氏朝鮮に対して、そのあまりの清国・李氏朝鮮の傲慢・無反省ぶりに、「真似をしていたら列強から同じように見られ、同じ目に遭う」との思いから福沢が言ったものです。 つまり、悪友と謝絶せよと。このとき、世界はやるか、やられるかの状況に入っており、日本は選択を迫られました。日本はやる方に回り、世界に冠たる先進国になりました。やらない側に回った中国・韓国・北朝鮮は言うまでもありません。 |
| 井上正治「田中角栄は無罪である」189P | |
|
| 井上正治「田中角栄は無罪である」59P | |
|
| 福沢諭吉「学問のススメ」での「怨望の害あるを論ず」 | |
(解説) 嫉妬の弊害に対する鋭い警告。同じくヒルティーも、「眠られぬ夜のために」の中で、「人間の全ての性質の中で、嫉妬は一番醜く、虚栄心は一番危険なもの。心の中のこの二匹の蛇から逃れることができたら、なんとすばらしいことか」がある。「他人の不幸は蜜の味」 |
| 林房雄 | |||
|
|||
| 中曽根康弘日記 | ||
|
||
ある人の言葉に次のようなものがある。
|
女優・山田五十鈴の言葉。
|
|
| 「あぁ学識無くして徒に感情にのみ支配せられし当時の思想の誤れしことよ」(景山(福田)英子「妾(わらわ)の生涯」)。 |
| 「人間の歴史の高さは、どれほど多くの人間の内奥に、その精神の自主性を呼び覚ましたかによって測られる」(市井三郎「明治維新の哲学」) |
| 高橋是清蔵相「是清翁遺訓」 |
| 「子が相当の年齢に達した以上は、全くの独立独歩、一厘一銭も親の厄介にはならず、自分の奮闘によって、自分の運命を開拓していく。いかに親に財産があっても、子は独立の人間として、一本立ちで社会に立たなくてはならぬ」 |
| 「日本では、自由と責任の概念が曲解されている。自由とは自己責任において与えられるものだ。それを理解しない社会に真の繁栄はないだろう。」 「自分の意見が世間一般の意見と食い違っていても、後暗さを感じる必要は全くない。価値観は十人十色なのだから自分を偽らずに自分の感覚に忠実であるべきだ。」 |
| 石橋湛山「東洋経済」社説 |
| 「如何に善政を布かれても、日本国民は、日本国民以外の支配を受けるを快とせざるが如く、支那国民にもまた同様の感情が存することを許さねばならぬ。然るに我が国民の満蒙問題を論ずる者は、往々にして右の感情の存在を支那人に向かって否定せんとする」。 |
| 鈴木永二・日経連会長 |
| 「リーダーとは、歴史観・倫理観・正義観が三位一体の人を言う。更に云えば、戦術(目先のこと)しか使えない者はリーダーではなく、単なるボスに過ぎない。リーダーは加えて、戦略(中・長期的視野に基づいた構想力)がなければならない」。 |
| 後藤田正晴官房長官「中央公論」平成元年2月号 |
| 「民主主義社会であればあるほど、真のリーダーシップが求められる。これが独裁政治であれば、その体制に支えられて、さほどのリーダーシップがなくても組織の維持ははかれる。民主主義というのは、てんでんばらばらだから、ソ連みたいな国と日本とリーダーシップの発揮の仕方はどちらが難しいかと言えば、そりゃずっと日本だ」。 |
| 氏名不詳 |
| 自由とは幸せな気分で目覚め、一日期待すること。 自由とは今日一日に対処し楽しむことが出来ると知っていること、 そして、
恐らく、明日も、又、次の日もそうできると知っていることである。Freedom is getting up happy
and looking forward to the day ahead. Freedom is knowing that you can cope with and enjoy this day, and, very likely, tomorrow, and tomorrow. |
| ラ・ロシュフーコー[1613-80](仏:モラリスト.政治家.思想家.公爵):箴言34 |
| 世間が美徳と称しているものは、普通は我々の情念が作り出した幻影に過ぎない。罰せられることなしに自分のやりたいことをやるために、人々はこの幻影に立派な名前をつけたのである |
| 5年もすれば、今どんな車に乗り、どんな家に住み、何を着て、いくら貯金があるかはどうでも良いことになるだろう。大切なのは、子供の心に何を育てられたかである。それこそが、世の中を少しでも、良くすることにつながるのだ。 |
| クラウゼヴィッツ・テーゼ「戦争論」 |
| 「一頭のライオンが率いる百匹の羊と、一匹の羊が指揮する百頭のライオンが戦えば、いったい、どちらが勝つだろうか。もちろん、ライオンを大将にした羊の集団が勝つのである」 |
| 勝海舟 |
| 「オレが政権を奉還して、江戸城を引き払うように主張したのは、いわゆる国家主義から割り出したものだ。三百年の根底であるからといったところで、時勢が許さなかったらどうなるものか。また都府というものは、天下の共有物であって、決して一個人の私有物ではない」。 |
| 小室直樹「悪の民主主義」 |
| 「日本の舵取りをしている役人がこのありさまでは、日本は難破するしかないではないか。国民は、民主主義を理解してないから、こんな役人に舵取りを任せきっていることがどんなに危険か気づいていない。狂乱を既倒に廻らす者は誰ぞ」。 |
| 坂本竜馬文久(1863)6.29日坂本乙女宛手紙の一節 |
| 「(幕府の)姦吏を一事に軍いたし打ち殺し、日本を今一度、せんたくいたし申し候事にいたすべくとの神願にて候」 |
| 「私が死ぬる日は天下大変にて、生きておりても役に立たず、おろんともたたぬよふにならねば、中々狡(こす)い嫌なやつで死にはせぬ。しかるに、土佐の芋掘りともなんともいはれぬ居候に生まれて、一人の力で天下動かすべきは、是(これ)また、天よりする事なり」 |
| 「世に活物(いきもの)たるもの皆衆生なれば、いずれを上下とも定め難し。今世の活物にては、ただ我をもって最上とすべし。されば天皇を志すべし」 |
| 「恥ということを打捨てて世の事は成るべし」 |
| 坂本竜馬の西郷隆盛評 |
| 「少しくたたけば少しく響き、大きくたたけば大きく響く。もし馬鹿なら大きな馬鹿で、利口ならば大きな利口だろう」 |
| 坂本竜馬の畢生の哲学 |
| 「世に生を得るは、事を為すにあり」、「国の為天下の為、力を尽くしおり申し候」 |
| 木村幸比古「日本を今一度せんたくいたし申し候」245P |
| 「組織は本来、下の者の意見は上の者が責任をとるぐらいの姿勢がなければ、協調性や信頼感は生まれてこない」 |
| ヴァルター・ヤコブ・ゲーリング博士 |
| 「定説に挑戦し、それを覆す勇気を持ってほしい。教科書には本当に間違いが多いので、教科書を書き換えるぐらいの気持ちで勉強してもらいたい」。 |
| 前尾繁三郎元自民党幹事長 |
| 「語源を研究することは、物事の本質を探究する一つの方法であり、十二支の研究は人間のものの考え方を理解する道しるべだ」、「人間を知ろうとすれば複雑怪奇で、一筋縄ではいかない。理解したと思ったとたんに、するりと抜け出してしまう」 |
| 中内功 |
| 「私は、ビジネスの基本はオネスト、正直さだと思っています。‐‐‐付き合っていただく人に対してオネストであらねばなりません。嘘をついたり、騙したりということが絶対にないように。私もフィリピンの戦線から還ってきた身で、たくさんの戦友の死を目の前で見ました。彼等に顔を合わせることができる生き方をしたい」。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)