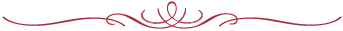
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年.1.6日
| その5、組織論考察 |
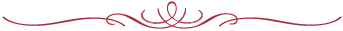
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年.1.6日
「何ほど国家に勲労有るとも、その職に任(た)えぬ人を官職を以って賞するは善からぬことの第一なり。官はその人を選びてこれを授け、功有る者に俸禄を以って賞し、これを愛し置くものぞ」、「開闢(かいびゃく)以来世上一般十に七八は小人なれば、能く小人の情を察し、その長所を取りこれを小職に用い、その材芸を尽くさしむるなり」、「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也」、「一家の遺事人知る否や、児孫の為に美田を買わず」(西郷隆盛・1827-1877「大西郷遺訓」)
「階級の周流の結果、政治的エリートは絶えず緩やかに変わっている。それは大河のように流れる。今日の政治的選良は、もはや昨日のそれではない」(パレート・1848-1923「一般社会学概論」)
| 「忙しい怠け者」 |
| 第20回大会でのフルシチョフ報告の1節。「党の事務所にいて、朝から晩まで忙しくしており、資料を作り通達を出し、全国を回って尻をひっぱたいてくる。しかし、絶対、大衆には顔を向けない、学ぼうとしない。こういう態度ではいけない」。 |
| 孫子 |
| 「卒を見ること愛子の如し。故にこれとともに死すべし。しかれども、厚う(厚遇)してよく使わず、愛してよく令せざれば、乱るれども治むるあたわず。例えば馬喬児の如し。用いるべからず」 |
| (解説)人を使うには愛情を込めて使え。そうすれば生死を共にする関係になれる。可愛がるだけで仕事をさせぬと、その者が人の上に立った時乱れ、統治できないことになる。 |
| 管子 |
| 「一年の計は穀を樹(う)うるに如かず。十年の計は木を樹うるに如かず。百年の計は人を樹うるに如かず。一樹一獲は穀なり。一樹十獲は木なり。一樹百獲は人なり」
(解説)人を育てることがいかに大事なことであるか、時間がかかるかということ。 |
| 孟子 |
| 「力を以って仁を籍(*クサ冠)る者は覇たり、徳を以って仁を行う者は王たり、力を以って人を服する者は心服するに非ざるなり、徳を以って人を服する者は中心に悦びて誠に服するなり」 |
| 「綸言(りんげん)汗の如し」 |
|
皇帝が一旦発した言葉(綸言)は取り消したり訂正することができないという中国歴史上の格言。出典は孔子の「礼記」緇衣篇である。原文では「王言如絲,其出如綸;王言如綸,其出如綍」(王の言は糸のごとくなれば、その出るや綸の如し。王の言は綸の如くなれば、その出るやフツの如し)。綸はひも、フツは綱。王のちょっとした言葉は初め絲(細い糸)のように細くとも一度口に出れば、ひもや綱のように重い意味を持つとの教訓である。現代風に云えば、指導的な立場にある者の言はささいなことでも公言された以上は重大な影響を及ぼすという戒めになる。続いて、「大人は遊言を唱えず」(地位ある人はいい加減なことを口にしない)、「言うべくして行うべからざるは、君子き言わざるなり」(言っても実行できないことは言わないことだ)とある。「汗の如し(如汗)」の出典は漢書劉向伝であり、原文は「言号令如汗,汗出而不反者也」である。 古来より、皇帝など国家の支配者の発言は神聖であり絶対無誤謬性を有するとされ、臣下が疑念や異議を差し挟むことは不敬とされた。 このため、一旦皇帝より発せられた言葉は仮に誤りがあっても、それを訂正することは皇帝が自らの絶対無誤謬性を否定することになり、皇帝の権威を貶めてしまうためタブーとされた。 このため、「綸言汗の如し」(皇帝の発言は、かいてしまった汗のように体に戻すことができない)という古典典籍の言葉を引用、格言として軽率な発言やその訂正を戒めた。 この慣例は発言のみならず文書にも適用され、清の乾隆帝が先に入手した黄公望の「富春山居図」模本に賛を記入してしまったため、後に入手した真本に賛を入れることが出来なかったという故事が残されている。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)