親思う心にまさる親心
吉田松陰です。
吉田松陰らが心服した上杉鷹山公が藩主隠居後に江戸屋敷の新しい藩主に嫁ぐことになった孫娘(参姫二十歳)に藩主の妻たるべきものの心得を懇切丁寧に説いて手紙にしたためました。「上杉鷹山に学ぶ」鈴村進著(三笠書房)から著者による現代語訳文を長文乍ら全文転載します。
◎上杉鷹山公「参姫への手紙」
「人は三つのことによって、成育するものである。父母によって生まれ、師によって教えられ、君によって養われるのである。これはすべて深い恩なのだが、その中で最も深く尊いのは父母の恩である。これは山よりも高く、海よりも深いものであって、これに報いることはとてもできないが、せめてその万分の一だけでもと、心の及ぶだけ、力の届くだけを尽くし、努めることを孝行という。
その仕方にはいろいろあるが、結局は、この身が天地の間に生まれたのは父母の高恩であり、この身は父母の遺体であることを常に忘れず、真実より父母をいとおしみ、大切にする心に少しの偽りもないことが、その根本である。ここに誠実さがあれば実際に多少の手違いがあっても、心が届かぬということはないものである。このことは、自分は徳がないからとても行き届きません、と遠慮すべきではない。その気になって、できる限りのことを十分に努めるべきである。そうしておれば、やがては徳も進み、相手に心が達するものである。あらん限りの力をもって尽くされたい。
男女の別は人の道において、大きな意義のあるところである。男は外に向かって外事をし、女は内にあって、内事を治めるものである。国を治め、天下の政(まつりごと)を行うといえば、大変なことのように思われるであろうが、天下の本は国であり、国の本は家である。家がよくととのえられるためには、一家の男女の行いが正しいことがその根本となる。根本が乱れて、末が治まることはありえない。
普通に考えれば、婦人は政治には関係がないと思われるであろうが、政治の本は一家の中から起こることであり、身を治め徳を積み、夫は妻の天であってこの天にそむいてはならない。これを常に心に銘記して恭敬を忘れず、夫に従順であれば、やがては政事を輔(たす)けることとなるものである。
あなたはまだ稚(おさな)いので、人々から程遠い奥向きで徳を積んでみても、その影響が一国に及ぶはずがないと思われるであろう。しかし、感通とは妙なもので、人に知られず身を修めていると、いつかはそれが知られて、効果が大いに表われることは疑いのないところである。『鶴九皐に泣いて声天に聞こゆ(かく、きゅうこうにないて、せい、てんにきこゆ
・・・鶴は奥深い谷底で
鳴いても、その気品ある泣き声は天に届く。つまり優れた人物はどこに身を隠しても、その名声は自然に広く世間に知れ渡るというたとえ)』と詩経に書かれているのはこのことである。奥向きで正しく徳のある行いをしておれば、一国の賢夫人と仰がれるようになる。そうなれば、あなたの行いによって人々が感化されないはずがない。誠があれば、それは決して隠れたままにはならない。ひたすら努めに努められよ。
年が若いので、時折美しい着物を着たいと思われることもあるだろう。それも人情ではあるが、少しでもそんなことに心を動かして、これまでの質素な習慣を失うことのないよう、『終わり有る鮮し(詩経の大雅・蕩
「初め有らざること靡(な)し 克(よ)く終わり有ること鮮(すくな)し」 何事でも、初めはともかくもやっていくが、それを終わりまで全うするものは少ない)
』の戒(いまし)めを守られるべきである。そうすれば、いつまでも従来の質素な習慣は続けられるであろう。そして、養蚕女工のことを思い、一方では和歌や歌書などを勉強されたい。しかし、ただ物知りになったり、歌人になったりしようなどとは考えるべきではない。学問は元来、自分の身を修める道を知るためのものである。昔のことを学んで、それを今日のことに当てはめ、善いことを自分のものとし、悪いことは自分の戒めとされよ。和歌を学べば、物の哀れを深く知るようになり、月花に対して感興を深くし、自然に情操を高めることとなるであろう。
くれぐれも両親へ孝養を尽くし、その心を安んじるとともに、夫に対しては従順であり、貞静の徳を積み、夫婦睦まじく、家を繁栄させて、わが国の賢夫人と仰がれるようになってもらいたい。出発に際して、末永く祝うとともに、婦徳を望む祖父の心中を汲み取られよ。他へこそ行かないが、今日より後、いつ会えるかわからないので、名残り惜しく思う。
武蔵野の江戸なる館へ赴きたまうはなむけに
春を得て花すり衣(ごろも)重ぬとも わが故郷(ふるさと)の寒さ忘るな はる憲」
魏志倭人伝にも記されているように、大昔から親が天から授かった我が子を何物にも替え難い宝であると我が家の中で自分より立派な大人になるよう願いを込めて敬い慈しみ育ててきた大和民族庶民が、最近のように我が子を自分に附属した所有物だとして人間では無く物扱いするとか奴隷扱いするようになったのは、いつ頃からでしょうか。私は、カラーテレビが日本人の家庭に入り込んできたときからだと認識しております。
動物として考えると、子どもがこの世で一番会いたい人は誰でしょうか。なったばかりの2歳児(昔で言えば数え三歳の三つ子)にそう訊けば100%お母さんかお父さんつまり親だと答えます。お母さん(時々お父さん)に親がこの世で一番会いたい人は誰ですかと訊けばほぼ100%子どもと答える。その一番会いたい者同士が会うのはどこで会うかと言えば家の中です。
だいたいこどもは皆保育園とか行って親は日中働いてますから、会えるのは夕方から翌朝までの間しかない。そして夜は皆寝るから実質一日のうち三時間くらいしか会えない。会うというのは、お互いに目と目を合わせてお話しすることだし、子どもはだっこされることを一番喜ぶから、大昔から白黒テレビの昭和まで子どもも親もその短い貴重な時間を抱っこを介して思う存分会いたい人に会って過ごして来た。それこそが本当の家族の団らんでした。
だから大和民族庶民のこどもは卑弥呼以前の大昔から白黒テレビの昭和の田中角栄時代までずっと、大好きないつも優しい親に反抗したり無礼なタメ口をきいたりなど絶対にしないで、いつも親を尊敬して親の言うことに従順に従い幼くとも自分が弁える最高の礼儀を以て親に相対して、子どものうちに親から人間としてのすべてを学んで、数え16歳満14歳で元服して成人すれば死ぬまで親孝行に尽くしてきたのです。
そして子どものうちに親から学んだ知識と技術を大人になったら存分に揮って、親が成し遂げたことよりもさらに進化したことを成し遂げてきた。これが地球の歴史で常に同時代世界一の真善美慈悲道徳和合仏心社会を営々と伝えてきた大和民族庶民の大和魂なのです。
国を治めんと欲すれば先ず家を治めよ。庶民の家がこのように親の無私の慈愛によって治まってきたからこそ、おのずとこの国がどの時代においても常に世界一治まった奇蹟の品格国民和合国家であり続けることが出来たことは、言を俟たないでしょう。
その世界一治まった日本人の家庭の中に今から40年ばかり前にいっせいにカラーテレビが送り込まれたのです。カラーテレビの画面に映る色は赤青黄三原色の電気的発光体をとり混ぜて色を作っているため、色から電磁波が出ています。我々や自然物天然物の天然色から電磁波は出ていない。二種の性質が異なる色が混在すれば眼のある動物は犬猫でも人間でも皆が電磁波が出ている刺激が強い色に視線を強制的に奪われる。
その結果、何万年も昔から家の中で目と目を合わせてお話ししてこの世で互いに一番会いたい者同士である親とその子が会い続けた大和民族庶民の最も大切な大和魂を伝える「家族の団らん」が、全員がカラーテレビに視線を奪われて互いにまったく会えなくなることで家の中から消し去られてしまったのです。
このように家の中が治まらなくさせられると直ちに国が乱れて、現在の日本は世界中どこの国にも無い小学生以下の国語能力算数能力しか無い白痴の智慧遅れが総理大臣になってるという、世界一破廉恥な恥ずかしい国になり果てているのです。これがフリーメーソン総務省鬼畜の日本人子ども皆殺し大和民族絶滅作戦であることはもはや明々白日ですね。
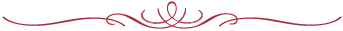
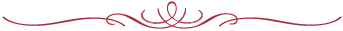
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
1. 火は粗末にするな
2. 朝、機嫌を良くしろ
3. 朝早く起きろ
4. 神仏(かみほとけ)を祈れ
5. 身を大切にもて
6. 不浄をみるな
7. 身の出世を願へ
8. 不吉を言ふな
9. 家内笑うて暮らせ
10. 人に腹を立たせるな
11. 人に恥をかかせるな
12. 人に割を食はせるな *損をさせるな
13. 人に馬鹿にされていろ
14. 人を羨むな
15. 利口は利口にしておけ
16. 年寄りをいたはれ
17. 恩はどうかして返せ
18. 万事油断をするな
19. 女房の言ふ事半分聞け
20. 子の言ふ事は九ッ聞くな
21. 家業は精を出いだせ
22. 何事も我慢をしろ
23. 子供の頭を打つな
24. 己が股をつねれ *わが身をつねって人の痛さを知れ
25. たんと儲けて使へ
26. 借りて使ふな
27. 人には貸してやれ
28. 女郎を買ふな
29. 女房を探せ
30. 病人は労いたはれ
31. 難渋な人には施せ
32. 始末をしろ *無駄遣いをするな
33. 生き物を殺すな
34. 鳥獣(とりけだもの)は食ふな
35. 年忌・法事をよくしろ
36. 親の日は万事慎め *親の年忌・命日には謹慎しろ
37. 義理を欠くな
38. 子供はだまかせ *だまくらして上手に扱え
39. 女房に欺されるな
40. 博奕をするな
41. 喧嘩をするな
42. 大酒を飲むな
43. 大飯を食ふな
44. 判事(はんごと)はするな *印判を押す=保証人になるな
45. 世話焼きになるな
46. 門口(かどぐち)を奇麗にしろ
47. 三日に氏神へ参れ
48. 晦日に内を掃除しろ
49. 貧乏を苦にするな
50. 火事の覚悟をしておけ
51. 火事には人をやれ、内を守れ *出火の際は消火要員を出す一方で家も守れ
52. 風吹きに遠出をするな
53. 火事には欲を捨てろ
54. 火口箱(ほくちばこ)を湿すな *火打ち石などが入った道具箱を湿らすな
55. 水を絶やすな
56. 塩は絶やすな
57. 戸締まりをよくしろ
58. 夜更けに歩くな
59. 寒さを凌げ
60. 暑さも凌げ
61. 泊まりがけに出るな
62. 高見(たかみ)へ登るな *高見の見物のように傍観するな
63. 雷らいの鳴る時、仰向あおむいて寝るな
64. 寒気の時、湯に入るな
65. 怪我と災難はバチと思へ
66. 物を拾ひ、身に付けるな
67. 冬は物を取り、始末をして置け *冬場は物を大切に保管し、浪費をするな
68. 若い内は寝ずに稼げ
69. 年寄ったら楽をしろ
70. 折々に寺参りをしろ
71. 身寄りのない人を労いたはれ
72. 小商物こあきなひを値切るな *薄利の商売では値切るな
73. 風吹きには舟に乗るな
74. 何事も身分相応にしろ
75. 身持ち女は大切にしろ *妊婦は大事にしろ
76. 産後は、なほ大切にしろ
77. 小便は小便所へしろ
78. 泣き言を言ふな
79. 病気は仰山にしろ *病気は大袈裟に思え(軽々しく思うな)
80. 人の気を揉む時、力を付けてやれ
81. 悪しき事も「よし、よし」と祝ひ直せ
以上、八十一ヶ条
上様や大名方は生きた神 滅多にするとバチが怖ひぞ
我人と隔てのつくが凡夫なり 仲良くするが仏付き合ひ
嘉永五壬子年九月吉日 施主 神田住
http://hidenori1212.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-96c3.html#comment-100569467