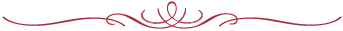
| その11、文芸論 |
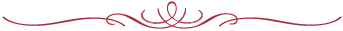
更新日/2017.3.24日
作詞家の藤田まさと。「岸壁の母」、「浪花節だよ人生は」など、昭和を代表する演歌を次々に生み出している。
|
| 【古典とは】 | |
(2003.2.15日付け朝日新聞文化欄、俳人・長谷川櫂「時のかたち」より抜粋)
|
|
【石川九楊(書家)の「本居宣長から疑え」】
|
|
石川九楊(書家)の「本居宣長から疑えー『神の国』、『三国人』発言を越えて」。
|
|
| 「国語教育を強めると共に漢語教育を復活して、日本語の水準を高めることが必要」の論旨は良いのだが、ひらなが、かたかなの理解が違うと思う。ひらなが、かたかなこそ日本文の原点であり、そこに漢字を乗せて日本語を創造したのが実相なのでは。日本語をひらなが、かたかな、漢字のアンサンブル言語として磨き、英語と並ぶ世界言語として押し出していくべきではなかろうか。 2024.4.9日 れんだいこ拝 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)