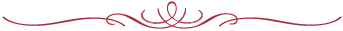
| 格言・名句(短)その3(ハ~ワ行) |
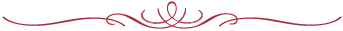
更新日/2016.11.3日
| ハ | ||
|
||
| 「灰の中に深く隠れた情熱の火は最も激しい」(詩人・オヴァディウス) | ||
| 「化け物の正体見たり枯れ尾花」(江戸中期の俳人・横井也有の句) | ||
|
||
|
「始め、われ、人におけるや、その言を聴きてその行を信ぜり。今、われ、人におけるや、その言を聴きてその行を観る」(孔子) |
||
| 「20才でリベラル(進歩派)でないとしたら心がない。40才で保守派でないとしたら頭がない」(“If you're not a liberal at twenty you have no heart, if you're not a conservative at forty you have no brain.”)。 | ||
| 「働く人の成功を怠け者が評価するとき、これを幸運と言う」 | ||
| 「働けば働くほど働ける。忙しければ忙しいほど暇が出来る」(批評家・ウィリアム・ハズリッド) | ||
| 「花も嵐も踏み越えて」 | ||
| 「花ひらけば風雨多く 人生別離おおし」(唐詩撰) | ||
| 「話すことの二倍 人から聞くべきである」(デモクリトス) | ||
| 「歯のくいしばり と血のにじみ」(伊吹一番) | ||
| 「浜の真砂は尽きるとも、世に心配の種は尽きまじ」 | ||
| 「腹が立ったら十まで数えよ。うんと腹が立ったら百まで数えよ」(トーマス・ジェファーソン) | ||
| 「半分の池がハスで埋まるにはもの凄く年月がかかるが、半分が埋まれば一日で埋まる」 | ||
| 「晩節を汚す」 | ||
| 「万人のうちでもっとも偉大なのは、万人のために鼓動する心をもった人である」(ロマン・ロラン) | ||
|
||
| 「万人向きの書物は常に悪臭を放つ書物である」(ニーチェ) |
| ヒ | ||
| 「日頃は何とも覚えぬ鎧が、今日は重うなったるぞや」(木曾義仲・1154-1188「平家物語」巻9) | ||
|
||
| 「ビジネスの世界には静止した状態はありえない。それは常に移り変わる世界である」(実業家・ポール・ゲッティー) | ||
| 「秘すれば花なり秘せずば花なるべからず」(世阿弥) | ||
| 「必要は発明の母である」(グーテンベルグ) | ||
| 「必要はもっとも確実なる理想である」(石川啄木) | ||
| 「人みな人に忍びざるの心あり」(孟子) | ||
| 「人がどんな哲学を選ぶかは、彼がどんな人であるかによって決まる」(フィヒテ・1762-1814「知識学への第一論」) | ||
| 「人が共同するためには先ず自立的精神に富まなくてはならない」(三橋喜久雄) | ||
| 「人と生まれたからには、万人にすぐれた人物となって、人を救おうという志を立て、人々のために心を砕くことをこそ、一生を思い出とするだけの覚悟を持つべきである」(葉隠れ) | ||
| 「人に従うことを知らない者は良き指導者になり得ない」(アリストテレス) | ||
| 「人の数だけ意見がある」(古代ローマの喜劇詩人・テレンティウス) | ||
| 「人の一生は重き荷を負うて遠き道をゆくがごとし。急ぐべからず。不自由を常とおもへば不足なし 」(徳川家康遺訓) | ||
| 「人の一生には焔の時と灰の時がある」(レニエ) | ||
| 「人の行く裏に道あり花の山」。 | ||
| 「人の身の五尺、六尺の魂も一尺の面に表われる」 | ||
| 「人の天性は良草を生ずるか、雑草を生ずるか、そのいずれかである。だから、折を見て良草に水をやり、雑草を除かねばならない」(ベーコン「随筆集」) | ||
| 「人は愛している限り許す」(人生批評家 ラ・ロシュフーコー) | ||
| 「人はおのれの力の限界を越えなくてはならない」(ブラウニング) | ||
| 「人は、恋をして始めて全ての子供らしさから脱皮する。この革命がなければ、気取りや芝居気がいつまでも抜けないだろう」(スタンダール[1783-1842](仏:作家):恋愛論) | ||
| 「人は何も云う事がないと、いつも悪口を云う」(ヴォルテール) | ||
| 「人はもう何も云う事がなくなるとかぐに、『若い人ってものは』、なんて云い出す」(チェーホフ・1860-1904「かもめ」) | ||
| 「人はパンだけで生きるものではない」(イエス) | ||
| 「人は習わし次第のものだ」(シェークスピア) | ||
| 「人は彼の頭脳をもって描き出すのであって、手をもって描くのではない」(ミケランジェロ・1475-1564「書簡」) | ||
| 「人は本当に劣悪になると他人の不幸を喜ぶこと以外に興味を持たなくなる」(ゲーテ「箴言と省察」) | ||
| 「人々は愛によって生きている」(トルストイ) | ||
| 「人を育てるには、一方で甘えさせて一方で鍛錬することだ」(出光佐三) | ||
| 「人をほめれば、その人と対等になれる」(ゲーテ) | ||
| 「人が多く人を動かす秘訣は、無償の行為である」(山岡荘八・小説家) | ||
| 「人を挙ぐるには須らく退を好む者を挙ぐべし」(朱子・帝王学書「宋名臣言行録」) | ||
| 「人を用い候にはその長所をとりて短所に目を付け申さず候事聖人の道にて御座候」(荻生徂徠) | ||
| 「一人殺したら殺人者、百万人殺したら英雄だ」(チャップリン) | ||
| 「一人の敵も作らぬ人は、一人の友も作れない」(詩人・アルフレッド・テニソン) | ||
| 「独り善がりの荒っぼい漕ぎ方をすれば、誰であれ、歓迎されないだろう」(R.W.エマソン[1803-82](米:思想家.詩人)。 | ||
| 「一朝目覚めれば時の人」(詩人 ジョージ・パイロン) | ||
| 「日は沈めども日は昇るものなり」 | ||
| 「百年を羊のように生きるよりも、一日をライオンのように生きる方がましだ」(イタリアの銀貨の銘) | ||
| 「美と醜は表裏一体。美の面に囚われ、反面の醜を責めるに急なのは、真実を知らぬ姿である」(松下幸之助[1894-1989](松下電気器具製作所創業)。 | ||
| 「貧乏は呼べばいつでも来る」(ゴールドスミス) |
| フ | ||
| 「不可能だと思わない限り、人間は決して敗北しない」(D.カーネギー) | ||
| 「不正に対して敵する人だけが神に愛でられる」(デモクリトス) | ||
|
「仏道を習うとは自己を習うなり」(道元禅師) |
||
| 「副社長を十年やっても、社長の一年とは違う。困ったときに”社長のご意見は”で逃げられる。決断力、寂寥感、ハラのくくり方、すべてが違う。副社長をいくらやったからといって、社長の器かは、別問題だ」(西武鉄道グループ 堤義明) | ||
|
||
| 「不平は個人にとっても、国家にとっても進歩の第一段である」(詩人、劇作家・オスカー・ワイルド) | ||
| 「踏まれても どこまでも ついて行く 下駄の雪」 | ||
| 「冬来たりなば 春遠からじ」(シェリー) | ||
| 「文は人なり」、「(日蓮を評して)小人の文は文に非ずして精神也」(高山樗牛ちょぎゅう・1871-1902) | ||
| 「文学は糊口の為になすべきものならず。思いの馳するまま、こころの趣くままにこそ筆はとらめ」(樋口一葉・1872-1896「一葉日記」) | ||
|
「文明のおかげで人間の残虐さは醜悪になった」(ドストエフスキー) |
| へ | ||
|
||
| 「兵を養うこと千日、用いるは一朝にあり」(水滸伝) | ||
| 「平和の時には息子が父を葬り、戦時には父が息子を葬る」(古代ギリシャの歴史家ヘロドトスの名言、日野原抄訳)」 | ||
| 「蛇のように賢く 鳩のように純真であれ」(新約聖書) | ||
| 「変化無限」(大山康晴) | ||
| 「ペンは剣よりも強し(The pen is mighter than the sword)」 |
| ホ | ||
| 「忘却なくして幸福はあり得ない」(モロウ) | ||
| 「奉仕を主とする事業は栄え、利益を主とする事業は衰う」(実業家・ヘンリー・フォード) | ||
| 「帽子には素早く手を持っていき、財布にはゆっくりと手を持っていけ」(デンマークの諺) | ||
| 「飽食暖衣、逸居して教うることなければ、則ち禽獣に近し」(『小学』) | ||
|
||
| 「法は殺人剣ではなく、活人剣でなくてはならぬ」(団藤重光「我が心の旅路」有斐閣) | ||
|
||
| 「ホームページ作成。それは寝不足を強いるものであり、そして永遠に終了しないものである」(貧乏学生・くろみつ) | ||
| 「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出来る」(詩人・彫刻家・高村光太郎) | ||
| 「僕の言葉は風の中の歌のように消える」(芥川竜之介・1892-1927「或る旧友に送る手記」) | ||
| 「凡才は天才を見分けてこれを避ける」(エルヴェシユス) | ||
| 「凡人は小欲なり 聖人は大欲なり」(二宮金次郎) | ||
| 「本当の『自立』というのは、『相互依存』や『パートナーシップ』に至るまでの段階である」(チャック・スペザーノ) | ||
| 「本当の雄弁は必要なことは全部喋らず、必要以外は一切喋らぬということである」(ラ・ロシュフーコー) |
| マ | ||
|
||
| 「まず自分をこの世に必要な人間とせよ。そしたらパンは自然に得られる」(思想家・ラルフ・エマソン) | ||
| 「貧しくとも君の生活を愛しなさい」(ソーロー) | ||
| 「メディアは地球上で最も強力な存在だ。彼等は無実の人を有罪にし有罪の人を無実にする力がある。それこそ力だ。なぜなら大衆の心を支配できるからだ」 (マルコムX ) | ||
|
||
|
||
| 「窓からでは、全世界は決して見渡せない」(スペインの諺) | ||
| 「迷うな。風は勇者の念ずる方向へ吹く」(ネルソン提督・1758~1805) | ||
| 「満足した豚となるよりは不満足な人間となるほうがいい。満足した愚者よりも不満足なソクラテスとなる方がいい」(ミル・1806-1873「功利主義論」) | ||
| 「満を持す者には、天の助けがある」(史記) |
| ミ | ||
| 「見えないところで、私のことを良く言っている人は、私の友人である」(トーマス・フラー) | ||
| 「見ざる、云わざる、聞かざるの事なかれ主義」 | ||
| 「自ら労して自ら食うは、人生独立の本源なり」(教育者・福沢諭吉) | ||
| 「自らを軽んずる者、人これを軽んず」 | ||
| 「見た目の個性なんかより、野球には勝負強さが必要だし、その為に不可欠なのが、三つのカンです。感性のカン、第六感のカン、全体を見渡す大局観のカン、この三つが揃わないと一流にはなれません」(野村克哉、週間ポスト2001.2.16日号「野村の講演会」) | ||
| 「三たび肘を折って良医となる」(五経『春秋左氏伝』) | ||
| 「自らが正義と考えたとき、真中に留まることはむしろ不正義である」(安岡正篤) | ||
|
||
| 「自らを楽しむことのできない人々は、しばしば他人を恨む」(イソップ) | ||
|
||
| 「道を間違えたら、間違えた地点まで戻る以外ない」 | ||
|
||
| 「民主主義の眼目は、率直で力を込めた討論である」(英国首相・マーガレット・サッチャー) | ||
| 「民主主義は最悪の政体である。これまで試されたあらゆる政体を別にすれば」(英国首相・チャーチル) | ||
| 「民衆の中には、忍耐強い無言の悲しみがある」(ドストエフスー「カラマーゾフの兄弟」) |
| ム | ||
| 「無為自然」(老子) | ||
| 「無一物無尽蔵」 | ||
|
||
| 「無限より来りて無限に帰る」(河野廣道) | ||
|
||
| 「無知を恐れるな。いつわりの知識を恐れよ」(パスカル 仏の哲学者) | ||
| 「むやみに喋(しゃへ)り散らしては、こっちが云うべき台詞(セリフ)を向こうから聞かされる」(ソフォクレスの箴言しんげん) |
| メ |
| 「名将の下に弱卒無し」 |
| 「目下の人間に少しも気がねしない人間に限って、目上の人間には気を使う」(.露の小説家・ツルゲーネフ) |
| モ | ||
| 「もうはまだなり。まだはもうなり」。 | ||
|
||
| 「もしあなたが、過失を擁護する態度をとるだけであれば、進歩の望みはないだろう」(W.チャーチル、1874-1965、英:政治家) | ||
| 「もしあなたが口を開かなければ、他の人は馬鹿のように思うだろう。しかし、本当の馬鹿は口を開いて人々を自分の意見によって説得しようと努める愚か者である」(ユダヤの諺) | ||
| 「もしも美しいまつ毛の下に涙がたまったら、あふれ出ないように、強い勇気でこらえるべきだ」(ベートーベン・1770-1827「手記」) | ||
| 「もっとも長生きした人とは、もっとも多くの歳月を生きた人ではなく、もっともよく人生を体験した人だ」(思想家・ジャン・ジャック・ルソー) | ||
| 「もっとも優れた人間は、苦悩を突き抜けて喜びを手にれる」(作曲家・ベートヴェン) | ||
|
「最も正しき戦争よりも最も不正なる平和を取らん」(古代ローマの政治家キケロ) |
||
| 「もっともよく考える人はもっとも行動的である」 | ||
| 「本立ちて道生ず」(「論語」学而) | ||
| 「もともと地上に道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ」(文学者・魯迅) | ||
| 「ものを生み出してもわがものとせず、大きな仕事をしてもそれを誇らず、指導者になっても支配者を気取るようなことはしない」(『老子』10章) | ||
| 「物には時節あり。花の開閉、人間の生死なげくべからず」(作家、俳人・井原西鶴) | ||
| 「門閥制度は親の敵(かたき)でござる」(福沢諭吉) |
| ヤ | ||
|
||
| 「野蛮であるとはすぐれたものを認めないこと」(エッカーマン) | ||
| 「野党はうまい話ばかりする。まるで、毛バリで釣りをするようなもので、毛バリで釣られる魚(有権者)は知能指数が低い」(渡辺美智雄) | ||
| 「病のある身ほど、人の情けの真と偽りとを激しく感ずるものはない」(島崎藤村、破壊) | ||
| 「病は馬に乗って訪れ、歩いて帰る」(中世ラテンの諺) | ||
| 「闇から出てきた人こそ、本当に光のありがたさがわかる」(文学家・小林多喜二) | ||
| 「やる気は目に出る。知性は声に出る。生活は顔に出る」(木谷実9段が伯父の囲碁棋士初段・木谷好美) |
| ユ |
| 「憂国の士があって国が滅ぶのさ」(勝海舟) |
| 「友情は成長の遅い植物である」(ワシントン) |
| 「友情は人生のワインである 」(T・ヤング) |
| 「友情は成長の遅い植物である」(ワシントン) |
| 「勇気と力だけがあっても、慎重さを欠いていたら、それは無に等しい」(画家、登山家・エドワード・ウィンパー) |
| 「勇断なき人は事をなすことあたわず」(島津斉彬) |
| 「有能な者は行動するが、無能な者は講釈ばかりする」(バーナード・ショウ) |
| 「幽霊の正体見たり枯れ尾花」 |
| 「故なくして、人を謗る者は奈落に堕ち、故あって、人を謗る者は地獄に堕ちる」 |
| ヨ | |||
| 「容赦は復讐にまさる」(エピクテトス) | |||
|
「欲に手足を付けたのが人間である」(井原西鶴)
|
|||
| 「よく考え抜かれたことは、極めて明晰な表現をとる」(デカルト) | |||
| 「よく集め、よく散ずるを英雄と言う。よく集め、散ぜざるものをもって守銭奴、集めるを知らずして使うのを阿呆という」(井原西鶴「世間胸算用」) | |||
| 「世に語られる歴史は、ほとんどウソである」(17世紀のフランスの箴言家・フランソワ・ラ・ロシュフコー) | |||
| 「世に処するは一歩を護るを高しと為す。歩を退くるは即ち歩を進むるの張本なり」(儒者・洪自誠)
(解説)他人に一歩譲って控え目にするのが立派な態度であり、それが結局は自分のためにもなるのだ。 |
|||
|
|||
| 「由(よ)らしむべし、知らしむべからず」 | |||
| 「世の中で一番寂しいことは仕事がないことである」(福沢諭吉)。 | |||
| 「世の中で一番楽しく立派なことは一生涯を貫く仕事を持つと云う事です」。 | |||
| 「世の中には勝利よりももっと勝ち誇るに足りる敗北があるものだ」(モラリスト ミシェル・モンテーニュ) | |||
| 「世の中はなんのヘチマと思えども、一寸先は闇夜の提灯(ちょうちん)」 | |||
| 「世の中は君の理解する以上に光栄にみちている」(チェスタトン) | |||
| 「世は定めなきこそいみじけれ」(兼好法師) | |||
| 「輿論は常に私刑(リンチ)であり、私刑(リンチ)はまた常に娯楽である。たといピストルを用うる代わりに新聞の記事を用いたとしても」(芥川龍之介「しゅ儒種の言葉」) | |||
| 「良き金言、警句は、どの時代にも食事と同じように滋養を与え、何世紀にもわたって生きつづけるものである」(ニーチェ) | |||
| 「弱いものを救い上げるだけでは十分ではない。その後も支えてやらなければ」(シェークスピア) | |||
| 「喜ぶ者と共に喜び 泣く者と共に泣け」(パウロ) |
| ラ |
| リ | ||
|
||
|
||
| 「利の第一は無病なり、満足の第一は財なり、親族の第一は信頼なり、楽の第一は涅槃なり」(経典・『法句経』) | ||
| 「利潤の自然的傾向は低下にある」(リカード・1772-1823「経済学及び課税の原理」) | ||
| 「流言は知者に止まる」(『荀子』) [根拠のない噂のようなものを、知者は信じない。噂は知者のところで止まる――という意味] |
||
| 「龍蛇(りょうだ)の冬ごもりは身を存するためなり」(思想・占い書『易経(えききょう)』) | ||
| 「綸言汗の如し」 |
| ル | ||
|
||
| 「ルビコン河を渡る」 | ||
| 「良識なき知識は、人間の魂を滅ぼす」(ラブレー) |
| レ |
| 「礼儀正しさこそがこの徳らしいみせかけなのであり、諸々の徳はここから生ずる」(アンドレ・コント=スポンヴィル) |
| 「歴史の連続性が失われると正気が失われる」 |
| 「歴史は夜つくられる」 |
| 「歴史は繰り返す。最初は悲劇として、二度目は喜劇として」 |
|
「歴史はいつも今創られている」(れんだいこ)
|
| 「歴史を真摯に観察すれば、平和主義者が戦争を起こしたという逆説(パラドックス)に満ち満ちている」(小室直樹「大東亜戦争ここに蘇る」) |
| ロ |
| 「路上の人々の悲しみや苦痛が本当に分からないと、世界平和の仕事はやっていけない」(堀川辰吉郎、辰吉郎は明治天皇と千種任子権掌侍・ちくさことこごんのしょうじの間に生まれた隠れ皇族と云われる) |
| 「労働者階級は単に出来合いの国家機構を掌握して、それを自分自身の目的のために使用することはできない」(マルクス(『フランスの内乱』木下半治訳、岩波文庫、p.90.) |
| 「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」(イギリス軍歌『J・フォリイ』) |
| ワ | ||
| 「私の生涯は一遍の美しい童話である。それほど豊かで幸福なものだった!」(童話作家・ハンス・アンデルセン) | ||
| 「私は少なくとも、自らが知らぬことを知っているとは思わない」(哲学者・ソクラテス) | ||
| 「私はいつかは私の部署で倒れるでしょう。市街戦か牢獄の中で」(ローザ・ルクセンブルク) | ||
| 「私は君の意見に反対である。しかし私は、君がその意見を主張する権利を、死を賭してでも守る」(ヴォルテール) | ||
| 「私は私自身の証人である」(テクジュベリ) | ||
| 「笑いは全人類の謎を解く合鍵である」(カーライル) | ||
| 「我事に於いて後悔せず」(宮本武蔵「独行道」) | ||
| 「我に七難八苦を与えたまえ」(戦国武将・山中鹿之助) | ||
| 「我に自由を与えよ、しからずんば死を(give me liverty or give me death)」(パトリック・ヘンリー) | ||
|
||
| 「私達のやるべき事は成功ではない。失敗にも負けずに突き進むことである」(スチーブンソン) | ||
|
||
| 「我々自身が抱いている自信が、他人に対する信用を芽生えさせる」(ラ・ロシュフコー) | ||
| 「我々は宗派でもなければ、学派でも無い」(シュムペーター・1883-1950「計量経済学の常識」) | ||
| 「我々に武器を執らしめるものはいつも敵に対する恐怖である。 しかも屡々実在しない架空の敵に対する恐怖である」(芥川龍之介[1892-1927](小説家):侏儒の言葉) | ||
| 「我々は『間違いをおかす動物』です。『間違いをおかさない』ことは大切ですが、それよりも『間違った時にそれをどう解決していくか』の中にその人の真実性があらわれる」(まっぺん) | ||
| 「我々の生活に必要な思想は、三千年前に尽きたかも知れない。我々はタダ古い薪に新しい炎を加えるだけであろう」 (芥川龍之介[1892-1927](小説家):河童) | ||
| 「悪い状況は、放置しておくと、なお悪くなる 」(Arthur Bloch:Murphy's Law) | ||
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)