| 「大行(たいこう)は細瑾(さいきん)を顧みず」
|
| (解説) 司馬遷著『史記』の一節で、大事業を行おうとする者は些細な欠点はあまり顧慮しないものだ、の意。 |
|
「大山鳴動して鼠一匹」(古代ローマの詩人・ホラティウス)
(解説)前触ればかり大きくて小さな結果しか生まないという意味です。 |
| 「大衆はものを書かない批評家である」(ボルテール)
|
| (解説) ボルテールは18世紀のフランスの文学者、啓蒙思想家。 |
|
| 「大衆は愚にして賢」(西村栄一元自民党副総裁) |
| 「大丈夫、心配するな、何とかなる」(一休禅師) |
| 「大切な事はこの世に何年生きるかではなく、どれだけ価値のあることをするかにある」(詩人、劇作家、批評家・ウィリアム・ヘンリー) |
| 「大抵の友情は見せかけであり、大抵の恋は愚かさでしかない」(シェ−クスピア) |
| 「大部分の女性は多くの言葉を費やして、ごくわずかしか語らない」(聖職者、文学者・フランシス・フェヌロン) |
| 「倒れるごとに必ず起きあがること」(ゴールドスミス) |
| 「唾棄すべきは『お上』に頼る日本人のメンタリティーだ。これからは、自身の能力を信じて日本人は『お上』から自立すべきだ。自立した者には自由が与えられる」 |
| 「巧みな言葉を使い、他人の気に入るような顔つきをするものに誠実な人間は殆どいない」(論語) |
| 「多数の友を持つはひとりの友を持たず」(アリストテレス) |
| 「戦いは逆徳なり、争いは事の末なり」
|
| (解説) 司馬遷著『史記』の一節で、戦いは徳に逆らうものであり争いは万事の末である、の意。 |
|
| 「戦って勝つは易しく、守って勝つは難し」(兵法家・呉子) |
| 「闘わない理由はいくらでも出てくるが、闘う理由はひとつあればいい」 |
| 「脱皮できない蛇は滅びる」 |
| 「たった一言で、人の心を傷つける。たった一言で、人の心を温める」(仏語) |
| 「たどりてきて 未だ山麓」(升田幸三) |
| 「他人と比較して、他人が自分より優れていたとしても、それは恥ではない。しかし、去年の自分より今年の自分が優れていないのは立派な恥だ」(ラポック(英:自然探検家) |
| 「達人の人を見る眼は、少しも誤る所あるからず」。「達人の見るまなこは、おそろしきものとや」(徒然草第194段) |
| 「他人に対して善行をなす者は、何よりも多く己自身に対して善行をなす」(セネカ) |
| 「他人の知識で物知りになれるにしても、私たち自身の知恵によってでなければ知恵者にはなれない」モンテーニュ(1533−1592)「随想録」 |
| 「他人の後ろから行くものは、決して前進しているのではない」(ロマン・ロラン「ミケランジェロ」) |
| 「他人もまた同じ悲しみに悩んでいると思えば、心の傷は癒されなくても、気は楽になる」(シェークスピア) |
| 「種を蒔くのは収穫するほど難しくない。」(ゲ−テ) |
| 「旅に病んで夢は枯野を駆け巡る」(松尾芭蕉・1644−1694「笈(おい)日記」) |
| 「だました奴をだますことは二倍の喜び」(フォンテーヌ) |
| 「民富めば国富むの理」 |
| 「民を貴しと為し社稷(しゃしょく)之に次ぐ」(孟子)
|
| (解説) 社稷とは国家、政府のことです。民を第一に貴ばなければならない、国家のことは二の次だ、という意味です。「人民があって国家があり、国家があってこそ治める君がある。だから軽重をいえば根本である民が一番貴い」。諸橋轍次著「中国古典名言事典」(講談社学術文庫)には、「社は土神を祀り、稷は穀神を祭る。人君が国を建てると、必ずこの二者を祭るから『社稷』は国家の意となる」とある。 |
|
| 「民を視(み)ること傷(いた)むが如し」(孟子)
|
| (解説) 政治指導者は苦しんでいる人民に対していたわる気持ちで接するべきだ、という意味。 |
|
| 「誰の役にも立たないということは、はっきりいって何の価値もないということである」(デカルト) |
| 「男子、三日見ざれば、剋目して待つべし」 |
| 「断じて行えば鬼神もこれを避く」(司馬遷著『史記』の一節) |
| 「単純さ−−−真理そのものみたいに単純」(コーリキー・1868−1936「人間レーニン」) |
| 「談話の際は誰に話すか、何を話すか、何処で話すかに注意せよ」(詩人・ホラチウス) |
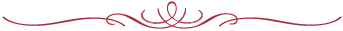
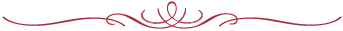
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)