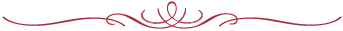
| 格言・名句(短)その1(ア~サ行) |
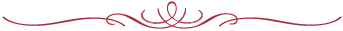
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年3.15日
| ア |
| 【愛】 | ||
| 「愛叉は憎しみと共演しないとき、女は凡庸な役者だ」(ニーチェ「善悪の悲願」) | ||
|
||
| 「愛する人が病気なら、ただ心配するのではなく、健康、活力、治癒を想像しなさい」(ジョゼフ・マーフィー) | ||
| 「愛は惜しみなく与う 」(トルストイ) | ||
| 「愛は幸運の財布である。与えれば与えるほど、中身が増す」(W.ミュラー) |
| 「アイデアが重要なのではない、一つのアイデアをどうやって具体的にしていくかが重要だ」(井深大) |
| 【悪】 | ||
|
||
|
||
| 「悪魔は9割核心に迫る事を言い、1割で巧妙なウソをつく」 |
| 【朝】 | ||
|
||
| 「朝に道を聞かば夕に死すとも可なり」(孔子) |
| 【足】 |
| 「足の皮は厚きがよし、面の皮は薄きがよし」(儒医・三浦梅園・1723-1789「戯示学徒」) |
| 【明日】 | ||
|
||
| 「明日何を為すべきかを知らない人間は不幸である」(ゴーリキー「フォーマ・ゴルデーエフ」) | ||
| 「明日の朝にしようと言ってはならぬ。朝が仕事を仕上げて持って来てくれるわけでは無い」(司教・クリソストムス) |
| 【汗】 |
| 「汗は自分で掻きましょう。手柄は人にあげましょう」、「相手に点数稼がせる」 |
| 【遊び】 |
| 「遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん。遊ぶ子供の声聞けば、わが身さへこそ動(ゆる)がるれ」(平安時代の歌謡集「梁塵秘抄」)。 |
| 【頭】 |
| 「頭が良くても、堅ければどうしようもない」 |
| 「頭が全てと思う者の愚かさよ! 」 |
| 「頭で考えるな 肌で掴め」(ブルース・リー) |
| 【アダム】 | ||
|
| 【新しい】 |
| 「新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ」(新約聖書) |
| 【あちこち】 |
| 「あちこちを旅して廻っても自分から逃げることは出来ない」(ヘミング・ウエイ) |
| 【あなた】 |
| 「あなたが深淵をのぞく時、深淵もまたあなたをのぞいている」(ニーチェ) |
| 「あなたの顔を日に向けよ。そうすればあなたは影を見ることができなくなる」(女流教育家・ヘレン・ケラー) |
| 「あなたの実力以上に有徳であろうとするな!できそうもないことを己に要求するな!」(F.W.ニーチェ・独の哲学者「ツァラトゥストラはこう言った」) |
| 「あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは、世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである」(ガンジー)。 |
| 「アホにアホ云う人はホンマのアホでっせ」(藤山寛美) |
| 【アメリカ】 |
| 「アメリカ企業の凄いところは、状況に応じて社員を上手く使い、勝負どころで的確な判断を下せることだ。つまり、大局を見極められるトップがいるということなのだ」 |
| 「危うきこと累卵の如し」 |
| (解説) 司馬遷著『史記』の一節で、その危ないこと、あたかも卵を積み重ねたようである、の意。累卵は卵を積み重ねること。きわめて危険な状態にあるという意味。 |
| 「過(あやま)てばすなわち改むるに憚ることなかれ」(論語・学而第一)」 | ||
|
| 【あらゆる】 |
| 「あらゆる恐怖の中で最も恐るべき恐怖は狂気にとりつかれた人間である」(ドイツの詩人シラー・1759~1805) |
|
「あらゆる堕落のなかで最も軽蔑すべきものは――他人の首にぶらさがることである」(ドストエフスキー『白痴』) |
| 「あらゆる芸術の士は、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえに尊い。(漱石)」 |
| 「あらゆることに深い意味があるわけではない。太陽は輝いているから、輝いているのであり、幸せな子供時代を送ったからではない」(E.S.スターン) |
| 【ある】 |
| 「ある一人の人間が傍にいると、他の人間の存在など、まったく問題にならない時がある。それが恋というものである」(ツルゲーネフ) |
| 「或る程度の精神の不健康さなしに、誰も詩人にはなりえない。 或いは叉、誰も詩を楽しむことは出来ない」(T.H.マコーレイ) |
| 「或ることを為した為に不正である場合のみならず、或ることを為さない為に不正である場合も少なくない」(マルクス・アウレーリウス「自省録」・神谷恵子訳) |
| イ |
| 「言う者は水に流す、言われた者は石に刻む」 | ||
| 「家は洩らぬ程、食事は飢えぬ程にて、足ることなり」(南坊宗啓「南方録」) | ||
| 「いかなる個人も時代の子である」(ヘーゲル) | ||
| 「いかなる人の知識も、その人の経験を越えるものではない」(J.ロック・英の哲学者・政治思想家) | ||
| 「いかなる師にも盲目的に従うことを禁ずるものは、伝統それ自身なのである」(ロダン・1840-1917「遺言」) | ||
| 「いかなる名参謀も、将師の決断力不足だけは補佐できない」(クラウゼヴィッツ) | ||
|
||
|
||
| 「いかに弱き人と言えども、その全力単一の目的に集中すれば必ずその事をなし得る」(春日潜庵(せんあん)明治の儒家) | ||
| 「怒りは愚かな者を殺し 妬みは馬鹿者の生命を奪う」(旧約聖書) | ||
| 「怒った人間は口を開いて目を閉じる」(カトー) | ||
| 「怒りの鎮まる時 後悔がやってくる」(ソフォクレス) | ||
|
||
|
||
| 「生きる事の最大の障害は期待を持つという事であるが、それは明日に依存して今日を失う事である」(哲学者 セネカ) | ||
| 「憤りをもって過去を振り返るな。 恐れをもって未来をみるな。 しっかりと現在を見つめよ」(J.サーバー[1894-1961](米:小説家.随筆家)) | ||
| 「意見というものは結局感情によって決められる、知性によってではなく」(H.スペンサー[1820-1903]・英:進化論哲学者) | ||
| 「諌めてくれる部下は、一番槍をする勇士より値打ちがある」(徳川家康) | ||
| 「医師の薬を用いるに、下医は薬を毒と為し、中医は毒を毒に使い、上医き毒を医に用う」(鎌倉時代の「沙石集」)。 | ||
| 「一家は習慣の学校なり。父母は習慣の教師なり」(教育者・福沢諭吉) | ||
| 「一芸は万芸に通ず」(世阿弥「花伝書」、宮本武蔵) | ||
|
||
| 「一切の善の始まりであり根であるのは、胃袋の快である」(哲学者・エピクロス) | ||
| 「一丈の堀を越えんと思わん人は、一丈五尺を超えんと励むべきなり」(法然又の名を源空・1133-1212「一言芳談」) | ||
| 「一緒に縛り首になろう(let us hang together)」(ベンジャミン・フランクリン) | ||
| 「一生の仕事を見出した人は幸福である。彼には他の幸福を捜させる必要はない」(思想家、歴史家・トーマス・カーライル) | ||
|
||
|
||
|
||
| 「一日生きることは一歩進むことでありたい(湯川秀樹)」 | ||
| 「一日の苦労は一日にて足れり」(新約聖書) | ||
| 「一年の計は、穀を樹うるに如くはなく、十年の計は、木を樹うるに如くはなく、 終身の計は、人を樹うるに如くはなし」(中国の春秋時代、名宰相と呼ばれた管仲)。 | ||
|
||
| 「一流のリーダー、二流のボス」 | ||
|
||
| 「意識とは絶望の関数である」(キルケゴール) | ||
| 「急いで結婚する必要はない、結婚は果実と違って季節はずれに成ることはない。」(トルストイ) | ||
| 「急がず 休まず」(ゲーテ) | ||
| 「忙しい人間は涙のための時間を持たない」 (バイロン) | ||
|
||
| 「衣食足りて礼節を知る」 | ||
| 「偉人の企てを立派に受け継ぐことが、偉人の生命を引き延ばすことになる」(思想家、劇作家・ベルナール・フォントネル) | ||
|
||
| 「いつまでも続く不幸というものはない。じっと我慢するか勇気を出して追い払うかのいずれかだ」(作家・ロマン・ローラン) | ||
| 「いつまでも若くありたいと思うならば、青年の心をもって心としなければならない」(政治家・ウィリアム・グラッドストン) | ||
|
||
|
||
| 「今は憂世に思い置く事なし。さらば暇申して」(平忠度ただのり・1444-1484) | ||
| 「いのち短し、恋せよ乙女、紅きくちびるあせぬまに」 | ||
| 「今が最悪の事態と言える間は最悪ではない」(シェークスピア) | ||
|
||
| 「今は実際みんなお先真っ暗でござんすよ」(若山牧水・1885-1928「石川啄木の啄木日記」) | ||
| 「未だ生を知らず いずくんぞ死を知らん」(論語) | ||
| 「いまだかって1度も敵を作った事のないような人間は決して友人も持たない」(テニスン) |
| ウ |
| 「上、下を知るのに三年、下、上を知るのに三日」 | ||
| 「牛飼いが歌詠む時に世の中の新しき歌大いにおこる」(伊藤左千夫「左千夫歌集」) | ||
| 「嘘も方便である。しかし善意から発したものでなくてはならない」 | ||
|
||
|
「瓜田に履を納れず。李下に冠を正さず」。 |
||
| 「運命と云うものは、人をいかなる災難に合わせても、必ず一方の戸口を開けておいて、そこから救いの手を差し伸べてくれるものよ」(セルバンテス「ドン・キホーテ」) | ||
| 「運命の中に偶然はない。人間はある運命に出会う以前に自分がそれをつくっているのだ」(政治家・トーマス・ウィルソン) | ||
| 「運命はな……災難にあわせても、一方の扉を必ず開いて、救いの道を残すのじゃ」(作家・セルバンテス) | ||
| 「運、不運はナイフのようなものだ。その刃を握るか柄を握るかで、我々を傷つけたり、役に立ったりする」(アメリカの詩人J・R・ローウェル) | ||
| 「運命の中に偶然はない」(ウィルソン) | ||
| 「運は我々から富を奪うことは出来ても、勇気を奪うことは出来ない」(セネカ) |
| エ |
| 「絵は語らざる詩であり、詩は語る才能を伴いし絵なり」(プルタルコス「シモニデスの生涯」) | ||
| 「英知は泉である。その水を飲めば飲むほど、ますます大きく、力強く、再び吹き出してくる」(アンゲルス・ジレジウス「さすらいの天使」) | ||
|
||
| 「偉くなるには、まず大将のふところに入ることだ」(田中角栄) | ||
|
||
| 「演説とは英語にて『スピイチ』と云い、大勢の人を会して説を述べ、席上われ思うところを人に伝えるの法なり。我が国は古(いにしえ)よりその法あるを聞かず」(福沢諭吉「学問のすすめ」の一節)。 | ||
|
| オ |
| 「おあしす運動」(おはよう・ありがとう・失礼します・すみません) | ||
| 「負いかた一つで、重荷も軽い」(作家・ヘンリー・フィールディング) | ||
| 「大いなる若気の至りが個性の芽を育てる」(本田宗一郎) | ||
| 「大きな町には大きな孤独」(ストラボン) | ||
| 「大きな悲しみには勇気をもって立ち向かい、小さな悲しみには忍耐を持って立ち向かうのです。そして一日の仕事を終えたら安らかに眠るのです。あとは神が守ってくださるのです」(ビクトル・ユーゴ)。 | ||
| 「多くの仕事をしようとする者は、今すぐに一つの仕事をしなければならない」(実業家・ロスチャイルド) | ||
| 「多くの婦人を愛した人間よりも、たった一人の婦人だけを愛した人間の方が遙かに深く女というものを知っている」(トルストイ) | ||
| 「大きい街には大きな孤独」(イギリスの諺) | ||
| 「大きな敗北を別にすれば……大きな勝利ほど恐ろしいものはない」(軍人、政治家・アーサー・ウェリントン) | ||
| 「臆病でためらいがちな人間にとって、一切は不可能である。なぜなら、一切が不可能のように見えるからだ」(詩人、作家・ウォルター・スコット) | ||
| 「王侯将相いずくんぞ種あらんや」 | ||
| 「王にせよ農夫にせよ、その家において平和を見いだす者は最も幸福な人である」(ゲーテ) | ||
| 「王侯の宮廷や貴族の応接室では、しばしばおべっかと嘘が功績や能力などより幅を利かす」(アダム・スミス・1723-1790「道徳情操論」) | ||
| 「大文字ばかりで印刷された本は読みにくい。休日ばかりの人生もそれと同じだ」(言語学者・ヘルマン・パウル) | ||
| 「起きて半畳、寝て一畳、天下とっても二合半」 | ||
| 「臆病者の目には、常に敵が大軍に見える」(織田信長、長篠の合戦) | ||
| 「起こったことをそのまま受け入れることは不幸を克服する第一歩である」(哲学者、心理学者・ウィリアム・ジェームズ) | ||
| 「怒った人間は口を開いて目を閉じる 」(カトー) | ||
| 「驕(おご)れる者は久しからず、ただ春の夜の夢の如し…」(「平家物語」) | ||
| 「教える事は二度習う事である」(モラリスト・ジョセフ・ジュベール) | ||
| 「おなじ河を二度下ることはできない」(ヘラクレイトス) | ||
| 「同じ状況でも、凡将が見ればピンチであり、名将が見ればチャンスである」 | ||
| 「己の欲せざる所を人に施すことなかれ」(『論語』) | ||
| 「おのれの職分を守り黙々として勤めることは、中傷に対する最上の答えである」(政治家、大統領・ジョージ・ワシントン) | ||
|
||
|
||
| 「面白きことのなき世を面白く」(高杉晋作) | ||
|
||
|
||
| 「女は深く見る、男は遠くを見る」(グラッペ) |
| カ |
|
||
| 「快楽こそ生まれつきの善である」(エピクロス) | ||
| 「快楽を得ようと努力するのではなく、努力そのものの中に快楽を見出す事、それが私の幸福への秘密である」(作家・アンドレ・ジート) | ||
| 「快楽は罪だ そしてときとして罪は快楽だ」(バイロン) | ||
| 「顔の表情が感情を左右する重要な要素であることは明らかである」(フリッツ・シュトラーク・独:社会心理学者) | ||
| 「科学者になるには自然を恋人としなければならない。自然はやはりその恋人のみ真心を打ち明けるものである」(物理学者、文学者 ・寺田寅彦) | ||
| 「確信は真理にとってウソより危険だ」(フリードリッヒ・ニーチェ、1878年) | ||
| 「『革命の経験』をやり遂げることは、それを筆にすることよりも、より愉快であり、より有益である」(レーニン・1870-1924「国家と革命」) | ||
| 「かくも僅かしか為さず、かくも為すべき事多くして」(政治家・セシル・ローズ) | ||
| 「学問そのものは自らの使用法を教えない」(ベイコン・1561-1626「随筆集」) | ||
| 「学問のある馬鹿は、無知な馬鹿よりもっと馬鹿だ」(劇作家 モリエール) | ||
| 「過去に無知な者は同じ過ちを犯す運命にある」(米国の哲学者・ジョージ・サンタヤーナ) | ||
| 「過去に目を閉ざす者は現在に盲目になる」(元西ドイツ大統領のヴァイツゼッカーが終戦40周年の1985年におこなった演説のくだり) | ||
| 「過失の弁解をすると、その過失を目立たせる」(シェイクスピア「ジョン王-4篇3場」) | ||
| 「形あるものが役立つのは、形無き空間が根底で形ある物を支えているからである」(『老子』11章) | ||
| 「勝つことばかり知りて負くることを知らざれば、害その身に至る」(徳川家康「遺訓」) | ||
|
「勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし」(肥前国平戸藩第9代藩主、松浦静山が残した言葉。野村克也元楽天監督が2010自民党党大会に参加し、引用した) |
||
| 「家畜ですら牧場を去るべき時機を知っている。愚かな人は、自分の食欲の限度を知らない」(アンデルセン「断片」) | ||
| 「かってない困難からは、かってない革新が生まれ、かってない革新からはかってない飛躍が生まれる」(松下幸之助) | ||
| 「悲しみは、人に打ち明ける事で、たとえ癒されはしないまでも、やわらげられる」(B.P.カルデロン) | ||
| 「悲しむことはない。いまの状態で何ができるかを考えて、ベストを尽くすことだ」(哲学者、作家・ジャン・ポール・サルトル) | ||
| 「金があれば世の中何でもできる。しかし青春は金では買えないのだ」(ライムント) | ||
| 「金を貸すと金も友達もなくしてしまう」(シェイクスピア) | ||
| 「金は良い召使でもあるが、悪い主人でもある」(政治家、哲学者・フランシス・ベーコン) | ||
| 「金も地位も名誉も欲しくない、命すら要らぬというのはバカだが、そのバカこそ天下国家のためになる」(西郷隆盛) | ||
| 「金持ちでも貧乏でも、自分の家庭で平和を見出せる人が、一番幸福な人間である」(ゲーテ) | ||
| 「金を失うことは小さい事である。信用を失うことは大きい事である。勇気を失うことは自分を失う事である 」(大山倍達) | ||
|
||
|
||
| 「神々は死んだ」(二ィチェ・1844-1900「ツァラツゥストラはかく語った」) | ||
|
ネイティブアメリカンの名言
■「神はすべてのものをシンプルに創った。インディアンの人生はとてもシンプルだ。わしらは自由に生きている。従うべきただひとつの法は自然の法、神の法だ。わしらはその法にしか従わない」(ラコタ族マシュー・キングの言葉) |
||
| 「神は人の敬いによって威を増し、人は神の徳によって運を添う」 | ||
|
||
| 「彼(相手)を知り、己を知れば、百戦して殆(あや)うからず。彼を知らず、己を知らざれば、戦う毎に必ず殆うし」(孫子『謀攻扁第3』) | ||
|
||
| 「可愛くバ五つ教えて三つ褒め、二つ叱って良き人とせよ」(二宮尊徳の教訓歌) | ||
| 「感覚が麻痺するような生活は、時に幸せを鈍化させるのではと」(ボクシング・WBAミドル級世界王者の村田諒太選手(32)が、飛行機に乗った際に感じた若者に対するボヤきをフェイスブックに綴る)。 | ||
| 「『姦淫するなかれ』と云へることあるを汝等きけり。されど我は汝等に告ぐ、すべて色情を懷きて女を見るものは、既に心のうち姦淫したるなり」(マタイ 5.27) | ||
| 「感謝する事を知らぬ子供を持つことは、蛇の歯よりもいかに怖るべきことか」(劇作家・ウィリアム・シェークスピア) | ||
| 「簡単なことを完璧にやる忍耐力の持ち主だけが、いつも困難ことを軽々とこなす熟練を身につける」(ドイツ詩人・シラー) | ||
| 「願望の実現が夢の内容である」(フロイト・1856-1939「精神分析学入門」) |
| キ |
|
||
| 「岸を見失う勇気が無ければ、新しい太洋を発見できない」(ジード) | ||
| 「疑心は暗鬼を生ず」(「列子」) | ||
| 「奇跡は誰にでも毎日起きている。本当のチャレンジは、それに気づいて、受け入れること」(E.S.スターン) | ||
| 「木に縁(よ)って魚を求める」(孟子)
(解説)[手段が誤っているという意味。孟子(BC372-289)は中国・戦国時代の思想家] |
||
|
||
|
||
| 「義務は知ることは容易だが、人がいちばん果たしたがらないものだ」(イギリスの諺) | ||
| 「義を見てせざるは勇無きなり」(論語) | ||
| 「希望は人を成功に導く方法である。希望がなければ、何事も達成できるものではない」(へレン・ケラー) | ||
| 「希望は不幸な人間の第二の魂である 」(ゲーテ) | ||
| 「希望は強い勇気であり新たな意志である」(ルター) | ||
| 「希望は永久に人間の胸に湧く。人間は常に現在幸せであることはなく、いつもこれから幸せになるのだ」(ポープ「人間論」) | ||
| 「逆境の利益とはすばらしいものだ」(シェイクスピア) | ||
| 「逆境と苦悩のにじみ出る所に真実はある」(メンケン) | ||
| 「逆境は最良の教師なり」(ディズレーリ) | ||
| 「逆境にも希望と喜びがなくはない」(ベーコン) | ||
| 「牛乳を配達する人間は、これを飲む人間よりも健康である」(西洋の諺) | ||
| 「京ニ居レバ京者ノ外ノ知恵ヲ出セ、江戸ニ居レバ江戸者ノ外ノ知恵ヲ出セ」(思想家・海保青陵) | ||
| 「ギョエテとは俺の事かとゲーテいい」 | ||
|
||
|
||
| 「九じんの功をいっきに欠く」
(長い間の努力もちょっとした手違いで失敗すること) |
||
| 「今日できることは明日まで延ばすな」 | ||
| 「今日の問題をまじめに考えるという態度をもっていないならば、 明日の事は絶対に考えることは出来ない」(中野重治[1902-79](詩人.小説家.評論家):啄木と「近代」) | ||
| 「境遇が人間を作るのではない。人間が境遇を作るのだ」(政治家ベンジャミン・ディズレーリ) | ||
| 「境遇とか!われ境遇を作らん」(ナポレオン) | ||
| 「共同の所有物は共同でなおざりにする」(中世ラテンの諺) | ||
| 「恐怖感を持つ人間は、善いことよりも悪いことを信じやすく、悪いことは誇大に考えやすい」(クラウゼウィッツ) | ||
| 「金銭は底のない海のごとし。良心も名誉も溺れて浮かばれず。借金するのは自由を売ることなり」(政治家、出版業者、科学者・ベンジャミン・フランクリン) | ||
| 「金言は一人の人間の機知であり、万人の知恵である」(19世紀のイギリスの社会批評家・ジョン・ラスキン) |
| ク |
| 「愚者は自分の経験から学び、賢者は他人の経験から学ぶ」(ビスマルク) | ||
| 「悔は凶より吉におもむく道なり」(中江藤樹) | ||
| 「空想は知識よりも重要である」(アインシュタイン) | ||
| 「偶然は準備のできていない人を助けない」(パスツール) | ||
| 「薬(仏法の事)あればとて毒を好むべからず」(僧侶・親鸞) | ||
| 「口に蜜あり、腹に剣あり」(「唐書」の「李林甫伝」) | ||
|
||
| 「苦悩をくぐりぬけて歓喜へ!」(ベートーベン) | ||
| 「苦しみの中に道はひらかれた」(アグネス・スメドレー) | ||
| 「黒猫でも白猫でも、ねずみを取るのはいいネコだ」(鄧小平) | ||
|
||
|
||
|
||
| 「君子は安けれども危うきを忘れず、存すれども亡ぶるを忘れず。治まれども乱るるを忘れず。ここを以って身安くして、国家保つべきなり」(易経) | ||
| 「君子は豹変す」(易経) | ||
| 「君子は和して流れず。強なるかな矯たり。中立してかたよらず。強なるかな矯たり」(中庸) |
| ケ |
| 「稽古とは一より習い、十を知り、十よりかへる元のその一」(千利休) | ||
|
||
| 「鶏口となるも、牛後となるなかれ」(中国古典「戦国策」)」 | ||
| 「芸術は音楽に憧れる。とすれば同じ意味合いで、思想は言語に憧れる。政治は宗教に憧れる」(れんだいこ) | ||
| 「芸術家である前に人間であること」(ロダン・1840-1917「遺言」) | ||
| 「結局、勝利は流した汗と涙の量による」(田中角栄) | ||
| 「結婚前にはしっかりと目を開き、結婚してからは目をつむっていることだ」(神学者、警句家・トーマス・ヘラー) | ||
| 「決闘に侵略決闘と防衛決闘の区別があると考えるのは馬鹿げたことではないか」(弁護士レービンソン) | ||
| 「月雪花は一度に眺められず」(日本の諺) | ||
| 「謙虚であることをわきまえている人は最高のことを企てることができる」(ゲーテ・1749―1832) | ||
| 「言論の自由を殺すのは真理を殺すことである」(ミルトン) | ||
| 「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」 | ||
| 「元始、女性は太陽であった。真正の人であった」(文学者・平塚雷鳥) | ||
| 「現場に神宿る」(中坊公平) | ||
| 「賢者は他人の体験から学ぶ」、「賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク) | ||
|
||
| 「言論の自由ではなく、自由な言論を!」(竹中労) | ||
| 「言論の自由を殺すのは真理を殺すことである」(17世紀イギリスの詩人ミルトン・1608―74) | ||
| 「剣を取る者は、皆、剣で滅びる」(『新約聖書』) |
| コ |
| 「孤に徹し、衆と和す」 | ||
| 「光陰矢のごとし」 | ||
| 「行為する者にとって、行為せざる者は最も過酷な批判者である」 | ||
| 「皇国の興廃この一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」 | ||
|
||
| 「幸運は心の準備ができている者を好む」(パスツール) | ||
| 「幸福とは、そのまま変わらないで続いて欲しいような、そんな状態である」(フォントネル・1657-1757「幸福論」) | ||
| 「幸福は、「行動する手間」を省く人のところには来ない。幸福とはその人間の希望と才能にかなった仕事のある状態を言う。不幸とは働くエネルギーを保ちながら、無為に過ごしている状態をいうのである」(B.ナポレオン[1769-1821](仏:軍人.皇帝)) | ||
| 「幸福だけの幸福はパンばかりのようなものだ。食えはするがごちそうにはならない。無駄なもの、無用なもの、余計なもの、多過ぎるもの、何の役にも立たないもの、それらがわしは好きだ」(ユーゴー「レ・ミゼラブル」) | ||
|
||
| 「香餌の下には必ず死魚あり」(兵法書・『三略』) | ||
|
||
|
||
| 「心ここに在らざれば視れども視えず、聴けども聞こえず」(『大学』) | ||
| 「心に愛がなければ、どんな言葉も相手の胸に響かない」(心の燭/カトリック教會) | ||
| 「心は天国を作りまた地獄を作る」(ミルトン) | ||
| 「志定まれば 気さかんなり」(吉田松陰) | ||
|
||
| 「五色のけばけばしい色彩は人間の目をくらます」(『老子』12章) | ||
| 「古人の跡を求めず古人の求めたる所をもとめよ」(松尾芭蕉) | ||
|
||
| 「国家の実力は地方に存する 」(徳富蘆花) | ||
| 「コップに半分の水を見て、『もう半分しかない』と自重を促すのは銀行であり、『まだ半分も残っている』と勇み立つのは経営者というものである」 | ||
| 「言葉は磨けば宝石よりも光り輝き、正しく使えば、どんな武力にも負けない力を発揮する」 | ||
| 「孤独は山になく、街にある。一人の人間にあるのではなく、大勢の人間の『間』にあるのである」(三木清「人生論ノート」) | ||
| 「子に過ぎたる宝なし。千の倉より子は宝」(幸若「鎌田」) | ||
| 「子供には、すべて、最も大きな可能性がある」(トルストイ) | ||
| 「この世の中に人間ほど凶悪な動物はいない。狼は共食いをしないが、人間は人間を生きながら丸呑みにする」(ガルーシン、19世紀のロシアの作家) | ||
| 「この世の人は、男は女にあうことをす、女は男にあう事をす」(『竹取物語』) | ||
|
「この世の中で一番むずかしいことは、自分自身を知ることである」(ターレス) |
||
| 「この世界における大事件の歴史は、犯罪史のほか何ものでもない」(ヴォルテール) | ||
| 「高慢には必ず墜落がある」(シェークスピア) | ||
|
||
| 「五十にして四十九の非を知る」(『淮南子』) | ||
| 「ゴルフはアホには最高のゲーム」(英国貴族にして詩人のサー・ウォルター・シンプソン) | ||
| 「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者の如かず」(学者・思想家 孔子) | ||
|
||
| 「『これが最悪』などと言える間は、まだ実際のどん底なのではない」(劇作家・ウィリアム・シェークスピア) | ||
| 「これは意見が一致しないだろうということで、みなの意見が一致した」 | ||
| 「子を思う親の心で弟子を導け」(双葉山) | ||
| サ |
| 「最高の男性は独身者の中にいるが、最高の女性は既婚者の中にいる」(R・L・スチブンソン) | ||
| 「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候 死ぬ時節には死ぬがよく候、これはこれ災難を逃るる 妙法にて候」(良寛) | ||
| 「才能はひとりでに培われる。しかし、性格は世間の荒波にもまれてつくられる」(ゲーテ「タッソー」) | ||
| 「才能が終わると形式が始まる」(リーベルマン) | ||
| 「才能とは、自分自身を、自分の力を、信ずることである 」(露のプロレタリア文学最大の作家・ゴーリキー) | ||
| 「才能と意志の欠けているところに、一番嫉妬が生まれる」(ヒルティ) | ||
|
||
|
||
| 「財布が軽ければ心は重い」(ゲーテ) | ||
| 「最良の予言者は過去なり」(バイロン) | ||
| 「座して食らえば、泰山も空(むな)し」 | ||
| 「最大の説得力は実践だ」(土光敏夫) | ||
|
||
| 「酒と人間とは絶えず闘い、絶えず和解している仲の良い2人の闘士のような気がする。負けた方が常に勝った方を抱擁する。 (ボ-ドレ-ル 仏の詩人)」 | ||
|
||
| 「酒の一杯は健康のため、二杯は快楽のため、三杯は放縦のため、四杯は狂気のため」(哲学者・アナカルシス) | ||
| 「雑草とは何か?その美点がまだ発見されていない植物である」(エマーソン「共和国の繁栄」) | ||
| 「悟りとは悟らで悟る悟りなり 悟る悟りは夢の悟りぞ」 | ||
| 「されば人、死を憎まば生を愛すべし、存命の喜び日々楽しまざらんや」(徒然草) | ||
| 「去る者、日々に疎し」 | ||
| 「去る者は追わず、来るものは拒まず」(哲学者・孟子) | ||
| 「参加することに意義あり」 | ||
| 「残虐はすべて弱さから生ずる」(セネカ) | ||
| 「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」(王陽明) | ||
| 「三人の女を互いに喧嘩をさせず、うまく御していくだけの力量がないと、一国の宰相にはなれぬ」(中国の俗諺) |
| シ |
| 「士たる者、その志を立てざるべからず。それ志あるところ、気も又従う」(吉田松陰) | ||
| 「塩漬けのない肉と折檻されない子供は腐敗する」(デンマークの諺) | ||
| 「四季はそれぞれ季節が来れば常に我々に一番良い」(思想家、随筆家・ヘンリー・ソロー) | ||
| 「至言は耳にさからう」(韓非子) | ||
| 「自己に慢じて先に進む事を知らざる人は、身を終わるとも達人に成り難し」(向井去来) | ||
| 「自己を知ることはやがて他人を知ることである」(三木清) | ||
| 「自己を燈明とし依処とせよ」(仏陀) | ||
| 「地獄への道は善意で敷き詰められている」 | ||
| 「仕事が楽しみなら、人生は天国だ! 仕事が義務なら人生は地獄だ!」(哲学者・セネカ) | ||
| 「真実(事実)は小説よりも奇なり」(詩人・ジョージ・バイロン) | ||
| 「事実がわかっていなくても前進することだ、やってる間に事実もわかってこよう」(フォード) | ||
| 「自然より出て自然に帰る」(アウレリウス) | ||
| 「時代が欲求するなら受けて立つ人間になれ」() | ||
| 「時代閉塞の現状に宣戦しなければならぬ」(石川啄木・1885-1912「時代閉塞の現状」) | ||
| 「士は己を知る者のために死す」 | ||
| 「死中に活を得、活中に死を得」(仏書 碧巌録(へきがんろく))
(解説)死を覚悟して物事を行えば、かえってその中に生きる道が得られ、生きることにのみ執着して物事を行うとその為に死ぬ事にもなる。 |
||
| 「死に至る病とは絶望の事である」(キェルケゴール) | ||
| 「死んでから佛になるハいらぬもの 生きたる中によき人となれ」(某禅師の狂歌) | ||
| 「死はあるいは泰山より重く、あるいは鴻毛より軽し」(司馬遷「報任卿書」)。 | ||
| 「詩とは感情の神経を掴んだものである。生きて働く心理学である」(萩原朔太郎・1866-1942) | ||
| 「子孫の為に計画を立てる場合、美徳は相続されないことを忘れてはならない」(トーマス・ペイン「コモン・センス」) | ||
|
||
| 「実に敵という敵の中で山の神ほど恐ろしい敵はない」(森鴎外) | ||
| 「失敗の言い訳をすると、その失敗を際立たせる」(シェークスピア) | ||
| 「失敗だって? 私はまだそんな目にあったことはないよ。 一寸立ち止まっただけさ」(ドディ・ウォルターズ) | ||
| 「失敗・挫折・徒労をくぐりぬけたところにしか存在しない資質-私はこういった資質だけしか信じられないように思われる」(アルベルト・ジャコメッティ) | ||
| 「失敗しても必ず何かを学ぶが、やってみなければ、悔いだけが残る」(キングスレイ・ウォード「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」) | ||
|
||
| 「してみせて、云って聞かせて、やらせてみ、それで褒めねば人は動かじ」 | ||
|
||
|
||
| 「しばしの別離は再会をいっそう快いものにする」(ミルトン) | ||
| 「自分しか歩けない道を自分で探しながらマイペースで歩け」(紀伊国屋創業者・田辺茂一) | ||
| 「自分一人で石を持ち上げる気がなかったら、二人がかりでも石は持ち上がらない」(ゲーテ) | ||
| 「自分がなりたいと思うような人間に、既になった気持ちで行動せよ。間もなく必ずそうなる」(ジョージ・クレイン) | ||
| 「自分が自分にならないで誰が自分になる」(相田みつを) | ||
| 「自分のつらが曲がっているのに、鏡を責めて何になろう」(作家・ニコライ・ゴーゴリ) | ||
| 「志は、気の師なり」(孟子) | ||
| 「社長を使える人間が、その会社にいれば大したもので、百人いれば無限に発展する」(松下幸之助) | ||
| 「邪教が栄える時、国に災悪が起る」(日蓮)。 | ||
| 「ジャーナリズムとは報じられたくない事を報じることだ。それ以外のものは広報にすぎない」(ジョージ・オーウェル) | ||
|
||
| 「重要なことはなにを堪え忍んだかではなく、いかに堪え忍んだかである」(セネカ) | ||
| 「充実して過ごされた一生は安らかな死を与える」(画家、建築家、彫刻家・レオナルド・ダ・ヴィンチ) | ||
| 「熟練だけでは十分ではない。インテリジェントな思想のみ、芸術を理解し、創造する」(フランチェスコ・ド・オランダ編「対話」) | ||
| 「順境にいる時、逆境に備えよ」(菜根譚) | ||
| 「初心忘るべからず」(能役者 世阿弥元清・1363-1443「花伝書」) | ||
|
||
|
||
|
「修身 斉家 治国 平天下」(中国の『四経』の最も基本とされる『大学』) |
||
| 「柔は能く剛を制し、弱は能く強を制す」(兵法書・『三略』) | ||
| 「習慣とは帝王である。それによってなし得ないものはなにもない」 | ||
| 「所詮、IQなんて反射的判断力や早見え能力しか反映していない。人生で真に大切な能力は、人の嫌う辛い仕事を、長い時間かけてでもやり抜く力だ」(数学者/秋山仁)。 | ||
| 「衆生本来、仏なり。衆生の外に仏なし。衆生近きを知らずして、遠く求むるはかなさよ。例えば水の中に居て、渇を叫ぶが如くなり」(白隠禅師)。 | ||
| 「書を読めば万倍の利あり」(王安石) | ||
|
||
| 「生涯一捕手」(野村克也) | ||
| 「勝者敗因を秘め、敗者勝因を蔵す」 | ||
| 「勝利は同じ人間の上には永くとどまることはない」(ホメロス) | ||
| 「将、我が計を聴き、これを用うれば必ず勝たん」(孫子) | ||
|
||
| 「少年よ大志を抱け(Boys be ambisious)」(クラーク) | ||
| 「少年老いやすく学成りがたし。一寸の光陰軽んずべからず。未ださめやらず池とう春草の夢、階前のご桐すでに秋声」(朱き) | ||
| 「上手とは外(ほか)をそしらず自慢せず 身の及ばぬを恥づる人なり」 | ||
| 「主君の頭脳の程度はその宰相を見ればわかる」(政治学者、歴史家・ニコロ・マキャヴェリ) | ||
| 「主役たるの条件は、トラブルを解決することで、これの出来ない者は、いかに美男美女でも、通行人に過ぎない」(ジョージ・三木) | ||
| 「自由と我儘との界(さかい)は、他人の妨(さまたげ)を為すと為さざるとの間にあり 」(福沢諭吉『学問のすゝめ』)。 | ||
| 「自由には義務という保証人が必要だ。それが無ければ単なるわがままとなる」(ツルゲーネフ) | ||
| 「自由こそ高度の教養が芽生えてくる土壌である」(ドイツの哲学者フィヒテ・1762―1814) | ||
| 「自由は重荷である」(サルトル) | ||
| 「小の虫を殺して大の虫を助ける」 | ||
| 「将を射んと欲すれば、まず馬を射よ」 | ||
| 「常識は本能であり、それが十分にあるのが天才である」(バーナード・ショウ「断片」) | ||
| 「知らしむべからず依らしむべし」 | ||
|
||
| 「知る事が難しいのではない。いかにその知っている事を身に処するかが難しいのだ」(『史記』) | ||
| 「春宵(しゅんしょう)一刻価千金」 | ||
| 「白砂糖は黒砂糖からできる」(秋山真之) | ||
|
||
|
「深慮遠望、これこそが勇気である」(古代ギリシアの悲劇詩人エウリピデス) |
||
| 「人生五十年、下天のうちを比ぶれば、夢、幻のごとくなり」(幸若舞)(謡曲「敦盛」) | ||
| 「人生そのものが登山であり冒険である」(ヒラリー) | ||
|
||
| 「人生とは切符を買って軌道上の道を走る車に乗っている人には分からないものである」(作家・サマセット・モーム) | ||
| 「人生において大事なのは生きることであって、生きた結果ではない」(ゲーテ) | ||
| 「人生は、私たちが人生とは何かを知る前にもう半分過ぎている」((アーネスト・ヘンリー)) | ||
| 「人生は一箱のマッチに似ている。 重大に扱うのはばかばかしい。 重大に扱わねば危険である」(芥川龍之介)。 | ||
| 「人生も物語のようなものだ。重要なことはどんなに長いかということではなく、どんなに良いかということだ」(セネカ) | ||
| 「人生に成功する秘訣は、自分が好む仕事をすることではなく、自分のやっている仕事を好きになることである」(ゲーテ) | ||
| 「人生の行路をかなり遠くまで辿ってくると、以前は偶然の道連れに過ぎぬと考えていた多くの人が、ふと気がつくと、実は誠実な友だったことがわかる」(H.カロッサ[1878-1956](独:詩人.小説家) | ||
| 「人生 二つの永遠の間のわずかな一閃」(カーライル) | ||
| 「人生は宿屋 死は旅行の終わり」(ドライデン) | ||
| 「人生は海、船頭は金である。船頭がいなければ、うまく世渡りができない」(ヴェッケルリン「格言詩集」) | ||
| 「人生の目的は行為にして思想にあらず」(カーライル) | ||
|
||
|
||
| 論語に「仁者寿」(じんしゃは、いのちながし)。 | ||
| 「心配事で人の元気を消耗させる原因は、外の仕事にあるというよりも内の細事にある」(政治家・勝海舟) | ||
| 「真の勇気とは、人の見ていないときに示される」(ラ・ロシュフーコー「箴言集」) | ||
| 「真実を見極めることは難しいのだから、上辺だけでワナに陥らないよう気をつけよ」 | ||
| 「真実が靴の紐を結ばぬうちに、虚偽のニュースは世界を一周してしまう」(「トム・ソウヤーの冒険」の著者として知られるマーク・トウェーン) | ||
| 「心配や憂いは新しいものを考え出す一つの転機。正々堂々とこれに取り組めば新たな道が開けてくる」(松下幸之助) | ||
| 「シンプル・イズ・ベスト」 | ||
| 「進歩とは反省の厳しさに正比例する」(本田宗一郎) |
| ス |
| 「水中を泳ぐ魚が水を飲んでも知られることがないように、職務に任じられた官吏が財を着服しても知られる事は無い」(カウティリア「実利論」) | ||
|
||
| 「過ぎたるは猶及ばざるが如し」(論語) | ||
| 「すぐれた人間の大きな特徴は不幸で苦しい境遇にじっと耐え忍ぶこと」(ベートーベン) | ||
| 「スコットランドには裏切り者がたくさんいる。私はここで外国の手に落ちて苦労が絶えない」(ロバート・バーンズ「メアリ女王を悼む」・スコットランド女王メアリより) | ||
| 「進む時は人任せ、退く時は自ら決せよ」(越後・長岡藩・河井継之助) | ||
| 「すべて真の生とは、出会いである」(哲学者・マルティン・ブーバー) | ||
| 「すべての偉大な人々は謙虚である」(18世紀ドイツの劇作家レッシング・1729―81) | ||
| 「すべての残忍性は臆病から生ず」(セネカ) | ||
|
||
| 「すべての嬰児は、神がまだ人間に絶望していないというメッセージを携えて生まれてくる」(詩人、思想家・ラビンドラナート・タゴール) | ||
| 「素直ではない悪餓鬼は叱り飛ばすに限る」(木村愛二) | ||
| 「すべての人間は生まれつき知ることを欲す」(アリストテレス) | ||
|
| セ |
|
||
| 「聖なるものを犬にやるな。恐らく彼らはそれを足で踏みつけ、向き直ってあなたがたに噛み付いてくるであろう」(新約聖書「マタイ伝」) | ||
| 「生は貪るべく 死は畏るべし」(万葉集) | ||
| 「正義の極みは不正義の極み」(キケロ) | ||
| 「正をもって合し、奇をもって勝つ」(孫子) | ||
| 「精出せば、凍る間もなし水車」 | ||
| 「成功の秘訣は断固とした決意にある」(ディズレーリ) | ||
| 「成功は失敗の母」 | ||
| 「誠実に勝れる知恵なし」(ディスレーリ) | ||
| 「静寂と自由とは最大の財宝」(ベートーベン) | ||
| 「青年の失敗こそは、彼の成功の尺度でもある」(軍人・ヘルムス・モルトケ) | ||
| 「青年は未来があるというだけで幸せである」(ゴーゴリ) | ||
| 「青年は安全な株を買ってはならない」(コクトー) | ||
| 「青春の夢に忠実であれ」(詩人 シラー) | ||
| 「青春は短い。宝石の如くにしてそれを惜しめ」(評論家・劇作家・倉田百三) | ||
| 「精神の一番美しい特権のひとつは、老いて尊敬される事である」(作家・スタンダール) | ||
|
||
| 「政治指導者の堕落した国家は滅びる」 | ||
|
||
|
||
| 「政治家は仕事に対し全責任を負担する精神をもたなければならない」(マックス・ウェーバー) | ||
| 「政治家にとって大切なのは将来と将来に対する責任である。ところが『倫理』はこれについて苦慮する代わりに、解決不可能だから政治的にも不毛な過去の責任問題の追及に明け暮れる。政治的な罪とは-もしそんなものがあるとすれば-こういう態度のことである」(マックス・ウェーバー「職業としての政治」) | ||
| 「政治的行為の最終結果が、往々にして、いや決まって、当初の意図と食い違い、しばしば正反対のものとなる、というのはまったく真実で一切の歴史の根本的事実である」(ドイツの社会学者マックス・ウェーバー「職業としての政治」)。 | ||
| 「政治家に徳目を求めるのは、八百屋で魚をくれと言うのに等しい」(元法相・秦野章) | ||
| 「政治の目的は善が為し易く悪の為し難い社会をつくることにある」(19世紀英国の大政治家・グラッドストーン) | ||
| in politics,nothing happens by accident.if it happens,you can bet it was planned that wayt(Franklin Delano Roosevelt) | ||
|
「政治においては何事も偶然には起こらない。もし何かが起こったら、そのように計画されていたと見て間違いない」(Fルーズベルト)。 |
||
|
||
| 「青年は、未来があるというだけでも幸福である」(作家・ニコライ・ゴーゴリ) | ||
| 「青年は決して安全な株を買ってはならぬ」(文学者、演出者・ジャン・コクトー) | ||
| 「青年よ大志を抱け」(科学者・教育家/ ウィリアム=スミス=クラーク) | ||
|
||
| 「世界は偉人たちの水準で生きることはできない」(文化人類学者・ジョージ・フレイザー) | ||
| 「世界は自由だ。私は好きなことをやる 」(ソクラテス・アリストテレス・オナシス海運王) | ||
| 「倅(せがれ)叱るな来た道じゃもの 親父笑うな行く道じゃもの」 | ||
| 「世間が必要としているものと、あなたの才能が交わっているところに天職がある」(アリストテレス) | ||
| 「世間においては、お互いに騙され合っていなければ、とても長くは暮らして行けない」(ラ・ロシュフーコー) | ||
| 「世間の人に交わらず、己が家ばかりにて生長したる人は、心のままに振る舞い、己が心を先として人目を知らず、人の心をかねざる人、必ずあしきなり」(道元[1200-53](曹道宗開祖) | ||
| 「『絶壁の時代』においては、過去の経験や材料は役に立つどころか、マイナスになるかもしれない」(経営学者・ピーター・ドラッカー) | ||
| 「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」 | ||
| 「戦争を知っている癖に、抵抗を知らない、愚かで哀れな人達なのである 」 | ||
| 「戦争は形を変えた政治の一形態である」(クラウゼヴィッツ) | ||
| 「戦争はその経験なき人々には甘美である。だが経験したものは、戦争が近づくと心底大いに恐れる」(古代ギリシアの抒情詩人ピンダロス) | ||
| 「善悪につき他をねたまず」(宮本武蔵) | ||
|
||
| 「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」、「他力を頼みたてまつる悪人、もっとも往生の正因なり」(親鸞・1173-1262「歎異抄」) | ||
| 「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」(宮本武蔵・1584-1646) | ||
|
||
| 「前事不忘後事之師」(過去の経験を忘れなければ、後の教訓となる)。 | ||
| 「戦術とは、ある一点に最大の力をふるうことだ」(ナポレンオン1世) | ||
| 「戦争はその経験なき人々には甘美である。だが経験した者は戦争が近づくと心底大いに恐れる」 (古代ギリシアの詩人ピンダロス) | ||
| 「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」(宮本武蔵) | ||
| 「千里の馬は常に有れども、伯楽は常に有らず」(文章家・韓愈) | ||
| 「選択とは すなわち取捨の義なり」(法然) | ||
|
| ソ |
|
||
| 「その妻とその子供達を愛さない男は、自分の家に牝獅子を飼い、憎しみの巣を作りあげている人間と言える」(テーラー)。 | ||
| 「その年齢の知恵を持たない者は、その年齢のすべての困苦を持つ」(思想家・ボルテール) | ||
| 「其の本乱れて、末治まる者は否(あら)ず」(「大学」経一章) | ||
| 「それでも地球は回っている」(ガリレオ) |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)