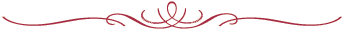
| 幕末史上最大の謎・坂本竜馬暗殺 |
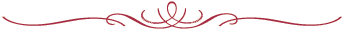
(最新見直し2012.08.18日)
| (例題) |
| 1867(慶応3)年11.15日坂本龍馬、中岡慎太郎が、京都瓦町近江屋で暗殺された。暗殺者は誰か諸説あるも、今日まで決着がついていない。竜馬はほぼ即死、中岡は二日後の17日まで生き延びた。同じ土佐出身の谷干城が駆けつけ、中岡から様子を聞いている。それによると、暗殺者は二人、中岡を襲った男は、刀を振り下ろした時、『こなくそ』と叫び、中岡に止めを刺そうとしたとき、もう一人の男が『もういい、もういい』と制して、部屋から立ち去ったと云う。襲撃グループは、わずかの時間に実に手際よく犯行を終え姿を消した。部屋には、二つの遺留品が残されていた。一つは、蝋(ろう)色の鞘(さや)。もう一つは、ひょうたんの焼き印の入った下駄の片方。鞘の持ち主と下駄の出所は分かった。鞘は、新撰組の原田左之助だった。この事実は、新撰組を脱退していた伊藤甲子太郎(きねたろう)の証言で判明した。下駄は、先斗町(ぽんとちょう)の瓢(ひさご)亭のものだとされた。瓢亭には、新撰組の連中がよく遊びに云っている。『こなくそ』は、四国伊予地方の方言である。鞘の所有者とされる原田は、伊予松山の出身。 |
| この例題に対し、以下のような見たてがある。これを確認する。 |
| 解説1、新撰組―紀州藩共同説 刀の鞘、下駄、こなくその三点セットが揃った。これだけ条件が整えば、暗殺者の一人は原田に相違ないということになるであろう。谷は共犯者を紀州藩の三浦休太郎と割り出し、二人による共同犯行とし推理した。しかし、襲撃の一部始終からして相当な剣の使い手であるということと、遺留品が残されていった経緯が判然としない。逆に、遺留品が作為の工作である可能性が高い。 |
| 解説2、薩摩藩―土佐藩共同説 遺留品の鞘について、事件の数日前に、原田が京都の料亭で飲んだとき、藤堂平助にすりかえられたという事実が確認された。藤堂は、伊藤と一緒に新撰組を脱退した人物で、二人とも、薩摩藩邸に出入りしていた。下駄についても、瓢亭のものではなく、祇園の二軒茶屋・中村屋とかいかい堂のそれであることも判明した。この茶屋は、土佐藩がひいきにしているところであった。 |
| 解説3、新撰組―見廻組共同説 事件から2年後、旧新撰組の大石鍬次郎(くわじろう)が、竜馬と中岡を暗殺したのは新撰組であると自供した。大石は、薩摩藩邸で、そう自供した。薩摩藩は、彼の身柄を兵部省(後の陸軍省)に引き渡した。兵部省の取調べで、大石は一転して竜馬暗殺は新撰組ではなく、見廻り組だと云い始めた。しかも、暗殺者は見廻組の海野、高橋、今井たちだと、具体的に名前を挙げた。今井とは、今井信郎(のぶお)で、函館戦争の時五稜郭で降伏していた。この時の降伏組みには、新撰組の横倉甚五郎、相馬主殿という二人の隊士がいた。 京都見廻組は、幕末に幕府によってつくられた京都の治安回復と維持を目的とする警ら隊。新撰組と共に京都守護職に属し、尊攘派の摘発に当たっていた。 |
| 解説4、見廻組説 兵武省は、竜馬暗殺を刑事事件として扱い、今井、大石、横倉、相馬の4人を刑部(ぎょうぶ)省に移し、審理を委ねた。今井は、暗殺は見廻組のリーダー佐々木唯三郎の指揮で行われたが、自分は見張り役で実行行為には加わっていないと主張した。結局、今井は禁固刑に処せられ、静岡県に引き渡された。大石は斬罪、相馬は伊豆新島(にいじま)に流罪、横倉は判決前に獄死。この時の裁判記録は一切公表されなかった。これは何を意味するのだろう。 |
| 解説5、薩摩藩、長州藩、土佐藩のいずれか説 当時、竜馬に敵意を持つのは幕府側のみならず尊皇攘夷派にも存在した。例えば、薩摩藩、長州藩、土佐藩。幕末の大詰めで、竜馬らは大政奉還を主張し、親徳川的行動を取り始めており、これを裏切りとみなす武力倒幕派各藩の思惑が交差していた。更に、いろは丸衝突事件で、竜馬に多額の賠償金を突きつけられて憤激していた紀州藩なども反竜馬であった。 |
| 解説6、犯人不明説 薩長連合から大政奉還に至るまで、微妙な立場で暗躍した竜馬は、幕府の密偵に執拗に捜査されていた。幕府にとって竜馬は最重要危険人物であり、抹殺すべき存在であった。のみならず、倒幕派各派もまた煙たがっていた。つまり、佐幕派、倒幕派どちらも複雑で様々な思惑を秘めて激しく流動していたが、竜馬はまさに、その渦の真っ只中にいた。 |
| (設問) さて、以上から、竜馬は誰に、どの勢力に暗殺されたのか、してその黒幕は? あなたならどう推理しますか。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)