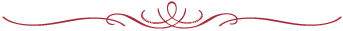
| 「世論、輿論、与論」考 |
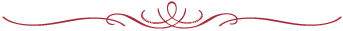
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
白川静「常用字解」(平凡社、2800円)
| 【世論】 |
| (2004.3.28日日経新聞の京都国立博物館長・興膳宏氏の「漢字コトバ散策」参照) 世論は、もと輿論(よろん)と書かれていたが、戦後制定された当用漢字表から「輿」字がはずされたために「世」字が代用され、世論となった。輿論の「輿」は、「輿人」のことで、文字通りには車体を作る職人の意だが、更に発展して身分の低い不特定多数の人々を意味する。 次のような歴史的逸話がある。「春秋左氏伝」き公28年に見える故事。春秋五覇の一人晋の文公は、南方の大国楚との戦闘中に、進むべきか退くべきか大いに悩んでいた。その時ふと聞こえてきた「輿人の誦(しょう)」、即ち大勢の兵卒達の歌声に耳を傾けていると、民の声はどうも積極策でいけといっているらしい。それがきっかけとなって、晋軍は積極的な大攻勢に出て、その結果見事に勝利を収めた。 そこから一般大衆の意見という意味で、「輿誦」(よしょう)更には「輿論」という言葉が用いられるようになった。為政者の任務は、たえず民の心に耳を傾け、それを適切に治政に生かしていくことであり、それは昔も今も変わらない。日本では戦後の当用漢字表規制で世論と書かれるようになったが、中国語では今も「輿論」を用いている。「政治家にとって、頼みは世論、されど頼みがたきもまた世論である」。 |
| 「世論」(せろん)と「輿論」(よろん)はほぼ同一の意味であるが、かっては、世論は世間の空気的な意見、輿論は議論を踏まえた人々の公的意見として使い分けられていた。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)