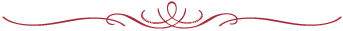
| 「社会、会社」考 |
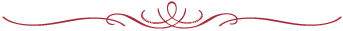
白川静「常用字解」(平凡社、2800円)
| 【「社会」という意味】 |
| 【「会社」という意味】 |
| 近松門左衛門の「国性爺合戦」に欧州の会社(オランダ東インド会社辺りを想定していると思われる)に虐待された者が「アァ、どうよくな(ひどい)こんぱんや」と泣くシーンを筆している。この頃、「こんぱにあ」、「こんぱんや」、「こんはんや」と記されていたらしい。 会社という言葉は、江戸後期の蘭学者青地林宗が、騎士団を意味する「Ritterorden」と学校を意味する「Scholen」の二つの単語を会社と訳したことを嚆矢とする。いずれも「有志の集合体」という意味であった。なぜ会社と訳したのかに付き、浜田道代・名古屋大教授は「会所と社中の合体ではないか」と推測している。 日本で会社という言葉を使ったのは福沢諭吉の「西洋事情」を嚆矢とする。その中で、「商人の会社」、「病院を作る会社」、「新聞を作る会社」、「学校を作る会社」、「宗教の会社」というように述べている。このことは、「会社」という字義が英語のカンパニーの訳であり、「有志の非営利的集団ないし結社」的意味合いで理解されていたことを窺わせる。「みずみずしい市民社会と一体のカンパニーが、言葉だけでなく実体を伴うものとして正確に理解され、継受されていたのである」(上村達男「市民社会と株主」、2004.4.14日付け日本経済新聞)。 上村氏曰く、概要「その後、オランダ語を系譜に持つ『商社』の語が、営利企業の意味で使用され始める。明治以降の商法典は、商人の会社を商社と同一視し、営利企業を表わすものとしてのみ会社の語を用い、今日に至っている。今再び、日本で、非営利法人の為の中間法人法が制定され、病院株式会社をめぐる規制緩和などが話題になっているが、福沢が草葉の陰で笑っているかも知れない」。 「生き生きとしたカンパニーから、市民社会の息吹が消え去り、株式会社を、単に営利追及の道具とみる発想が、日本の企業社会を席巻していく」(上村達男「市民社会と株主」、2004.4.14日付け日本経済新聞)。 |
| 【「社会」と「会社」】 |
| 「社会」と「会社」。語源的に一卵性双生児の関係にある。元来、「社」とは、土地神のこと。「会」は土地神を祭る集会を意味した。中国各地の村落では、古来、春と秋に土地神を祭る集会を盛大に開いて、五穀の豊穣を祈り、又収穫への感謝を示した。一つの土地ごとに、神を祭る集会が行われ、自然発生的に村落が成立した。この村落を単位として開かれる村人の集まりを「社会」と称するようになった。 明治初期の文明開化の時代、この「社会」がソサエティーの訳語にあてられた。その前には「仲間」、「結社」、「社中」、「俗間」、「人間会社」などの訳語があてられていた。 「社会」なる語は元々は中国語。ソサエティーの訳語として日本で「社会」が創られ、これが中国に輸出された。ヨーロッパ語の訳で、中国起源の言葉が日本経由で中国に導入された用語には、革命、経済、文学などがある。 「社会」がソサエティーの訳語として定着した為に、その煽りを受けて「会社」がカンパニーの訳語になった。中国語では「公司(コンス)」。2004.6.6日、日経「漢字と散策」、興膳宏(京都国立博物館長)。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)