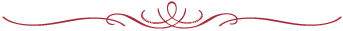
| 「正、政」考 |
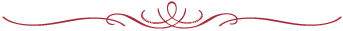
白川静「常用字解」(平凡社、2800円)
| 【「正」について】 |
| 「正」という字は、「一」と「止」が合わさった字形であり、原義は「足」を意味している。「一」は「□」を意味しており、城壁で囲われた都市を意味している。つまり、城に向かって軍隊が進軍するという意味を持つ。これに、十字路の左半分を象(かたど)り、道を行くことを意味する「ぎょうにん篇」が加えられると「征」となる。「政」は、進軍して敵を征服するという意味を持つ。旁(つくり)の「(ぼく)」の元の形は「(ぼく)」であり、「」は木の枝を意味する「ト」と手を意味する「叉」を合わせた字形である。つまり、手で木の枝を叩くという意味がある。つまり、「征」とは、征服した土地の人民を木の枝で叩いて税金を取り立てたり使役するという意味を持つ。それを司る役目の長官を「正」と云う。 「武」は、「(ほこ)」と「止」を合わせた字形である。「(ほこ)」を持って進軍すると云う意味を持つ。但し、日本的咀嚼理解によれば、「止」を「止める」と読み、「(ほこ)」を止めるのを真髄とするのが「武」とする。解釈が生まれている。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)