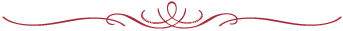
| 「女編」考 |
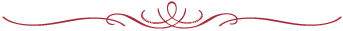
白川静「常用字解」(平凡社、2800円)
更新日/2024(平成31.5.1栄和改元/栄和6)年.2.24日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「女編/考」をものしておく。 2008.8.31日 れんだいこ |
| 【れんだいこ特選№8、女編漢字意味深考】 |
| 「女へん漢字」は意味深で為になり味わいがある。その代表例を確認しておく。 「始(はじ)める」が意味深である。「始」の偏は「女」、旁(つくり)は「台」である。これによると、「女」を「台」にするのを「始める」としている。この意味は子供には分からないだろうが大人にはすぐ分かる。 「努力」の「努」は、「女」の「又」に「力」と書く。これによると、「女」の「又」に「力」を入れる上に更に「力」を入れるのが「努力」の本意と云うことになる。この意味も子供には分からないだろう。青年も分からんかも知れん。なるほどと理解するようになるのは中年辺りからだろう。 「嬉(うれ)しい」の「嬉」は、偏は「女」、旁(つくり)が「喜」である。女性の「嬉」ぶ姿なり心なりが「嬉(うれ)しい」の原点なのだろう。 「怒る」もなるほどの文字である。「女」の「又」の「心」と書く。してみれば、頭で考えた口撃は本当の怒りではなく、「女」の「又」辺りから発する金切り声こそが怒りの本来の姿と云うことになる。してみれば、「怒り」は女性的なものであり、男の怒りは似合わないと云うことになる。 「嫌う」は「女」を「兼ねる」と書く。これによると、女性は昔から「兼ねられる」のを嫌っていたことになる。 「好く」は「女」偏に「子」と書く。「子」は男の意味で、合わせて「男女」の意味になる。これが「好く」の正意と云うことになる。 「奴」は「女」に「又」。女の又ばかりを追いかけるような者を「やっこ」と云うのではなかろうか。 「嫁」は偏が「女」、旁(つくり)が「家」である。女性が男性の家の人となるのが「嫁」(よめ)であり、これを「嫁(とつ)ぐ」と云う。 「婚」は、偏が「女」、旁(つくり)が上に「氏」、下に「日」である。女性が男性の氏の人となる日と云う意味だろう。昔は家(氏)と家(氏)の同盟的な結婚だったことによるものと思われる。「婚」がまとまると晴れて結婚式を迎えることになる。 「妊(はら)む」は偏が「女」、旁(つくり)が「壬」である。 「姓」は偏が「女」、旁(つくり)が「生」である。女性が子を産むと「姓」が付くという意味だろうか。 「婦」は偏が「女」、旁(つくり)が「箒」(ほうき)である。家の中で「箒」(ほうき)仕事が似合い始める頃から「婦人」(ふじん)になるのだろう。 娯楽の「娯」は「女」偏に「呉」(ご)と書く。女性を傍に置いて楽しむのが付き物であることを意味しているように思われる。 「安」(あん)は頭のウカンムリ、その下に女と書く。つまり家の中に女性がいる状態を表している。この状態が安全であり安心、安らぐと云うことか。 宴会の「宴」もなるほどである。頭のウカンムリは家を表す。中の日は日中という意味だろう。下に女が付く。こうなると日中から家の中に女を侍(はべ)らせて一緒に飲んで騒ぐのが「宴」なんだろう。 女3つで成り立つ漢字の「姦」(かん)に「しい」を付けた「姦しい」は「かしましい」と読む。女性が3人集まってしゃべり始める様子から生まれた言葉だろう。これは大昔から変わらぬ光景なのだろう。 「婆」は顔とか体が波打つようなシワまみれの状態を云うのだろう。どれも中々当たっている気がする。「姑」、「娘」、「姉」、「妹」、「姪」。 「妬(ねた)む」、「嫉妬」も偏が「女」である。「女」が「石」になるのが「妬」とすれば、女が石のように固まった状態の心と解析しているのだろう。その心の状態に「嫉」をつけたのが「嫉妬」であり、咄嗟に妬(ねた)んだ心の状態と解析しているのだろう。 「妻」という字義を知りたいが分からない。 如、妃、妖、妙、姻、娩、姫、嬪、妥、妄、妾、委、姿、威、娑婆、その他諸々「女へん漢字」は面白い。 |
| 【部首が女「おんな」の漢字一覧】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部首が「おんなへん」の漢字一覧は次の通り。女性、婚姻、感情などに関する漢字に「おんなへん」を含む漢字が多く集められています。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)