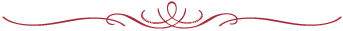
| 「気象」考 |
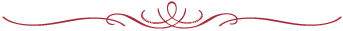
白川静「常用字解」(平凡社、2800円)
| 【「気象」考】 |
| 「気象」の「気」とは、この世界のありとあらゆるものごとを構成する元素であり、また「象」とは、人の目に見えない「気」が具体的な形をとって現れるさまを云う。天気予報の「天気」とは、「天」の「気」の「象(かたち)」ということになる。 古事記の序に、「混元既に凝りて、気象未だあらわれず」とあるのは、天地草創期にあって、万物がまだ形さえも成していない状態を云う。マクロの宇宙的次元で使われている用例である。人体のメカニズムについても使われている。中国最古の医学書「黄帝内経」には「平人気象論」という章があり、正常な人間の健康状態を論じている。ここでの「気象」は、人体における「気」の在り方を意味している。「気」の在り方が異常であれば、それが病気を引き起こすもとになる。 唐代になると、肉体面よりもむしろ精神面について用いられることが多くなる。宋代では、朱子をはじめとする儒学者によって、言動や著作など人間の精神活動全般を論ずる哲学用語になった。中国では、人は一種の小宇宙として意識されたから、人に天と同様の「気象」が備わるのも当然である。天の「気象」としての用法が主流になるのは、近代以後のことである。 興膳宏(京都国立博物館長)「漢字コトバ散策」、日経新聞コラム |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)