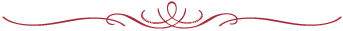
| 「歯、噛む、齟齬」考 |
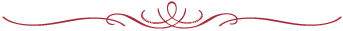
白川静「常用字解」(平凡社、2800円)
| 【「齟」について】 |
| 「歯」のつく漢字も多い。古来より、「歯」はからだの大切な部分とみられてきていたことが分かる。「齟」の「右つくりのソ」は、土を積み重ねて作った墓の象形と思われる。そのことから「ソ」は重なるの意。例えば、「組」は糸を重ねて作った組みひものこと。「阻」は山々が重なる険しさに行く手を阻まれることを意味する。 「歯」と「ソ」を組み合わせて「齟」となると、歯が食い違って重なる、つまり上下の歯がうまく噛み合わない状態を表わしている。歯科では不正交合という。そこから物事が食い違ってうまくいかない、事が矛盾する、予期に反するなどの意味で「齟齬」が使われることになる。「齟」にはかむという意もある。食物を噛み砕いたり、物事や文章の意味をよく味わうことを「咀嚼(そしゃく)」すると表現することになる。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)