| 【8、花宴(はなのえん)5節】 |
| あらすじは次の通り。 |
源氏二十歳の春、南殿で桜の宴が催された。源氏は帝に所望され、詩や舞を披露し賞賛される。そんな源氏に対して、弘徽殿の女御は憎しみを募らせる。
宴が終わり、酔い心地で源氏が弘徽殿に忍び込むと、「朧月夜に似るものはなき」と口ずさみながら来る女(朧月夜)がいた。源氏が袖をとらえると女は最初おびえるが、源氏と知って心を許す。翌朝ふたりは名前も交わさぬまま扇だけを取り交わして別れた。その後、源氏は女が政敵である右大臣の娘、弘徽殿の女御の妹と知り、再会の困難を思う。
朧月夜は東宮に輿入れする予定だったが、源氏との逢瀬に思いふけていた。そんな折、右大臣家の宴に招かれた源氏は酔いすぎた風を装い、姫君たちの居室に向かった。当て推量で先日の扇の持ち主を問いかけると、返した声はまさにその人自身のものであった。 |
| 8-1、二月二十余日、紫宸殿の桜花の宴 |
の二十日あまり、 南殿の桜の宴せさせたまふ。后、春宮の御局、左右にして、参う上りたまふ。弘徽殿の女御、中宮のかくておはするを、をりふしごとにやすからず思せど、物見にはえ過ぐしたまはで、参りたまふ。
日いとよく晴れて、空のけしき、鳥の声も、心地よげなるに、親王たち、上達部よりはじめて、その道のは皆、探韻賜はりて文つくりたまふ。宰相中将、「春といふ文字賜はれり」と、のたまふ声さへ、例の、人に異なり。次に頭中将、人の目移しも、ただならずおぼゆべかめれど、いとめやすくもてしづめて、声づかひなど、ものものしくすぐれたり。さての人びとは、皆臆しがちに鼻白める多かり。 地下の人は、まして、帝、春宮の御才かしこくすぐれておはします、かかる方にやむごとなき人多くものしたまふころなるに、恥づかしく、はるばると曇りなき庭に立ち出づるほど、はしたなくて、やすきことなれど、苦しげなり。年老いたる博士どもの、なりあやしくやつれて、例馴れたるも、あはれに、さまざま御覧ずるなむ、をかしかりける。
楽どもなどは、さらにもいはずととのへさせたまへり。やうやう入り日になるほど、春の鴬囀るといふ舞、いとおもしろく見ゆるに、源氏の御紅葉の賀の折、思し出でられて、春宮、かざしたまはせて、せちに責めのたまはするに、逃がれがたくて、立ちてのどかに袖返すところを一折れ、けしきばかり舞ひたまへるに、似るべきものなく見ゆ。左大臣、恨めしさも忘れて、涙落したまふ。
「頭中将、いづら。遅し」
とあれば、柳花苑といふ舞を、これは今すこし過ぐして、かかることもやと、心づかひやしけむ、いとおもしろければ、御衣賜はりて、いとめづらしきことに人思へり。上達部皆乱れて舞ひたまへど、夜に入りては、ことにけぢめも見えず。文など講ずるにも、源氏の君の御をば、講師もえ読みやらず、句ごとに誦じののしる。博士どもの心にも、いみじう思へり。
かうやうの折にも、まづこの君を光にしたまへれば、帝もいかでかおろかに思されむ。中宮、御目のとまるにつけて、「春宮の女御のあながちに憎みたまふらむもあやしう、わがかう思ふも心憂し」とぞ、みづから思し返されける。
「おほかたに花の姿を見ましかば
つゆも心のおかれましやは」
御心のうちなりけむこと、いかで漏りにけむ。 |
二月の二十日余りに、南殿の桜の宴が催された。藤壺中宮と東宮の御座所を左右にして、お二人が参内した。弘徽殿の女御は藤壺の中宮が臨席するのが、ことごとに安からず思っていたが、催し物は見過ごさず出るのだった。
日はよく晴れて、空のけしきや鳥の声も心地よげにさえずり、親王たちやまた上達部など、その道の人たちは皆、探韻を賜って文を作った。源氏の宰相中将は、「春といふ文字賜はれり」と、仰せになる声さえ他の人と違うのであった。次に頭中将、源氏の後では尋常でなかったが、感じはよく落ち着いて、声づかいなども堂々としていた。続く人たちはみな臆しがちで気後れしている人が多かった。地下の文人たちは、まして、帝や春宮の御才かしこくすぐれていて、この方面で秀でた人たちが多く臨席しているので、恥づかしく、曇りなく晴れ渡った庭に立つと、きまりが悪く落ち着かないので、詩作は容易であっても、何でもないことなのだが、苦しげであった。年老いたる博士どものは、身なりも粗末ながら場馴れしていて、それなりにあわれで興があった。
楽なども、いうまでもなく準備万端であった。ようやく日が入るころになって、春の鶯囀るという舞がすごくい面白かったので、源氏が紅葉賀で舞ったのが思い出されて、東宮はかざしを賜って、是非にと頼むので、逃れがたく、立ってのどかに袖を返すところを一節、形ばかり舞ったのであるが、比類ないものであった。左大臣は、恨めしいのも忘れて、感涙にむせぶのであった。
「頭中将、どうした、早くせよ」
と帝が仰せなので、中将は、柳花苑といふ舞を、もう少し入念に、このようなことも心積りをしていたので、実に見事に舞うと、御衣を賜り、人びとは稀なことと思った。上達部も皆乱れて舞ったが、夜になったので、上手下手もよくわからない。詩を披露するにも、源氏の君の詩は講師も一気に読めず、句ごとに誦した。博士どもの心にも、感ずるものがあった。
このような折にも、まずこの君を一座の光にするので、帝は詩も粗略には扱われない。(藤壺)中宮は、目にとまるにつけて、「東宮の母君が、一方的に憎むのも尋常ではない。わたしがこう思うのも情けない」と、心の中で思うのであった。
(藤壺の歌)「普通に花の姿を見ることができれば
これほど心引かれることはないであろうに」
心のなかで詠ったものが、どうして漏れたのだろうか。 |
|
| 8-2、宴の後、朧月夜の君と出逢う |
夜いたう更けてなむ、事果てける。
上達部おのおのあかれ、后、春宮帰らせたまひぬれば、のどやかになりぬるに、月いと明うさし出でてをかしきを、源氏の君、酔ひ心地に、見過ぐしがたくおぼえたまひければ、「上の人びともうち休みて、かやうに思ひかけぬほどに、もしさりぬべき隙もやある」と、藤壺わたりを、わりなう忍びてうかがひありけど、語らふべき戸口も鎖してければ、うち嘆きて、なほあらじに、弘徽殿の細殿に立ち寄りたまへれば、三の口開きたり。
女御は、上の御局にやがて参う上りたまひにければ、人少ななるけはひなり。奥の枢戸も開きて、人音もせず。
「かやうにて、世の中のあやまちはするぞかし」と思ひて、やをら上りて覗きたまふ。人は皆寝たるべし。いと若うをかしげなる声の、なべての人とは聞こえぬ、
「朧月夜に似るものぞなき」
とうち誦じて、こなたざまには来るものか。いとうれしくて、ふと袖をとらへたまふ。女、恐ろしと思へるけしきにて、
「あな、むくつけ。こは、誰そ」とのたまへど、
「何か、疎ましき」とて、
「深き夜のあはれを知るも入る月の
おぼろけならぬ契りとぞ思ふ」
とて、やをら抱き下ろして、戸は押し立てつ。あさましきにあきれたるさま、いとなつかしうをかしげなり。わななくわななく、
「ここに、人」
と、のたまへど、
「まろは、皆人に許されたれば、召し寄せたりとも、なんでふことかあらむ。ただ、忍びてこそ」
とのたまふ声に、この君なりけりと聞き定めて、いささか慰めけり。わびしと思へるものから、情けなくこはごはしうは見えじ、と思へり。酔ひ心地や例ならざりけむ、許さむことは口惜しきに、女も若うたをやぎて、強き心も知らぬなるべし
らうたしと見たまふに、ほどなく明けゆけば、心あわたたし。女は、まして、さまざまに思ひ乱れたるけしきなり。
「なほ、名のりしたまへ。いかでか、聞こゆべき。かうてやみなむとは、さりとも思されじ」
とのたまへば、
「憂き身世にやがて消えなば尋ねても
草の原をば問はじとや思ふ」
と言ふさま、艶になまめきたり。
「ことわりや。聞こえ違へたる文字かな」とて、
「いづれぞと露のやどりを分かむまに
小笹が原に風もこそ吹け
わづらはしく思すことならずは、何かつつまむ。もし、すかいたまふか」
とも言ひあへず、人々起き騒ぎ、上の御局に参りちがふけしきども、しげくまよへば、いとわりなくて、扇ばかりをしるしに取り換へて、出でたまひぬ。
桐壺には、人びと多くさぶらひて、おどろきたるもあれば、かかるを、
「さも、たゆみなき御忍びありきかな」
とつきじろひつつ、そら寝をぞしあへる。入りたまひて臥したまへれど、寝入られず。
「をかしかりつる人のさまかな。女御の御おとうとたちにこそはあらめ。まだ世に馴れぬは、五、六の君ならむかし。帥宮の北の方、頭中将のすさめぬ四の君などこそ、よしと聞きしか。なかなかそれならましかば、今すこしをかしからまし。六は春宮にたてまつらむとこころざしたまへるを、いとほしうもあるべいかな。 わづらはしう、尋ねむほどもまぎらはし、 さて絶えなむとは思はぬけしきなりつるを、いかなれば、 言通はすべきさまを教へずなりぬらむ」
など、よろづに思ふも、心のとまるなるべし。かうやうなるにつけても、まづ、「かのわたりのありさまの、こよなう奥まりたるはや」と、ありがたう思ひ比べられたまふ。 |
夜が更けてから、宴は終わった。
上達部たちはおのおの去り、中宮や東宮もお帰りになったので、あたりは静かになり、月が明るく照らして風情を覚えたので、源氏は酔い心地で去りがたく思ったので、「殿上人もみな休んだこの思いがけぬ機会に、幸運な時にめぐりあうかもしれない」と、藤壺のあたりをうろうろしていると、声をかけようにも戸口が鎖されていて、がっかりしたが、まだ去りがたく、弘徽殿の細殿に立ち寄ってみると、三の口が開いていた。
弘徽殿女御は、そのまま上の御局に参上したので、人が少ない様であった。奥の枢戸も開いて、人気がなかった。
「こうした不用心から、男女の過ちもおこるのだ」と思って、静かに上がって覗き込んだ。皆寝込んでいるようだ。ごく若く美しい声で、並みの身分と思えぬ女が、
「朧月夜に似るものぞなき」
と誦じて、こちらに近づいてくるではないか。うれしくなって、ふと袖をとらえた。女は、恐がっていると思える様子で、
「あら、嫌だ。誰ですか」と女が言うと、
「何を嫌がることがありましょう」とて、
(源氏の歌)「深い夜のあわれを知れるのは朧月夜の
おぼろげならぬ前世の縁かと思います」
とて、静かに抱きあげて下ろし、戸を閉めた。女の、あまりのことに驚く様が、可愛らしく心がひかれた。わななきながら、
「ここに人が」
と声を出したが、
「わたしは、皆に許されているので、人を呼んでも、何にもなりませんよ。静かにしてらっしゃい」
と仰せになる声で、源氏と分かったので、少し安心した。困ったと思う一方で、情がなく不粋だと見られないように、と思うのだった。君はことのほか酔っていたのであろう、このまま放すのは残念で、女も世間知らずで素直で、はねつけることも知らなかったのであろう。
(源氏が)可愛らしいと見ているうちに、ほどなく夜が明けて、あわただしい。女はさまざまに思い乱れている様子だった。
「名は何という。どうやって文をしたらいいのか。これで終わりだ、とは思わないでしょう」
と仰れば、
(朧月夜の歌)「この憂き身がこのまま名乗らずにこの世から消えても
草の原を分けてでも尋ねてくれるでしょうか」
との言い方が、なんともなまめかしい。
「もっともだ。言いそこねました」とて、
(源氏の歌)「名を知らぬまま露の宿を捜しても分からずに
世間に噂だけが立ってしまうでしょう
迷惑でなければ、わたしは隠すことなどない。もし、だますおつもりか」
とも言い終わらないうちに、人々が起きてきてざわめき、上の御局に行き交う様子がしきりとするので、やむなく、扇をしるしに交換して、部屋を出た。
桐壷には、女房たちが大勢侍していて、気づいた者は、この朝帰りを、
「ご熱心なお忍びですこと」
とつつき合って、寝たふりをしている。君は部屋に入って臥したが、寝られない。
「美しい人だったなあ。女御の妹たちだろう。まだ世馴れぬ様子だったので、五の君か六の君だろうな。帥宮の北の方や、頭中将が嫌う四の君などは、器量よしと聞いている。むしろそのような女たちだったら、もっとおもしろかっただろう。六の君は、春宮に妻あわせる心づもりだろうから、かわいそうなことをしたのかな。どちらが誰かと、尋ねるのもわずらわしい、これで終わりとは思えなかったので、どうして文を交わす手立てを教えなかったの か」
などあれこれ思うのも、未練があるからだろう。こういうことにつけても、まず、「あの藤壺の辺りの様子は、まことに奥ゆかしいものだ」と、ありがたく思い比べられた。 |
|
| 8-3、桜宴の翌日、昨夜の女性の素性を知りたがる |
その日は後宴のことありて、まぎれ暮らしたまひつ。箏の琴仕うまつりたまふ。昨日のことよりも、なまめかしうおもしろし。藤壺は、暁に参う上りたまひにけり。「かの有明、出でやしぬらむ」と、心もそらにて、思ひ至らぬ隈なき良清、惟光をつけて、うかがはせたまひければ、御前よりまかでたまひけるほどに、
「ただ今、北の陣より、かねてより隠れ立ちてはべりつる車どもまかり出づる。御方々の里人はべりつるなかに、四位の少将、右中弁など急ぎ出でて、送りしはべりつるや、弘徽殿の御あかれならむと見たまへつる。けしうはあらぬけはひどもしるくて、車三つばかりはべりつ」
と聞こゆるにも、胸うちつぶれたまふ。
「いかにして、いづれと知らむ。父大臣など聞きて、ことことしうもてなさむも、いかにぞや。まだ、人のありさまよく見さだめぬほどは、わづらはしかるべし。さりとて、知らであらむ、はた、いと口惜しかるべければ、いかにせまし」と、思しわづらひて、つくづくとながめ臥したまへり。
「姫君、いかにつれづれならむ。日ごろになれば、屈してやあらむ」と、らうたく思しやる。かのしるしの扇は、桜襲にて、濃きかたにかすめる月を描きて、水にうつしたる心ばへ、目馴れたれど、ゆゑなつかしうもてならしたり。「草の原をば」と言ひしさまのみ、心にかかりたまへば、
「世に知らぬ心地こそすれ有明の
月のゆくへを空にまがへて」
と書きつけたまひて、置きたまへり。 |
その日は後宴があって、それにまぎれて過ぎていった。箏の琴を演奏した。昨日よりも艶っぽくておもしろい。藤壺は暁ころに上局に参内した。「あの有明の君は退出してしまったのか」と、気もそぞろで、万事ぬかりのない良清と惟光をつけて、見張らせていたのだが、君が帝の御前より退出されたときに、
「ただ今、北の陣から、事前に隠しておいた車が出立しました。女御方の実家の人たちが来ていたなかに、四位の少将や右中弁などが急いで見送りに出ましたので、弘徽殿から別れてきたものと思います。相当な身分の方々と見えまして、車は三台ばかりありました」
との報告にも、胸がつぶれる思いであった。
「どうやって姫を見極めよう。父の大臣に知れて、ものものしく扱われるのも、いやだ。まだ人柄をよく知らないうちは、なんとも面倒なものだ。そうかといって、知らないままでは、まことにいまいましいし、どうしよう」と思いわずらい、ぼんやりして眺めながら臥しているのであった。
「若紫は、さびしくしているだろう。何日も会っていないから、ふさぎこんでいるだろうか」といとおしく思う。あの扇は、桜重ねで、色の濃い方に銀泥の霞む月を描き、水に映した趣向は、珍しくはないが、持ち主の風情がしのばれ使いならしている。「草の原をば」と言った面影が忘れられず、
(源氏の歌)「初めて味わうのやるせない気持ちだ
有明の月の行方を途中で見失ってしまって」
と書き付けて、置いておいた。 |
|
| 8-4、紫の君の理想的成長ぶり、葵の上との夫婦仲不仲 |
「大殿にも久しうなりにける」と思せど、若君も心苦しければ、 こしらへむと思して、二条院へおはしぬ。見るままに、いとうつくしげに生ひなりて、愛敬づきらうらうじき心ばへ、いとことなり。飽かぬところなう、わが御心のままに教へなさむ、と思すにかなひぬべし。男の御教へなれば、すこし人馴れたることや混じらむと思ふこそ、うしろめたけれ。
日ごろの御物語、御琴など教へ暮らして出でたまふを、例のと、口惜しう思せど、今はいとようならはされて、わりなくは慕ひまつはさず。
大殿には、例の、ふとも対面したまはず。つれづれとよろづ思しめぐらされて、箏の御琴まさぐりて、
「やはらかに寝る夜はなくて」
とうたひたまふ。大臣渡りたまひて、一日の興ありしこと、聞こえたまふ。
「ここらの齢にて、明王の御代、四代をなむ見はべりぬれど、このたびのやうに、文ども警策に、舞、楽、物の音どもととのほりて、齢延ぶることなむはべらざりつる。道々のものの上手ども多かるころほひ、詳しうしろしめし、ととのへさせたまへるけなり。翁もほとほと舞ひ出でぬべき心地なむしはべりし」
と聞こえたまへば、
「ことにととのへ行ふこともはべらず。ただ公事に、そしうなる物の師どもを、ここかしこに尋ねはべりしなり。よろづのことよりは、「柳花苑」、まことに後代の例ともなりぬべく見たまへしに、まして「さかゆく春」に立ち出でさせたまへらましかば、世の面目にやはべらまし」
と聞こえたまふ。
弁、中将など参りあひて、高欄に背中おしつつ、とりどりに物の音ども調べ合はせて遊びたまふ、いとおもしろし。 |
「左大臣邸にも久しくご無沙汰している」と思うけれど、若紫もかわいそうなので、ご機嫌を取るべく二条院へ戻った。目に見えて、可愛らしく成長し、愛敬もあり利発な気性がきわだってきていた。不足がないよう、また自分の思い通りに教えようとの期待にかなうに違いない。男手の教えなので、すこし男になれた点が混じるか、心配ではある。
日頃の出来事を話し、琴を教えてから、(左大臣邸へ)出かけたが、(若紫は)残念には思うが、昨今は馴れて、駄々をこねなくなった。
(左大臣邸では)葵の上は、例の通り、すぐには顔を出さない。君は所在なげにあれこれと思い巡らし、琴を奏して、
「やはらかに寝る夜はなくて」
と謡う。大臣がやって来て、先日の花の宴でとりわけ興を覚えた話をした。
「この年で、名君の帝四代にお仕えしましたが、今回のように、詩文にすぐれ、舞、楽、その他鳴り物をそろえて、命の延びる思いをしたことがございません。それぞれの道で上手は多いでしょうが、詳しく調べて名手をそろえたからでしょう。わたしまでがつい舞い出そうな心地がいたしました」
と申し上げれば、
「ことさらそろえたわけではありません。ただお役目として優れた専門家をあちこちに尋ね歩いただけです。それよりも、「柳花苑」は後代の手本ともなるべくものでしょう、まして(左大臣殿が)「栄ゆく春に」 立ち出でて舞ったならば、一世一代の花となったでありましたでしょう」
と仰るのであった。
左中弁や頭中将などもやって来て、高欄にもたれて、それぞれが合奏して遊ぶのが、たいへんおもしろかった。 |
|
| 8-5、三月二十余日、右大臣邸の藤花の宴 |
かの有明の君は、はかなかりし夢を思し出でて、いともの嘆かしうながめたまふ。春宮には、卯月ばかりと思し定めたれば、いとわりなう思し乱れたるを、男も、尋ねたまはむにあとはかなくはあらねど、いづれとも知らで、ことに許したまはぬあたりにかかづらはむも、 人悪く思ひわづらひたまふに、弥生の二十余日、右の大殿の弓の結に、上達部、親王たち多く集へたまひて、やがて藤の宴したまふ。
花盛りは過ぎにたるを、「ほかの散りなむ」とや教へられたりけむ、遅れて咲く桜、二木ぞいとおもしろき。新しう造りたまへる殿を、宮たちの御裳着の日、磨きしつらはれたり。はなばなとものしたまふ殿のやうにて、何ごとも今めかしうもてなしたまへり。
源氏の君にも、一日、内裏にて御対面のついでに、聞こえたまひしかど、おはせねば、口惜しう、ものの栄なしと思して、御子の四位少将をたてまつりたまふ。
「わが宿の花しなべての色ならば
何かはさらに君を待たまし」
内裏におはするほどにて、主上に奏したまふ。
「したり顔なりや」と笑はせたまひて、
「わざとあめるを、早うものせよかし。 女御子たちなども、生ひ出づるところなれば、なべてのさまには思ふまじきを」
などのたまはす。御装ひなどひきつくろひたまひて、いたう暮るるほどに、待たれてぞ渡りたまふ。
桜の唐の綺の御直衣、葡萄染の下襲、裾いと長く引きて。皆人は表の衣なるに、あざれたる大君姿のなまめきたるにて、いつかれ入りたまへる御さま、げにいと異なり。花の匂ひもけおされて、なかなかことざましになむ。
遊びなどいとおもしろうしたまひて、夜すこし更けゆくほどに、源氏の君、いたく酔ひ悩めるさまにもてなしたまひて、紛れ立ちたまひぬ。
寝殿に、女一宮、女三宮のおはします。東の戸口におはして、寄りゐたまへり。藤はこなたの妻にあたりてあれば、御格子ども上げわたして、人びと出でゐたり。袖口など、踏歌の折おぼえて、ことさらめきもて出でたるを、ふさはしからずと、まづ藤壺わたり思し出でらる。
「なやましきに、いといたう強ひられて、わびにてはべり。かしこけれど、この御前にこそは、蔭にも隠させたまはめ」
とて、妻戸の御簾を引き着たまへば、
「あな、わづらはし。よからぬ人こそ、やむごとなきゆかりはかこちはべるなれ」
と言ふけしきを見たまふに、重々しうはあらねど、おしなべての若人どもにはあらず、あてにをかしきけはひしるし。
そらだきもの、いと煙たうくゆりて、衣の音なひ、いとはなやかにふるまひなして、心にくく奥まりたるけはひはたちおくれ、今めかしきことを好みたるわたりにて、やむごとなき御方々もの見たまふとて、この戸口は占めたまへるなるべし。さしもあるまじきことなれど、さすがにをかしう思ほされて、「いづれならむ」と、胸うちつぶれて、
「扇を取られて、からきめを見る」
と、うちおほどけたる声に言ひなして、寄りゐたまへり。
「あやしくも、さま変へける高麗人かな」
といらふるは、心知らぬにやあらむ。いらへはせで、ただ時々、うち嘆くけはひする方に寄りかかりて、几帳越しに手をとらへて、
「梓弓いるさの山に惑ふかな
ほの見し月の影や見ゆると
何ゆゑか」
と、推し当てにのたまふを、え忍ばぬなるべし。
「心いる方ならませば弓張の
月なき空に迷はましやは」
と言ふ声、ただそれなり。いとうれしきものから。 |
あの有明の君は、はかない夢を思い出して、やるせない気持ちだった。東宮には四月ころ入内と決められているので、どうしようもなく思い乱れていたが、男も、尋ねれば手がかりもあったが、どちらの妹ともわからず特に源氏を目の敵にするご一家にかかわっては、体裁が悪いと思っていた頃、三月の二十余日、右大臣の弓の競技会に、上達部や親王たちが多く集って、続いて藤の宴を催した。
花の盛りは過ぎたのだが、「ほかの散った桜」のあとに咲けと教えられたのか、遅れて二本咲いているのがすごく趣があった。新しく作った御殿を、娘たちの御裳着の日、磨いてととのえた。派手好みの殿の流儀で、何ごとも今風にめかしてしつらえていた。
源氏の君にも、ある日内裏で会った時、御案内があったのだが、来られなかったので、残念がって、花がないと思って、子息の四位少将を遣ったのであった。
(右大臣の歌)「わたしの宿の花が並みの美しさなら、
どうしてお誘いしてあなたのお越しを待っていますでしょうか」
(源氏が)内裏にいたので、帝に奏上した。
「得意顔だな」と(帝は)笑って、
「わざわざ迎えを寄越したのだ、早く行きなさい。内親王たちもいることだから、他人とは思わないだろう」
などと仰せになる。(源氏は)装ひをととのえて、暮れも遅くなって、待たれているところに登場した。
桜がさねの直衣を着て、葡萄染の下がさねをはき、裾を長く引いている。皆正装であったが、しゃれた略装の皇子姿はなまめかしく、かしずかれて入ってくる様子は、格別であった。藤の花の香りも圧倒されて、かえって興ざめのようだった。
遊びなど実におもしろくされて、次第に夜も更けてゆくころ、源氏の君はそうとうに酔いすぎたように見せかけて、そっと席をたった。
寝殿に女一の宮、女三の宮がおられる。君は東の戸口で、寄りかかっている。藤の花はこちら側の角に当たっているので、格子をずっとあげて、女房たちは出ていた。袖口を出すなど踏歌のまねを思い出し、わざとらしいので興ざめし、奥ゆかしい藤壺の方を思い出した。
「気分がよくないのに、酒を強いられて、困っています。恐れ入りますが、こちらにわたしを隠していただきたいのですが」
と言って、妻戸の御簾を上げると、
「いけませんよ。卑賎な身分の方が、高貴な縁者を頼るものです、あなたのような高貴な方が」
と言う様子を見ると、重々しくはないが、どこにでもいる若人ではなく、高貴で由緒ある様子であることが明らかだった。
空薫物の香が、煙たいほどたかれて、衣ずれの音がはなやかに聞こえ、心にくく奥ゆかしい気配はあまりなくて、なんでも当世風の趣向を好むお邸で、高貴な女房たちがご覧になるということで、この戸口をそれに当てているのだろう。場所柄やってはいけないことだったが、さすがに興を覚えて、「どの女だろう」と胸をときめかせて、
「まったく『扇を取られて、からきめを見る』だ」
と、おどけた声で言って、寄りかかっているのだった。
「あら、変な高麗人ですこと」
と返答するのは、事情の知らぬものだろう。返答もせず、ただ時々ため息をつく方に寄って、几帳越しに手をつかみ、
(源氏の歌)「いるさの山のなかで惑っています
ここに来れば垣間見た月影が見えると思いまして
何故でしょう」
と、あて推量に言うと、耐え難くなったのだろう。
(朧月夜の歌)「深く心のかけている方なら
月影がなくても迷いはしないでしょう」
と言ふ声だけがした。実にうれしいことだ。 |
|
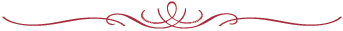
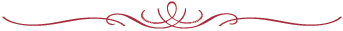
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)