| 【50、東屋(あずまや)42節】 |
| あらすじは次の通り。 |
浮舟の母(中将の君)は薫の思いを知るが、身分の差を考え、浮舟を左近少将に嫁がせようとする。財産目当ての左近少将は浮舟が父•常陸介の実子でないと知ると、話を一方的に破断する。中将の君は中の君に浮舟の後見を頼み、薫との縁を願う。
匂の宮は邸に帰ると、誰とは知らぬまま浮舟に言い寄る。中将の君は、事なきを得た浮舟を三条に移す。
九月、浮舟が三条にいると知った薫は、浮舟と会い契りを結ぶ。翌日、薫は浮舟と連れ立って宇治に向かう。 |
| 50.1 浮舟の母、娘の良縁を願う |
筑波山を分け見まほしき御心はありながら、端山の繁りまであながちに思ひ入らむも、いと人聞き軽々しう、かたはらいたかるべきほどなれば、思し憚りて、御消息をだにえ伝へさせたまはず。
かの尼君のもとよりぞ、母北の方にのたまひしさまなど、たびたびほのめかしおこせけれど、まめやかに御心とまるべきこととも思はねば、ただ、さまでも尋ね知りたまふらむこと、とばかりをかしう思ひて、人の御ほどのただ今世にありがたげなるをも、数ならましかば、などぞよろづに思ひける。
守の子どもは、母亡くなりにけるなど、あまた、この腹にも、姫君とつけてかしづくあり、まだ幼きなど、すぎすぎに五、六人ありければ、さまざまにこの扱ひをしつつ、異人と思ひ隔てたる心のありければ、常にいとつらきものに守をも恨みつつ、「いかでひきすぐれて、おもだたしきほどにしなしても見えにしがな」と、明け暮れ、この母君は思ひ扱ひける。
さま容貌の、なのめに、とりまぜてもありぬべくは、いとかうしも何かは苦しきまでももてなやまじ、同じごと思はせてもありぬべき世を、ものにも混じらず、あはれにかたじけなく生ひ出でたまへば、あたらしく心苦しき者に思へり。
娘多かりと聞きて、なま君達めく人びとも、おとなひ言ふ、いとあまたありけり。初めの腹の二、三人は、皆さまざまに配りて、大人びさせたり。今はわが姫君を、「思ふやうにて見たてまつらばや」と、明け暮れ護りて、なでかしづくこと限りなし。 |
薫は、筑波山を分け入ってでも見たい気持ちはあったが、小さな山にまで入ってまで探しだそうとするのは、人聞き悪く見苦しいことなので、憚って、文でさえ取り次がすことをなさらない。
あの尼君から、薫の意向を母北の方に、たびたびほのめかすが、母は、まじめに受け取るべき話しとも思わなかったので、ただそんなにまで調べて素性を知っていることに感心して、薫の人柄身分が当節ではまたとないお方と思うにつけ、こちらが人並みの身分だったら、などとあれこれ思うのだった。
守(常陸の介)の子供は、先妻との間に、大勢おり、浮船の母とも、姫君と呼んで大切にしている娘がいて、ほかにもまだ幼い子が次々に五、六人あって、守はそれぞれに面倒を見ているが、浮舟を分け隔てする気持ちがあり、冷たい人と守を恨みながらも、「どうかして優れた、晴れがましい婿殿にめあわせたい」といつも母は思っていた。
姿や顔立ちが、並みで、他の娘たちと区別せずに考えてもよいなら、何で切ないほど思い悩むことがあろう、ほかの娘と同じ分際だと世間に思わせてもよかったが 、ひとり際立って、美しく成長したので、受領風情の娘では惜しいと思っていた。
娘がたくさんいると聞いて、ちょっとした家柄の若君たちは、文をよこすものがたくさんいた。先妻腹の二、三人は、zそれぞれ縁付けて、一人前にした。今度はわが娘を、「理想的な婿を取らせてお世話しよう」と、明け暮れ気をつけて、大切にすることこの上ない。 |
|
| 50.2 継父常陸介と求婚者左近少将 |
守も卑しき人にはあらざりけり。上達部の筋にて、仲らひもものきたなき人ならず、徳いかめしうなどあれば、ほどほどにつけては思ひ上がりて、家の内もきらきらしく、ものきよげに住みなし、事好みしたるほどよりは、あやしう荒らかに田舎びたる心ぞつきたりける。
若うより、さる東方の、遥かなる世界に埋もれて年経ければにや、声などほとほとうちゆがみぬべく、ものうち言ふ、すこしたみたるやうにて、豪家のあたり恐ろしくわづらはしきものに憚り懼ぢ、すべていとまたく隙間なき心もあり。
をかしきさまに琴笛の道は遠う、弓をなむいとよく引ける。なほなほしきあたりともいはず、勢ひに引かされて、よき若人ども、装束ありさまはえならず調へつつ、腰折れたる歌合せ、物語、庚申をし、まばゆく見苦しく、遊びがちに好めるを、この懸想の君達、
「らうらうじくこそあるべけれ。容貌なむいみじかなる」
など、をかしき方に言ひなして、心を尽くし合へる中に、左近少将とて、年二十二、三ばかりのほどにて、心ばせしめやかに、才ありといふ方は、人に許されたれど、きらきらしう今めいてなどはえあらぬにや、通ひし所なども絶えて、いとねむごろに言ひわたりけり。
この母君、あまたかかること言ふ人びとの中に、
「この君は、人柄もめやすかなり。心定まりてももの思ひ知りぬべかなるを、人もあてなりや。これよりまさりて、ことことしき際の人はた、かかるあたりを、さいへど、尋ね寄らじ」
と思ひて、この御方に取りつぎて、さるべき折々は、をかしきさまに返り事などせさせたてまつる。心一つに思ひまうく。
「守こそおろかに思ひなすとも、我は命を譲りてかしづきて、さま容貌のめでたきを見つきなば、さりとも、おろかになどは、よも思ふ人あらじ」
と思ひ立ちて、八月ばかりと契りて、調度をまうけ、はかなき遊びものをせさせても、さまことにやうをかしう、蒔絵、螺鈿のこまやかなる心ばへまさりて見ゆるものをば、この御方にと取り隠して、劣りのを、
「これなむよき」
とて見すれば、守はよくしも見知らず、そこはかとない物どもの、人の調度といふ限りは、ただとり集めて並べ据ゑつつ、目をはつかにさし出づるばかりにて、琴、琵琶の師とて、内教坊のわたりより迎へ取りつつ習はす。
手一つ弾き取れば、師を立ち居拝みてよろこび、禄を取らすること、埋むばかりにてもて騒ぐ。はやりかなる曲物など教へて、師と、をかしき夕暮などに、弾き合はせて遊ぶ時は、涙もつつまず、をこがましきまで、さすがにものめでしたり。かかることどもを、母君は、すこしもののゆゑ知りて、いと見苦しと思へば、ことにあへしらはぬを、
「吾子をば、思ひ落としたまへり」
と、常に恨みけり。 |
常陸の介も、素性の悪い人ではない。上達部の血筋で、一族も地位の低い人たちではなく、財産もたいそうあるので、そうした身分の者なりに気位も高く、家の中も飾り立て、こざっぱりした暮らしぶりで、風流を好むわりには、なぜか粗野で田舎じみたところがとれないのだった。
若い頃から、はるか東国で、田舎に埋もれて長年暮らしてきたので、言葉も聞き取りにくく、ものを言うにも少し訛りがあって、身分の高い権勢家を恐れて、面倒なものと恐縮するところがあるが、何かにつけて用心深いところもあった。
風雅に琴笛を奏するのは疎く、弓をよくする。身分の低いのを問題にせず、その財力にひかれて、若い女房たちが集まり、装束や身なりは立派に調えて、下手な歌合せ、物語し、徹夜で競って遊ぶのを、仰々しくみっともなく、遊びごとに興じているのを、求婚者の若者たちは、
「才たけた娘たちに違いない。顔立ちも大したものらしい」
など、いい女であるかのように噂して、姫君を競っている中で、左近少将といって、年二十二、三ばかりで、性格も落ち着いていて、学問があるということでは人に認められ、きらびやかな当世風にしていられない事情があるのか、通っていた処とも縁を切り、熱心に求婚していた。
この母君は、たくさん求愛するものの中で、
「この君は、人柄もいい。落ち着いているし物の道理も分かっている、人柄も品がある。この人以上の身分の人が、受領風情の娘を求めてくるはずもないだろう」
と思って、文を取り継いで、しかるべき折々には、風情ある返事を書かせるなどしていた、母君は自分ひとりであれこれ思案する。
「守がこの姫をなおざりに思っていても、わたしは命に換えてもこの結婚の世話をして、娘の顔立ちの好いのを見れば、軽んじる人はあるまい」
と思い込んで、八月に結婚と決めて、調度類を支度し、遊び具も用意して、細工も特別にして、蒔絵、螺鈿のよいものは、この姫に隠して、劣っているのを、
「これはいいものだ」
と言えば、守はよく分からないので、これといった価値のないものでも、調度類は、部屋中にただ集めて並べて、娘たちが目をわずかに出すばかりで、琴、琵琶の師でも、内教坊などから迎えて習わすのだった。
一曲弾き終われば、師を奉って拝み喜び、禄は埋まるほど与えて騒ぐのだった。調子の速い曲などを教えて、師と、趣ある夕方などに、弾き合わせて遊ぶときは、涙を隠さず、ばかばかしいほど武骨者であるが感じ入っている。夫のこのような振舞いの数々を、母君は少し物事に心得があるので、見苦しく思い、特別相手にしないのを、
「自分の子を、見下げている」
といつも恨んでいる。 |
|
| 50.3 左近少将、浮舟が継子だと知る |
かくて、この少将、契りしほどを待ちつけで、「同じくは疾く」とせめければ、わが心一つに、かう思ひ急ぐも、いとつつましう、人の心の知りがたさを思ひて、初めより伝へそめける人の来たるに、近う呼び寄せて語らふ。
「よろづ多く思ひ憚ることの多かるを、月ごろかうのたまひてほど経ぬるを、並々の人にもものしたまはねば、かたじけなう心苦しうて。かう思ひ立ちにたるを、親などものしたまはぬ人なれば、心一つなるやうにて、かたはらいたう、うちあはぬさまに見えたてまつることもやと、かねてなむ思ふ。
若き人びとあまたはべれど、思ふ人具したるは、おのづからと思ひ譲られて、この君の御ことをのみなむ、はかなき世の中を見るにも、うしろめたくいみじきを、もの思ひ知りぬべき御心ざまと聞きて、かうよろづのつつましさを忘れぬべかめるをしも、もし思はずなる御心ばへも見えば、人笑へに悲しうなむ」
と言ひけるを、少将の君に参うでて、
「しかしかなむ」
と申しけるに、けしき悪しくなりぬ。
「初めより、さらに、守の御娘にあらずといふことをなむ聞かざりつる。同じことなれど、人聞きもけ劣りたる心地して、出で入りせむにもよからずなむあるべき。ようも案内せで、浮かびたることを伝へける」
とのたまふに、いとほしくなりて、
「詳しくも知りたまへず。女どもの知るたよりにて、仰せ言を伝へ始めはべりしに、中にかしづく娘とのみ聞きはべれば、守のにこそは、とこそ思ひたまへつれ。異人の子持たまへらむとも、問ひ聞きはべらざりつるなり。
容貌、心もすぐれてものしたまふこと、母上のかなしうしたまひて、おもだたしう気高きことをせむと、あがめかしづかると聞きはべりしかば、いかでかの辺のこと伝へつべからむ人もがな、とのたまはせしかば、さるたより知りたまへりと、取り申ししなり。さらに、浮かびたる罪、はべるまじきことなり」
と、腹悪しく言葉多かる者にて、申すに、君、いとあてやかならぬさまにて、
「かやうのあたりに行き通はむ、人のをさをさ許さぬことなれど、今様のことにて、咎あるまじう、もてあがめて後見だつに、罪隠してなむあるたぐひもあめるを、同じこととうちうちには思ふとも、よそのおぼえなむ、へつらひて人言ひなすべき。
源少納言、讃岐守などの、うけばりたるけしきにて出で入らむに、守にもをさをさ受けられぬさまにて交じらはむなむ、いと人げなかるべき」
とのたまふ。 |
こうして、この少将は、約束の日を待ちきれず、「同じなら早く」と急がしたので、母は、自分ひとりで支度しても、気がかりだったので、相手の思惑も知りたくなり、初めに縁談を持って来た人を、呼び寄せて相談した。
「何につけても気がひけることが多いのですが、何か月も熱心に申し出てくれまして、並みのお方ではありませんのに、ありがたく心苦しく思います。この縁組を決心しましたのも、父親のない娘なので、わたしひとりで世話してましたので、はた目にも行き届かぬこともあろうかと、案じております。
若い娘たちは大勢いますが、父親がいる娘は放っておいても縁ずくだろうと任せる気になりまして、この娘のことばかりが気がかりで、はかないこの世を見て心配していましたが、あちら様は物の情の分るお方とお聞きして、こうして一切の遠慮も忘れております、もし心変わりでもありましたら、笑い者になって悲しいでしょう」
と言っているのを少将の処に行って、
「これこれと言う話です」
と申し上げると、少将の気色が急に悪くなった。
「初めから、守の娘でないと聞いていないぞ。同じことだけれど、世間体も悪く、出入りするにも格好が悪い。よく調べもしないで、いい加減な話を持ってきたものだ」
と言われると、困ってしまって、
「わたしも詳しくは知りません。女たちが知っている限りで、言われたことを伝えたのですが、特に大事に世話している姫と聞いておりましたが、守の娘と思っておりました。まさか他人の子だとは、尋ねもしなかった。
顔立ち、気立てもよく、母上が可愛がって、世間に自慢できるような身分の高い人との縁組を望んでいると、大切にしていると聞いていましたので、何とかして、あの家と伝のある人がいないか、と言っておられたので、都合の良いのを存じております、と申したのです。決して、いい加減な積りではありません」
と口さがない者が、言い張るので、少将は全く上品なところが一つもない調子で、
「あのような家に出入りするのは、世間体が悪いが、当節流行りのことで、非難されることでもない、相手が後見として、こちらの世話を焼いてくれるので、その不体裁を取り繕っている連中もいるし、姫を実子と同じように扱っていても、世間では私が追従しているように見るだろう。
源少納言、讃岐守などが、我が物顔に出入りしているのに、わたしははかばかしく守に認められないで交らうのは、全く肩身が狭い」
と言うのだった。 |
|
| 50.4 左近少将、常陸介の実娘を所望す |
この人、追従あるうたてある人の心にて、これをいと口惜しう、こなたかなたに思ひければ、
「まことに守の娘と思さば、まだ若うなどおはすとも、しか伝へはべらむかし。中にあたるなむ、姫君とて、守、いとかなしうしたまふなる」
と聞こゆ。
「いさや。初めよりしか言ひ寄れることをおきて、また言はむこそうたてあれ。されど、わが本意は、かの守の主の、人柄もものものしく、大人しき人なれば、後見にもせまほしう、見るところありて思ひ始めしことなり。もはら顔、容貌のすぐれたらむ女の願ひもなし。品あてに艶ならむ女を願はば、やすく得つべし。
されど、寂しうことうち合はぬ、みやび好める人の果て果ては、ものきよくもなく、人にも人ともおぼえたらぬを見れば、すこし人にそしらるとも、なだらかにて世の中を過ぐさむことを願ふなり。守に、かくなむと語らひて、さもと許すけしきあらば、何かは、さも」
とのたまふ。 |
この仲人は、追従の心ある嫌な人で、破談をどちらの家にも残念なことと思って、
「守の実の娘といえば、まだ年若いのだが、そう伝えましょう。中将の君腹の第二子を、姫君と呼んで守がたいそう可愛がっているそうです」
と言う。
「さあね、初めからあのように申し込んでいたことをさしおいて、別に求婚するのも嫌なことだ。だが、わたしの本意は、あの守の、人柄も立派で、老成しているので、後見になってほしい、と思ってはじめたことなのだ。顔立ちの美しい女を願っているわけではない。家柄がよくて優雅な女ならたやすく手に入ろう。
けれども、家運衰えて万事不如意な、風雅を愛した人々の行きつく果ては、小奇麗な暮らしもできず、世間からも人並みに思われていない有様を見ると、少し人に悪口を言われても、暮らしに困らないで世の中を過ごすことを願う。守にこう言って、そうかと許す気色が守にあれば、何のかまわぬ」
と言うのだった。 |
|
| 50.5 常陸介、左近少将に満足す |
この人は、妹のこの西の御方にあるたよりに、かかる御文なども取り伝へはじめけれど、守には詳しくも見え知られぬ者なりけり。ただ行きに、守の居たりける前に行きて、
「とり申すべきことありて」
など言はす。守、
「このわたりに時々出で入りはすと聞けど、前には呼び出でぬ人の、何ごと言ひにかはあらむ」
と、なま荒々しきけしきなれど、
「左近少将殿の御消息にてなむさぶらふ」
と言はせたれば、会ひたり。語らひがたげなる顔して、近うゐ寄りて、
† 「月ごろ、内の御方に消息聞こえさせたまふを、御許しありて、この月のほどにと契りきこえさせたまふことはべるを、日をはからひて、いつしかと思すほどに、ある人の申しけるやう、
『まことに北の方の御はからひにものしたまへど、守の殿の御娘にはおはせず。君達のおはし通はむに、世の聞こえなむへつらひたるやうならむ。受領の御婿になりたまふかやうの君達は、ただ私の君のごとく思ひかしづきたてまつり、手に捧げたるごと、思ひ扱ひ後見たてまつるにかかりてなむ、さる振る舞ひしたまふ人びとものしたまふめるを、さすがにその御願ひはあながちなるやうにて、をさをさ受けられたまはで、け劣りておはし通はむこと、便なかりぬべきよし』
をなむ、切にそしり申す人びとあまたはべるなれば、ただ今思しわづらひてなむ。
『初めよりただきらぎらしう、人の後見と頼みきこえむに、堪へたまへる御おぼえを選び申して、聞こえ始め申ししなり。さらに、異人ものしたまふらむといふこと知らざりければ、もとの心ざしのままに、まだ幼きものあまたおはすなるを、許いたまはば、いとどうれしくなむ。御けしき見て参うで来』
と仰せられつれば」
と言ふに、守、
「さらに、かかる御消息はべるよし、詳しく承らず。まことに同じことに思うたまふべき人なれど、よからぬ童べあまたはべりて、はかばかしからぬ身に、さまざま思ひたまへ扱ふほどに、母なる者も、これを異人と思ひ分けたることと、くねり言ふことはべりて、ともかくも口入れさせぬ人のことにはべれば、ほのかに、しかなむ仰せらるることはべりとは聞きはべりしかど、なにがしを取り所に思しける御心は、知りはべらざりけり。
さるは、いとうれしく思ひたまへらるる御ことにこそはべるなれ。いとらうたしと思ふ女の童は、あまたの中に、これをなむ命にも代へむと思ひはべる。のたまふ人びとあれど、今の世の人の御心、定めなく聞こえはべるに、なかなか胸いたき目をや見むの憚りに、思ひ定むることもなくてなむ。
いかでうしろやすくも見たまへおかむと、明け暮れかなしく思うたまふるを、少将殿におきたてまつりては、故大将殿にも、若くより参り仕うまつりき。家の子にて見たてまつりしに、いと警策に、仕うまつらまほしと、心つきて思ひきこえしかど、遥かなる所に、うち続きて過ぐしはべる年ごろのほどに、うひうひしくおぼえはべりてなむ、参りも仕まつらぬを、かかる御心ざしのはべりけるを。
返す返す、仰せの事たてまつらむはやすきことなれど、月ごろの御心違へたるやうに、この人、思ひたまへむことをなむ、思うたまへ憚りはべる」
と、いとこまやかに言ふ。 |
この人(仲人)は、妹のこの西の御方(浮舟)に仕えてていて、このような文も取り次ぎできるのだが、守には詳しく知られていない者だった。 守の御前にずかずかと進んで、
「申し上げねばならぬことがあります」
などと取り次がす。守は、
「この家に時々出入りしていると聞いているが、目通りさせたことのない者が、何の用事だろう」
と、守は不愛想な風情で、
「左近少将殿のお言葉をお伝えに参りました」
と取り次ぎに言わせて会った。仲人は言いにくそうに、近くに寄って、
「幾月も、北の方様に求婚の文を差し上げていましたが、お許しがあって、この八月のうちにとお約束されまして、吉日を選んで早く式を挙げようという時になって、ある人が申しますには、
『確かに北の方の産んだお子ですが、守殿の実の娘ではありません。公達が受領の家に通うのは、世間の目では公達が追従しへつらったように見えるだろう。受領の婿になろうとする公達は、主君のようにかしずかれて、大事にされて、気を配られて、後見されのが取り柄で、そのような縁組をする者もいるようですが、とはいえそんな願いは無理と思われ、きちんと婿として受け入れられず、他の婿たちに劣った扱いをされるのは具合が悪いことです』
こう言って、しきりに悪口を申す人々が大勢いるので、今は考え直しています。
『初めから、ただ盛んなご威勢を見込んで、然るべき後見を当てにして、十分なご声望があると見込んで申し入れています。まして実子でないなどと聞いていませんので、元の望みのままに、まだ幼い姫君がたくさんおられるので、他の姫君をお許し下されば、たいへんうれしく存じます、ご意見を伺って来い』
と少将殿が仰いますので」
と申し上げると、守は、
「そのような事情にあるとは、詳しくは聞いておりません。実子同然に世話すべき姫ですが、ほかにも不出来な娘がたくさんいまして、たいしたこともできぬままに、それぞれに面倒見ているうちに、母もこの姫を分け隔てしていると、ひが事を言うことがありまして、妻は口出しさせぬ人なので、うすうすそのようなことがあると聞いていましたが、わたしが取り柄と思っている、その後見を当てにしての求婚とは知りませんでした。
そうであれば、たいそううれしく思います。娘がたくさんいるの中で、命に換えていいも思うくらい可愛いい娘がいます。所望する者たちはたくさんいますが、当世の若者は、当てにならぬと言われますので、かえって痛い目にあうのではないかと心配で、決めることができないでいます。
是非とも、安心できる境遇にと、明け暮れ心を痛めておりますが、少将殿におかれては、亡き大将殿にわたしは若い頃から仕えておりました。 出入りの家来として、日頃拝見していましたが、たいそう優秀な人と知られ、お仕えしたいと心底思っておりましたが、遙か東国に長年過ごしてきまして、お目通りできずにいまして、参上してお仕えできませんでしたが、お慕いしていました。
まことに、仰せの通り娘を差し上げたいのですが、今までの経緯もあり、母親の気持ちを妨げるようなことになるのではないか、気にしていますす」
と、守は細やかに言うのだった。 |
|
| 50.6 仲人、左近少将を絶賛す |
よろしげなめりと、うれしく思ふ。
「何かと思し憚るべきことにもはべらず。かの御心ざしは、ただ一所の御許しはべらむを願ひ思して、『いはけなく年足らぬほどにおはすとも、真実のやむごとなく思ひおきてたまへらむをこそ、本意叶ふにはせめ。もはらさやうのほとりばみたらむ振る舞ひすべきにもあらず』と、なむのたまひつる。
人柄はいとやむごとなく、おぼえ心にくくおはする君なりけり。若き君達とて、好き好きしくあてびてもおはしまさず、世のありさまもいとよく知りたまへり。領じたまふ所々もいと多くはべり。まだころの御徳なきやうなれど、おのづからやむごとなき人の御けはひのありげなるやう、直人の限りなき富といふめる勢ひには、まさりたまへり。来年、四位になりたまひなむ。こたみの頭は疑ひなく、帝の御口づからごてたまへるなり。
『よろづのこと足らひてめやすき朝臣の、妻をなむ定めざなる。はやさるべき人選りて、後見をまうけよ。上達部には、我しあれば、今日明日といふばかりになし上げてむ』とこそ仰せらるなれ。何事も、ただこの君ぞ、帝にも親しく仕うまつりたまふなる。
御心はた、いみじう警策に、重々しくなむおはしますめる。あたら人の御婿を。かう聞きたまふほどに、思ほし立ちなむこそよからめ。かの殿には、我も我も婿にとりたてまつらむと、所々にはべるなれば、ここにしぶしぶなる御けはひあらば、他ざまにも思しなりなむ。これ、ただうしろやすきことをとり申すなり」
と、いと多く、よげに言ひ続くるに、いとあさましく鄙びたる守にて、うち笑みつつ聞きゐたり。 |
どうやら乗り気らしい、と仲人はうれしく思う。
「何やかやとお気遣いなさるようなことでもございません。少将の気持ちはただ一つ、主人である守のお許しが出るように、『年端がゆかぬ姫でも、大切に思っている実の子こそ、念願がかないます。絶対にそのような主人のご存じないような振舞いをすべきでない』と少将は仰せでした。
少将は、人柄が上品で、世間の声望もよい方でございます。若い公達といっても、女好きで遊んでいるというお方ではなく、世間の道理もよくわきまえておられます。ご所領もたくさんございます。まだ今のところお金まわりはぱっとしないようですが、何といっても立派な家柄に生まれた風格の具わったことといったら、平の人の膨大な財産の勢いより、まさっております。来年四位になります。次の蔵人頭は間違いなく、帝の口ずからのお言葉です。
『万事具わっているそなたが、妻を持っていない。早く適当な人を選んで、後見者をつくりなさい。上達部には、わたしがいることだから、すぐにも昇進させよう』と仰せになって、何ごとも、ただこの少将こそ、帝にも親しくお仕えしております。
少将のお考えはまことに立派でしっかりしております、せっかくの立派な婿を、そうと聞いたらすぐにも決めるのがいいでしょう。あの殿には、婿に取ろうとしている所があちこちにありますので、こちらでぐずぐずしていると、ほかの家に変えるかもしれません。これは、こちらの為と思って申し上げているのです」
と長々と、調子のよい話を言い立てるので、守は全くの田舎者なので、笑みを浮かべて聞いている。 |
|
| 50.7 左近少将、浮舟から常陸介の実娘にのり換える |
「このころの御徳などの心もとなからむことは、なのたまひそ。なにがし命はべらむほどは、頂に捧げたてまつりてむ。心もとなく、何を飽かぬとか思すべき。たとひあへずして仕うまつりさしつとも、残りの宝物、領じはべる所々、一つにてもまた取り争ふべき人なし。
子ども多くはべれど、これはさま異に思ひそめたる者にはべり。ただ真心に思し顧みさせたまはば、大臣の位を求めむと思し願ひて、世になき宝物をも尽くさむとしたまはむに、なきものはべるまじ。
当時の帝、しか恵み申したまふなれば、御後見は心もとなかるまじ。これ、かの御ためにも、なにがしが女の童のためにも、幸ひとあるべきことにやとも知らず」
と、よろしげに言ふ時に、いとうれしくなりて、妹にもかかることありとも語らず、あなたにも寄りつかで、守の言ひつることを、「いともいともよげにめでたし」と思ひて聞こゆれば、君、「すこし鄙びてぞある」とは聞きたまへど、憎からず、うち笑みて聞きゐたまへり。大臣にならむ贖労を取らむなどぞ、あまりおどろおどろしきことと、耳とどまりける。
「さて、かの北の方には、かくとものしつや。心ざしことに思ひ始めたまへらむに、ひき違へたらむ、ひがひがしくねぢけたるやうにとりなす人もあらむ。いさや」
と思したゆたひたるを、
「何か。北の方も、かの姫君をば、いとやむごとなきものに思ひかしづきたてまつりたまふなりけり。ただ中のこのかみにて、年も大人びたまふを、心苦しきことに思ひて、そなたにとおもむけて申されけるなりけり」
と聞こゆ。「月ごろは、またなく世の常ならずかしづくと言ひつるものの、うちつけにかく言ふもいかならむと思へども、なほ、 一わたりはつらしと思はれ、人にはすこし誹らるとも、長らへて頼もしき事をこそ」と、いとまたくかしこき君にて、思ひ取りてければ、日をだにとり替へで、契りし暮れにぞ、おはし始めける。 |
今現在の財力が心もとないことなどは、言ってくれるな。わたしの命がある限りは、頂きに捧げましょう。心もとなく、何を不足と思うことがありましょうか。たとえ寿命が尽きてお世話できなくなっても、あとに残す宝物、領地など、一つとして取り合いする者はおりません。
子供はたくさんいますが、この娘は特別に思っているのです。少将が、娘を真心こめて大事にして下さるのなら、たとえ大臣の位を得るために、珍しい宝物が必要だとしても、何でも用意しましょう。
当代の帝がそのような心にかけて仰るのですから、後見は引き受けましょう。これは、少将の為にも、わたしの娘のためにも幸せになるかどうか分かりませんが」
とまんざらでもなく言うので、仲人はすっかりうれしくなり、妹にもこういうことがあったと伝えず、母北の方の方にも寄らず、守の言ったことを、「何とも結構な話だ」と思って報告すれば、少将の君は、「少し田舎びてるな」とは思ったが、悪い気はせず、微笑んで聞いていた。大臣になるための財物の調達など、仰々しい言い方だと、耳にとまった。
「ところで、あの北の方には話はこうなったと伝えたか。たいへんな熱意で思い立たれたそうですから、約束を違えたら、間違ってる、ひどい話しだ、と非難する人もいるだろう。どうしたものか」
と思って躊躇していると、
「何の、北の方はあの姫君を、たいそう大切に思い育てておられます。ただ姉妹の中で一番年長の姉なので、年もいってるし、可哀そうに思って、そちらの方はどうですかと振り向けて申されたのだと思います」
と仲人が言う。「今までは、この上なく特別に大切に思っていると言っていたのに、急に変わって、このように言うのもどんなものかと思ったが、やはり一度はひどい男と恨まれ、世間からも悪く言われても、長く頼りになるのが大事」と抜け目なく利口な男で、決心したので、日も変えないで、約束した日の暮れに出かけた。 |
|
| 50.8 浮舟の縁談、破綻す |
北の方は、人知れずいそぎ立ちて、人びとの装束せさせ、しつらひなどよしよししうしたまふ。御方をも、頭洗はせ、取りつくろひて見るに、少将などいふほどの人に見せむも、惜しくあたらしきさまを、
「あはれや。親に知られたてまつりて生ひ立ちたまはましかば、おはせずなりにたれども、大将殿ののたまふらむさまに、おほけなくとも、などかは思ひ立たざらまし。されど、うちうちにこそかく思へ、他の音聞きは、守の子とも思ひ分かず、また、実を尋ね知らむ人も、なかなか落としめ思ひぬべきこそ悲しけれ」
など、思ひ続く。
「いかがはせむ。盛り過ぎたまはむもあいなし。卑しからず、めやすきほどの人の、かくねむごろにのたまふめるを」
など、心一つに思ひ定むるも、媒のかく言よくいみじきに、女はましてすかされたるにやあらむ。明日明後日と思へば、心あわたたしくいそがしきに、こなたにも心のどかに居られたらず、そそめきありくに、守外より入り来て、ながながと、とどこほるところもなく言ひ続けて、
「我を思ひ隔てて、吾子の御懸想人を奪はむとしたまひける、おほけなく心幼きこと。めでたからむ御娘をば、要ぜさせたまふ君達あらじ。卑しく異やうならむなにがしらが女子をぞ、いやしうも尋ねのたまふめれ。かしこく思ひ企てられけれど、もはら本意なしとて、他ざまへ思ひなりたまふべかなれば、同じくはと思ひてなむ、さらば御心、と許し申しつる」
など、あやしく奥なく、人の思はむところも知らぬ人にて、言ひ散らしゐたり。
北の方、あきれて物も言はれで、とばかり思ふに、心憂さをかき連ね、涙も落ちぬばかり思ひ続けられて、やをら立ちぬ。 |
北の方は、誰にも言わず支度をして、女房たちの装束を新調し、部屋の飾りつけも趣深くさせた。姫にも、頭を洗わせ、身づくろいして見ると、少将程度の者にやるのも、惜しいほどの美しさになり、
「可哀そうに、父宮に認知されて育ったなら、亡くなったけれども、大将(薫)殿がご所望のよしだが、分に過ぎるようだが、何で決心しないことがあろうか。けれど、自分だけがこう思っていても、世間の人は、守の子と区別して思っていないし、ほんとうのことを聞き知った人も、かえって軽く見られるのが悲しい」
などと思う。
「仕方ない。娘盛りが過ぎてしまうのも残念だ。家柄も悪くないし大して難がない人が、熱心に仰って下さるので」
などと、母君ひとりで決めてしまうのも、仲人が口先がうまく調子がいいいので、母はすっかりのせられたのであろう。明日明後日と日も迫り、せわしく忙しいのに、娘の部屋にもゆくり落ち着いてもいられず、あちこちしていると、守が外から帰ってきて、長々と喋って、
「わたしに隠して、我が子を好いてくださる人を横取りしようとなさるとは、愚かなことだ。さぞかし立派な娘御を妻にしようとする公達はおるまい。身分も低いみっともないわたしらの娘に、わざわざお声をかけてくださるそうだ。あなたは賢く計画したようだが、少将は自分の意に反するとして、他家の婿になるつもりいるので、同じことなら、お望みのままに実の娘を、と許可したよ」
遠慮なく、人の思惑を気にしない人なので、守はずけずけ言うのだった。
北の方は、あきれて物も言えず、しばし考えて、情けなさがこみあげて、涙がこぼれんばかりに思い詰めて、黙ってその場を去った。 |
|
| 50.9 浮舟の母と乳母の嘆き |
こなたに渡りて見るに、いとらうたげにをかしげにて居たまへるに、「さりとも、人には劣りたまはじ」とは思ひ慰む。乳母と二人、
「心憂きものは人の心なりけり。おのれは、同じごと思ひ扱ふとも、この君のゆかりと思はむ人のためには、命をも譲りつべくこそ思へ、親なしと聞きあなづりて、まだ幼くなりあはぬ人を、さし越えて、かくは言ひなるべしや。
かく心憂く、近きあたりに見じ聞かじと思ひぬれど、守のかくおもだたしきことに思ひて、受け取り騒ぐめれば、あひあひにたる世の人のありさまを、すべてかかることに口入れじと思ふ。いかでここならぬ所に、しばしありにしがな」
とうち嘆きつつ言ふ。乳母もいと腹立たしく、「わが君をかく落としむること」と思ふに、
「何か、これも御幸ひにて違ふこととも知らず。かく心口惜しくいましける君なれば、あたら御さまをも見知らざらまし。わが君をば、心ばせあり、もの思ひ知りたらむ人にこそ、見せたてまつらまほしけれ。
大将殿の御さま容貌の、ほのかに見たてまつりしに、さも命延ぶる心地のしはべりしかな。あはれにはた聞こえたまふなり。御宿世にまかせて、思し寄りねかし」
と言へば、
「あな、恐ろしや。人の言ふを聞けば、年ごろ、おぼろけならむ人をば見じとのたまひて、右の大殿、按察使大納言、式部卿宮などの、いとねむごろにほのめかしたまひけれど、聞き過ぐして、帝の御かしづき女を得たまへる君は、いかばかりの人かまめやかには思さむ。
かの母宮などの御方にあらせて、時々も見むとは思しもしなむ、それはた、げにめでたき御あたりなれども、いと胸痛かるべきことなり。宮の上の、かく幸ひ人と申すなれど、もの思はしげに思したるを見れば、いかにもいかにも、二心なからむ人のみこそ、めやすく頼もしきことにはあらめ。わが身にても知りにき。
故宮の御ありさまは、いと情け情けしく、めでたくをかしくおはせしかど、人数にも思さざりしかば、いかばかりかは心憂くつらかりし。このいと言ふかひなく、情けなく、さま悪しき人なれど、ひたおもむきに二心なきを見れば、心やすくて年ごろをも過ぐしつるなり。
をりふしの心ばへの、かやうに愛敬なく用意なきことこそ憎けれ、嘆かしく恨めしきこともなく、かたみにうちいさかひても、心にあはぬことをばあきらめつ。上達部、親王たちにて、みやびかに心恥づかしき人の御あたりといふとも、わが数ならでは甲斐あらじ。
よろづのこと、わが身からなりけりと思へば、よろづに悲しうこそ見たてまつれ。いかにして、人笑へならずしたてたてまつらむ」
と語らふ。 |
姫の部屋に戻って見ると、ほんとうに可愛らしくしているので、「たとえこんなことになっても、人には劣らない」と思って慰める。乳母と二人、
「情けないのは人の心です。自分は同じに思って扱っていても、この姫の婿と思う人には、命に換えてもと思っている、父親がいないと馬鹿にして、姉君を飛び越えて、まだ幼い娘に、こんなふうに話をつけていいものだろうか。
「こんなに情けないことを、同じ家の中で見たり聞いたりしたくないと思うが、守があんなに晴れがましく思って、承諾して喜んでいると、似た者同士の有様だ、今度の縁組に一切口出ししないと思う。当座の間どこかいっていたい」
と嘆くのだった、乳母も腹だたしく、「我が姫君をこんなに見下げて」と思うと、
「何か、これも幸運なのかもしれない。あのような情けない気持ちの公達ですから、姫の美しさもお分かりにならないでしょう。わが姫を、心根もやさしく、物の道理も分かった人にお引き合わせしたい。
大将殿(薫)の風采や容貌を、ちらっと拝見しましたが、命が延びる心地がしました。世話したいと仰せだそうではありませんか。ご運にまかせて、そちらにお決めになっては」
と言えば、
「まあ、とんでもない。年来、並みの人とは結婚する気はないと仰っていて、右の大殿(夕霧)、按察使大納言(紅梅大納言)、式部卿などから、婿にとの話を、聞き過ごして、帝が可愛がっている内親王を得た君は、どれほどの女を世話しようと思うでしょう。
あの女三の宮の御方に仕えて、時々お逢いして、それはそれでめでたいお勤め先ではありますが、気のもめることでしょう。宮の上(中の君)が幸運な人だと申すけれど、物思いがちに沈んでいるのを見ますと、何はさておいて、二心のない人を婿にしてこそ、夫婦仲も見苦しくなく頼もしいでしょう。自分の経験からそうでした。
亡き八の宮の人柄は、たいそうやさしく、優雅で上品な方でしたが、わたしを人並みには思ってくだされなかったので、どれだけつらかったことか。今の常陸の介は、お話にならない、不体裁な人ですが、浮気をしないので、気をもむことなく長年過ごして来ました。
何かの折に、このようにぶっきらぼうになるのが、憎らしいが、嘆くことも恨めしくなることもなく、互いに言い争いをしても合点のゆかないことははっきりさせました。上達部親王の処で、優雅で気後れするほど立派な方に仕えるとしても、自分の身分が低いのではどうにもならない。
万事、自分の身の程によるのだと思えば、何につけても、悲しいく思います。どうやって姫に物笑いにならないよう立派な縁組をさせたい」
と語るのだった。 |
|
| 50.10 継父常陸介、実娘の結婚の準備 |
守は急ぎたちて、
「女房など、こなたにめやすきあまたあなるを、このほどは、あらせたまへ。やがて、帳なども新しく仕立てられためる方を、事にはかになりにためれば、取り渡し、とかく改むまじ」
とて、西の方に来て、立ち居、とかくしつらひ騒ぐ。めやすきさまにさはらかに、あたりあたりあるべき限りしたる所を、さかしらに屏風ども持て来て、いぶせきまで立て集めて、厨子二階など、あやしきまでし加へて、心をやりて急げば、北の方見苦しく見れど、口入れじと言ひてしかば、ただに見聞く。御方は、北面に居たり。
「人の御心は、見知り果てぬ。ただ同じ子なれば、さりとも、いとかくは思ひ放ちたまはじとこそ思ひつれ。さはれ、世に母なき子は、なくやはある」
とて、娘を、昼より乳母と二人、撫でつくろひ立てたれば、憎げにもあらず、十五、六のほどにて、いと小さやかにふくらかなる人の、髪うつくしげにて小袿のほどなり、裾いとふさやかなり。これをいとめでたしと思ひて、撫でつくろふ。
「何か、人の異ざまに思ひ構へられける人をしも、と思へど、人柄のあたらしく、警策にものしたまふ君なれば、我も我もと、婿に取らまほしくする人の多かなるに、取られなむも口惜しくてなむ」
と、かの仲人にはかられて言ふもいとをこなり。男君も、「このほどのいかめしく思ふやうなること」と、よろづの罪あるまじう思ひて、その夜も替へず来そめぬ。 |
守は、準備に急いで、
「女房などは、こちらに見栄えの好いのがたくさんいるので、当分の間わたしに貸してください。簾台なども新しく作ったようだから、急を要するので、それを使わせてもらい、新しく作ることはしないでおこう」
と言って、西の方に来て、あれこれ騒がしくしている。あちらこちら十分に手入れされている部屋に、屏風などを持ってきて、見苦しいほどに立てつけて、二層の厨子など、余計に加えて、得意になって支度するので、北の方は見苦しくなったと見ていたが、口出ししないと言った手前、ただ見ているばかり。姫君は北面にいた。
「北の方の本心はよくわかった。同じ実子なのに、これほど冷たくすることはないでしょう。まあ、世間に母無し子がいないわけではないだろう」
と言って、娘を昼から乳母と二人で、撫で繕ったので、可愛らしくなり、十五、六の年で、小柄でふっくらして、髪が美しく小袿の丈までのびていて、裾がふっくらしている。常陸の介は、これをたいそう美しいと思って、撫でつくろうのだった。
「何も、北の方が他の娘にと心積もりしていた婿を、わざわざと思うが、少将は人柄もすばらしいし、学問もある方だから、我も我もと婿の希望だ多い人なので、取られてしまうのも口惜しいので」
と、あの仲人に騙されてその通りに言うのも馬鹿げている。少将も、「これほどの仰々しい過分な扱い」と、申し分なく思って、その夜も替えずに通うのだった。 |
|
| 50.11 浮舟の母、京の中君に手紙を贈る |
母君、御方の乳母、いとあさましく思ふ。ひがひがしきやうなれば、とかく見扱ふも心づきなければ、宮の北の方の御もとに、御文たてまつる。
「そのこととはべらでは、なれなれしくやとかしこまりて、え思ひたまふるままにも聞こえさせぬを、つつしむべきことはべりて、しばし所変へさせむと思うたまふるに、いと忍びてさぶらひぬべき隠れの方さぶらはば、いともいともうれしくなむ。数ならぬ身一つの蔭に隠れもあへず、あはれなることのみ多くはべる世なれば、頼もしき方にはまづなむ」
と、うち泣きつつ書きたる文を、あはれとは見たまひけれど、「故宮の、さばかり許したまはでやみにし人を、我一人残りて、知り語らはむもいとつつましく、また見苦しきさまにて世にあぶれむも、知らず顔にて聞かむこそ心苦しかるべけれ。ことなることなくてかたみに散りぼはむも、亡き人の御ために見苦しかるべきわざ」を思しわづらふ。
大輔がもとにも、いと心苦しげに言ひやりたりければ、
「さるやうこそははべらめ。人憎くはしたなくも、なのたまはせそ。かかる劣りの者の、人の御中に交じりたまふも、世の常のことなり」
など聞こえて、
「さらば、かの西の方に、隠ろへたる所し出でて、いとむつかしげなめれど、さても過ぐいたまひつべくは、しばしのほど」
と言ひつかはしつ。いとうれしと思ほして、人知れず出で立つ。御方も、かの御あたりをば、睦びきこえまほしと思ふ心なれば、なかなか、かかることどもの出で来たるを、うれしと思ふ。 |
母君や乳母は、あきれてものも言えない。何やら異常な気がするので、あれこれ世話を焼くのも気に染まないの、宮の北の方(中の君)に文を出した。
「格別のご用もございませんので、失礼ではとご遠慮申してましたが、心に思うことを知らせずにいましたが、忌避すべきことがございまして、娘の居所を変えようと思います、隠れて住まいできる処がございましたら、大へんうれしいです。数ならぬこの身でかくまうこともできず、あわれなことの多いこの世で、お頼みする先としてまずあなた様を」
と、泣きながら書いた文を、あわれと思ったが、「亡き父宮が決してお認めにならなかった人を、わたしだけが世に残って親しく付き合うのも気がひけるし、また、見っともなく落ちぶれているのを、知らん顔で見過ごすのも、気の毒だし、大して幸せにならずにどちらも落ちぶれているのも、亡き父の為にも不面目だ」と思い煩う。
大輔の処にも、母君から心配でならぬ旨言ってきたので、
「何かわけがあるのでしょう。冷たく断るのは、お止めください。こんな身分違いの母は、姉妹の中で時々いるのも、よくあることです」
と言って、
それでは、あの西の廂に人目のつかぬ部屋をしつらえて、ずいぶんむさ苦しいでしょうが、そこにしばらく住んでもらえば」
母に言ってやった。母君はたいそううれしく思って、こっそり出立しようとする。姫君も中の君と、親しくしたいと思っていたので、かえってこんなことになったのも、うれしく思った。 |
|
| 50.12 母、浮舟を匂宮邸に連れ出す |
守、少将の扱ひを、いかばかりめでたきことをせむと思ふに、そのきらきらしかるべきことも知らぬ心には、ただ、あららかなる東絹どもを、押しまろがして投げ出でつ。食ひ物も、所狭きまでなむ運び出でてののしりける。
下衆などは、それをいとかしこき情けに思ひければ、君も、「いとあらまほしく、心かしこく取り寄りにけり」と思ひけり。北の方、「このほどを見捨てて知らざらむもひがみたらむ」と思ひ念じて、ただするままにまかせて見ゐたり。
† 客人の御出居、侍ひとしつらひ騒げば、家は広けれど、源少納言、東の対には住む、男子などの多かるに、所もなし。この御方に客人住みつきぬれば、廊などほとりばみたらむに住ませたてまつらむも、飽かずいとほしくおぼえて、とかく思ひめぐらすほど、宮にとは思ふなりけり。
† 「この御方ざまに、数まへたまふ人のなきを、あなづるなめり」と思へば、ことに許いたまはざりしあたりを、あながちに参らず。乳母、若き人びと、二、三人ばかりして、西の廂の北に寄りて、人げ遠き方に局したり。
年ごろ、かくはかなかりつれど、疎く思すまじき人なれば、参る時は恥ぢたまはず、いとあらまほしく、けはひことにて、若君の御扱ひをしておはする御ありさま、うらやましくおぼゆるもあはれなり。
「我も、故北の方には、離れたてまつるべき人かは。仕うまつるといひしばかりに、数まへられたてまつらず、口惜しくて、かく人にはあなづらるる」
と思ふには、かくしひて睦びきこゆるもあぢきなし。ここには、御物忌と言ひてければ、人も通はず。二、三日ばかり母君もゐたり。こたみは、心のどかにこの御ありさまを見る。 |
守は、少将の新婚のもてなしを、どんなに立派にしようかと思っていたが、その晴れがましい様子を知らないので、ただ荒い東国の絹を、無造作に投げ出している。食べ物も、置き場もないほど運び出して騒いでいる。
下人たちも、それをたいそうな主人の心遣いと思い、少将も、「まったく思い通りだ。利口な縁組だった」と思う。北の方は、「結婚の座にいないで知らん顔しているのも意地悪のようだ」と我慢して、ただするに任せて見ていた。
客人(少将)の居室、供人控室の用意に大騒ぎしている、家は広いが、源少納言が東の対に住んいて、男子が多いので、余裕がない。 姫君の居室だった西の対に客人が住むので、廊下の端に住まわせるのも、かわいそうなので、あれこれ思いめぐらしていると、匂宮の邸を思いついた。
†「この姫君の身内に、後見がいないので、軽んじられている」と思い、父宮には認知されなかったのは、目をつぶって参上させる。乳母、若い女房二、三人ばかり伴って、西の廂の北寄りで、人気のない処を部屋にした。
長年、お付き合いはなかったが、他人とは思われない人なので、御前に参るときは、恥じらわなかった。何一つ不足なところはなく、上品で、若君の赤子をあやす様子も、うらやましく思われ胸にせまる。
「わたしだって故北の方には、縁遠い人ではないのに、北の方に仕えていたばかりに、人並みに扱っていただけず、口惜しく、人に軽んじられている」
と思っているので、こうして押しかけて親しくするのもおもしろくない。こちらの邸には物忌といってあるので、人も来ない。二、三日ばかり母君も滞在した。今回はゆっくりした気分で暮らしぶりを拝見する。 |
|
| 50.13 浮舟の母、匂宮と中君夫妻を垣間見る |
宮渡りたまふ。ゆかしくてもののはさまより見れば、いときよらに、桜を折りたるさましたまひて、わが頼もし人に思ひて、恨めしけれど、心には違はじと思ふ常陸守より、さま容貌も人のほども、こよなく見ゆる五位四位ども、あひひざまづきさぶらひて、このことかのことと、あたりあたりのことども、家司どもなど申す。
また若やかなる五位ども、顔も知らぬどもも多かり。わが継子の式部丞にて蔵人なる、内裏の御使にて参れり。御あたりにもえ近く参らず。こよなき人の御けはひを、
「あはれ、こは何人ぞ。かかる御あたりにおはするめでたさよ。よそに思ふ時は、めでたき人びとと聞こゆとも、つらき目見せたまはばと、もの憂く推し量りきこえさせつらむあさましさよ。この御ありさま容貌を見れば、七夕ばかりにても、かやうに見たてまつり通はむは、いといみじかるべきわざかな」
と思ふに、若君抱きてうつくしみおはす。女君、短き几帳を隔てておはするを、押しやりて、ものなど聞こえたまふ御容貌ども、いときよらに似合ひたり。故宮の寂しくおはせし御ありさまを思ひ比ぶるに、「宮たちと聞こゆれど、いとこよなきわざにこそありけれ」とおぼゆ。
几帳の内に入りたまひぬれば、若君は、若き人、乳母などもてあそびきこゆ。人びと参り集まれど、悩ましとて、大殿籠もり暮らしつ。御台こなたに参る。よろづのこと気高く、心ことに見ゆれば、わがいみじきことを尽くすと見思へど、「なほなほしき人のあたりは、口惜しかりけり」と思ひなりぬれば、「わが娘も、かやうにてさし並べたらむには、かたはならじかし。勢ひを頼みて、父ぬしの、后にもなしてむと思ひたる人びと、同じわが子ながら、けはひこよなきを思ふも、なほ今よりのちも、心は高くつかふべかりけり」と、夜一夜あらまし語り思ひ続けらる。 |
匂宮が西の対に、お越しになる。拝見したくて母君は物の隙間から覗いてみると、とても美しく、桜を折ったようで、頼りにしている夫、恨めしい時もあるが、その意には違うまいと思っている常陸守より、姿も顔立ちも風采も、立派に見える五位四位たちが、ひざまずいて、あれこれと、報告する、家司も申し上げる。
まだ若い五位もいて、顔も知らない者も多かった。自分の継子である式部丞の蔵人が、帝の使いで来たが、匂宮のそばにも寄れない。この上もない宮の様子を、
「ああ、これは何というお方だろう。このような方の奥方になられためでたさよ。遠から見るときは、いくら結構なご身分と言っても、つらい目に会えば、気持ちも落ち込むだろうと、推察していたが、とんでもない。この御様子を見れば、七夕のようでも、こうして拝見できるだけでも、素晴らしいことだ」
と思うと、若君をあやしている。女君が、短い几帳を隔てていたが、匂宮は押しやって、話している様子は、お二人とも美しくお似合いだった。亡き八の宮のひっそり暮らしていた様子と比べると、「同じ宮様といっても、大へんな違いだ」と思う。
「几帳のなかに入ったので、若君は、若い女房、乳母などに渡された。廷臣たちが集まってくるが、気分が悪いといって、お休みになった。食膳はこちらに運ばせる。万事が高貴で、立派に見えるので、我が家は素晴らしい暮らしぶりだと思っていたが、「身分の低い者の暮らしぶりはたかが知れている」と悟ってしまえば、「わが娘も(浮舟)高貴な方のそばに仕えさせたら、おかしくない。財力に頼んで、父親(常陸の介) のように、皇后にでもしたいと思っている娘たちは、同じ我が子ながら、気配がまるで違う、志は高く持とう」と一晩中思うのであった。 |
|
| 50.14 浮舟の母、左近少将を垣間見て失望 |
宮、日たけて起きたまひて、
「后の宮、例の、悩ましくしたまへば、参るべし」
とて、御装束などしたまひておはす。ゆかしうおぼえて覗けば、うるはしくひきつくろひたまへる、はた、似るものなく気高く愛敬づききよらにて、若君をえ見捨てたまはで遊びおはす。御粥、強飯など参りてぞ、こなたより出でたまふ。
今朝より参りて、さぶらひの方にやすらひける人びと、今ぞ参りてものなど聞こゆる中に、きよげだちて、なでふことなき人のすさまじき顔したる、直衣着て太刀佩きたるあり。御前にて何とも見えぬを、
「かれぞ、この常陸守の婿の少将な。初めは御方にと定めけるを、守の娘を得てこそいたはられめ、など言ひて、かしけたる女の童を持たるななり」
「いさ、この御あたりの人はかけても言はず。かの君の方より、よく聞くたよりのあるぞ」
など、おのがどち言ふ。聞くらむとも知らで、人のかく言ふにつけても、胸つぶれて、少将をめやすきほどと思ひける心も口惜しく、「げに、ことなることなかるべかりけり」と思ひて、いとどしくあなづらはしく思ひなりぬ。
若君のはひ出でて、御簾のつまよりのぞきたまへるを、うち見たまひて、立ち返り寄りおはしたり。
「御心地よろしく見えたまはば、やがてまかでなむ。なほ苦しくしたまはば、今宵は宿直にぞ。今は、一夜を隔つるもおぼつかなきこそ苦しけれ」
とて、しばし慰め遊ばして、出でたまひぬるさまの、返す返す見るとも見るとも、飽くまじく、匂ひやかにをかしければ、出でたまひぬる名残、さうざうしくぞ眺めらるる。 |
匂宮は、日が高くなって起きて、
「明石の中宮の具合が悪いので、参内しなければ」
と言って、装束を調え、見てみたいので覗けば、美しく着付けている姿は格別で、似る者もなく気高く魅力があって美しく、若君を手放さずに遊んでいらっしゃる。粥、強飯を召し上がってから、西の対から内裏に出かけようとしている。
今朝から参上して、詰め所に控えていた廷臣たちで、宮に何かと報告している中に、小ざっぱりしているが、これといった特徴もなく荒ぶった顔で、直衣に大刀を佩いている者がいた。御前では何も目立たず、
「かれが常陸の守の婿の少将だ。はじめは、このお方(浮舟)にと決めていたのに、実の娘を得て優遇されたいので、幼い娘をもらったそうよ」
「いえ、こちらの方(浮舟方の女房)は何も言いません。あちらの(少将方)方から、詳しく聞く伝があります」
など女房たちが話している。聞いているとも知らないで、人がこんな噂をしているのも、胸が痛く、少将を見苦しくないと思ったのも口惜しく、「見ての通り、大した人物ではない」と思って、いよいよ軽んずる気持ちになる。
若君が這い出て、御簾の端から覗いているので、宮は戻ってきて相手をするのだった。
「中宮様の気分が良いようでしたら、すぐに退出して参ろう。相変わらず具合が悪いようだったら、今宵は宿直する。今は一夜を隔てるのも恋しい」
と言って、若君の相手をしてから、出かけた様子が、何度見返しても、飽きない、輝くばかりの美しさなので、お出かけになった名残りが、残念に思われるのだった。 |
|
| 50.15 浮舟の母、中君と談話す |
女君の御前に出で来て、いみじくめでたてまつれば、田舎びたる、と思して笑ひたまふ。
「故上の亡せたまひしほどは、言ふかひなく幼き御ほどにて、いかにならせたまはむと、見たてまつる人も、故宮も思し嘆きしを、こよなき御宿世のほどなりければ、さる山ふところのなかにも、生ひ出でさせたまひしにこそありけれ。口惜しく、故姫君のおはしまさずなりにたるこそ、飽かぬことなれ」
など、うち泣きつつ聞こゆ。君もうち泣きたまひて、
「世の中の恨めしく心細き折々も、またかくながらふれば、すこしも思ひ慰めつべき折もあるを、いにしへ頼みきこえける蔭どもに後れたてまつりけるは、なかなかに世の常に思ひなされて、見たてまつり知らずなりにければ、あるを、なほこの御ことは、尽きせずいみじくこそ。大将の、よろづのことに心の移らぬよしを愁へつつ、浅からぬ御心のさまを見るにつけても、いとこそ口惜しけれ」
とのたまへば、
「大将殿は、さばかり世にためしなきまで、帝のかしづき思したなるに、心おごりしたまふらむかし。おはしまさましかば、なほこのこと、せかれしもしたまはざらましや」
など聞こゆ。
「いさや、やうのものと、人笑はれなる心地せましも、なかなかにやあらまし。見果てぬにつけて、心にくくもある世にこそ、と思へど、かの君は、いかなるにかあらむ、あやしきまでもの忘れせず、故宮の御後の世をさへ、思ひやり深く後見ありきたまふめる」
など、心うつくしう語りたまふ。
「かの過ぎにし御代はりに尋ねて見むと、この数ならぬ人をさへなむ、かの弁の尼君にはのたまひける。さもやと、思うたまへ寄るべきことにははべらねど、一本ゆゑにこそはと、かたじけなけれど、あはれになむ思うたまへらるる御心深さなる」
など言ふついでに、この君をもてわづらふこと、泣く泣く語る。 |
母君が中の君の前に出て、匂宮を大げさに誉めるので、中の君は、田舎くさいと思って笑う。
「故北の方の亡くなった時は、中の君があんまり幼かったので、どうなるかと仕えていた人も、故宮も思い嘆いていましたが、この上ない宿世の運がありましたので、あんなに辺鄙な山奥で、お育ちになったのでしょう。口惜しいことに、故大君がお亡くなりになりましたのが、まことに残念でございます」
などと、泣いて話すをする。中の君も泣いて、
「世の中が恨めしく心細い折々にも、こうして命永らえれば、多少なりと気の晴れることもありますが、昔お頼りしていたご両親に先立たれましたことは、かえって世によくあること、と思って、特に母上は顔も知らないでので、やはり姉上のことは、いつまでも悲しいのです。大将(薫)の、どんなことにも心移りせず、いつも嘆いておられるのは、浅からぬ御心の様子を見るにつけ、残念です」
と仰ると、
「大将殿(薫)は、これほど世間に例がないほど、帝に厚遇されているので、奢りの心が生じたのでしょう。大君が存命でしたら、やはり、ご降嫁はありましたかどうか」
などと母君が仰る。
「さあどうでしょう。姉妹とも同じ運命だ、と世間の笑い者になっているかもしないし、どうでしょう。途中で亡くなったので、いつまでも心に残るのでしょうか、思いますに、あの方(薫)、昔のことをよく覚えていまして、故八の宮の来世のことまで、後見としてご心配してますから」
と中の君が仰せになるので、
あの亡くなった大君の身代わりに、引き取って世話をしたい、わたしなどの数にならぬ娘のことさえ、あの弁の尼君には言っていました。そのようには賛同できかねることですが、それも娘が大君のゆかりの者だからこそ、声をかけてくださるのです」
などと言うが、この娘のことを思い悩んで、泣く泣く語るのだった。 |
|
| 50.16 浮舟の母、娘の不運を訴える |
こまかにはあらねど、人も聞きけりと思ふに、少将の思ひあなづりけるさまなどほのめかして、
「命はべらむ限りは、何か、朝夕の慰めぐさにて見過ぐしつべし。うち捨てはべりなむのちは、思はずなるさまに散りぼひはべらむが悲しさに、尼になして、深き山にやし据ゑて、さる方に世の中を思ひ絶えてはべらましなどなむ、思うたまへわびては、思ひ寄りはべる」
など言ふ。
「げに、心苦しき御ありさまにこそはあなれど、何か、人にあなづらるる御ありさまは、かやうになりぬる人のさがにこそ。さりとても、堪へぬわざなりければ、むげにその方に思ひおきてたまへりし身だに、かく心より外にながらふれば、まいていとあるまじき御ことなり。やついたまはむも、いとほしげなる御さまにこそ」
など、いと大人びてのたまへば、母君、いとうれしと思ひたり。ねびにたるさまなれど、よしなからぬさましてきよげなり。いたく肥え過ぎにたるなむ、常陸殿とは見えける。
「故宮の、つらう情けなく思し放ちたりしに、いとど人げなく、人にもあなづられたまふと見たまふれど、かう聞こえさせ御覧ぜらるるにつけてなむ、いにしへの憂さも慰みはべる」
など、年ごろの物語、浮島のあはれなりしことも聞こえ出づ。
「わが身一つのとのみ、言ひ合はする人もなき筑波山のありさまも、かくあきらめきこえさせて、いつも、いとかくてさぶらはまほしく思ひたまへなりはべりぬれど、かしこにはよからぬあやしの者ども、いかにたち騷ぎ求めはべらむ。さすがに心あわたたしく思ひたまへらるる。かかるほどのありさまに身をやつすは、口惜しきものになむはべりけると、身にも思ひ知らるるを、この君は、ただ任せきこえさせて、知りはべらじ」
など、かこちきこえかくれば、「げに、見苦しからでもあらなむ」と見たまふ。 |
詳しくではないが、女房たちも知っていると思って、少将の人を馬鹿にした違約などほのめかして、
「わたしが生きている限りは、朝夕の話し相手やっていけましょう。一人残して先立った後は、不本意に落ちぶれてしまう悲しさに、尼になって、山奥に住まわって、世俗のこととは縁を切って生きてゆく、と思いあぐねてはそんなことも考えます」
などと母君は言う。
「ほんとうにお気の毒な身の上でしょうけれど、何か、人に軽んじられるのは、親のいない者の常ですから、そうは言っても、山住もなかなかできることではないので、父宮がそのように決めたわたしでさえ、こうして思いがけない生活をしています、まして出家などとんでもないです。尼になるのも、とてもいとおしく、美しいですから」
など、分別あり気に言うので、母君はうれしいと思う。母君は年はとっているが、風雅のたしなみもなくはなく小ざっぱりしている。なるほど太り気味で常陸殿の妻の風情である。
「故八の宮が、薄情に見捨てたので、人並みでなく、人にも軽んじられたと思っておりましたが、中の君にこうしてお話しお会いできるにgつけて、昔の憂さも慰められます」
など積年の話、奥州時代のつらかったことなど話すのだった。
「わたしひとりがなぜつらい目に、と思っても話の出来る人もない常陸の国の様子を、縷縷申し上げて、いつもお側にはべらしてもらいたいと思いましたが、あちらには出来の悪い子供らが、母がいないと騒いでいるだろう。さすがに落ち着かない気持ちです。こんな受領風情の妻に身をやつすのは、自分で身にしみて分かりましたので、この姫君(浮舟)は中の君にお任せしようと思いまして、もう構いません」
などと、中の君にお預け申し上げるので、「ほんとうに見苦しくない縁組ができれば」と姫君を見るのだった。 |
|
| 50.17 浮舟の母、薫を見て感嘆す |
容貌も心ざまも、え憎むまじうらうたげなり。もの恥ぢもおどろおどろしからず、さまよう児めいたるものから、かどなからず、近くさぶらふ人びとにも、いとよく隠れてゐたまへり。ものなど言ひたるも、昔の人の御さまに、あやしきまでおぼえたてまつりてぞあるや。かの人形求めたまふ人に見せたてまつらばやと、うち思ひ出でたまふ折しも、
「大将殿参りたまふ」
と、人聞こゆれば、例の、御几帳ひきつくろひて、心づかひす。この客人の母君、
「いで、見たてまつらむ。ほのかに見たてまつりける人の、いみじきものに聞こゆめれど、宮の御ありさまには、え並びたまはじ」
と言へば、御前にさぶらふ人びと、
「いさや、えこそ聞こえ定めね」
と聞こえあへり。
「いかばかりならむ人か、宮をば消ちたてまつらむ」
など言ふほどに、「今ぞ、車より降りたまふなる」と聞くほど、かしかましきまで追ひののしりて、とみにも見えたまはず。待たれたまふほどに、歩み入りたまふさまを見れば、げに、あなめでた、をかしげとも見えずながらぞ、なまめかしうあてにきよげなるや。
すずろに見え苦しう恥づかしくて、額髪などもひきつくろはれて、心恥づかしげに用意多く、際もなきさまぞしたまへる。内裏より参りたまへるなるべし、御前どものけはひあまたして、
「昨夜、后の宮の悩みたまふよし承りて参りたりしかば、宮たちのさぶらひたまはざりしかば、いとほしく見たてまつりて、宮の御代はりに今までさぶらひはべりつる。今朝もいと懈怠して参らせたまへるを、あいなう、御あやまちに推し量りきこえさせてなむ」
と聞こえたまへば、
「げに、おろかならず、思ひやり深き御用意になむ」
とばかりいらへきこえたまふ。宮は内裏にとまりたまひぬるを見おきて、ただならずおはしたるなめり。 |
浮舟の容貌も性格も、とても憎めそうもなく可愛らしい。度を過ぎて恥ずかしがることもなく、よい具合におっとりして、才気がないではなく、仕える女房たちからも、よく隠れている。物を言う様子も、大君によく似ていて、不思議なほどそっくりだった。あの人形を求めた人に見せてやりたいと思う、折も折、
「大将(薫)がお越しになりました」
と呼ばわったので、いつものように、几帳を調えて、気遣いする。客人の母君は、
「さあ、拝見しましょう。ちらりとお姿を見た人が、素晴らしいと言っておられたが、匂宮の風姿には、とても及ばないとも言っていた」
と言えば、御前に仕える女房たちが、
「いいえ、どちらとも決められません」
と言い合うのだった。
「いったいどれほどの人が、匂宮を圧倒できますか」
などと言っていると、「今、車より降りました」と告げている、やかましいほど先払いの声が聞こえて、すぐには現れない。一同待っていると、歩み入る様を見るに、さすが、すばらしく、風情があるようには見えないが、優雅で上品で美しい。
うっかり拝見するのも決まり悪く気おくれして、額髪に思わず手をやっるほど、気がひけるほど慎み深く、この上ないすばらしさでおられる。内裏からの帰りだろう、御前にいた気配が満ちていて、
「昨夜、后の宮(明石の中宮)の具合が悪いとお聞きしているので、御子の宮たちがお側にいらっしゃらないので、おいたわしく思い、匂宮の代わりに今まで付き添っていました。今朝もたいそう遅くなってお見えになったので、失礼ながら、中の君が引き留められたと推測します」
と仰せになるので、
「それはまあ、行き届いたご配慮ですね」
とばかり返事をする。匂宮が内裏に宿直するのを見届けて、思うところがあって来たようです。 |
|
| 50.18 中君、薫に浮舟を勧める |
例の、物語いとなつかしげに聞こえたまふ。事に触れて、ただいにしへの忘れがたく、世の中のもの憂くなりまさるよしを、あらはには言ひなさで、かすめ愁へたまふ。
「さしも、いかでか、世を経て心に離れずのみはあらむ。なほ、浅からず言ひ初めてしことの筋なれば、名残なからじとにや」など、見なしたまへど、人の御けしきはしるきものなれば、見もてゆくままに、あはれなる御心ざまを、岩木ならねば、思ほし知る。
怨みきこえたまふことも多かれば、いとわりなくうち嘆きて、かかる御心をやむる禊をせさせたてまつらまほしく思ほすにやあらむ、かの人形のたまひ出でて、
「いと忍びてこのわたりになむ」
と、ほのめかしきこえたまふを、かれもなべての心地はせず、ゆかしくなりにたれど、うちつけにふと移らむ心地はたせず。
「いでや、その本尊、願ひ満てたまふべくはこそ尊からめ、時々、心やましくは、なかなか山水も濁りぬべく」
とのたまへば、果て果ては、
「うたての御聖心や」
と、ほのかに笑ひたまふも、をかしう聞こゆ。
「いで、さらば、伝へ果てさせたまへかし。この御逃れ言葉こそ、思ひ出づればゆゆしく」
とのたまひても、また涙ぐみぬ。
「見し人の形代ならば身に添へて
恋しき瀬々のなでものにせむ」
と、例の、戯れに言ひなして、紛らはしたまふ。
「みそぎ河瀬々に出ださむなでものを
身に添ふ影と誰れか頼まむ
引く手あまたに、とかや。いとほしくぞはべるや」
とのたまへば、
「つひに寄る瀬は、さらなりや。いとうれたきやうなる水の泡にも争ひはべるかな。かき流さるるなでものは、いで、まことぞかし。いかで慰むべきことぞ」
など言ひつつ、暗うなるもうるさければ、かりそめにものしたる人も、あやしくと思ふらむもつつましきを、
「今宵は、なほ、とく帰りたまひね」
と、こしらへやりたまふ。 |
薫は、いつものように、なつかしそうに話をするのだった。何かにつけて、亡き人を忘れがたく、夫婦仲が気にそまなくなるのを、あからさまには言わずに、それとなく憂えるのであった。
「そんなにまで、どうしていつまでも忘れられないのだろう。深く思っていると初めから言っていたので、すっかり忘れたと思われたくないからか」などと思って見たが、人の気色は現れるものなので、見ているうちに、薫のあわれな心情を、岩木でないので、思い知るのだった。
恨みごとになることも多いので、中の君は困って嘆いて、このような思いを断つ禊をさせたらどうかと思ったからであろうか、あの人形のことを言い出して、
「ごく内々でこちらに来ております」
とちらっと一言言ったので、薫も平気ではおれず、会ってみたいと思ったが、すぐにそちらへ行こうという気にもならない。
「さて、その本尊が、願いを叶えてくだされば尊いのですが、時々、やましい心が生じますので、かえって悟りの境地もおぼつかない」
と仰ると、いまいには、
「困った道心ですこと」
とかすかに笑われるのも、好もしく聞こえる。
「さあ、それでは、先方に伝えてください。この言い逃れが忌々しいことになったのですが」
と仰って、また涙ぐむ。
「亡き大君の形見ならば、そばに置いて
なつかしんで撫物にしよう」
といつものように、戯れに、気を紛らしている。
「禊河の瀬々で洗い流すのなら
一生そばにおいてくださると誰が頼みましょう」
女が大勢いては、浮舟が可哀そう」
と中の君が言えば、
「終の寄る辺は、申すまでもありません。いまいましいことに水の泡のようなわたしです。流される撫物は全くわたしのこと。どうしたらこの思いが晴れるでしょう」
などと言いながらも、暗くなってきて面倒なので、しばらく泊まりき来ている浮舟の母も、不審に思うだろうと気にして、
「今宵は、このまま早くお帰りなさいませ」
とと、ほどよくなだめて帰すのだった。 |
|
| 50.19 浮舟の母、娘に貴人の婿を願う |
「さらば、その客人に、かかる心の願ひ年経ぬるを、うちつけになど、浅う思ひなすまじう、のたまはせ知らせたまひて、はしたなげなるまじうはこそ。いとうひうひしうならひにてはべる身は、何ごともをこがましきまでなむ」
と、語らひきこえおきて出でたまひぬるに、この母君、
「いとめでたく、思ふやうなるさまかな」
とめでて、乳母ゆくりかに思ひよりて、たびたび言ひしことを、あるまじきことに言ひしかど、この御ありさまを見るには、「天の川を渡りても、かかる彦星の光をこそ待ちつけさせめ。わが娘は、なのめならむ人に見せむは惜しげなるさまを、夷めきたる人をのみ見ならひて、少将をかしこきものに思ひける」を、悔しきまで思ひなりにけり。
寄りゐたまへりつる真木柱も茵も、名残匂へる移り香、言へばいとことさらめきたるまでありがたし。時々見たてまつる人だに、たびごとにめできこゆ。
「経などを読みて、功徳のすぐれたることあめるにも、香の香うばしきをやむごとなきことに、仏のたまひおきけるも、ことわりなりや。薬王品などに、取り分きてのたまへる、牛頭栴檀とかや、おどろおどろしきものの名なれど、まづかの殿の近く振る舞ひたまへば、仏はまことしたまひけり、とこそおぼゆれ。幼くおはしけるより、行ひもいみじくしたまひければよ」
など言ふもあり。また、
「前の世こそゆかしき御ありさまなれ」
など、口々めづることどもを、すずろに笑みて聞きゐたり。 |
「では、その客人に、このように長年思い詰めていたことでして、軽い思い付きでなどではないことを、お伝えしていただいて、くれぐれも失礼のないようにしてください。このようなことは初めてのことなので、何をするにも不調法でして」
と語ってお帰りになるのを、母君は、
「何とすばらしい。非の打ち所がない」
と感嘆して、乳母が折に触れてたびたび言っていたことを、あり得ないことと思ったが、この薫の様子を見て、「天の川を渡って、年に一度の彦星を待つ甲斐がある。わが娘は、並みの人に嫁がせるのはもったいない気がして、武骨な人ばかり見ているので、少将ごときを素晴らしいと見てしまう」のを、口惜しく思い出すのだった。
寄りかかっていた真木柱も茵にも、名残りの移り香、あえて言うとわざとらしくなるほどすばらしい。時々見ている女房たちも、その度に賞賛するのだった。
「経などを読めば、功徳のすぐれていることが書いてあるようですが、香の香ばしいのは貴いと、仏も説いておられるが、それも当然のことだ。薬王品などに、特に述べられている、牛頭栴檀と言った、恐ろしい名前ですが、何といってもあの方が近くで振舞えば、仏のお説きになったことは本当だった、と思えます。薫は幼い時から、お勤めもよくなさったから」
などと言う女房もいる。また、
「前世こそ知りたいものです」
などと、口々に愛でるのを、母君は思わずにこにこして聞いていた。 |
|
| 50.20 浮舟の母、中君に娘を託す |
君は、忍びてのたまひつることを、ほのめかしのたまふ。
「思ひ初めつること、執念きまで軽々しからずものしたまふめるを、げに、ただ今のありさまなどを思へば、わづらはしき心地すべけれど、かの世を背きても、など思ひ寄りたまふらむも、同じことに思ひなして、試みたまへかし」
とのたまへば、
「つらき目見せず、人にあなづられじの心にてこそ、鳥の音聞こえざらむ住まひまで思ひたまへおきつれ。げに、人の御ありさまけはひを見たてまつり思ひたまふるは、下仕へのほどなどにても、かかる人の御あたりに、馴れきこえむは、かひありぬべし。まいて若き人は、心つけたてまつりぬべくはべるめれど、数ならぬ身に、もの思ふ種をやいとど蒔かせて見はべらむ。
高きも短きも、女といふものは、かかる筋にてこそ、この世、後の世まで、苦しき身になりはべるなれ、と思ひたまへはべればなむ、いとほしく思ひたまへはべる。それもただ御心になむ。ともかくも、思し捨てず、ものせさせたまへ」
と聞こゆれば、いとわづらはしくなりて、
「いさや。来し方の心深さにうちとけて、行く先のありさまは知りがたきを」
とうち嘆きて、ことに物ものたまはずなりぬ。
明けぬれば、車など率て来て、守の消息など、いと腹立たしげに脅かしたれば、
「かたじけなく、よろづに頼みきこえさせてなむ。なほ、しばし隠させたまひて、巌の中にとも、いかにとも、思ひたまへめぐらしはべるほど、数にはべらずとも、思ほし放たず、何ごとをも教へさせたまへ」
など聞こえおきて、この御方も、いと心細く、ならはぬ心地に、立ち離れむを思へど、今めかしくをかしく見ゆるあたりに、しばしも見馴れたてまつらむと思へば、さすがにうれしくもおぼえけり。 |
中の君は、薫が内々に依頼したことを、それとなく仰る。
「いったん思い染めたことは、しつこくやり続けて軽々しく変えない方なので、なるほど今の境遇を思えば、戸惑うでしょうが、あの尼にしてでもと思い込んだのなら、同じように思い切って、運を試してみてはいかがでしょう」
と中の君が仰れば、
「娘を、つらい目に合わせず、人に馬鹿にされないように、鳥の声も聞こえぬ山奥住まいまで考えてみたのです。ほんとうに薫君のご様子を拝見しまして、あの方の下働きにでもおいてもらって、おそばに仕えるだけで、甲斐あるというものです。まして若い女人は、きっと慕うでしょうが、数ならぬ身では、つらい思いの種をまくようなものになりましょうか。
身分の高い人でも低い者でも、女というものは男女の仲で、この世と言わず来世まで苦しむことになるもの、と思ってしまえば、いとおしい思います。それもあなた様にお任せします。ともかくも、お見捨てることなく世話してやってください」
と申し上げると、中の君は煩わしくなって、
「さあ、今までの心の深さに安心していたのですが、この先は分かりませんから」
と嘆いて、物も言わなくなった。
夜が明けると、車などを率いて来て、守の近況など、腹立たし気に咎めているので、
「恐れながら、、万事よろしくお願いします。娘はもうしばらくかくまってください。尼になるとも、いかようにも、思案を巡らす時には、数にも入らない身ですが、お見捨てなく、教えてやってください」
などと言って、娘の方も、たいそう心細く、初めてのことなので、離れ離れになるのを不安に思うが、はなやかで趣深い所に暮らすのは、しばらく側にいられると思うと、うれしくもあった。 |
|
| 50.21 匂宮、二条院に帰邸 |
車引き出づるほどの、すこし明うなりぬるに、宮、内裏よりまかでたまふ。若君おぼつかなくおぼえたまひければ、忍びたるさまにて、車なども例ならでおはしますにさしあひて、おしとどめて立てたれば、廊に御車寄せて降りたまふ。
「なぞの車ぞ。暗きほどに急ぎ出づるは」
と目とどめさせたまふ。「かやうにてぞ、忍びたる所には出づるかし」と、御心ならひに思し寄るも、むくつけし。
「常陸殿のまかでさせたまふ」
と申す。若やかなる御前ども、
「殿こそ、あざやかなれ」
と、笑ひあへるを聞くも、「げに、こよなの身のほどや」と悲しく思ふ。ただ、この御方のことを思ふゆゑにぞ、おのれも人びとしくならまほしくおぼえける。まして、正身をなほなほしくやつして見むことは、いみじくあたらしう思ひなりぬ。宮、入りたまひて、
「常陸殿といふ人や、ここに通はしたまふ。心ある朝ぼらけに、急ぎ出でつる車副などこそ、ことさらめきて見えつれ」
など、なほ思し疑ひてのたまふ。「聞きにくくかたはらいたし」と思して、
「大輔などが若くてのころ、友達にてありける人は。ことに今めかしうも見えざめるを、ゆゑゆゑしげにものたまひなすかな。人の聞きとがめつべきことをのみ、常にとりないたまふこそ、なき名は立てで」
と、うち背きたまふも、らうたげにをかし。
明くるも知らず大殿籠もりたるに、人びとあまた参りたまへば、寝殿に渡りたまひぬ。后の宮は、ことことしき御悩みにもあらで、おこたりたまひにければ、心地よげにて、右の大殿の君達など、碁打ち韻塞などしつつ遊びたまふ。 |
母君の車を出すころ、少し空が明るくなるころに、匂宮が内裏から帰って来た。若君がどうしているか気にかかっていたので、忍びの様子で、車もいつもと違う車に、ばったり出会って、母君は車を止めて立てていると、宮は廓に車を寄せて降りた。
「誰の車か。暗いうちに急いで出かけるとは」
と目を止めた。「こんなふうにして、女の処からこっそり帰るものだ」と自分の経験から察知するのも困ったものだ。
「常陸殿の北の方がお帰りになります」
と言う。若い前駆の者たちが、
「殿とはご立派なことだ」
と笑い合っているのを聞いて、「ほんとうに何という身分の差だろう」と母君は悲しう。ただ姫君のことだけ思って、自分も人並みの身分になりたいと思う。まして姫君が身分の低い男と結婚させるのは、ひどく惜しいと思った。匂宮が入って、
「常陸殿という人が、来ているのか。風情たっぷりの夜明け方に、急いで出てきた供の者がわけあり気に見えたぞ」
などと疑って言う。「訛りのある供の者たちをどう思うのか」と思って、
「大輔などが、若い頃、友達だった人です。特に今めかしくもないのに、わけあり気に仰るのですね。人が聞き咎めることを、いつも意味ありげに仰る、無実を取り上げて」
と横を向いてしまうのも、かわいらしく風情がある。
宮は、夜が明けるのも知らぬ気にゆっくりお休みになっていると、廷臣たちが大勢やってきたので、寝殿に移った。明石の中宮は大した病気でもなく、元気になって、心地よさそうなので、右大臣の子息たちは、碁を打ったり韻字遊びなどをした。 |
|
| 50.22 匂宮、浮舟に言い寄る |
夕つ方、宮こなたに渡らせたまへれば、女君は、御ゆするのほどなりけり。人びともおのおのうち休みなどして、御前には人もなし。小さき童のあるして、
「折悪しき御ゆするのほどこそ、見苦しかめれ。さうざうしくてや、眺めむ」
と、聞こえたまへば、
「げに、おはしまさぬ隙々にこそ、例は済ませ。あやしう日ごろももの憂がらせたまひて、今日過ぎば、この月は日もなし。九、十月は、いかでかはとて、仕まつらせつるを」
と、大輔いとほしがる。
若君も寝たまへりければ、そなたにこれかれあるほどに、宮はたたずみ歩きたまひて、西の方に例ならぬ童の見えつるを、「今参りたるか」など思して、さし覗きたまふ。中のほどなる障子の、細目に開きたるより見たまへば、障子のあなたに、一尺ばかりひきさけて、屏風立てたり。そのつまに、几帳、簾に添へて立てたり。
帷一重をうちかけて、紫苑色のはなやかなるに、女郎花の織物と見ゆる重なりて、袖口さし出でたり。屏風の一枚たたまれたるより、「心にもあらで見ゆるなめり。今参りの口惜しからぬなめり」と思して、この廂に通ふ障子を、いとみそかに押し開けたまひて、やをら歩み寄りたまふも、人知らず。
こなたの廊の中の壺前栽の、いとをかしう色々に咲き乱れたるに、遣水のわたり、石高きほど、いとをかしければ、端近く添ひ臥して眺むるなりけり。開きたる障子を、今すこし押し開けて、屏風のつまより覗きたまふに、宮とは思ひもかけず、「例こなたに来馴れたる人にやあらむ」と思ひて、起き上がりたる様体、いとをかしう見ゆるに、例の御心は過ぐしたまはで、衣の裾を捉へたまひて、こなたの障子は引き立てたまひて、屏風のはさまに居たまひぬ。
あやしと思ひて、扇をさし隠して見返りたるさま、いとをかし。扇を持たせながら捉へたまひて、
「誰れぞ。名のりこそ、ゆかしけれ」
とのたまふに、むくつけくなりぬ。さるもののつらに、顔を他ざまにもて隠して、いといたう忍びたまへれば、「このただならずほのめかしたまふらむ大将にや、香うばしきけはひなども」思ひわたさるるに、いと恥づかしくせむ方なし。 |
夕方、匂宮がこちらにお越しになった時、中の君は洗髪の最中だった。女房たちもそれぞれに休んでいて、御座所の前には誰もいない。小さい童がいるので使いにやって、
「あいにくの御洗髪とは、困りましたね。することもなくぼんやりしているのかな」
と仰ると
「ほんとうに、おられない暇ひまに、いつもは済ませています。なぜかこの頃は洗髪を億劫がって、今日を過ごせば、今月はいい日がないのです。九、十月はとてもできないので、今日になったのです」
と大輔が困っている。
若君も寝ているので、そちらに何人か女房がお付きしている折、宮はぶらぶらされて、西の方に新参の童の見えるのを、「新参の童か」などと思って、覗いてみる。中ほどの襖が、細目に開いたところから見ると、襖の向こうに、一尺ばかり離して、屏風を立ててあった。その端に几帳が簾に添って立ててある。
帷一枚をかけて、紫苑色はなやかな袿に女郎花の織物を重ねて袖口を差し出している。屏風の一枚がたたんであるので、見るともなしに見えてしまう。新参の女房でかなりの身分の者のようだ」と思って、この廂に通じる襖を、音を立てぬように押し開けて、ゆっくり歩み寄るが、気がつかない。
こちら側の廊の中の壺前裁が、風情があり色とりどりに咲いていて、遣水のあたり、石が高く積んで趣あるので、端近くに横になって眺めていた。開いた襖をもう少し開けて、屏風の端から覗いてみると、宮とは思いもかけず、「いつもこちらに来ている女房だろう」と思っていると、起き上がった姿が、たいそう風情があったので、好色の気性が見逃さず、衣の裾をとらえて、こちら側の襖はもう一方の手で閉めて、屏風の間に座り込んでしまった。
変だと思って、扇をかざして見返る様子が、たいそう美しかった。屏風を持たせたままその手をとらえて、
「誰だ、名前は何という」
と言うと、女は気味悪くなった。宮は屏風の際に、顔をあちらに向けて隠れるようにして、用心して誰か分からぬ様にして、「あのただならず熱心に申し出てくれる大将だろうか、このような香ばしい香りは」と思われるので、とても恥ずかしくてどうしていいか分からない。 |
|
| 50.23 浮舟の乳母、困惑、右近、中君に急報 |
乳母、人げの例ならぬを、あやしと思ひて、あなたなる屏風を押し開けて来たり。
「これは、いかなることにかはべらむ。あやしきわざにもはべる」
など聞こゆれど、憚りたまふべきことにもあらず。かくうちつけなる御しわざなれど、言の葉多かる本性なれば、何やかやとのたまふに、暮れ果てぬれど、
「誰れと聞かざらむほどは許さじ」
とて、なれなれしく臥したまふに、「宮なりけり」と思ひ果つるに、乳母、言はむ方なくあきれてゐたり。
大殿油は灯籠にて、「今渡らせたまひなむ」と人びと言ふなり。御前ならぬ方の御格子どもぞ下ろすなる。こなたは離れたる方にしなして、高き棚厨子一具立て、屏風の袋に入れこめたる、所々に寄せかけ、何かの荒らかなるさまにし放ちたり。かく人のものしたまへばとて、通ふ道の障子一間ばかりぞ開けたるを、右近とて、大輔が娘のさぶらふ来て、格子下ろしてここに寄り来なり。
「あな、暗や。まだ大殿油も参らざりけり。御格子を、苦しきに、急ぎ参りて、闇に惑ふよ」
とて、引き上ぐるに、宮も、「なま苦し」と聞きたまふ。乳母はた、いと苦しと思ひて、ものづつみせずはやりかにおぞき人にて、
「もの聞こえはべらむ。ここに、いとあやしきことのはべるに、見たまへ極じてなむ、え動きはべらでなむ」
「何ごとぞ」
とて、探り寄るに、袿姿なる男の、いと香うばしくて添ひ臥したまへるを、「例のけしからぬ御さま」と思ひ寄りにけり。「女の心合はせたまふまじきこと」と推し量らるれば、
「げに、いと見苦しきことにもはべるかな。右近は、いかにか聞こえさせむ。今参りて、御前にこそは忍びて聞こえさせめ」
とて立つを、あさましくかたはに、誰も誰も思へど、宮は懼ぢたまはず。
「あさましきまであてにをかしき人かな。なほ、何人ならむ。右近が言ひつるけしきも、いとおしなべての今参りにはあらざめり」
心得がたく思されて、と言ひかく言ひ、怨みたまふ。心づきなげにけしきばみてももてなさねど、ただいみじう死ぬばかり思へるがいとほしければ、情けありてこしらへたまふ。
右近、上に、
「しかしかこそおはしませ。いとほしく、いかに思ふらむ」
と聞こゆれば、
「例の、心憂き御さまかな。かの母も、いかにあはあはしく、けしからぬさまに思ひたまはむとすらむ。うしろやすくと、返す返す言ひおきつるものを」
と、いとほしく思せど、「いかが聞こえむ。さぶらふ人びとも、すこし若やかによろしきは、見捨てたまふなく、あやしき人の御癖なれば、いかがは思ひ寄りたまひけむ」とあさましきに、ものも言はれたまはず。 |
乳母が人の気配がするので、あやしいと思って、向こう側の屏風を開いて来た。
「これはどうしたことでしょう。おかしなことでございます」
などと言うが、宮はそんなことで遠慮されるはずもない。その場の出来心のたわむれであるが、口の上手な性分なので、何やかやと言ううちに、日も暮れて来たので、
「名前を聞かないうちは放さない」
とて、くつろいで横になるので、「匂宮なのだ」と合点するが、乳母は言葉もなくあきれていた。
明かりは灯篭にともして、「中の君がこちらにお越しになります」女房たちが言う。御座所以外の格子は下ろすのである。こちらは離れになっていて、高い棚厨子ひとつあるだけで、屏風を袋に入れてしまってあるのを、所々に寄せて、荒れたままに放置してあった。今は客が逗留しているので、通る襖の一間だけ開けているのを、右近といって、大輔の娘がやって来て、格子を下ろしてここに来た。
「あら、暗い。まだ明かりも来てない。格子を下ろすの、大へんなのに、早く明かりが来てくれないと。暗闇に迷います」
と言ってまた格子を上げるので、宮も「少々困った」と聞いている。乳母は、困ったと思って、尻込みせずせっかちで気の強い人だったので、
「申し上げます。ここに、あやしいことがあります。監視もできず困って動けません」
「何ごとですか」
とて、探り寄ると、袿姿の男が、香ばしい香りがして女に寄り添って臥している。「例によって悪い癖が出たのだ」と右近は気づく。「姫君の同意はないのだろう」と推測され、
「ほんとうに困ったことでございます。右近は何と申し上げていいか、今参上して、中の君にこっそり申し上げよう」
と思って立つと、ひどく見苦しいと誰もが思うが、宮は全く気にしない。
「驚くほど上品で美しい人だな。でも、誰だろう。右近の言い方からしても、普通の新参の女房ではなさそうだ」
納得できなく思って、あれこれ言って恨むのだった。嫌がっている素振りもあらわには見せないけれど、ただもう死ぬほどつらいと思っているのがかわいそうなので、やさしく機嫌をとる。
右近は、中の君に、
「これこれでございます。姫君がかわいそう、どんなお気持ちでしょう」
と申し上げれば、
「いつもの悪い癖でしょう。母君がどんなに軽はずみで、不届きなことと思われることでしょう。よろしく頼むと、くれぐれも言いおいて行かれたのに」
と困ったと思ったが、「宮に何と申し上げよう。お側の女房でも、少し若くてそれなりの者は、見逃すことなく、あの人の癖なのだから、それにしてもどうして浮舟に気づいたのだろう」と、あきれて物も言えない。 |
|
| 50.24 宮中から使者が来て、浮舟、危機を脱出 |
「上達部あまた参りたまふ日にて、遊び戯れては、例も、かかる時は遅くも渡りたまへば、皆うちとけてやすみたまふぞかし。さても、いかにすべきことぞ。かの乳母こそ、おぞましかりけれ。つと添ひゐて護りたてまつり、引きもかなぐりたてまつりつべくこそ思ひたりつれ」
と、少将と二人していとほしがるほどに、内裏より人参りて、大宮この夕暮より御胸悩ませたまふを、ただ今いみじく重く悩ませたまふよし申さす。右近、
「心なき折の御悩みかな。聞こえさせむ」
とて立つ。少将、
「いでや、今は、かひなくもあべいことを、をこがましく、あまりな脅かしきこえたまひそ」
と言へば、
「いな、まだしかるべし」
と、忍びてささめき交はすを、上は、「いと聞きにくき人の御本性にこそあめれ。すこし心あらむ人は、わがあたりをさへ疎みぬべかめり」と思す。
参りて、御使の申すよりも、今すこしあわたたしげに申しなせば、動きたまふべきさまにもあらぬ御けしきに、
「誰れか参りたる。例の、おどろおどろしく脅かす」
とのたまはすれば、
「宮の侍に、平重経となむ名のりはべりつる」
と聞こゆ。出でたまはむことのいとわりなく口惜しきに、人目も思されぬに、右近立ち出でて、この御使を西面にてと言問へば、申し次ぎつる人も寄り来て、
「中務宮、参らせたまひぬ。大夫は、ただ今なむ、参りつる道に、御車引き出づる、見はべりつ」
と申せば、「げに、にはかに時々悩みたまふ折々もあるを」と思すに、人の思すらむこともはしたなくなりて、いみじう怨み契りおきて出でたまひぬ。 |
「今日は、上達部が大勢参上する日なので、宮も遊び戯れて、いつものように、こういう時は、遅くお帰りなので、女房たちは皆安心して休んでいました。それにしてもどうしましょう。あの乳母は、気の強い人です。すぐそばに付き添って、手荒く引き離しする権幕でした」
と少将と二人して困っているときに、内裏から使いが来て、明石の中宮がこの夕暮から胸が痛くて、今はひどく具合が悪そうですと申すのだった。 右近が、
「おあいにくの病気ですこと。お伝え申し上げましょう」
と言って、立つ。少将、
「いいえ、もう手遅れではないでしょうか、出過ぎて、脅かすこともないでしょう」
と言えば、
「いえ、まだ大丈夫でしょう」
と二人がひそひそ言っているのを、中の君は、「ほんとうに人聞きの悪いご性格だこと。少し考えのある人なら、わたしまで嫌がるだろう」と思う。
右近が宮の処に行って、使いの言うよりも、もっと急を要するように申し上げると、宮は動きそうもない様子で、
「誰が来たのか。大げさに言って脅しているのではないか」
と宮が言えば、
「中宮職の侍で平重経と言っています」
と申し上げる。宮は、ここを出たくはないので、人目を憚る気持ちもないのので、右近が立ち出でて、この使いを西面に伝えると、取り次ぐ人もこちらに来て、
「中務の宮は参内されました。太夫はたった今、こちらに来る途中で、車を出されているところでした」
と申し上げると、「なるほど、急に具合が悪くなる時もあるから」と思い、人々がどう思うかも気になって、たいそう残念がり約束して出かけた。 |
|
| 50.25 乳母、浮舟を慰める |
恐ろしき夢の覚めたる心地して、汗におし浸して臥したまへり。乳母、うち扇ぎなどして、
「かかる御住まひは、よろづにつけて、つつましう便なかりけり。かくおはしましそめて、さらに、よきことはべらじ。あな、恐ろしや。限りなき人と聞こゆとも、やすからぬ御ありさまは、いとあぢきなかるべし。
よそのさし離れたらむ人にこそ、善しとも悪しともおぼえられたまはめ、人聞きもかたはらいたきこと、と思ひたまへて、降魔の相を出だして、つと見たてまつりつれば、いとむくつけく、下衆下衆しき女と思して、手をいといたくつませたまひつるこそ、直人の懸想だちて、いとをかしくもおぼえはべりつれ。
かの殿には、今日もいみじくいさかひたまひけり。「ただ一所の御上を見扱ひたまふとて、わが子どもをば思し捨てたり、客人のおはするほどの御旅居見苦し」と、荒々しきまでぞ聞こえたまひける。下人さへ聞きいとほしがりけり。
「すべてこの少将の君ぞ、いと愛敬なくおぼえたまふ。この御ことはべらざらましかば、うちうちやすからずむつかしきことは、折々はべりとも、なだらかに、年ごろのままにておはしますべきものを」
など、うち嘆きつつ言ふ。
君は、ただ今はともかくも思ひめぐらされず、ただいみじくはしたなく、見知らぬ目を見つるに添へても、「いかに思すらむ」と思ふに、わびしければ、うつぶし臥して泣きたまふ。いと苦しと見扱ひて、
「何か、かく思す。母おはせぬ人こそ、たづきなう悲しかるべけれ。よそのおぼえは、父なき人はいと口惜しけれど、さがなき継母に憎まれむよりは、これはいとやすし。ともかくもしたてまつりたまひてむ。な思し屈ぜそ。
さりとも、初瀬の観音おはしませば、あはれと思ひきこえたまふらむ。ならはぬ御身に、たびたびしきりて詣でたまふことは、人のかくあなづりざまにのみ思ひきこえたるを、かくもありけり、と思ふばかりの御幸ひおはしませ、とこそ念じはべれ。あが君は、人笑はれにては、やみたまひなむや」
と、世をやすげに言ひゐたり。 |
姫君は、恐ろしい夢が覚めた心地がして、汗びっしょりで臥していた。乳母が、扇であおいだりして、
「このような宿は、何ごとにつけ、気兼ねが多いです。宮が来られたからには、ゆめ、よいことはないでしょう。ああ、恐ろしい。高い身分の方が、安心できない振舞いをされのは、ほんとうに困ったことです。
関係のない他所に離れた人なら、善いとも悪いともどう思ってもらっても構いませんが、これだけは世間に漏れてはいけないと思って、降魔の顔をして睨んでいましたので、気色の悪い下衆の女と思されて、わたしの手を強くつねったのは、下々の者がやる色事のようで、とてもおかしかったと思います。
常陸の邸では、今日は激しい言い争いがあったとか。「ただ一人の娘ばかり世話して、わが子供たちをお構いなしにして、客人(婿の少将)がいるのに外泊は見苦しい」と荒々しい声で叱っている。下人さえ聞いて気の毒に思っている。
「すべてはこの少将のせいだ、ほんとうに憎らしい人だ。少将との縁談がなければ、内々で多少のもめごとが時にはあっても、穏やかに今までのように過ごせたのに」
などと、嘆いている。
姫君は、今はあれこれと考える余裕もなく、ただひどくみじめで、出会ったこともない目に会って、その上、「中の君が何と思うだろう」と思うにつけ、つらく、うつ伏して泣いた。乳母はとてもお気の毒に思って、
「心配されますな。母がいない人なら、頼む人もなく悲しいでしょう。世間から見れば、父なき人は気の毒であるが、意地悪な継母に憎まれるよりは、気楽です。母君が何とかしてくれるでしょう。くよくよなさいますな。
それでも、初瀬の観音がおりますので、情けをかけてくれるでしょう。旅慣れぬ御身が、たびたび詣でるのは、人があなどるように思われるでしょうが、こういうこともあるのだ、と思うばかりの幸運をお祈りしております。あなた様は世間の笑い者で終わってしまうような方ではありません」
と何の心配もなさそうに言った。 |
|
| 50.26 匂宮、宮中へ出向く |
宮は、急ぎて出でたまふなり。内裏近き方にやあらむ、こなたの御門より出でたまへば、もののたまふ御声も聞こゆ。いとあてに限りもなく聞こえて、心ばへある古言などうち誦じたまひて過ぎたまふほど、すずろにわづらはしくおぼゆ。移し馬ども牽き出だして、宿直にさぶらふ人、十人ばかりして参りたまふ。
上、いとほしく、うたて思ふらむとて、知らず顔にて、
「大宮悩みたまふとて参りたまひぬれば、今宵は出でたまはじ。泔ゆするの名残にや、心地も悩ましくて起きゐはべるを、渡りたまへ。つれづれにも思さるらむ」
と聞こえたまへり。
「乱り心地のいと苦しうはべるを、ためらひて」
と、乳母して聞こえたまふ。
「いかなる御心地ぞ」
と、返り訪らひきこえたまへば、
「何心地ともおぼえはべらず、ただいと苦しくはべり」
と聞こえたまへば、少将、右近目まじろきをして、
「かたはらぞいたくおはすらむ」
と言ふも、ただなるよりはいとほし。
「いと口惜しう心苦しきわざかな。大将の心とどめたるさまにのたまふめりしを、いかにあはあはしく思ひ落とさむ。かく乱りがはしくおはする人は、聞きにくく、実ならぬことをもくねり言ひ、またまことにすこし思はずならむことをも、さすがに見許しつべうこそおはすめれ。
この君は、言はで憂しと思はむこと、いと恥づかしげに心深きを、あいなく思ふこと添ひぬる人の上なめり。年ごろ見ず知らざりつる人の上なれど、心ばへ容貌を見れば、え思ひ離るまじう、らうたく心苦しきに、世の中はありがたくむつかしげなるものかな。
わが身のありさまは、飽かぬこと多かる心地すれど、かくものはかなき目も見つべかりける身の、さは、はふれずなりにけるにこそ、げに、めやすきなりけれ。今はただ、この憎き心添ひたまへる人の、なだらかにて思ひ離れなば、さらに何ごとも思ひ入れずなりなむ」
と思ほす。いと多かる御髪なれば、とみにもえ乾しやらず、起きゐたまへるも苦し。白き御衣一襲ばかりにておはする、細やかにてをかしげなり。 |
匂宮は急いで出かけた。こちら側のの方が内裏に近いのだろう、こちらの門から出て行く、宮の話し声が聞こえる。実に上品な声で、趣のある古歌など誦しながら過ぎてゆくの様子は、わけもなく煩わしく聞こえる。移し馬を引き出して、お宿直の人々が、十人ばかり馬に乗って供について、一同出立した。
中の君は、姫君がかわいそう、嫌な気持ちだろうと思い、知らぬ顔で、
「后の宮がご病気ということで参内したので、今宵は戻らないだろう。髪を洗ったせいか気分がすぐれず起きているので、こちらへお出で下さい。退屈でしょう」
と言づける。
「気分がたいそう悪うございまして、おさまりましてから」
と乳母を通して言づける。
「どうなさったのですか」
と折り返し容態をお尋ねになると、
「どこが悪いとも分かりません、ただひどく苦しいのです」
とお返事なさるので、少将、右近は目くばせして、
「姫君がきまり悪く思っていられるでしょうね」
と言うが、普通の場合より気の毒だ。
「ほんとうに残念でいたわしいことだ。大将(薫)がお気に召したように言っていたのに、どんなに軽薄な女と見下げることだろう。このしまりのない人は、聞くに堪えない難癖をつけるが、また多少心外なことでも、自分の日ごろのことがあるから、大目に見るところがある。
一方薫君は、口には出さず嫌なことも、こちらが気がひけるほど思慮深いのに、難儀なことに心配事が増えた妹の身の上だ。長年見ず知らずの妹だが、心ばえや顔立ちを見れば、惹きつけられ、可愛らしくいじらしい、女の一生は生きにくく煩わしいことが多いものだ。
わが身の有様は、十分ではないが、こうしたつまらぬ目に会ってもおかしくなかったが、そう落ちぶれずに過ごして来たので、幸運だったのだ。今はただ、困った恋心を持った人が、何ごともなく諦めてくだされば、思い悩むことはなくなるだろう」
と中の君は思うのだった。髪が多いので、すぐには乾かず、起きているのもつらい。白い衣一襲ばかりでいる。ほっそりして美しい。 |
|
| 50.27 中君、浮舟を慰める |
この君は、まことに心地も悪しくなりにたれど、乳母、
「いとかたはらいたし。事しもあり顔に思すらむを。ただおほどかにて見えたてまつりたまへ。右近の君などには、事のありさま、初めより語りはべらむ」
と、せめてそそのかしたてて、こなたの障子のもとにて、
「右近の君にもの聞こえさせむ」
と言へば、立ちて出でたれば、
「いとあやしくはべりつることの名残に、身も熱うなりたまひて、まめやかに苦しげに見えさせたまふを、いとほしく見はべる。御前にて慰めきこえさせたまへ、とてなむ。過ちもおはせぬ身を、いとつつましげに思ほしわびためるも、いささかにても世を知りたまへる人こそあれ、いかでかはと、ことわりに、いとほしく見たてまつる」
とて、引き起こして参らせたてまつる。
我にもあらず、人の思ふらむことも恥づかしけれど、いとやはらかにおほどき過ぎたまへる君にて、押し出でられて居たまへり。額髪などの、いたう濡れたる、もて隠して、灯火の方に背きたまへるさま、上をたぐひなく見たてまつるに、け劣るとも見えず、あてにをかし。
「これに思しつきなば、めざましげなることはありなむかし。いとかからぬをだに、めづらしき人、をかしうしたまふ御心を」
と、二人ばかりぞ、御前にてえ恥ぢたまはねば、見ゐたりける。物語いとなつかしくしたまひて、
「例ならずつつましき所など、な思ひなしたまひそ。故姫君のおはせずなりにしのち、忘るる世なくいみじく、身も恨めしく、たぐひなき心地して過ぐすに、いとよく思ひよそへられたまふ御さまを見れば、慰む心地してあはれになむ。思ふ人もなき身に、昔の御心ざしのやうに思ほさば、いとうれしくなむ」
など語らひたまへど、いとものつつましくて、また鄙びたる心に、いらへきこえむこともなくて、
「年ごろ、いと遥かにのみ思ひきこえさせしに、かう見たてまつりはべるは、何ごとも慰む心地しはべりてなむ」
とばかり、いと若びたる声にて言ふ。 |
姫君は、ほんとうに気分が悪くなって、乳母は、
「ほんとうにお気の毒なこと。 何かあったと顔に表れています。ただ何ごともなかったようにしていなさい。右近の君が、事の有様を、初めから語ってくれましょう」
と無理やり勧めて、こちらの襖の処で、
「右近の君に申し上げます」
と言えば、右近が来たので、
「ほんとうにおかしなことがあったせいで、熱も出たりして、真実苦しそうにしておりますので、かわいそうでございます。中の君の御前に出て、慰めていただけるように思いまして。何の間違いもない身なのに、肩身が狭いように悩んでいるので、男女の仲を知っている人ならともかく、平気ではいらっしゃれまいと、気の毒に思います」
と言って、姫を起こして御前に行かせる。
姫君は正体もなく、人がどう見ているか恥ずかしかったが、ごく素直でおっとりした性格なので、乳母に押し出されたままでいた。額髪などが、涙で濡れているのを、扇で隠し、灯火に背を向けている、女房たちは中の君を類なく美しい方と見ていたが、劣らず、上品で美しい。
「匂宮が、この姫にご執心になったら、大へんなことになるだろう。これほどに美人でなくても、新参の女房にも興味を持たれる性格なので」
と二人には、姫が御前では恥ずかしがる素振りをしないので、よく見えた。中の君は、世間話をやさしくされて、
「馴れない気づまりな所と思わないでください。故大君が亡くなってからは、忘れる時はなく悲しく、この身も恨めしく、類なく不幸な気持ちで過ごしてきましたが、よく似ておられる様を見れば、慰む心地がします。思ってくれる人もないこの身ですが、亡き姉同様に思ってくだされば、大へんうれしいです」
などと中の君が語ってくれるので、姫は物怖じして、また田舎育ちで、気の利いた返事ができず、
「長年お近づきできないお方と思っておりましたが、こうしてお会いでて、何もかも満たさるる心地がします」
とだけ、たいそう若い声で言う。 |
|
| 50.28 浮舟と中君、物語絵を見ながら語らう |
絵など取り出でさせて、右近に詞読ませて見たまふに、向ひてもの恥ぢもえしあへたまはず、心に入れて見たまへる灯火影、さらにここと見ゆる所なく、こまかにをかしげなり。額つき、まみの薫りたる心地して、いとおほどかなるあてさは、ただそれとのみ思ひ出でらるれば、絵はことに目もとどめたまはで、
「いとあはれなる人の容貌かな。いかでかうしもありけるにかあらむ。故宮にいとよく似たてまつりたるなめりかし。故姫君は、宮の御方ざまに、我は母上に似たてまつりたるとこそは、古人ども言ふなりしか。げに、似たる人はいみじきものなりけり」
と思し比ぶるに、涙ぐみて見たまふ。
「かれは、限りなくあてに気高きものから、なつかしうなよよかに、かたはなるまで、なよなよとたわみたるさまのしたまへりしにこそ。
これは、またもてなしのうひうひしげに、よろづのことをつつましうのみ思ひたるけにや、見所多かるなまめかしさぞ劣りたる。ゆゑゆゑしきけはひだにもてつけたらば、大将の見たまはむにも、さらにかたはなるまじ」
など、このかみ心に思ひ扱はれたまふ。
物語などしたまひて、暁方になりてぞ寝たまふ。かたはらに臥せたまひて、故宮の御ことども、年ごろおはせし御ありさまなど、まほならねど語りたまふ。いとゆかしう、見たてまつらずなりにけるを、「いと口惜しう悲し」と思ひたり。昨夜の心知りの人びとは、
「いかなりつらむな。いとらうたげなる御さまを。いみじう思すとも、甲斐あるべきことかは。いとほし」
と言へば、右近ぞ、
「さも、あらじ。かの御乳母の、ひき据ゑてすずろに語り愁へしけしき、 もて離れてぞ言ひし。宮も、逢ひても逢はぬやうなる心ばへにこそ、うちうそぶき口ずさびたまひしか」
「いさや。ことさらにもやあらむ。そは、知らずかし」
「昨夜の火影のいとおほどかなりしも、事あり顔には見えたまはざりしを」
など、うちささめきていとほしがる。 |
絵物語を取り出させて、右近に詞書を読ませながら見るに、姫は向かい合って恥じらう様子もなく、一心に見入っている火影の姿は、どこといって欠点はなく、目鼻立ちが整って美しい。額のあたりや目元が匂うような心地がして、まことにおっとりした上品な感じは、ただ姉君にそっくりなので、絵は上の空で、
「ほんとうになつかしい人の顔立ちだ。どうしてこうまで似るのだろう。故父宮によく似ている。亡き大君は、父の方に、わたしは母上に似ていると、古い女房たちは言っていた。ほんとうに似ているというのは、なつかしいものだ」
と思い出して、涙ぐんでご覧になる。
亡き大君は、この上なく高貴で上品な感じから、あたたかく人を引き付ける柔らかく、度が過ぎるくらい、ものやさしい感じでいらっしゃった。
この姫君は、物越しがいかにも人馴れせず、何ごとにも気おくれしているせいか、見栄えのする優雅さという点では劣っているが、もう少し重々しい感じが身につけば、大将(薫)の相手をしても、決しておかしくない」
などと、いつのまにか姉ぶった思いで考えるのだった。
お二人はあれこれ話をして、明け方に寝た。側に臥せって、故父宮のことや、生前のあれこれの様子など、ぽつりぽつりと話をする。とても会いたい。お会いできなかったのが、「残念で悲しい」と思った。昨夜のいきさつを知っている女房たちは、
「どうだったのでしょう。とても可愛らしいですが、中の君が大事になさろうと、甲斐がないでしょう。お気の毒に」
と言えば、右近は、
「そうではありません。あの乳母殿がわたしを掴まえて、とりとめもなく嘆いていましたが、何もなかったと言っていました。宮も逢って逢わないような歌を口ずさんでいましたし」
「そうね。わざと言ったのかも知れないし。それは分かりません」
「昨夜の火影でおっとりした様子でも、何かあったようには見えなかった」
など、ひそひそ言って気の毒がる。 |
|
| 50.29 乳母の急報に浮舟の母、動転す |
乳母、車請ひて、常陸殿へ往住ぬ。北の方にかうかうと言へば、胸つぶれ騷ぎて、「人もけしからぬさまに言ひ思ふらむ。正身もいかが思すべき。かかる筋のもの憎みは、貴人もなきものなり」と、おのが心ならひに、あわたたしく思ひなりて、夕つ方参りぬ。
宮おはしまさねば心やすくて、
「あやしく心幼げなる人を参らせおきて、うしろやすくは頼みきこえさせながら、鼬鼬のはべらむやうなる心地のしはべれば、よからぬものどもに、憎み恨みられはべる」
と聞こゆ。
「いとさ言ふばかりの幼さにはあらざめるを。うしろめたげにけしきばみたる御まかげこそ、わづらはしけれ」
とて笑ひたまへるが、心恥づかしげなる御まみを見るも、心の鬼に恥づかしくぞおぼゆる。「いかに思すらむ」と思へば、えもうち出で聞こえず。
「かくてさぶらひたまはば、年ごろの願ひの満つ心地して、人の漏り聞きはべらむもめやすく、おもだたしきことになむ思ひたまふるを、さすがにつつましきことになむはべりける。深き山の本意は、みさをになむはべるべきを」
とて、うち泣くもいといとほしくて、
「ここには、何事かうしろめたくおぼえたまふべき。とてもかくても、疎々しく思ひ放ちきこえばこそあらめ、けしからずだちてよからぬ人の、時々ものしたまふめれど、その心を皆人見知りためれば、心づかひして、便なうはもてなしきこえじと思ふを、いかに推し量りたまふにか」
とのたまふ。
「さらに、御心をば隔てありても思ひきこえさせはべらず。かたはらいたう許しなかりし筋は、何にかかけても聞こえさせはべらむ。その方ならで、思ほし放つまじき綱もはべるをなむ、とらへ所に頼みきこえさする」
など、おろかならず聞こえて、
「明日明後日、かたき物忌にはべるを、おほぞうならぬ所にて過ぐして、またも参らせはべらむ」
と聞こえて、いざなふ。「いとほしく本意なきわざかな」と思せど、えとどめたまはず。あさましうかたはなることに驚き騷ぎたれば、をさをさものも聞こえで出でぬ。 |
乳母、車の手配を頼んで、常陸殿へ帰った。北の方にこれこれと言えば、北の方は仰天して、「女房たちも怪しからんことと噂するだろう。中の君は何と思っているか。こうした筋の焼もちは貴人も何もないだろう」と、自分の経験から思って、じっとしていられず、夕方参上した。
匂宮がいないので、ほっとして、
「子供っぽい娘をお預けして、一安心と思いましたが、鼬のように疑心が生じまして、一方では、ろくでもない家の者たちに憎まれるし恨まれております」
と母君は申し上げる。
「それほど、幼くはありませんよ。心配そうに気色ばんで疑うことこそ、気になりますこと」
と中の君は笑うが、気がひけるような目元を見るにつけ、内心気が咎める。「中の君が何と思っているか」と思えば、昨夜のことは言い出せない。
「こうして娘をおそばに置いていただけるのは、長年の願いが叶った気持ちがして、人が聞いても体裁よく、晴れがましいと思いますが、そうは申しても慎むべきことでした。出家の本願は、変わりようもないはずのものでして」
と言って泣くのも気の毒で、
「ここには、何か心配なことがおありでしょうか。いずれにしても、わたしが放置してお構いせずにいるのならともかく、振舞いのよくない人が、時々お見えになりますので、そんな事情を女房たちも知っていますので、不都合な扱いはいたさぬつもりですが、どんなものでしょう」
と中の君は言う。
「決して御厚情に隔てがあるとは思いません。恥ずかしながら父宮に認知されなかったことは、何で愚痴を言えましょう。その方面ではなく、お見捨てになれない絆がありますので、それを頼りに申しています」
などと精一杯申し上げて、
「明日明後日、厳に守るべき物忌みがありますので、きちんと籠れるところで過ごして、また参りましょう」
と言って連れて行く。「かわいそうな。不本意なことよ」と思うが、引き留めない。母君は考えもしなかった不祥事に動転していたので、ろくに挨拶もされずに退去した。 |
|
| 50.30 浮舟の母、娘を三条の隠れ家に移す |
かやうの方違へ所と思ひて、小さき家まうけたりけり。三条わたりに、さればみたるが、まだ造りさしたる所なれば、はかばかしきしつらひもせでなむありける。
「あはれ、この御身一つを、よろづにもて悩みきこゆるかな。心にかなはぬ世には、あり経まじきものにこそありけれ。みづからばかりは、ただひたぶるに品々しからず人げなう、たださる方にはひ籠もりて過ぐしつべし。このゆかりは、心憂しと思ひきこえしあたりを、睦びきこゆるに、便なきことも出で来なば、いと人笑へなるべし。あぢきなし。ことやうなりとも、ここを人にも知らせず、忍びておはせよ。おのづからともかくも仕うまつりてむ」
と言ひおきて、みづからは帰りなむとす。君は、うち泣きて、「世にあらむこと所狭げなる身」と、思ひ屈したまへるさま、いとあはれなり。親はた、ましてあたらしく惜しければ、つつがなくて思ふごと見なさむと思ひ、さるかたはらいたきことにつけて、人にもあはあはしく思はれむが、やすからぬなりけり。
心地なくなどはあらぬ人の、なま腹立ちやすく、思ひのままにぞすこしありける。かの家にも隠ろへては据ゑたりぬべけれど、しか隠ろへたらむをいとほしと思ひて、かく扱ふに、年ごろかたはら去らず、明け暮れ見ならひて、かたみに心細くわりなしと思へり。
「ここは、またかくあばれて、危ふげなる所なめり。さる心したまへ。曹司曹司にある物ども、召し出でて使ひたまへ。宿直人のことなど言ひおきてはべるも、いとうしろめたけれど、かしこに腹立ち恨みらるるが、いと苦しければ」
と、うち泣きて帰る。 |
こういう場合の方違えのためにと思って、家を用意していた。三条のあたりに、しゃれたいて、まだ造りかけなので、十分な設備も用意していなかった。
「ああ、あなたの身一つをうまく世話できない。ままならぬ憂き世には、とても生きて行けるものではありません。自分ひとりの身なら、身分が低く人数に入らなくても、それなりに埋もれて世を過ごしましょう。この親戚筋は、ひどい扱いだったが、当方からお近づきして、不都合なことが生じたら、世間の物笑いになるでしょう。つまらないことだ。粗末な家でも、人に知らせず、ひっそり暮らしなさい。そのうちうまくいくようにしますから」
と言い置いて、母君は帰ろうとする。姫は泣いて、「生きているのも肩身の狭い身の上」と、気がふさいでいる様は、あわれであった。母親としては、いっそう惜しい気がして、何の支障もなく望み通り縁組させたい、あんな体裁の悪いことが起こったにつけても、人に軽々しく思われるのではないかと気が気でなかった。
母君は物分かりの悪い人ではなく、怒りっぽく、少し我儘なところがあった。常陸邸でも、人目につかずに住まわせることはできたが、隅っこに住まわせるのはかわいそうに思って、苦労するのだが、長年二人一緒に生活していたので、互いに心細く仕方ないと思っている。
「この家はまだ粗造りで、不用心のところがある。気をつけてください。部屋部屋にある道具類は取り寄せて使ってください。宿直人にもよく言い付けてありますが、それでも心配だから、常陸の邸で怒って恨まれるのが、困るので」
と、泣いて帰るのだった。 |
|
| 50.31 母、左近少将と和歌を贈答す |
少将の扱ひを、守は、またなきものに思ひ急ぎて、「もろ心に、さま悪しく、営まず」と怨ずるなりけり。「いと心憂く、この人により、かかる紛れどももあるぞかし」と、またなく思ふ方のことのかかれば、つらく心憂くて、をさをさ見入れず。
かの宮の御前にて、いと人げなく見えしに、多く思ひ落としてければ、「私ものに思ひかしづかましを」など、思ひしことはやみにたり。「ここにては、いかが見ゆらむ。まだうちとけたるさま見ぬに」と思ひて、のどかにゐたまへる昼つ方、こなたに渡りて、ものより覗く。
白き綾のなつかしげなるに、今様色の擣目などもきよらなるを着て、端の方に前栽見るとて居たるは、「いづこかは劣る。いときよげなめるは」と見ゆ。娘、まだ片なりに、何心もなきさまにて添ひ臥したり。宮の上の並びておはせし御さまどもの思ひ出づれば、「口惜しのさまどもや」と見ゆ。
前なる御達にものなど言ひ戯れて、うちとけたるは、いと見しやうに、匂ひなく人悪ろげにて見えぬを、「かの宮なりしは、異少将なりけり」と思ふ折しも、言ふことよ。
「兵部卿宮の萩の、なほことにおもしろくもあるかな。いかで、さる種ありけむ。同じ枝さしなどのいと艶なるこそ。一日参りて、出でたまふほどなりしかば、え折らずなりにき。『ことだに惜しき』と、宮のうち誦じたまへりしを、若き人たちに見せたらましかば」
とて、我も歌詠みゐたり。
「いでや。心ばせのほどを思へば、人ともおぼえず、出で消えはいとこよなかりけるに。何ごと言ひたるぞ」
とつぶやかるれど、いと心地なげなるさまは、さすがにしたらねば、いかが言ふとて、試みに、
「しめ結ひし小萩が上も迷はぬに
いかなる露に映る下葉ぞ」
とあるに、惜しくおぼえて、
「宮城野の小萩がもとと知らませば
露も心を分かずぞあらまし
いかでみづから聞こえさせあきらめむ」
と言ひたり。 |
少将の扱いを、常陸介はこの上なく大事に考えて支度をし、面目ないことに、母親が一緒になってやろうとしない」と恨むのだった。「ほんとうに情けない。この少将のせいで、こんな錯綜したことが起こったのだ」と、大事な娘がこんなことになって、嫌な人だ、と婿の世話もしない。
「匂宮の御前では、まことに貧相に見えたので、軽く見る気持ちになり、秘蔵の婿にして世話しよう」などの思いは消し飛んだ。「この邸ではどんなにふうにしているのだろう。まだうちとけた姿は見ていないが」と思って、のんびりした昼頃、少将の所に行って、物陰から覗いた。
白い綾の着馴れた下着に、今様色の艶のある美しい袿を着て、端の方で前裁を見ていたのは、「どこが劣っていよう。美しい」と見る。娘はまだ幼げな姿で、何心なく少将のそばで臥している。匂宮と中の君がより添った姿を思い出すが、「お話にもならない様子だ」と見るのだった。
少将が、控えている女房に冗談を言って、くつろいだ様子は、前に見た宮の御前の見栄えのしない男のようには見えず、「あの時の男は別の少将だったのか」と思った折も折、言うのだった。
「兵部卿宮(匂宮)の萩はとても美しかったなあ。どうやって、あの種を得たのだろう。同じ萩とはいえ枝ぶりがほんとうに趣がありました。ッ先日参上して、出かけるところだったので、折取れなかった。『ことだに惜しき』と、宮が誦したのを、若い女房たちに見せてあげたかった」
と言って、自分でも歌を詠んだ。
「いやいや、この男の根性を思えば、人並みとも思えず、見劣りがするのはひどいものだ。何と詠むのか」
とつい文句が出るが、さすがに無風流な様子はしないけれど、何と詠むか、試しに、
「標結いして囲った小萩の上葉は迷っていないのに
下葉の色が変わったのはどんな露のせいでしょうか」
と母君が詠ったのを、気の毒に思って、
「宮様の娘と知っていれば
決して心を他に分かつことはなかった
直接申しひらきがしたい。」
と少将は答えた。 |
|
| 50.32 母、薫のことを思う |
「故宮の御こと聞きたるなめり」と思ふに、「いとどいかで人と等しく」とのみ思ひ扱はる。あいなう、大将殿の御さま容貌ぞ、恋しう面影に見ゆる。同じうめでたしと見たてまつりしかど、宮は思ひ離れたまひて、心もとまらず。あなづりて押し入りたまへりけるを、思ふもねたし。
「この君は、さすがに尋ね思す心ばへのありながら、うちつけにも言ひかけたまはず、つれなし顔なるしもこそいたけれ、よろづにつけて思ひ出でらるれば、若き人は、まして、かくや思ひはてきこえたまふらむ。わがものにせむと、かく憎き人を思ひけむこそ、見苦しきことなべかりけれ」
など、ただ心にかかりて、眺めのみせられて、とてやかくてやと、よろづによからむあらまし事を思ひ続くるに、いと難し。
「やむごとなき御身のほど、御もてなし、見たてまつりたまへらむ人は、今すこしなのめならず、いかばかりにてかは心をとどめたまはむ。世の人のありさまを見聞くに、劣りまさり、いやしうあてなる、品に従ひて、容貌も心もあるべきものなりけり。
わが子どもを見るに、この君に似るべきやはある。少将を、この家のうちにまたなき者に思へども、宮に見比べたてまつりしは、いとも口惜しかりしに推し量らる。当帝の御かしづき女を得たてまつりたまへらむ人の御目移しには、いともいとも恥づかしく、つつましかるべきものかな」
と思ふに、すずろに心地もあくがれにけり。 |
「故八の宮の子と聞いているのだ」と思うと、「いよいよ人並みな縁につけたい」とのみ思うのだった。大それたことながら大将殿(薫)のお顔立ちが、恋しく思い浮かぶ。同じく素晴らしいと見るが、匂宮の方は問題にもしない。宮が、あなどって押し入ってきたのを思い、無念だった。
「この君(薫)は、さすがに言い寄ろうとする気持ちはありながら、だしぬけに言葉をかけることもなく、何気なく平静をよそおっているのは大したもので、年若い浮舟などは、ましてこんなふうに思って慕うことだろう。わが婿にしようと、こんな憎い田舎者を考えたのは、見苦しいことだった」
などと、浮舟のことのみ心配で、物思いにふけって、あれこれと、さまざまによかれと思う夢を思い続けているが、実現はとても難しい。
「薫様は高貴な生まれで、風采所作も素晴らしく、妻に迎えた人は、とても並みの人ではない。薫がどうして娘に心を留めたのか、世の人の話では、人の優劣、貴賤は、すべて身分によって、顔立ちも人柄も決まってくるものだ。
自分の子供たちを見ても、浮舟に似たものがいるだろうか。少将を、この常陸の介の家ではまたとない者に思っているが、匂宮に比べたらもうお話にならない。帝の秘蔵の娘を妻に迎えたような人の目から見ると、とても気がひけて、身の縮む思いがする」
と思うと、わけもなく憧れるのだった。 |
|
| 50.33 浮舟の三条のわび住まい |
旅の宿りは、つれづれにて、庭の草もいぶせき心地するに、いやしき東声したる者どもばかりのみ出で入り、慰めに見るべき前栽の花もなし。うちあばれて、晴れ晴れしからで明かし暮らすに、宮の上の御ありさま思ひ出づるに、若い心地に恋しかりけり。あやにくだちたまへりし人の御けはひも、さすがに思ひ出でられて、
「何事にかありけむ。いと多くあはれげにのたまひしかな」
名残をかしかりし御移り香も、まだ残りたる心地して、恐ろしかりしも思ひ出でらる。
「母君、たつやと、いとあはれなる文を書きておこせたまふ。おろかならず心苦しう思ひ扱ひたまふめるに、かひなうもて扱はれたてまつること」とうち泣かれて、
「いかにつれづれに見ならはぬ心地したまふらむ。しばし忍び過ぐしたまへ」
とある返り事に、
「つれづれは何か。心やすくてなむ。
ひたぶるにうれしからまし世の中に
あらぬ所と思はましかば」
と、幼げに言ひたるを見るままに、ほろほろとうち泣きて、「かう惑はしはふるるやうにもてなすこと」と、いみじければ、
「憂き世にはあらぬ所を求めても
君が盛りを見るよしもがな」
と、なほなほしきことどもを言ひ交はしてなむ、心のべける。 |
仮の宿は、何をすることもなく、庭の草もうっとうしく、卑しい東国訛りの者たちばかり出入りして、心を慰めとなる前裁の花もない。この邸は一体に未完成で気分も晴れず暮らしているうちに、中の君の様子を思い出し、若い娘心に恋しかった。嫌な振舞いをしたあの人の気配もさすがに思い出されて、
「何と仰っていたのだろう。いろいろとやさし気に言っておられた」
名残り惜しい移り香もまだ残っている心地がして、怖かった記憶もよみがえった。
「母君がたいそう情のこもった文を書いて寄こした。母が一方ならず不憫と思って、心配されているのに、お世話していただく甲斐もない」と姫君は泣いて、
「そんな所でどんなに退屈で落ち着かぬ気持がなさることでしょう。しばし辛抱してください」
と書かれた母の文の返事に、
「退屈などととんでもない。かえって気楽です。
どんなにうれしいことでしょうこの憂き世とは
別の世界にいると思えば」
と子供っぽく詠んでいるのを見ると、ほろほろ泣いて、「こうして娘を世に投げ出すようにしてしまった」のを、悲しく思い、
「この世の外を求めてでも
あなたの盛りを見たいものです」
と、思ったままのことを言い交わして心を慰めるのだった。 |
|
| 50.34 薫、宇治の御堂を見に出かける |
かの大将殿は、例の、秋深くなりゆくころ、ならひにしことなれば、寝覚め寝覚めにもの忘れせず、あはれにのみおぼえたまひければ、「宇治の御堂造り果てつ」と聞きたまふに、みづからおはしましたり。
久しう見たまはざりつるに、山の紅葉もめづらしうおぼゆ。こぼちし寝殿、こたみはいと晴れ晴れしう造りなしたり。昔いとことそぎて、聖だちたまへりし住まひを思ひ出づるに、この宮も恋しうおぼえたまひて、さま変へてけるも、口惜しきまで、常よりも眺めたまふ。
もとありし御しつらひは、いと尊げにて、今片つ方を女しくこまやかになど、一方ならざりしを、網代屏風何かのあらあらしきなどは、かの御堂の僧坊の具に、ことさらになさせたまへり。山里めきたる具どもを、ことさらにせさせたまひて、いたうもことそがず、いときよげにゆゑゆゑしくしつらはれたり。
遣水のほとりなる岩に居たまひて、
「絶え果てぬ清水になどか亡き人の
面影をだにとどめざりけむ」
涙を拭ひて、弁の尼君の方に立ち寄りたまへれば、いと悲しと見たてまつるに、ただひそみにひそむ。長押にかりそめに居たまひて、簾のつま引き上げて、物語したまふ。几帳に隠ろへて居たり。ことのついでに、
「かの人は、さいつころ宮にと聞きしを、さすがにうひうひしくおぼえてこそ、訪れ寄らね。なほ、これより伝へ果てたまへ」
とのたまへば、
「一日、かの母君の文はべりき。忌違ふとて、ここかしこになむあくがれたまふめる。このころも、あやしき小家に隠ろへものしたまふめるも心苦しく、すこし近きほどならましかば、そこにも渡して心やすかるべきを、荒ましき山道に、たはやすくもえ思ひ立たでなむ、とはべりし」
と聞こゆ。
「人びとのかく恐ろしくすめる道に、まろこそ古りがたく分け来れ。何ばかりの契りにかと思ふは、あはれになむ」
とて、例の、涙ぐみたまへり。
「さらば、その心やすからむ所に、消息したまへ。みづからやは、かしこに出でたまはぬ」
とのたまへば、
「仰せ言を伝へはべらむことはやすし。今さらに京を見はべらむことはもの憂くて、宮にだにえ参らぬを」
と聞こゆ。 |
薫は、例によって、秋が深まると、いつものことだが、寝覚め寝覚めに大君を忘れず、悲しく思い出しているので、「宇治の御堂ができた」と聞くと、自ら出かけた。
久しく行っていないので、山の紅葉もめづらしく感じた。解体した寝殿は、今度のは晴れやかに造っている。昔はたいそう簡素に、修行僧のように暮らしていたの思い出すと、亡き八の宮も恋しく覚えて、すっかり模様替えをしてしまったのも、残念に思って、物思いに沈んでいた。
元あった飾りつけは、まことに尊い感じがして、もう一方を姫君たちの女らしい造りにして、趣を変えて、網代屏風などの粗末な調度類は御堂の僧房用具に、供養のためにことさらに具した。山里めいた調度類は、寝殿のために新たに造らせて、さほど簡略にせず、こざっぱりした奥ゆかしい設備にしている。
遣水のそばの岩に腰かけて、
昔から絶えることのないこの清水に亡き人は
面影だけでもとどめておいてくださらなかったのか」
涙をぬぐって、弁の尼君の方に立ち寄ると、ほんとうに悲しいと思い、今にも泣きそうな顔をしている。弁尼は長押に腰を下ろして、簾の端を引き上げて話をする。几帳の陰に隠れていたのだった。話のついでに、
「例の姫君は、先ごろ宮様のお邸にいると聞きましたが、どうも踏み切れないで文も出していません。やはりあなた様からお伝えください」
と言うと、
「先日、母君から文がありました。方違えするため、あちこちに住いを変えているようです。このころは、粗末な小屋に隠れているのも気の毒なことで、宇治がもっと近くなら、そちらに行って安心したいのだが、荒々しい山道なので、容易に決心できかねます、と言っていました」
と弁が言う。
「人々が怖がる道を、わたしは昔を忘れず分け入って来るのです。どんな宿世の因縁でしょうか、感無量です」
と言って薫はまた涙ぐむのだった。
「では、その隠れ家に文を遣ってください。あなた自身はその家に出向くつもりはないか」
と薫が言うと、
「仰せごとを取り継ぐのはたやすいです。今さら京を見るのは億劫で、匂宮にもお伺いしてませんのに」
と弁は言う。 |
|
| 50.35 薫、弁の尼に依頼して出る |
などてか。ともかくも、人の聞き伝へばこそあらめ、愛宕の聖だに、時に従ひては出でずやはありける。深き契りを破りて、人の願ひを満てたまはむこそ尊からめ」
とのたまへば、
「人渡すこともはべらぬに、聞きにくきこともこそ、出でまうで来れ」
と、苦しげに思ひたれど、
「なほ、よき折なるを」
と、例ならずしひて、
「明後日ばかり、車たてまつらむ。その旅の所尋ねおきたまへ。ゆめをこがましうひがわざすまじきを」
と、ほほ笑みてのたまへば、わづらはしく、「いかに思すことならむ」と思へど、「奥なくあはあはしからぬ御心ざまなれば、おのづからわが御ためにも、人聞きなどは包みたまふらむ」と思ひて、
「さらば、承りぬ。近きほどにこそ。御文などを見せさせたまへかし。ふりはへさかしらめきて、心しらひのやうに思はれはべらむも、今さらに伊賀専女にや、と慎ましくてなむ」
と聞こゆ。
「文は、やすかるべきを、人のもの言ひ、いとうたてあるものなれば、右大将は、常陸守の娘をなむよばふなるなども、とりなしてむをや。その守の主、いと荒々しげなめり」
とのたまへば、うち笑ひて、いとほしと思ふ。
暗うなれば出でたまふ。下草のをかしき花ども、紅葉など折らせたまひて、宮に御覧ぜさせたまふ。甲斐なからずおはしぬべけれど、かしこまり置きたるさまにて、いたうも馴れきこえたまはずぞあめる。内裏より、ただの親めきて、入道の宮にも聞こえたまへば、いとやむごとなき方は、限りなく思ひきこえたまへり。こなたかなたと、かしづききこえたまふ宮仕ひに添へて、むつかしき私の心の添ひたるも、苦しかりけり。 |
「何構うまい。あれこれ人が取り沙汰するのならともかく、愛宕山の聖でさえ場合によっては山を出るでしょう。山籠りの深い誓いを破って凡人の願いを叶えてくれるのが尊いのです」
と薫が言うと、
「衆生済度の徳もないのに、聞き苦しい噂も立ちましょう」
と弁の尼君が言えば、困ったことと思ったが、
「好い機会だから行ってください」
と薫はいつになく無理押しして、
「明後日ほどに、車を差し向けましょう。その仮の住まいの場所を確かめておいてください。わたしは決して馬鹿げたことはしませんから」
と含み笑いして言うので、気が重く、「一体どういうお積りなのだろう」と思ったが、「浅はかで軽薄な所のないお人柄なので、おのずと自分のためにも、外聞の悪いことは慎んでのことだろう」と思って、
「それでは承知しました。お邸の近くですよ。;先に文をお遣りになってください。そうでないと、わざわざわたしが仲人を買って出たように思われますので、気がひけます」
と弁の尼君が言う。
「文をやるのは、何でもないが、世間の口はうるさいものだから、右大将が、常陸の守の娘に求愛したなどと噂されては困るし、その守は気性が荒々しいそうだし」
と薫が言えば、弁は笑ってお気の毒にと思う。
暗くなって、お帰りになった。木陰の秋の花々や、紅葉などを手折らせて、女二の宮にご覧に入れる。風流はお分かりの方だが、うやうやしく奉っていたので、うちとけるということはなかった。内裏からも、普通の親のように、入道の宮(母女二の宮)にも何かと頼まれるので、この上なく高貴な方は、限りなく大事にされていたのである。帝からも母宮からも言伝されて、自分の厄介な恋心もあって、つらいことであった。 |
|
| 50.36 弁の尼、三条の隠れ家を訪ねる |
のたまひしまだつとめて、睦ましく思す下臈侍一人、顔知らぬ牛飼つくり出でて遣はす。
「荘の者どもの田舎びたる召し出でつつ、つけよ」
とのたまふ。かならず出づべくのたまへりければ、いとつつましく苦しけれど、うち化粧じつくろひて乗りぬ。野山のけしきを見るにつけても、いにしへよりの古事ども思ひ出でられて、眺め暮らしてなむ来着きける。いとつれづれに人目も見えぬ所なれば、引き入れて、
「かくなむ、参り来つる」
と、しるべの男して言はせたれば、初瀬の供にありし若人、出で来て降ろす。あやしき所を眺め暮らし明かすに、昔語りもしつべき人の来たれば、うれしくて呼び入れたまひて、親と聞こえける人の御あたりの人と思ふに、睦ましきなるべし。
「あはれに、人知れず見たてまつりしのちよりは、思ひ出できこえぬ折なけれど、世の中かばかり思ひたまへ捨てたる身にて、かの宮にだに参りはべらぬを、この大将殿の、あやしきまでのたまはせしかば、思うたまへおこしてなむ」
と聞こゆ。君も乳母も、めでたしと見おききこえてし人の御さまなれば、忘れぬさまにのたまふらむも、あはれなれど、にはかにかく思したばかるらむと、思ひも寄らず。 |
仰せになった日の早朝、気心の知れた下級の侍一人、顔の知られていない牛飼い選んで宇治へ送り出す。
「荘園の者どもで田舎びたる者を召し出して供にせよ」
と言う。薫は、必ず京に行くように言っていたので、ひどく気おくれしてつらかったが、身支度して車に乗った。野山の景色を見るにつけ、昔のことが思い出されて、物思いに沈んで京に来た。閑散として人の出入りもないので、車を引き入れて、
「これこれの者が参りました」
と、案内の男に言わせると、初瀬詣でに供にしていた、若い女房が、出て来て弁を下ろす。粗末な家で、物思いに沈んでいたので、昔話のできる人が来たので、うれしく呼び入れて、親のお側に仕えていた人と思うと、親しく思うのだった。
「お懐かしい方と、胸の内で拝見してしましてから、思い出さない時はなく、世の中をこうして捨てた身では、あの匂宮邸にもご挨拶できていないので、この大将殿(薫)が熱心にお頼み申すので、意を決して出て参りました」
と弁尼君は言う。姫君も乳母も、素敵なお方と見ていた人のことなので、忘れず申し入れされるのも、ありがたいけれど、にわかに思い付いたこととは思いも寄らなかった。 |
|
| 50.37 薫、三条の隠れ家の浮舟と逢う |
宵うち過ぐるほどに、「宇治より人参れり」とて、門忍びやかにうちたたく。「さにやあらむ」と思へど、弁の開けさせたれば、車をぞ引き入るなる。「あやし」と思ふに、
「尼君に、対面賜はらむ」
とて、この近き御庄の預りの名のりをせさせたまへれば、戸口にゐざり出でたり。雨すこしうちそそくに、風はいと冷やかに吹き入りて、言ひ知らず薫り来れば、「かうなりけり」と、誰れも誰れも心ときめきしぬべき御けはひをかしければ、用意もなくあやしきに、まだ思ひあへぬほどなれば、心騷ぎて、
「いかなることにかあらむ」
と言ひあへり。
「心やすき所にて、月ごろの思ひあまることも聞こえさせむとてなむ」
と言はせたまへり。
「いかに聞こゆべきことにか」と、君は苦しげに思ひてゐたまへれば、乳母見苦しがりて、
「しかおはしましたらむを、立ちながらや、帰したてまつりたまはむ。かの殿にこそ、かくなむ、と忍びて聞こえめ。近きほどなれば」
と言ふ。
「うひうひしく。などてか、さはあらむ。若き御どちもの聞こえたまはむは、ふとしもしみつくべくもあらぬを。あやしきまで心のどかに、もの深うおはする君なれば、よも人の許しなくて、うちとけたまはじ」
など言ふほど、雨やや降り来れば、空はいと暗し。宿直人のあやしき声したる、夜行うちして、
「家宅の辰巳の隅の崩れ、いと危ふし。この、人の御車入るべくは、引き入れて御門鎖してよ。かかる人の御供人こそ、心はうたてあれ」
など言ひあへるも、むくむくしく聞きならはぬ心地したまふ。
「佐野のわたりに家もあらなくに」
など口ずさびて、里びたる簀子の端つ方に居たまへり。
「さしとむる葎やしげき東屋の
あまりほど降る雨そそきかな」
と、うち払ひたまへる、追風、いとかたはなるまで、東の里人も驚きぬべし。
とざまかうざまに聞こえ逃れむ方なければ、南の廂に御座ひきつくろひて、入れたてまつる。心やすくしも対面したまはぬを、これかれ押し出でたり。遣戸といふもの鎖して、いささか開けたれば、
「飛騨の工も恨めしき隔てかな。かかるものの外には、まだ居ならはず」
と愁へたまひて、いかがしたまひけむ、入りたまひぬ。かの人形の願ひものたまはで、ただ、
「おぼえなき、もののはさまより見しより、すずろに恋しきこと。さるべきにやあらむ、あやしきまでぞ思ひきこゆる」
とぞ語らひたまふべき。人のさま、いとらうたげにおほどきたれば、見劣りもせず、いとあはれと思しけり。 |
宵が過ぎる頃、弁尼の元に「宇治から人が来ました」と言って、門をこっそり叩く。「何だろう」と思ったが、弁が開けさせれば、車が入ってきた。「おや」と思っていると、
「尼君に、お目にかかりたい」
と言って、この近くの荘園の管理人の名前を言うので、弁尼君は、戸口にいざり出た。雨が少し降っていて、風が冷ややかに入ってきて、えも言えない香りが香ってくるので、「さては薫殿であったか」と誰もが心ときめかす気配なので、何の支度もなくむさくるしい所に、思いもしなかったので、女房たちは騒いで、
「どうしたことだろう」
と言い合うのだった。
「気の張らない所で、日頃の思いを伝えたい」
と弁尼君を通して、伝えた。
「どうした返事を申し上げるべきなのか」と姫君は困って黙っているので、乳母が気の毒に思って、
「せっかくお越しになって、座にもつかず、お帰しするわけも行きません。あちらの邸の母君に、秘かにお聞きしましょう、近いので」
と言う。
「小娘のよう。何で、お母様に相談することがありましょう。若い者同士が話をして、深い仲になるわけでもありません、薫殿は穏やかな思慮深い方ですので、姫君の許しなしに失礼なまねはなさらないでしょう」
などと弁尼君が言う程に、雨が降ってきて、空は暗い。宿直人の訛りのある声がして、夜回りをして、
「邸の東南の隅が崩れていて危ないです。この車は入れるなら入れて。門を鎖してください。このような人の供は、気が利かないね」
などと言い合っているのも、気持ち悪く聞きなれない。
「佐野の辺りに家もないのに」
と口ずさんで、薫は田舎びた簀子の端に座っていた。
「戸を閉ざす葎が生い茂る東屋の
外で長く待たされ降る雨に濡れてしまった
と雨の雫を追い払う風が、尋常でなく香り高く、東国の田舎者たちも驚くのだった。
あれこれと口実をつけても、お断わりするすべがないので、南の廂に座をつくって、入れた。姫君が気軽にお会いにならないので、女房たちが押し出した。引き戸を鎖して、少し開けてあるので、
「飛騨の工まで恨みます。こんなものの外に居たことは、未だありません」
と嘆いて、どうしたのだろう、中に入った。あの人形のことも仰らずに、ただ、
「思いがけず、物の狭間から見て以来、わけもなく恋しいのは、何かの因縁でしょうか。不思議にお慕い申しています」
とやさしく話すのであった。女の風情は、たいそうかわいらしく、期待に背かず、とてもいとおしいと思う。 |
|
| 50.38 薫と浮舟、宇治へ出発 |
ほどもなう明けぬ心地するに、鶏などは鳴かで、大路近き所に、おぼとほどれたる声して、いかにとか聞きも知らぬ名のりをして、うち群れて行くなどぞ聞こゆる。かやうの朝ぼらけに見れば、ものいただきたる者の、「鬼のやうなるぞかし」と聞きたまふも、かかる蓬のまろ寝にならひたまはぬ心地も、をかしくもありけり。
宿直人も門開けて出づる音する。おのおの入りて臥しなどするを聞きたまひて、人召して、車妻戸に寄せさせたまふ。かき抱きて乗せたまひつ。誰れも誰れも、あやしう、あへなきことを思ひ騒ぎて、
「九月にもありけるを。心憂のわざや。いかにしつることぞ」
と嘆けば、尼君も、いといとほしく、思ひの外なることどもなれど、
「おのづから思すやうあらむ。うしろめたうな思ひたまひそ。長月は、明日こそ節分と聞きしか」
と言ひ慰む。今日は、十三日なりけり。尼君、
「こたみは、え参らじ。宮の上、聞こし召さむこともあるに、忍びて行き帰りはべらむも、いとうたてなむ」
と聞こゆれど、まだきこのことを聞かせたてまつらむも、心恥づかしくおぼえたまひて、
「それは、のちにも罪さり申したまひてむ。かしこもしるべなくては、たづきなき所を」
と責めてのたまふ。
「人一人や、はべるべき」
とのたまへば、この君に添ひたる侍従と乗りぬ。乳母、尼君の供なりし童などもおくれて、いとあやしき心地してゐたり。 |
すぐにも夜が明ける心地がして、鶏は鳴かないが、大路も近い所なので、間延びした声で、何と言っているのか分からぬ名乗りをして、群になっていくのが聞こえる。こんな朝方を見ると、頭に載せた物売りが、「鬼のように見えるものだ」とお聞きになるのも、このような蓬の宿の仮寝もなれない心地も、興があった。
宿直人も門開けて出る音がする。夜番の者がおのおのが退いて寝に入るのを聞いたりして、人を呼び、車を妻戸に寄せさせた。姫君を抱き上げて乗せた。誰もが、とんでもなく急だったのであわてて、
「九月なのに、不吉だ。どうするつもりか」
と嘆いている、尼君も、お気の毒になり、予想外のことだったので、
「いずれ何かお考えがあるのでしょう。ご心配されることはありません。九月といっても、明日節分のようですから」
と言い慰める。今日は十三日だった。尼君は、
「今回はお供しません。こっそり行き帰りしたら、中の君がお聞きになって、何とお思いになりますか」
と言ったが、早々にこのことを中の君のお耳に入れるのも、何となく気がひけて、
「それは後で申し開きができるでしょう。あちらも案内がなくては、頼りない所ですから」
と無理強いされる。
「誰かひとりお供するように」
と言えば、姫君にお付きの侍従と一緒に乗った。乳母や尼君の供だった童たちは後に残されて、もう何が何やら分からぬ心地がしていた。 |
|
| 50.39 薫と浮舟の宇治への道行き |
「近きほどにや」と思へば、宇治へおはするなりけり。牛などひき替ふべき心まうけしたまへりけり。河原過ぎ、法性寺のわたりおはしますに、夜は明け果てぬ。
若き人は、いとほのかに見たてまつりて、めできこえて、すずろに恋ひたてまつるに、世の中のつつましさもおぼえず。君ぞいとあさましきに、ものもおぼえでうつぶし臥したるを、
「石高きわたりは、苦しきものを」
とて、抱きたまへり。羅の細長を、車の中に引き隔てたれば、はなやかにさし出でたる朝日影に、尼君はいとはしたなくおぼゆるにつけて、「故姫君の御供にこそ、かやうにても見たてまつりつべかりしか。あり経れば、思ひかけぬことをも見るかな」と、悲しうおぼえて、包むとすれど、うちひそみつつ泣くを、侍従はいと憎く、「ものの初めに形異にて乗り添ひたるをだに思ふに、なぞ、かくいやめなる」と、憎くをこにも思ふ。老いたる者は、すずろに涙もろにあるものぞと、おろそかにうち思ふなりけり。
君も、見る人は憎からねど、空のけしきにつけても、来し方の恋しさまさりて、山深く入るままにも、霧立ちわたる心地したまふ。うち眺めて寄りゐたまへる袖の、重なりながら長やかに出でたりけるが、川霧に濡れて、御衣の紅なるに、御直衣の花のおどろおどろしう移りたるを、落としがけの高き所に見つけて、引き入れたまふ。
「形見ぞと見るにつけては朝露の
ところせきまで濡るる袖かな」
と、心にもあらず一人ごちたまふを聞きて、いとどしぼるばかり、尼君の袖も泣き濡らすを、若き人、「あやしう見苦しき世かな」。心ゆく道に、いとむつかしきこと、添ひたる心地す。忍びがたげなる鼻すすりを聞きたまひて、我も忍びやかにうちかみて、「いかが思ふらむ」といとほしければ、
「あまたの年ごろ、この道を行き交ふたび重なるを思ふに、そこはかとなくものあはれなるかな。すこし起き上がりて、この山の色も見たまへ。いと埋れたりや」
と、しひてかき起こしたまへば、をかしきほどに、さし隠して、つつましげに見出だしたるまみなどは、いとよく思ひ出でらるれど、おいらかにあまりおほどき過ぎたるぞ、心もとなかめる。「いといたう児めいたるものから、用意の浅からずものしたまひしはや」と、なほ行く方なき悲しさは、むなしき空にも満ちぬべかめり。 |
「近い所なのか」と思ったが、宇治へ行くのだった。牛なども掛け替える準備をしていた。河原を過ぎ、法性寺のあたりを通るころには、すっかり夜が明けた。
若い侍従は、薫をちらりと見て、すばらしいお方と、一途に慕う気持ちになって、世間に憚る気もなく、姫君はあまりのことに恥ずかしく、何も分からず臥している。
「大きい石があるところは、つらいから」
と言って、抱きかかえていた。羅の細長を車中の隔てにしているので、あたりを照らし出した朝日に、尼君は自分がはしたなく感じて、「故大君のお供をして、こうした光景を見たかった。生きながらえていると、思いもかけないことを見るものだ」と悲しく、隠そうとするが涙を落とすのだった。侍従は、それが憎らしく、「新婚早々尼姿でお供するのは縁起でもないのに、そんなにめそめそして」と憎げに思う。年寄りは、何でもないことにも、涙もろいものだ、と事情を知らずに単純に思ったのだった。
薫も、目の前の人は愛しいが、空の気色を見ても、来し方の恋しさが勝って、山深く入るにつれて霧がたちこめる心地がした。物思いに沈んで、寄りかかっている袖が、重なって簾の下から長く出ているのが、川霧に濡れて、袿が紅なのに、直衣の薄藍色が変色しているのを、急坂の坂道で気がついて車の中へ引き入れるのだった。
「亡き大君の形見と見るにつけ朝霧のように
一面に涙で袖を濡らすことだ」
と、うっかり漏らしたひとり言を、尼君は涙を留められぬ思いで聞き、若い侍従は、「おかしいな、見っともない」。うれしいはずの道中に、何か事情があるのだろう。弁尼君が、がまんできなくて鼻ですすり泣くのを聞くと、薫もそっと鼻をかんで、姫君が「何と思っているだろう」とかわいそうで、
「長年この山道を何度も行き来したことを思うと、何とはなしに胸に迫るのです。あなたも少し起き上がって、この山の色をご覧なさい。たいそう塞いでいますね」
と、無理して起こすと、ほどよく扇で隠して、遠慮がちに外を見る目元などは、たいそう大君に似ているが、姫君が素直であまりおっとりしすぎているところは、心もとなかった。「大君はたいそう子供っぽいところもあったが、一方たいそう思慮深かったものです」と、とめどない悲しみは、空しく空に満ちるのだった。 |
|
| 50.40 宇治に到着、薫、京に手紙を書く |
おはし着きて、
「あはれ、亡き魂や宿りて見たまふらむ。誰によりて、かくすずろに惑ひありくものにもあらなくに」
と思ひ続けたまひて、降りてはすこし心しらひて、立ち去りたまへり。女は、母君の思ひたまはむことなど、いと嘆かしけれど、艶なるさまに、心深くあはれに語らひたまふに、思ひ慰めて降りぬ。
尼君は、ことさらに降りで、廊にぞ寄するを、「わざと思ふべき住まひにもあらぬを、用意こそあまりなれ」と見たまふ。御荘より、例の、人びと騒がしきまで参り集まる。女の御台は、尼君の方より参る。道は茂かりつれど、このありさまは、いと晴れ晴れし。
川のけしきも山の色も、もてはやしたる造りざまを見出だして、日ごろのいぶせさ、慰みぬる心地すれど、「いかにもてないたまはむとするにか」と、浮きてあやしうおぼゆ。
殿は、京に御文書きたまふ。
「なりあはぬ仏の御飾りなど見たまへおきて、今日吉ろしき日なりければ、急ぎものしはべりて、乱り心地の悩ましきに、物忌なりけるを思ひたまへ出でてなむ、今日明日ここにて慎みはべるべき」
など、母宮にも姫宮にも聞こえたまふ。 |
宇治に到着して、
「ああ、亡き大君の魂は、ここに留まってご覧になっているだろうか。誰ゆえに、こうしてさ迷い歩いているのだろう」
と思い続けて、車を降りて、少し気を利かせて、立ち去った。女は、母君が何と思っているか、悲しかったが、薫の容姿所作がすばらしく、やさしく話すので、気を取り直して下りた。
尼君は、こちらでは下りないで、廊に寄せるのを「わざわざ遠慮をしなくていい住まいなのに、気を使いすぎる」と見るのだった。例の荘園の人々が騒がしく集まって来る。女君の食事は、尼君から差し出す。道中は草木が繁ってうっとうしかったが、こちらは晴れていた。
姫君は、川の気色も山の色も、うまく取り入れた邸の造りを眺めやって、今までの晴れぬ心も慰む心地がするが、「自分をどうなさるつもりなのか」と不安だった。
薫は、京に文を出した。
まだ未完成の仏の飾りなどを見ていましたので、今日は吉日なので、急いで来ましたが、気分が悪くなりまして、物忌なのも思い出したので、今日明日はここで慎んでいます」
などと、母三の宮にも、正室の二の宮にも文を出した。 |
|
| 50.41 薫、浮舟の今後を思案す |
うちとけたる御ありさま、今すこしをかしくて入りおはしたるも恥づかしけれど、もて隠すべくもあらで居たまへり。女の装束など、色々にきよくと思ひてし重ねたれど、すこし田舎びたることもうち混じりてぞ、昔のいと萎えばみたりし御姿の、あてになまめかしかりしのみ思ひ出でられて、
「髪の裾のをかしげさなどは、こまごまとあてなり。宮の御髪のいみじくめでたきにも劣るまじかりけり」
と見たまふ。かつは、
「この人をいかにもてなしてあらせむとすらむ。ただ今、ものものしげにて、かの宮に迎へ据ゑむも、音聞き便なかるべし。さりとて、これかれある列にて、おほぞうに交じらはせむは本意なからむ。しばし、ここに隠してあらむ」
と思ふも、見ずはさうざうしかるべく、あはれにおぼえたまへば、おろかならず語らひ暮らしたまふ。故宮の御ことものたまひ出でて、昔物語をかしうこまやかに言ひ戯れたまへど、ただいとつつましげにて、ひたみちに恥ぢたるを、さうざうしう思す。
「あやまりても、かう心もとなきはいとよし。教へつつも見てむ。田舎びたるされ心もてつけて、品々しからず、はやりかならましかば、形代不用ならまし」
と思ひ直したまふ。 |
薫がくつろいだ様子で、また一段とすばらしい感じで入って来たのだが、姫君は気おくれして隠れるわけにもいかずただ座っていた。女の装束は、色々に美しく重ねていたが、少し田舎びたところも感じられて、昔大君の着馴れた衣の姿を、気品があって美しかったのが思い出されて、
「髪の裾の美しさなどは、一筋々々に品がある。女二の宮の美しい髪ににも劣らないだろう」
と見るのだった。また一方、
「この人をどのように扱ったらいいのだろう。今、大仰に、あの三条の宮に迎えても、世間体が悪いだろう。それでも、女房たちと同列で宮仕えさせても、大勢の中に交らせるのは本意ではあるまい。しばらく、ここに隠しておこう」
と思うが、会わないと物足りないだろうし、愛おしく思うので、細やかに話し合って過ごした。故宮のことも言い出して、昔の話を興味深く話してみるが、姫君はひどく気おくれして、恥ずかしがっているので、物足りなく思う。
しかし間違っても、こんなふうに頼りないのは結構だ。教えていこう。田舎びて風流気取りをされのは、品がなく、出しゃばって落ち着きがないのは、そんな身代わりならいらない」
と思い直すのだった。 |
|
| 50.42 薫と浮舟、琴を調べて語らう |
ここにありける琴、箏の琴召し出でて、「かかることはた、ましてえせじかし」と、口惜しければ、一人調べて、
「宮亡せたまひてのち、ここにてかかるものに、いと久しう手触れざりつかし」
と、めづらしく我ながらおぼえて、いとなつかしくまさぐりつつ眺めたまふに、月さし出でぬ。
「宮の御琴の音の、おどろおどろしくはあらで、いとをかしくあはれに弾きたまひしはや」
と思し出でて、
「昔、誰れも誰れもおはせし世に、ここに生ひ出でたまへらましかば、今すこしあはれはまさりなまし。親王の御ありさまは、よその人だに、あはれに恋しくこそ、思ひ出でられたまへ。などて、さる所には、年ごろ経たまひしぞ」
とのたまへば、いと恥づかしくて、白き扇をまさぐりつつ、添ひ臥したるかたはらめ、いと隈なう白うて、なまめいたる額髪の隙など、いとよく思ひ出でられてあはれなり。まいて、「かやうのこともつきなからず教へなさばや」と思して、
「これは、すこしほのめかいたまひたりや。あはれ、吾が妻といふ琴は、さりとも手ならしたまひけむ」
など問ひたまふ。
「その大和言葉だに、つきなくならひにければ、まして、これは」
と言ふ。いとかたはに心後れたりとは見えず。ここに置きて、え思ふままにも来ざらむことを思すが、今より苦しきは、なのめには思さぬなるべし。琴は押しやりて、
「楚王の台の上の夜の琴の声」
と誦じたまへるも、かの弓をのみ引くあたりにならひて、「いとめでたく、思ふやうなり」と、侍従も聞きゐたりけり。さるは、扇の色も心おきつべき閨のいにしへをば知らねば、ひとへにめできこゆるぞ、後れたるなめるかし。「ことこそあれ、あやしくも、言ひつるかな」と思す。
尼君の方より、くだもの参れり。箱の蓋に、紅葉、蔦など折り敷きて、ゆゑゆゑなからず取りまぜて、敷きたる紙に、ふつつかに書きたるもの、隈なき月にふと見ゆれば、目とどめたまふほどに、くだもの急ぎにぞ見えける。
「宿り木は色変はりぬる秋なれど
昔おぼえて澄める月かな」
と古めかしく書きたるを、恥づかしくもあはれにも思されて、
「里の名も昔ながらに見し人の
面変はりせる閨の月影」
わざと返り事とはなくてのたまふ、侍従なむ伝へけるとぞ。 |
この邸にあった琴、筝の琴を持って来させて、「このようなことは出来なくなるだろう」と残念に思い、ひとりで中弾くと、
「宮が亡くなってから、この邸で久しくこのようなものに触れていなかった」
自分でも珍しく思って、大事そうに弾きながら思い出にひたっていると、月が出た。
「亡き宮の琴の音は、大げさではなく、風情があって胸にしみるように弾いていた」
と思い出して、
「昔、誰もが在世中に、もしあなたがここで生まれ育っていたら、もっとあわれを感じたことでしょう。八の宮の御人柄は、他人のわたしでも、あわれに恋しく、思い出します。あなたはどうしてあんな田舎に生い育ったのですか」
と薫が言うと、姫君は恥ずかしくて、白い扇をいじりながら臥した横顔の、抜けるように白く、額髪のあたりのなまめかしさなど、よく大君に似ていたのだった。「このような琴のたしなみもひとかどの姫君らしく教えてやろう」と思って、
「これは少しは手習いましたか。あわれ、吾が妻という琴は、いくら何でも習ったでしょう」
などと薫が問う。
「その和歌も十分習ってはいないので、まして琴になると」
と言う。ひどく気の利かぬ者とも思われない。この邸に置いておけば、思い通りに通って来れないと思い、それが今からつらいのは、人並みの愛情ではないのだろう。琴を押しやって、
「楚王の台の上の夜の琴の声」
と薫が誦じるのも、あの弓ばかり引く東国に久しく過ごしたゆえ「ほんとうにすばらしい、申し分ない」と、侍従も聞いていた。実は、扇の色も気にしなければならない閨の故事を知らなければ、感心しているのは、心得がないのである。「いい加減に言ってしまった」と薫は思った。
尼君から、くだものが供された。箱の蓋に、紅葉、蔦など敷いて、たしなみの程を見せて、敷いた紙に、筆太に書いてあるのが、明るい月光にふと見えたので、目をとどめると、くだものを欲しがっているように見えた。
「宿木は色が変わった秋ですが
昔を懐かしんで月は澄んでいます」
と古めかしく書いたのを、恥ずかしくもあわれにも思って、
「里の名も変わっていないが
閨で逢う人は変わってしまった」
ことさら返歌ということではなく、詠ったものを、侍従が伝えた。 |
|
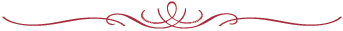
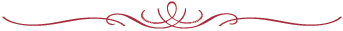
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)