| 【48、早蕨(さわらび)14節】 |
| あらすじは次の通り。 |
中の君が未だ悲嘆に暮れる中、宇治に春が訪れた。匂の宮は二月初旬に中の君を京へ迎えることにする。宇治を離れがたく思い悩む中の君に、薫は細やかな配慮を見せるが、心の中では匂の宮に中の君を譲ったことを悔いていた。中の君は、出家をしひとり宇治に残る弁と別れを惜しみ、後悔しつつも上京する。
匂の宮は薫の悔いを知り警戒する。中の君はそんな薫、匂の宮の心持ちを煩わしく思う。 |
| 48.1 宇治の新春、山の阿闍梨から山草が届く |
薮し分かねば、春の光を見たまふにつけても、「いかでかくながらへにける月日ならむ」と、夢のやうにのみおぼえたまふ。
行き交ふ時々にしたがひ、花鳥の色をも音をも、同じ心に起き臥し見つつ、はかなきことをも、本末をとりて言ひ交はし、心細き世の憂さもつらさも、うち語らひ合はせきこえしにこそ、慰む方もありしか、をかしきこと、あはれなるふしをも、聞き知る人もなきままに、よろづかきくらし、心一つをくだきて、宮のおはしまさずなりにし悲しさよりも、ややうちまさりて恋しくわびしきに、いかにせむと、明け暮るるも知らず惑はれたまへど、世にとまるべきほどは、限りあるわざなりければ、死なれぬもあさまし。
阿闍梨のもとより、
「年改まりては、何ごとかおはしますらむ。御祈りは、たゆみなく仕うまつりはべり。今は、一所の御ことをなむ、安からず念じきこえさする」
など聞こえて、蕨、つくづくし、をかしき籠に入れて、「これは、童べの供養じてはべる初穂なり」とて、たてまつれり。手は、いと悪しうて、歌は、わざとがましくひき放ちてぞ書きたる。
「君にとてあまたの春を摘みしかば
常を忘れぬ初蕨なり
御前に詠み申さしめたまへ」
とあり。 |
深い山里にも、春の光が注ぐものから、「どうしてこんなに生きながらえているのだろう」と中の君は夢のように思うのだった。
行き交う季節の折々につけ、花鳥の色も音も、姉君と同じ心に起き伏して見て、ちょっと和歌を詠むにしても、上の句と下の句を付け交わしたりして、心細い世の憂さつらさも、互いに語らい合って、慰めになったが、趣あることもあわれなことも、聞いてくれる人もないままに、心の晴れる時がなく、ひとり悲しみに沈み、父宮の時よりも、もっと姉君を恋しくつらいので、どうしたらよいのかと、日の明け暮れも知らず悲しみにくれていたが、世の寿命は定まっているので、死ぬことも叶わない、 何ということだろう。
阿闍梨から、
「年が改まって、いかがお過ごしでしょうか。無病息災のお祈りは、怠りなくさせていただいております。今は姫君おひとりの安泰を念じております」
などとあって、蕨、土筆などを趣ある籠に入れて、「これは童たちが供養した初物です」とて、供せられてた。悪筆で、歌は、ことさら一字一字を離して書いてある。
「長年宮様に春を摘んで献上してきましたので、
いつも通りの初蕨でございます
御前で詠みあげてください」
とあった。 |
|
| 48.2 中君、阿闍梨に返事を書く |
大事と思ひまはして詠み出だしつらむ、と思せば、歌の心ばへもいとあはれにて、なほざりに、さしも思さぬなめりと見ゆる言の葉を、めでたく好ましげに書き尽くしたまへる人の御文よりは、こよなく目とまりて、涙もこぼるれば、返り事、書かせたまふ。
「この春は誰れにか見せむ亡き人の
かたみに摘める峰の早蕨」
使に禄取らせさせたまふ。
いと盛りに匂ひ多くおはする人の、さまざまの御もの思ひに、すこしうち面痩せたまへる、いとあてになまめかしきけしきまさりて、昔人にもおぼえたまへり。並びたまへりし折は、とりどりにて、さらに似たまへりとも見えざりしを、うち忘れては、ふとそれかとおぼゆるまでかよひたまへるを、
「中納言殿の、骸をだにとどめて見たてまつるものならましかばと、朝夕に恋ひきこえたまふめるに、同じくは、見えたてまつりたまふ御宿世ならざりけむよ」
と、見たてまつる人びとは口惜しがる。
かの御あたりの人の通ひ来るたよりに、御ありさまは絶えず聞き交はしたまひけり。尽きせず思ひほれたまひて、「新しき年ともいはず、いや目になむ、なりたまへる」と聞きたまひても、「げに、うちつけの心浅さにはものしたまはざりけり」と、いとど今ぞあはれも深く、思ひ知らるる。
宮は、おはしますことのいと所狭くありがたければ、「京に渡しきこえむ」と思し立ちにたり。 |
阿闍梨は、大事なことと思って詠んだのだろう、と思うと、歌の真心にも深く打たれて、その場限りに、それほど感じてもいない言葉を、人の気に入るように書き分ける匂宮の文よりは、格段に心引かれて、涙がこぼれるので、返事を、女房に書かせる。
「今年の春は誰に見せましょう
亡き人の形見に摘んだ峰の早蕨を」
使いに禄を取らせる。
今が盛りの華やいだ感じの中の君が、様々な物思いに、少し面痩せて、とても気品があって優雅な気色がすばらしく、亡き大君に似て来たのだった。二人でいたころは、それぞれに美しく、似ているとも思えなかったが、つい忘れては、大君かと思えるほど似ていて、
「中納言殿(薫)が、亡骸を残して見ていたいと望んでいて、朝夕に慕っているのに、どうせなら、夫婦になればよかったのに、そうなる宿世ではなかったのだ」
と女房たちは口惜しがるのだった。
薫の家来が時々やって来るついでに、互いの様子は絶えず聞いていたが、薫がすっかりぼんやりしてしまって、おめでたい新年になっても、いつも涙ぐんでいると中の君が聞いても、「本当にその場限りの浅い気持ちではなかったのだ」と今はあわれも深く、思われた。
匂宮は、思いにまかせず、行けないので、「京にお迎えしよう」と思い立った。 |
|
| 48.3 正月下旬、薫、匂宮を訪問 |
内宴など、もの騒がしきころ過ぐして、中納言の君、「心にあまることをも、また誰れにかは語らはむ」と思しわびて、兵部卿宮の御方に参りたまへり。
しめやかなる夕暮なれば、宮うち眺めたまひて、端近くぞおはしましける。箏の御琴かき鳴らしつつ、例の、御心寄せなる梅の香をめでおはする、下枝を押し折りて参りたまへる、匂ひのいと艶にめでたきを、折をかしう思して、
「折る人の心にかよふ花なれや
色には出でず下に匂へる」
とのたまへば、
「見る人にかこと寄せける花の枝を
心してこそ折るべかりけれ
わづらはしく」
と、戯れ交はしたまへる、いとよき御あはひなり。
こまやかなる御物語どもになりては、かの山里の御ことをぞ、まづはいかにと、宮は聞こえたまふ。中納言も、過ぎにし方の飽かず悲しきこと、そのかみより今日まで思ひの絶えぬよし、折々につけて、あはれにもをかしくも、泣きみ笑ひみとかいふらむやうに、聞こえ出でたまふに、ましてさばかり色めかしく、涙もろなる御癖は、人の御上にてさへ、袖もしぼるばかりになりて、かひがひしくぞあひしらひきこえたまふめる。 |
内宴など、何かと多忙の時期が過ぎてから、中納言(薫)は、「心に余る悲しみも、誰に語ったらいいだろう」と思いわびて、兵部卿宮(匂宮の御殿)へ出かけた。
しめやかな夕暮れで、宮は物思わし気に庭を眺めて、端近くにいた。筝の琴をかき鳴らしながら、例によって、好みの梅の香を愛でている。下枝を折り取って来る様子が、梅の香と交って優雅で趣あるので、折りがらおもしろく思って、
「折る人の心の中で愛でる花なのでしょう
表には出さず心の中で思っているのですね」
と詠えば、
「見る人に口実を与える花の枝なら
気をつけて折らなければなりませんね
煩わしいことです」
と、戯れて返すのだった。仲の良い間柄だ。
うちとけた話になっては、あの山里のことを、まず大君の弔問を宮は申し上げる。薫も、今までのことの悲しくてならないことを、その当時から今まで、大君への思いが絶えないことを、その折々につけて、あわれにも趣深くもくも、悲喜こもごもというようだが、まさにそんな調子で話をして、宮は多情で涙もろい性格なので、人の身の上でも、袖をしぼるほど涙を流し、実に話甲斐のある相手だった。 |
|
| 48.4 匂宮、薫に中君を京に迎えることを言う |
空のけしきもまた、げにぞあはれ知り顔に霞みわたれる。夜になりて、烈しう吹き出づる風のけしき、まだ冬めきていと寒げに、大殿油も消えつつ、闇はあやなきたどたどしさなれど、かたみに聞きさしたまふべくもあらず、尽きせぬ御物語をえはるけやりたまはで、夜もいたう更けぬ。
世にためしありがたかりける仲の睦びを、「いで、さりとも、いとさのみはあらざりけむ」と、残りありげに問ひなしたまふぞ、わりなき御心ならひなめるかし。さりながらも、ものに心えたまひて、嘆かしき心のうちもあきらむばかり、かつは慰め、またあはれをもさまし、さまざまに語らひたまふ、御さまのをかしきにすかされたてまつりて、げに、心にあまるまで思ひ結ぼほるることども、すこしづつ語りきこえたまふぞ、こよなく胸のひまあく心地したまふ。
宮も、かの人近く渡しきこえてむとするほどのことども、語らひきこえたまふを、
「いとうれしきことにもはべるかな。あいなく、みづからの過ちとなむ思うたまへらるる。飽かぬ昔の名残を、また尋ぬべき方もはべらねば、おほかたには、何ごとにつけても、心寄せきこゆべき人となむ思うたまふるを、もし便なくや思し召さるべき」
とて、かの、「異人とな思ひわきそ」と、譲りたまひし心おきてをも、すこしは語りきこえたまへど、岩瀬の森の呼子鳥めいたりし夜のことは、残したりけり。心のうちには、「かく慰めがたき形見にも、げに、さてこそ、かやうにも扱ひきこゆべかりけれ」と、悔しきことやうやうまさりゆけど、今はかひなきものゆゑ、「常にかうのみ思はば、あるまじき心もこそ出で来れ。誰がためにもあぢきなく、をこがましからむ」と思ひ離る。「さても、おはしまさむにつけても、まことに思ひ後見きこえむ方は、また誰れかは」と思せば、御渡りのことどもも心まうけせさせたまふ。 |
空の気色も、実にあわれを知っているような風で一面に霞がかかっている。夜になって、激しく吹く風の気色が、まだ冬のようで寒く、灯明も消えそうになっても、互いに話を止める様子もなく、尽きせぬ話を心ゆくまで語りあえないうちに、夜もすっかり更けるのだった。
世にも稀な大君と薫の睦まじい間柄を、「いくら何でも、そんな清い関係ではないでしょう」と語り残したことがあるように宮が問うが、宮の好色な気性からいって仕方ないだろう。そうはいっても、宮は、何ごとにもよくわきまえたところのある人で、悲しみに沈む薫の心を晴れさせ、慰さめ、悲しみを散らし、あれこれとに語りかけたので、宮の話に乗せられて、薫は胸いっぱいの悲しみも、宮の話を聞くうちに、薫は胸が晴れる思いがするのだった。
匂宮も、中の君を、近々京にお移りさせたいと思っていることどもを語らうと、
「たいへんうれしいことでございます。不本意ながら、わたしの失敗だったと、思います。尽きぬ大君の名残りを、他に尋ねるべき人もないのですから、一通りは、何ごとに寄らず、お世話するべき人と思っておりますので、不都合なとお思いになりましょうか」
とて、「他人とは思わないでください」と、大君がお譲りになった意向も、少しは話したが、岩瀬の森の呼子鳥めいた夜のことは、話さずにいたのであった。心の中では、「恋しい大君の形見としても、やはり大君の言った通り、結婚して京に連れてくるのだった」と悔しさが募ってきたけれど、今となっては甲斐なきことゆえ、「いつもこんなことを思っていたら、あるまじきことも仕出かしそうだ、誰のためにもならない」と諦める。「中の君が京へ移るについては、後見として、他に誰がいよう」と思うと、移転についてもいろいろ支度されるのだった。 |
|
| 48.5 中君、姉大君の服喪が明ける |
かしこにも、よき若人童など求めて、人びとは心ゆき顔にいそぎ思ひたれど、今はとてこの伏見を荒らし果てむも、いみじく心細ければ、嘆かれたまふこと尽きせぬを、さりとても、またせめて心ごはく、絶え籠もりてもたけかるまじく、「浅からぬ仲の契りも、絶え果てぬべき御住まひを、いかに思しえたるぞ」とのみ、怨みきこえたまふも、すこしはことわりなれば、いかがすべからむ、と思ひ乱れたまへり。
如月の朔日ごろとあれば、ほど近くなるままに、花の木どものけしきばむも残りゆかしく、「峰の霞の立つを見捨てむことも、おのが常世にてだにあらぬ旅寝にて、いかにはしたなく人笑はれなることもこそ」など、よろづにつつましく、心一つに思ひ明かし暮らしたまふ。
御服も、限りあることなれば、脱ぎ捨てたまふに、禊も浅き心地ぞする。親一所は、見たてまつらざりしかば、恋しきことは思ほえず。その御代はりにも、この度の衣を深く染めむと、心には思しのたまへど、さすがに、さるべきゆゑもなきわざなれば、飽かず悲しきこと限りなし。
中納言殿より、御車、御前の人びと、博士などたてまつれたまへり。
「はかなしや霞の衣裁ちしまに
花のひもとく折も来にけり」
げに、色々いときよらにてたてまつれたまへり。御渡りのほどの被け物どもなど、ことことしからぬものから、品々にこまやかに思しやりつつ、いと多かり。
「折につけては、忘れぬさまなる御心寄せのありがたく、はらからなども、えいとかうまではおはせぬわざぞ」
など、人びとは聞こえ知らす。あざやかならぬ古人どもの心には、かかる方を心にしめて聞こゆ。若き人は、時々も見たてまつりならひて、今はと異ざまになりたまはむを、さうざうしく、「いかに恋しくおぼえさせたまはむ」と聞こえあへり。 |
宇治においても、若い可愛い童などを召しかかえて、女房たちは満足そうであっが、中の君はこの邸を荒れたままにしておくのも、たいそう心細く、嘆きは尽きないが、だからといって強情を張ってここに籠ってしまうのも、「浅からぬ私たちの縁も切れてしまいそうな、不便な住まいをどう思いますか」とのみ、匂宮が恨めし気に言うのも、もっともと思われる節もあり、どうしたものか、と思い悩むのだった。
二月の初め頃ということなので、その日が近くなるにつれて、花の木の蕾が膨らみ、盛りが待ち遠しくなう頃、「峰の霞を見捨てて、自分の常世でもない他人の家で、どんなに物笑いの種になることだろう」などと、何につけ気の引ける思いで、ひとり胸を痛めて過ごしていた。
喪服も、世間のきまりがあることなので、脱ぎ捨てるのも、禊の気持ちが浅い心地がする。母親は、顔を見たこともなかったので、恋しさはつのらないが、その代わり、姉君の喪には、衣を濃く染めようと思って言ったのだが、その理由も立たないので、尽きぬ悲しみに沈むのだった。
中納言(薫)から、車、前駆の人たち、陰陽博士などが、手配された。
「月日のたつのは早いもの、霞立つ頃に喪服をつくったのに、
花咲く春の衣に着替える時になりました」
薫から、実に色とりどりの美しい衣装を贈られた。移転の時に供の者たちが着るものなど、大げさにならぬように、それぞれに細かい心遣いが、たくさんあった。
「折につけて、忘れず心遣いされてありがたい、実の兄弟でもとてもこうまでは、お世話できない」
などと、女房たちは言うのだった。見栄えがしない老婆たちは、実生活の物を心からありがたく言うのだった。若い女房たちは、今まで時々は宇治に来ていたのが、姿を見せなくなったのを、物足りなく、「どんなに恋しく思われているだろう」と言い合うのだった。 |
|
| 48.6 薫、中君が宇治を出立する前日に訪問 |
みづからは、渡りたまはむこと明日とての、まだつとめておはしたり。例の、客人居の方におはするにつけても、今はやうやうもの馴れて、「我こそ、人より先に、かうやうにも思ひそめしか」など、ありしさま、のたまひし心ばへを思ひ出でつつ、「さすがに、かけ離れ、ことの外になどは、はしたなめたまはざりしを、わが心もて、あやしうも隔たりにしかな」と、胸いたく思ひ続けられたまふ。
垣間見せし障子の穴も思ひ出でらるれば、寄りて見たまへど、この中をば下ろし籠めたれば、いとかひなし。
内にも、人びと思ひ出できこえつつうちひそみあへり。中の宮は、まして、もよほさるる御涙の川に、明日の渡りもおぼえたまはず、ほれぼれしげにてながめ臥したまへるに、
「月ごろの積もりも、そこはかとなけれど、いぶせく思うたまへらるるを、片端もあきらめきこえさせて、慰めはべらばや。例の、はしたなくなさし放たせたまひそ。いとどあらぬ世の心地しはべり」
と聞こえたまへれば、
「はしたなしと思はれたてまつらむとしも思はねど、いさや、心地も例のやうにもおぼえず、かき乱りつつ、いとどはかばかしからぬひがこともやと、つつましうて」
など、苦しげにおぼいたれど、「いとほし」など、これかれ聞こえて、中の障子の口にて対面したまへり。
いと心恥づかしげになまめきて、また「このたびは、ねびまさりたまひにけり」と、目も驚くまで匂ひ多く、「人にも似ぬ用意など、あな、めでたの人や」とのみ見えたまへるを、姫宮は、面影さらぬ人の御ことをさへ思ひ出できこえたまふに、いとあはれと見たてまつりたまふ。
「尽きせぬ御物語なども、今日は言忌すべくや」
など言ひさしつつ、
「渡らせたまふべき所近く、このころ過ぐして移ろひはべるべければ、夜中暁と、つきづきしき人の言ひはべるめる、何事の折にも、疎からず思しのたまはせば、世にはべらむ限りは、聞こえさせ承りて過ぐさまほしくなむはべるを、いかがは思し召すらむ。人の心さまざまにはべる世なれば、あいなくやなど、一方にもえこそ思ひはべらね」
と聞こえたまへば、
「宿をばかれじと思ふ心深くはべるを、近く、などのたまはするにつけても、よろづに乱れはべりて、聞こえさせやるべき方もなく」
など、所々言ひ消ちて、いみじくものあはれと思ひたまへるけはひなど、いとようおぼえたまへるを、「心からよそのものに見なしつる」と、いと悔しく思ひゐたまへれど、かひなければ、その夜のことかけても言はず、忘れにけるにやと見ゆるまで、けざやかにもてなしたまへり。 |
薫自身は、明日移転するという日、まだ朝の内に見えた。例の客間の方にいるにつけても、今はようやく馴れて、「わたしこそ宮より先に大君を京へお迎えしたかった」となどと、大君生前の面影や仰せになった言葉を思い出して、「さすがに自分によそよそしくして、以ての外などの態度は、とらなかったのに、自分から妙なことに他人行儀で終わってしまった」とつらい気持ちで思うのだった。
垣間見た障子の穴を思い出して、見たけれど、簾がすっかり下ろしてあるので、見れなかった。
内では、女房たちが大君の思い出にひたって涙にくれている。中の君は、まして涙の川にあふれて、明日の移転も念頭になく、気の抜けたように物思いに沈んで臥している。
「日ごろのご無沙汰で積もった話も、何か胸につかえているのを、少しでも話をして、気を紛らわせてさし上げたい。いつものように、他人行儀にされては、知らない世界に来た気がします」
と申し上げれば、
「他人行儀にお扱いするつもりはありませんが、さあどうしたものでしょう。気分もすぐれませんので、変なことを言ってしまわないか、気になります」
などと迷惑そうに思っていたが、「お気の毒です」など、女房の誰来れが言って、中の障子の口で、対面した。
薫は、人が気恥ずかしくなるほど優雅な物越しで、「今日は一段と老成した感じがする」と目も見張るばかりに美しく、「並みはずれてたしなみ深い方だ」と見える姿を、中の君は、いつまでも面影の去らない姉君のことばかり思い出していて、あわれとのみ見るのだった。
「尽きない話は今日はひかえましょう」
などと言いながらも、
「お越しになる近くに、わたしも移る予定ですので、夜中、暁と親しい人が言うらしいが、何ごとにも、気兼ねなく声をかけてくだされば、世にいる限りは、相談にもあずかりご用も務めさせていただく所存ですので、いかがなものでしょうか。人の心様はさまざまな世ですから、かえってご迷惑かとも思いまして、一方的に思い込むわけにもいきませんので」
と言えば、
「この邸を離れたくない気持ちが強いので、近くと仰られても、何かと思い乱れまして返事のしようがございません」
などと、とぎれとぎれに言うので、しみじみと悲しく思っている様子など、たいそうよく大君に似ているので、「自分から進んで人のものにしてしまった」と悔しく思ったが、仕方のないことで、あの夜のことは一言も言わず、忘れてしまったのかと見えるまで、はっきりした態度だった。 |
|
| 48.7 中君と薫、紅梅を見ながら和歌を詠み交す |
御前近き紅梅の、色も香もなつかしきに、鴬だに見過ぐしがたげにうち鳴きて渡るめれば、まして「春や昔の」と心を惑はしたまふどちの御物語に、折あはれなりかし。風のさと吹き入るるに、花の香も客人の御匂ひも、橘ならねど、昔思ひ出でらるるつまなり。「つれづれの紛らはしにも、世の憂き慰めにも、心とどめてもてあそびたまひしものを」など、心にあまりたまへば、
「見る人もあらしにまよふ山里に
昔おぼゆる花の香ぞする」
言ふともなくほのかにて、たえだえ聞こえたるを、なつかしげにうち誦じなして、
「袖ふれし梅は変はらぬ匂ひにて
根ごめ移ろふ宿やことなる」
堪へぬ涙をさまよくのごひ隠して、言多くもあらず、
「またもなほ、かやうにてなむ、何ごとも聞こえさせよかるべき」
など、聞こえおきて立ちたまひぬ。
御渡りにあるべきことども、人びとにのたまひおく。この宿守に、かの鬚がちの宿直人などはさぶらふべければ、このわたりの近き御荘どもなどに、そのことどもものたまひ預けなど、こまやかなることどもをさへ定めおきたまふ。 |
御前に近い紅梅の、色も香も親しみがもてるので、鶯も見過ごせなくて鳴き渡って来るので、「春は昔の」心を惑わしている二人の話なので、折から悲しみもとても深い。風がさっと吹きこんくるたびに、花の香も客人の匂いも、橘ならぬ、大君を思い出すよすがだった。「つれづれの慰みにも、世の憂さを晴らすにも、大君はこの紅梅を愛でていたものを」など、中の君は思いがあふれて、
「見る人もいないでしょうに嵐にまどう山里に
昔懐かしい梅の香がします」
口ずさむともなく、かすかな聞こえるか聞こえないかの声で、親しみを込めて朗誦して、
「昔愛でられた梅は変わらぬ香を放っていますが
すっかり移ってしまうあなたの宿は別の所なのでしょう」
堪えきれない涙をぬぐい隠して、言葉多く語らず、
「また会う時も、このように親しければ、何ごとも話やすい」
などと言って座を立った。
移転に必要な様々なことを、女房たちに言うのだった。この山荘にあの髭ずらの宿直人が留守役でいることになっているので、この近くの荘園に山荘への心配りを言いつけて、日常の暮らし向きのことも細々と定めるのだった。 |
|
| 48.8 薫、弁の尼と対面 |
弁ぞ、
「かやうの御供にも、思ひかけず長き命いとつらくおぼえはべるを、人もゆゆしく見思ふべければ、今は世にあるものとも人に知られはべらじ」
とて、容貌も変へてけるを、しひて召し出でて、いとあはれと見たまふ。例の、昔物語などせさせたまひて、
「ここには、なほ、時々は参り来べきを、いとたつきなく心細かるべきに、かくてものしたまはむは、いとあはれにうれしかるべきことになむ」
など、えも言ひやらず泣きたまふ。
「厭ふにはえて延びはべる命のつらく、またいかにせよとて、うち捨てさせたまひけむ、と恨めしく、なべての世を思ひたまへ沈むに、罪もいかに深くはべらむ」
と、思ひけることどもを愁へかけきこゆるも、かたくなしげなれど、いとよく言ひ慰めたまふ。
いたくねびにたれど、昔、きよげなりける名残を削ぎ捨てたれば、額のほど、様変はれるに、すこし若くなりて、さる方に雅びかなり。
「思ひわびては、などかかる様にもなしたてまつらざりけむ。それに延ぶるやうもやあらまし。さても、いかに心深く語らひきこえてあらまし」
など、一方ならずおぼえたまふに、この人さへうらやましければ、隠ろへたる几帳をすこし引きやりて、こまかにぞ語らひたまふ。げに、むげに思ひほけたるさまながら、ものうち言ひたるけしき、用意、口惜しからず、ゆゑありける人の名残と見えたり。
「さきに立つ涙の川に身を投げば
人におくれぬ命ならまし」
と、うちひそみ聞こゆ。
「それもいと罪深かなることにこそ。かの岸に到ること、などか。さしもあるまじきことにてさへ、深き底に沈み過ぐさむもあいなし。すべて、なべてむなしく思ひとるべき世になむ」
などのたまふ。
「身を投げむ涙の川に沈みても
恋しき瀬々に忘れしもせじ
いかならむ世に、すこしも思ひ慰むることありなむ」
と、果てもなき心地したまふ。
帰らむ方もなく眺められて、日も暮れにけれど、すずろに旅寝せむも、人のとがむることやと、あいなければ、帰りたまひぬ。 |
弁が、
「こうしてお供するのも、思いがけぬ長生きをつらいと思い、人も縁起でもないと思うでしょう、今は世に生きていると誰にも知られたくないのです」
と言っていて、尼姿になっているのを、あえて召し出して、あわれと見るのだった。いつもの通り、昔話などして、
「ここには時々はくるでしょうから、その時はとても頼りなく心細いでしょうから、こうしてあなたがおいででしたら、あわれにうれしいです」
など、皆まで言えず泣くのだった。
「厭わしく思う程延びる命がつらく、どうしたらいいのか、大君に先立たれて、恨めしく、もう何もかもこの世が恨めしく思われのに、罪もどんなに深くなっていることでしょう」
と心に思ったことを憂えるのが愚痴っぽかったが、薫は、ねんごろに慰めるのだった。
弁はひどく年をとって、昔はさぞ美しかったであろう髪を尼削ぎして、額のあたりが様変わりして若く見え、品のよい感じになった。
「思いあぐねて、どうして大君を尼姿にしてあげなかったのだろう、それで命が延びて、来世のことを深く語らい合えたかもしれないのに」
などと、あれこれと思いがあふれるので、この弁さえ羨ましく思われて、隠れた几帳を少し引き上げて、細かく語らうのだった。すっかり悲しみに暮れている様子だったが、物を言う心遣いは並々ではなく、趣のある女房だったころの名残りが見えたのだった。
「先立って涙の川に身投げしたら
大君に後れることもなかった命なのに」
と泣き顔で言う。
「身を投げることも罪深いことです。彼岸に致ることなどどうしてできましょう。そんな余計なことをして、深い淵に沈んだまま過ごすのもつまらぬこと。総じて何もかも空しいと悟るのがこの世です」
などと弁は言うのだった。
「身を投げて涙の川に沈んでも
恋しい人の折々を忘れることはないでしょう
いつになったら、少しでもこの悲しみが紛れることがあろうか」
と、いつまでも果てぬ気がする。
帰る気にもなれず物思いに沈んでいたが、日も暮れたので、何となく泊まるのも、誤解をまねくので、やむなく帰った。 |
|
| 48.9 弁の尼、中君と語る |
思ほしのたまへるさまを語りて、弁は、いとど慰めがたくくれ惑ひたり。皆人は心ゆきたるけしきにて、もの縫ひいとなみつつ、老いゆがめる容貌も知らず、つくろひさまよふに、いよいよやつして、
「人はみないそぎたつめる袖の浦に
一人藻塩を垂るる海人かな」
と愁へきこゆれば、
「塩垂るる海人の衣に異なれや
浮きたる波に濡るるわが袖
世に住みつかむことも、いとありがたかるべきわざとおぼゆれば、さまに従ひて、ここをば荒れ果てじとなむ思ふを、さらば対面もありぬべけれど、しばしのほども、心細くて立ちとまりたまふを見おくに、いとど心もゆかずなむ。かかる容貌なる人も、かならずひたぶるにしも絶え籠もらぬわざなめるを、なほ世の常に思ひなして、時々も見えたまへ」
など、いとなつかしく語らひたまふ。昔の人のもてつかひたまひしさるべき御調度どもなどは、皆この人にとどめおきたまひて、
「かく、人より深く思ひ沈みたまへるを見れば、前の世も、取り分きたる契りもや、ものしたまひけむと思ふさへ、睦ましくあはれになむ」
とのたまふに、いよいよ童べの恋ひて泣くやうに、心をさめむ方なくおぼほれゐたり。 |
薫の悲しみにあふれた話しぶりを中の君に語って、弁は、ますます悲しくなるのだった。女房たちは、満足そうに、晴れ着を縫ったり忙しくして、老いて醜くなった容貌も知らず、弁はいっそう悲しく、
「人は皆忙しそうに意匠を縫っているが
わたしひとりは涙に暮れる尼です」
と嘆けば、
「涙にぬれる尼の衣と異なることはありません
浮いた波に涙を流しています」
京にずっと落ち着くことも、とても難しいことのように思われますので、事情によっては、この邸を荒れたままにはしておかないと思う、そうであれば、対面の折もありましょうが、しばらくの間にせよ、あなたはここにお残りになるので、気がかりですが、尼といっても引き籠ってばかりではないでしょうから、やはり世間並みに、時々は会いに来てください」
とやさしく言うのだった。亡き大君の遺品の調度類は、皆この弁の元に残して、
「こうして薫君が人一倍悲しみにくれているのを見ると、前世の宿縁も格別のものがあったと思うと、他人とも思えず胸いっぱいになります」
と中の君が言うのを、弁はいよいよ子供が慕うように泣いて悲しむのだった。 |
|
| 48.10 中君、京へ向けて宇治を出発 |
皆かき払ひ、よろづとりしたためて、御車ども寄せて、御前の人びと、四位五位いと多かり。御みづからも、いみじうおはしまさまほしけれど、ことことしくなりて、なかなか悪しかるべければ、ただ忍びたるさまにもてなして、心もとなく思さる。
中納言殿よりも、御前の人、数多くたてまつれたまへり。おほかたのことをこそ、宮よりは思しおきつめれ、こまやかなるうちうちの御扱ひは、ただこの殿より、思ひ寄らぬことなく訪らひきこえたまふ。
日暮れぬべしと、内にも外にも、もよほしきこゆるに、心あわたたしく、いづちならむと思ふにも、いとはかなく悲しとのみ思ほえたまふに、御車に乗る大輔の君といふ人の言ふ、
「ありふればうれしき瀬にも逢ひけるを
身を宇治川に投げてましかば」
うち笑みたるを、「弁の尼の心ばへに、こよなうもあるかな」と、心づきなうも見たまふ。いま一人、
「過ぎにしが恋しきことも忘れねど
今日はたまづもゆく心かな」
いづれも年経たる人びとにて、皆かの御方をば、心寄せまほしくきこえためりしを、今はかく思ひ改めて言忌するも、「心憂の世や」とおぼえたまへば、ものも言はれたまはず。
道のほどの、遥けくはげしき山路のありさまを見たまふにぞ、つらきにのみ思ひなされし人の御仲の通ひを、「ことわりの絶え間なりけり」と、すこし思し知られける。七日の月のさやかにさし出でたる影、をかしく霞みたるを見たまひつつ、いと遠きに、ならはず苦しければ、うち眺められて、
「眺むれば山より出でて行く月も
世に住みわびて山にこそ入れ」
様変はりて、つひにいかならむとのみ、あやふく、行く末うしろめたきに、年ごろ何ごとをか思ひけむとぞ、取り返さまほしきや。 |
すっかり掃除をすませ、何もかもきちんと始末して、車を寄せて、前駆の人々も、四位、五位の人々が多かった。匂宮自身も、ぜひにも迎えに来たかったが、大げさになって、かえって面倒なので、ひたすら内密にということになったので、やきもきしている。
中納言(薫)からも、前駆の人が大勢供された。大概のことは、宮から指図があったけれど、細やかな内々の扱いは、行き届かぬこともなく面倒を見るのだった。
日が暮れそうです、と邸の内外から、催促する声が聞こえて、あわただしく、どこへ行くのかと思うにつけて、頼りなく悲しいとのみ思うので、車に同乗する大輔の君という者の言うに、
「生きていればこそうれしいことにも出会えましたのに
身を厭って宇治川に身投げしてしまっていたらどうだったかしら」
微笑んでいるのを、「弁の尼と何と違っていることか」と、不愉快に思った。もう一人は、
「亡くなった人の恋しさは忘れないが
今日の引っ越しは何をさしおいても、うれしく思います」
いずれも年老いた人々で、皆あの方を贔屓にしていたのに、今はこうして気持ちを変えて、言及するのを避けているのも、「心憂き世」と思って、ものも言わない。
道中、はるかな険しい山路を見ると、ひどい仕打ちと思っていた人の通ってくる道中を、「間遠になるのももっともだ」と、少し思い知るのだった。七日の月がさやかに出た光が、風情ある様子で霞むのを見ながら、遠い道を、初めてのことで難儀なので、物思わしい気持ちになって、
「思えば山から出て空をわたってゆく月も
この世を住み侘びてまた山に入るのだろう」
今宇治を離れて、どうなるのだろう、と心配で、行く末が気になり、今まで何を思い悩んでいたのだろうと思い、昔の自分を取り返したい気持ちになった。 |
|
| 48.11 中君、京の二条院に到着 |
宵うち過ぎてぞおはし着きたる。見も知らぬさまに、目もかかやくやうなる殿造りの、三つば四つばなる中に引き入れて、宮、いつしかと待ちおはしましければ、御車のもとに、みづから寄らせたまひて下ろしたてまつりたまふ。
御しつらひなど、あるべき限りして、女房の局々まで、御心とどめさせたまひけるほどしるく見えて、いとあらまほしげなり。いかばかりのことにかと見えたまへる御ありさまの、にはかにかく定まりたまへば、「おぼろけならず思さるることなめり」と、世人も心にくく思ひおどろきけり。
中納言は、三条の宮に、この二十余日のほどに渡りたまはむとて、このころは日々におはしつつ見たまふに、この院近きほどなれば、けはひも聞かむとて、夜更くるまでおはしけるに、たてまつれたまへる御前の人びと帰り参りて、ありさまなど語りきこゆ。
いみじう御心に入りてもてなしたまふなるを聞きたまふにも、かつはうれしきものから、さすがに、わが心ながらをこがましく、胸うちつぶれて、「ものにもがなや」と、返す返す独りごたれて、
「しなてるや鳰の湖に漕ぐ舟の
まほならねどもあひ見しものを」
とぞ言ひくたさまほしき。 |
宵が過ぎてから二条院に着いた。見たこともないような、目も輝く立派な殿造りが、幾棟も立ち並ぶ中に車を入れて、匂宮が今か今かと気が気でなく待っていて、車の元に、自ら寄って中の君が降りるのを丁重に手伝うのだった。
部屋の飾りつけも、手を尽くして、女房の局々まで、気を配っている様子がはっきり見えて、まことに結構な扱いであった。その方の待遇はどんなものであろうかと、人が見守る中で、急に決まったことなので、「並々でないご寵愛だ」と、世人も中の君がよほどの方なのだろうと注目していた。
中納言(薫)は、三条の宮に、この二十日ばかりに引っ越しする予定なので、近頃は毎日三条の宮に来て見ているが、二条の院は近くなので、気配もそれとなく聞こうと思って、夜更けまで起きていて、差し向けた前駆の人々が帰って来て、様子を報告する。
匂宮が中の君を心からもてなす様子を聞いて、うれしくはあったが、さすがに我ながら未練がましく、胸もどきどきして、「昔を取り戻せないか」と、繰り返しひとり口ずさんで、
「鳰の湖にこぐ舟の真帆ではなかったが
一夜は会って添い寝したのに」
とでもけちをつけて見たい気がする。 |
|
| 48.12 夕霧、六の君の裳着を行い、結婚を思案す |
右の大殿は、六の君を宮にたてまつりたまはむこと、この月にと思し定めたりけるに、かく思ひの外の人を、このほどより先にと思し顔にかしづき据ゑたまひて、離れおはすれば、「いとものしげに思したり」と聞きたまふも、いとほしければ、御文は時々たてまつりたまふ。
御裳着のこと、世に響きていそぎたまへるを、延べたまはむも人笑へなるべければ、二十日あまりに着せたてまつりたまふ。
同じゆかりにめづらしげなくとも、この中納言をよそ人に譲らむが口惜しきに、
「さもやなしてまし。年ごろ人知れぬものに思ひけむ人をも亡くなして、もの心細くながめゐたまふなるを」
など思し寄りて、さるべき人してけしきとらせたまひけれど、
「世のはかなさを目に近く見しに、いと心憂く、身もゆゆしうおぼゆれば、いかにもいかにも、さやうのありさまはもの憂くなむ」
と、すさまじげなるよし聞きたまひて、
「いかでか、この君さへ、おほなおほな言出づることを、もの憂くはもてなすべきぞ」
と恨みたまひけれど、親しき御仲らひながらも、人ざまのいと心恥づかしげにものしたまへば、えしひてしも聞こえ動かしたまはざりけり。 |
右の大殿(夕霧)は、六の君を匂宮と結婚させること、この月にも思い定めていたのに、こうして思いも寄らない人を、以前から画策していたかのようにして、涼しい顔をしているので、「たいそう不快に思っている」と聞いていたが、お気の毒なので、匂宮は時々は六の君に文を遣っていた。
御裳着は、世の評判になるほど盛大に支度したが、延期するのも世間体が悪いので、二十日に裳を着せたのだった。
同じ一族内で面白くもないが、この中納言(薫)を知らぬ人の婿に取られるのも残念なので、
「いっそ婿にしてしまおうか。長年思いをかけていたという人にも先立たれて、世をはかなんで物思いがちだそうだが」
などと思って、人を介して気持ちを伺わせたが、
「世の無常を目の当たり見て、とても心憂く、この身も不吉な運命ではないかと思われて、そのような話には気が向かないのです」
まったくその気がないのを聞いて、
「どうして、このひとまでも、わたしの申し出を、気乗りのしない風にあしらってよいものか」
と恨んだが、薫は親しい間柄であったが、人が気がひけるほど立派なので、強いて説得して心を動かそうとまではしなかった。 |
|
| 48.13 薫、桜の花盛りに二条院を訪ね中君と語る |
花盛りのほど、二条の院の桜を見やりたまふに、主なき宿のまづ思ひやられたまへば、「心やすくや」など、独りごちあまりて、宮の御もとに参りたまへり。
ここがちにおはしましつきて、いとよう住み馴れたまひにたれば、「めやすのわざや」と見たてまつるものから、例の、いかにぞやおぼゆる心の添ひたるぞ、あやしきや。されど、実の御心ばへは、いとあはれにうしろやすくぞ思ひきこえたまひける。
何くれと御物語聞こえ交はしたまひて、夕つ方、宮は内裏へ参りたまはむとて、御車の装束して、人びと多く参り集まりなどすれば、立ち出でたまひて、対の御方へ参りたまへり。
山里のけはひ、ひきかへて、御簾のうち心にくく住みなして、をかしげなる童の、透影ほの見ゆるして、御消息聞こえたまへれば、御茵さし出でて、昔の心知れる人なるべし、出で来て御返り聞こゆ。
「朝夕の隔てもあるまじう思うたまへらるるほどながら、そのこととなくて聞こえさせむも、なかなかなれなれしきとがめやと、つつみはべるほどに、世の中変はりにたる心地のみぞしはべるや。御前の梢も霞隔てて見えはべるに、あはれなること多くもはべるかな」
と聞こえて、うち眺めてものしたまふけしき、心苦しげなるを、
「げに、おはせましかば、おぼつかなからず行き返り、かたみに花の色、鳥の声をも、折につけつつ、すこし心ゆきて過ぐしつべかりける世を」
など、思し出づるにつけては、ひたぶるに絶え籠もりたまへりし住まひの心細さよりも、飽かず悲しう、口惜しきことぞ、いとどまさりける。 |
花の盛りのころ、二条の院の桜を見ていると、主なき宇治の山荘の桜が思い出されるので、「気がねなく」などと、ひとり言を言って、匂宮の所へ行った。
宮はこの二条院におられることが多く、すっかり中の君との生活に住み馴れて、薫は、「結構なことです」と思っているが、例によって、ただではいられない気持ちになってくるのは、困ったこと。しかし、本当の気持ちは、心からうれしくこれで安心だと思っている。
薫と匂宮はあれこれと話をして、夕方、宮は内裏へ参上するので、車を整えて、お供が多く集まってきたので、薫は立ち上がって、中の君の対へ行った。
山荘の質素な様子とはうって変わって、御簾の内に奥ゆかしく暮らして、可愛らしい童が御簾の間からちらほら見えて、参上の挨拶をすれば、茵を差し出して、昔からの女房であろうが出て来て挨拶する。
「いつでもお尋ねできそうな近所にいながら、格別用事もないのに伺うのも、かえって親しすぎるとの咎めがありそうですが、遠慮している間に、世の中がすっかり変わってしまった気持ちがします。御前の梢も霞を隔てて見る心地がして、あわれなることも多い」
と言いながらも、物思いに沈んでいるいるのが、痛ましく、
「本当に大君がいらっしゃれば、心おきなく行き来して、互いに花の色、鳥の声も、その折々につけて、心楽しくこの世を生きていけましたのに」
などと、思い出すにつけ、世間と全く交渉もなく、籠っていた宇治の住まいの心細さよりも、ひたすら悲しく、残念に思う気持ちがまさって来た。 |
|
| 48.14 匂宮、中君と薫に疑心を抱く |
人びとも、
「世の常に、ことことしくなもてなしきこえさせたまひそ。限りなき御心のほどをば、今しもこそ、見たてまつり知らせたまふさまをも、見えたてまつらせたまふべけれ」
など聞こゆれど、人伝てならず、ふとさし出で聞こえむことの、なほつつましきを、やすらひたまふほどに、宮、出でたまはむとて、御まかり申しに渡りたまへり。いときよらにひきつくろひ化粧じたまひて、見るかひある御さまなり。
中納言はこなたになりけり、と見たまひて、
「などか、むげにさし放ちては、出だし据ゑたまへる。御あたりには、あまりあやしと思ふまで、うしろやすかりし心寄せを。わがためはをこがましきこともや、とおぼゆれど、さすがにむげに隔て多からむは、罪もこそ得れ。近やかにて、昔物語もうち語らひたまへかし」
など、聞こえたまふものから、
「さはありとも、あまり心ゆるびせむも、またいかにぞや。疑はしき下の心にぞあるや」
と、うち返しのたまへば、一方ならずわづらはしけれど、わが御心にも、あはれ深く思ひ知られにし人の御心を、今しもおろかなるべきならねば、「かの人も思ひのたまふめるやうに、いにしへの御代はりとなずらへきこえて、かう思ひ知りけりと、見えたてまつるふしもあらばや」とは思せど、さすがに、とかくやと、かたがたにやすからず聞こえなしたまへば、苦しう思されけり。 |
女房たちも、
「世間並みに、薫をよそよそしくお扱いなさいますな。この上ないご好意の深さを、今こそ、感謝しているということを、お分かりいただけるようになさらなくてはなりません」
などと申し上げるのだが、女房を介しての対面ではなく、いきなり直接話をするようなことは、気がひけてためらっているところへ、宮が、出かける挨拶にお越しになった。たいそう美しく装って、見るからにほれぼれするお姿だ。
中納言(薫)はこちらにいる、と見て、
「どうして他人行儀に、御簾の外に座らせているのか。あなたに対しては、本当にやりすぎと思う程、行き届いた世話をしていたのに。わたしが、物笑いなる心配もあるほどだったが、それでも、全く他人行儀に遇するのは、罰が当たります。もっと近くに寄って、昔話でも語らい会いなさい」
などと、宮は仰って、
「そうはいっても、あまり気を許すのも、いかがなものでしょう。どんな疑わしき下心が生じるか分からんものですからね」
と、宮がむし返して仰せになるので、どちらにも厄介だけれど、自分でも、薫のやさしさを身にしみて感じているので、今さらよそよそしくしてよいものではないし、あの方も思い言ってもいるように、薫君を亡き大君の身代わりと思って、こう思う程に感謝しているのだ、と気持ちを分かってもらえる折もあれば」と思っているが、さすがに、宮が何かにつけて嫉妬がましく言うので、つらく感じるのだった。 |
|
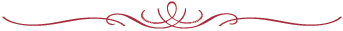
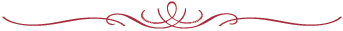
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)