| 【34、若菜上(わかな じょう)(前半)49節】 |
| あらすじは次の通り。 |
六条院への行幸後、病にかかり強く出家を望む朱雀院は、愛娘の女三の宮の行く末だけを気にかけていた。あれこれと候補者を考えた末、朱雀院は姫を源氏に託す決心をする。一度は固辞した源氏だが、正妻として姫を受け入れる。紫の上の心は激しく揺れるが、かろうじて冷静さを保っていた。
年が明け、玉鬘が源氏の四十の賀を催す。
二月中旬、女三の宮が六条院に迎えられた。源氏は紫の上とくらべ、あまりに幼い女三の宮にあきれ果てる。紫の上の苦悩は絶えず、その重苦しさから逃れるように、源氏は朧月夜を訪問する。
明石の女御が懐妊し、六条院に下がった。これを機に紫の上は女三の宮と対面し、六条院の秩序の維持に努める。
翌年三月、明石の女御は男児を出産。宿願をかなえた明石の入道は、山に入り、消息を絶つ。
春うららかな日、六条院で蹴鞠が催された。偶然にも猫が御簾を引き上げ、柏木が女三の宮を垣間見、懸想する。 |
| 34-1、朱雀院、女三の宮の将来を案じる |
朱雀院の帝、ありし御幸ののち、そのころほひより、例ならず悩みわたらせたまふ。もとよりあつしくおはしますうちに、このたびはもの心細く思し召されて、
「年ごろ行なひの本意深きを、后の宮おはしましつるほどは、よろづ憚りきこえさせたまひて、今まで思しとどこほりつるを、なほその方にもよほすにやあらむ、世に久しかるまじき心地なむする」
などのたまはせて、さるべき御心まうけどもせさせたまふ。
御子たちは、春宮をおきたてまつりて、女宮たちなむ四所おはしましける。その中に、 藤壺と聞こえしは、先帝の源氏にぞおはしましける。
まだ坊と聞こえさせし時参りたまひて、高き位にも定まりたまべかりし人の、取り立てたる御後見もおはせず、母方もその筋となく、ものはかなき更衣腹にてものしたまひければ、御交じらひのほども心細げにて、大后の、尚侍を参らせたてまつりたまひて、かたはらに並ぶ人なくもてなしきこえたまひなどせしほどに、気圧されて、帝も御心のうちに、いとほしきものには思ひきこえさせたまひながら、下りさせたまひにしかば、かひなく口惜しくて、世の中を恨みたるやうにて亡せたまひにし。
その御腹の女三の宮を、あまたの御中に、すぐれてかなしきものに思ひかしづききこえたまふ。
そのほど、御年、十三、四ばかりおはす。
「今はと背き捨て、山籠もりしなむ後の世にたちとまりて、誰を頼む蔭にてものしたまはむとすらむ」
と、ただこの御ことをうしろめたく思し嘆く。
西山なる御寺造り果てて、移ろはせたまはむほどの御いそぎをせさせたまふに添へて、またこの宮の御裳着のことを思しいそがせたまふ。
院のうちにやむごとなく思す御宝物、御調度どもをばさらにもいはず、はかなき御遊びものまで、すこしゆゑある限りをば、ただこの御方に取りわたしたてまつらせたまひて、その次々をなむ、異御子たちには、御処分どもありける。 |
朱雀院の帝は、先の御幸のあとで、行幸の頃から具合が悪かったのだが、病で体の調子が悪くなった。元来病弱な方で、今回はことさらに心細く感じられて、
「年来の出家の本願は深く、御母后の在世中は、はばかって、今までは思い止めていたのだが、やはり出家の道には心せくものがあり、わたしもこの世に長く生きていられない気がするのだ」
などと仰せになって、世を捨てる心積もりをするのであった。
御子たちは、春宮を別にして、女宮が四人いた。帝の女御たちの中に、藤壺という女御がいたが、これは先帝の源氏の出であった。
藤壺は朱雀帝がまだ東宮の頃に入内し、本来は高い位につくべき人であったが、取り立てて後見もいなかったので、母方も名のある家柄ではなく、はかない更衣腹であったので女御たちの交じらいの中でも心細げで、弘徽殿の大后が、朧月夜の尚侍を強引に入内させて、周りが及ばないほどに厚くもてなしたので、気圧されて、帝も心のうちではかわいそうに思っていたが、皇位を譲ったので、入内の甲斐もなく、口惜しく世を恨むようにして亡くなった。
その腹の、女三の宮を、多くの宮の中でも、ことさら可愛いがって大切に育てていた。
その子の年は、十三、四くらいであった。
「今は世に背いて、山籠りした、後に残った者たちは、誰を頼って生きていったらいいのだろう」
とただこのことを心配され、思い嘆くのだった。
西山に寺を造り終わって、一方では移転の支度をさせながら、またこの宮の裳着の儀式のことも思って準備をさせていた。
院の御所にあるとても貴重な宝物、調度類は言うに及ばず、ごくたわいない遊びの道具にいたるまで、少しでも由緒のあるものは、全部この三の宮に遺産分けして賜って、その次の残りの品々を他の宮たちに、分配して賜るのだった。 |
|
| 34.2 東宮、父朱雀院を見舞う |
春宮は、「かかる御悩みに添へて、世を背かせたまふべき御心づかひになむ」と聞かせたまひて、渡らせたまへり。母女御、添ひきこえさせたまひて参りたまへり。すぐれたる御おぼえにしもあらざりしかど、宮のかくておはします御宿世の、限りなくめでたければ、年ごろの御物語、こまやかに聞こえさせたまひけり。
宮にも、よろづのこと、世をたもちたまはむ御心づかひなど、聞こえ知らせたまふ。御年のほどよりはいとよく大人びさせたまひて、御後見どもも、こなたかなた、軽々しからぬ仲らひにものしたまへば、いとうしろやすく思ひきこえさせたまふ。
「この世に恨み残ることもはべらず。女宮たちのあまた残りとどまる行く先を思ひやるなむ、さらぬ別れにもほだしなりぬべかりける。さきざき、人の上に見聞きしにも、女は心よりほかに、あはあはしく、人におとしめらるる宿世あるなむ、いと口惜しく悲しき。
いづれをも、思ふやうならむ御世には、さまざまにつけて、御心とどめて思し尋ねよ。その中に、後見などあるは、さる方にも思ひ譲りはべり。
三の宮なむ、いはけなき齢にて、ただ一人を頼もしきものとならひて、うち捨ててむ後の世に、ただよひさすらへむこと、いといとうしろめたく悲しくはべる」
と、御目おし拭ひつつ、聞こえ知らせさせたまふ。
女御にも、うつくしきさまに聞こえつけさせたまふ。されど、女御の、人よりはまさりて時めきたまひしに、皆挑み交はしたまひしほど、御仲らひども、えうるはしからざりしかば、その名残にて、「げに、今はわざと憎しなどはなくとも、まことに心とどめて思ひ後見むとまでは思さずもや」とぞ推し量らるるかし。
朝夕に、この御ことを思し嘆く。年暮れゆくままに、御悩みまことに重くなりまさらせたまひて、御簾の外にも出でさせたまはず。御もののけにて、時々悩ませたまふこともありつれど、いとかくうちはへをやみなきさまにはおはしまさざりつるを、「このたびは、なほ、限りなり」と思し召したり。
御位を去らせたまひつれど、なほその世に頼みそめたてまつりたまへる人びとは、今もなつかしくめでたき御ありさまを、心やりどころに参り仕うまつりたまふ限りは、心を尽くして惜しみきこえたまふ。 |
春宮は、「帝がご病気に加えて、出家しようとしている」と聞いて、見舞いに来た。母の承香殿の女御も一緒に参上した。女御は帝の寵愛がすばらしく厚かったわけではないが、春宮がこうして立派に春宮の地位にいるのも宿世がめでたいかったからで、院は、長年の積もる思いをこと細やかに話されるのだった。
宮にも、諸事万端よろずのことを、世を統治する心構えをはじめて、いろいろとお話されるのだった。(春宮は)年よりは大人びて成長しているので、後見たちもあちこちに軽くはない身分の者たちがたくさんいて、後の心配はなかった。
「この世に未練はないが、女宮たちがたくさんいるので、それぞれの行く末が思いやられる。末期の別れの妨げになるかも知れぬ。先代の人に聞いても、女は意に反して、軽率に、世間の人に貶められる宿世もあるそうなので、とても心配しているし悲しく思う。
どなたをも、即位されたら、何かにつけて、忘れず世話をしてください。その中でも母方がしっかり後見がある宮は、その方に任せてよいと思います。
ただ三の宮は、まだ幼い年頃なので、わたしひとりを頼りに育ったので、出家したあとは、寄る辺ない生活をすることになるのではないか、すごく心配なのです」
と涙をぬぐいながら、語るのであった。
承香殿の女御にも、三の宮のことを面倒見てくれるよう頼むのであった。しかし、母の藤壺は人に勝って寵愛を得ていたので、みな競った仲でその関係はあまりよくなく、その名残が残っていて、「本当に、今は格別憎いということはないだろうが、心から世話をする気にならないのではないか」と承香殿の女御は思うのであった。
(朱雀院は)朝夕に女三の宮のことを思い嘆くのであった。年の暮れ頃になって、病気がますます重くなって、御簾の外にも出なくなった。 物の怪に時々悩まされることもあった。こんなにもいつまでも悪い病状ではなかったので、「もう今度が最後だ」と思った。
退位された後ではあったが、御在位中に恩顧を受けた人々は多くいて、今もやさしくすばらしい院のお人柄を、心の遣り所にしてお仕えして、心から惜しむのであった。 |
|
| 34.3 源氏の使者夕霧、朱雀院を見舞う |
六条院よりも、御訪らひしばしばあり。みづからも参りたまふべきよし、聞こし召して、院はいといたく喜びきこえさせたまふ。
中納言の君参りたまへるを、御簾の内に召し入れて、御物語こまやかなり。
「故院の上の、今はのきざみに、あまたの御遺言ありし中に、この院の御こと、今の内裏の御ことなむ、取り分きてのたまひ置きしを、公けとなりて、こと限りありければ、うちうちの御心寄せは、変らずながら、はかなきことのあやまりに、心おかれたてまつることもありけむと思ふを、年ごろことに触れて、その恨み残したまへるけしきをなむ漏らしたまはぬ。
賢しき人といへど、身の上になりぬれば、こと違ひて、心動き、かならずその報い見え、ゆがめることなむ、いにしへだに多かりける。
いかならむ折にか、その御心ばへほころぶべからむと、世の人もおもむけ疑ひけるを、つひに忍び過ぐしたまひて、春宮などにも心を寄せきこえたまふ。今はた、またなく親しかるべき仲となり、睦び交はしたまへるも、限りなく心には思ひながら、本性の愚かなるに添へて、子の道の闇にたち交じり、かたくななるさまにやとて、なかなかよそのことに聞こえ放ちたるさまにてはべる。
内裏の御ことは、かの御遺言違へず仕うまつりおきてしかば、かく末の世の明らけき君として、来しかたの御面をも起こしたまふ。本意のごと、いとうれしくなむ。
この秋の行幸の後、いにしへのこととり添へて、ゆかしくおぼつかなくなむおぼえたまふ。対面に聞こゆべきことどもはべり。かならずみづから訪らひものしたまふべきよし、もよほし申したまへ」
など、うちしほたれつつのたまはす。 |
六条院の源氏からも、お見舞いがしばしばあって、自分でも自らお見舞いに上がる旨、お伝えすると、朱雀院は大いに喜ぶのだった。
夕霧が参上すると、御簾の中に招じ入れられて、帝は細やかに物語をした。
「故桐壺院が、今わの際にたくさんの御遺言がありました中で、源氏のことと冷泉帝のことを、とりわけて言い残したのですが、 いざ即位してみると、自由にふるまうことが出来ず、わたし個人の気持は変わらないのだが、些細なことに行き違いが生じ、気にかけることもあると思うので、年頃何につけてもその恨みが残り口に出して漏らすこともあるはず。
賢明な人でも、自分のこととなれば、事情が異なり、感情に動かされ、かならず報復したり、道に外れたことをするのが、昔から多い。
どんな折に、その心ばえがほころぶだろうと、世間の人もその気で疑っていたが、源氏の君は、ついに最後まで我慢し通したし、春宮などにも心を寄せている。今は今で、この上なく、親しい仲となり、仲睦まじくしているのも、無上にうれしいと思いながら、親の子に対する本性は愚かな闇だなどの惑い、その見苦しい通説は、源氏の君にとっては、むしろよそ事のようにおもわれます。
(冷泉帝の)即位のことも、御遺言どおりに成し遂げたし、こうして末世に現われた名君として、昔の面目も取り戻しました。望みどおりでうれしく思います。
この秋の行幸の後、昔のことをいろいろ思い出されて、懐かしくお会いするのが待ち遠しいです。お会いして申し上げたいことがあります。どうか御自分がお越し下さるように、君にお伝えください」
など、涙ながらにおっしゃるのだった。 |
|
| 34.4 夕霧、源氏の言葉を言上す |
中納言の君、
「過ぎはべりにけむ方は、ともかくも思うたまへ分きがたくはべり。年まかり入りはべりて、朝廷にも仕うまつりはべるあひだ、世の中のことを見たまへまかりありくほどには、大小のことにつけても、うちうちのさるべき物語などのついでにも、『いにしへのうれはしきことありてなむ』など、うちかすめ申さるる折ははべらずなむ。
『かく朝廷の御後見を仕うまつりさして、静かなる思ひをかなへむと、ひとへに籠もりゐし後は、何ごとをも、知らぬやうにて、故院の御遺言のごともえ仕うまつらず、御位におはしましし世には、齢のほども、身のうつはものも及ばず、かしこき上の人びと多くて、その心ざしを遂げて御覧ぜらるることもなかりき。今、かく政事を去りて、静かにおはしますころほひ、心のうちをも隔てなく、参りうけたまはらまほしきを、さすがに何となく所狭き身のよそほひにて、おのづから月日を過ぐすこと』
となむ、折々嘆き申したまふ」
など、奏したまふ。
二十にもまだわづかなるほどなれど、いとよくととのひ過ぐして、容貌も盛りに匂ひて、いみじくきよらなるを、御目にとどめてうちまもらせたまひつつ、このもてわづらはせたまふ姫宮の御後見に、これをやなど、人知れず思し寄りけり。
「太政大臣のわたりに、今は住みつかれにたりとな。年ごろ心得ぬさまに聞きしが、いとほしかりしを、耳やすきものから、さすがにねたく思ふことこそあれ」
とのたまはする御けしきを、「いかにのたまはするにか」と、あやしく思ひめぐらすに、「この姫宮をかく思し扱ひて、さるべき人あらば、預けて、心やすく世をも思ひ離ればや、となむ思しのたまはする」と、おのづから漏り聞きたまふ便りありければ、「さやうの筋にや」とは思ひぬれど、ふと心得顔にも、何かはいらへきこえさせむ。ただ、
「はかばかしくもはべらぬ身には、寄るべもさぶらひがたくのみなむ」
とばかり奏して止みぬ。 |
中納言の君が申し上げる。
「過ぎ去った昔のことなどは、幼かったので、何とも分かりかねます。成人になってからは、朝廷にも仕えるようになって、世間での経験もいろいろ積んでからは、大小のことにつけても、親子の打ち解けた話のなかでも、『昔のことだがつらいことがあってな』などとは、一言も言われたことはありませんでした。
『(准太上天皇になって)朝廷の後見を途中で辞してからは、静かに生活しようと、すっかり隠居して籠もってからは、世事一切を振り捨てたようにしているので、故院のご遺言通りにお仕えすることも出来ず、朱雀帝が位におられた世は、歳も若く器量も及ばず、賢い人々が上にいて、思うところを十分に遂げることも出来なかった、今はこうして政事を去って、静かに暮らしているので、心のうちも隔てなく参上したいのですが、さすがに、大そうな身辺の様子ですので、つい思うに任せない』
と時々嘆いています」
などと院に申し上げる。
(夕霧は)まだ二十歳にもならないのだが、年齢よりはずっと立派で、容貌も若い盛りに輝いて、まことに美しいので、院は目を留めてじっと見ていて、今悩ましている姫宮の婿に、どうだろうか、などと人知れず思っていた。
「太政大臣の邸に、今は住んでいるそうだね。長い間、納得のいかない話だし、気の毒に思っていました。安心しましたが、やはり残念に思うところもあります」
と仰せになる様子を、「何を言っているのだろう」と、あやしく思い巡らすと「この姫君の身の上を心配されて、しかるべき 人がいれば、預けて、安心して出家しよう、と思っていらっしゃるのだ」と、自然と漏れ聞こえる噂があったので、「その筋の話か」とは思うが、得心がいった心地がしたが、さて今はどう返事したらいいのだろう。ただ、
「わたしのような頼りない者には、妻もなかなか来てくれません」
とばかり申し上げて黙り込んだ。 |
|
| 34.5 朱雀院の夕霧評 |
女房などは、覗きて見きこえて、
「いとありがたくも見えたまふ容貌、用意かな」
「あな、めでた」
など、集りて聞こゆるを、老いしらへるは、
「いで、さりとも、かの院のかばかりにおはせし御ありさまには、えなずらひきこえたまはざめり。いと目もあやにこそきよらにものしたまひしか」
など、言ひしろふを聞こしめして、
「まことに、かれはいとさま異なりし人ぞかし。今はまた、その世にもねびまさりて、光るとはこれを言ふべきにやと見ゆる匂ひなむ、いとど加はりにたる。うるはしだちて、はかばかしき方に見れば、いつくしくあざやかに、目も及ばぬ心地するを、また、うちとけて、戯れごとをも言ひ乱れ遊べば、その方につけては、似るものなく愛敬づき、なつかしくうつくしきことの、並びなきこそ、世にありがたけれ。何ごとにも前の世推し量られて、めづらかなる人のありさまなり。
宮の内に生ひ出でて、帝王の限りなくかなしきものにしたまひ、さばかり撫でかしづき、身に変へて思したりしかど、心のままにも驕らず、卑下して、二十がうちには、納言にもならずなりにきかし。一つ余りてや、宰相にて大将かけたまへりけむ。
それに、これはいとこよなく進みにためるは、次々の子の世のおぼえのまさるなめりかし。まことに賢き方の才、心もちゐなどは、これもをさをさ劣るまじく、あやまりても、およすけまさりたるおぼえ、いと異なめり」
など、めでさせたまふ。 |
女房たちがすき間から覗き見て、
「すばらしいお姿、容貌、所作ですこと」
「まあ、すばらしい」
などと言って集まっているのを、老いた女房は、
「さあ、それでも、あの院がこの年頃であったときの有様には、較べようもありませんね。本当にまぶしい ほどの美しさでした」
など、言い合っているのを院が聞いて、
「まことにあの方は格別に優れた人でした。今また、あの頃より貫禄がついて、光るとはこれを言うのかと見えるほどの美しさが加わっています。威儀を正して、公事に携わっているところを見ると、厳然として、端麗で、目もくらみそうな気がするが、また、打ち解けて冗談でふざけてたわむれる、そうした面では、すごく愛嬌があって、親しみがあって美しいこと目もくらみそうな程で、本当にまたとないほどです。何事も前世の因縁が推し量られて、稀有な人です。
内裏の中で育てられ、帝に限りなく愛されて育ち、それほど大事にされて、わが身以上に可愛がられて育ったのに、心におごりなく、自分を卑下して、二十歳のときには中納言にもなっていない。二十歳を一歳越えてから、宰相で大将になったのです。
それに、夕霧が早く昇進したしたのは、親から子へと世間の評判が上がっているからでしょう。まことに、漢学の才、心遣い、などは、夕霧もおさおさ源氏に劣らず、父親より老成しているという評判が、格別なのだ」
などと、褒めるのであった。 |
|
| 34.6 女三の宮の乳母、源氏を推薦 |
姫宮のいとうつくしげにて、若く何心なき御ありさまなるを見たてまつりたまふにも、
「見はやしたてまつり、かつはまた、片生ひならむことをば、見隠し教へきこえつべからむ人の、うしろやすからむに預けきこえばや」
など聞こえたまふ。
大人しき御乳母ども召し出でて、御裳着のほどのことなどのたまはするついでに、
「六条の大殿の、式部卿親王の女 生ほし立てけむやうに、この宮を預かりて育まむ人もがな。ただ人の中にはありがたし。内裏には中宮さぶらひたまふ。次々の女御たちとても、いとやむごとなき限りものせらるるに、はかばかしき後見なくて、さやうの交じらひ、いとなかなかならむ。
この権中納言の朝臣の独りありつるほどに、うちかすめてこそ試みるべかりけれ。若けれど、いと警策に、生ひ先頼もしげなる人にこそあめるを」
とのたまはす。
「中納言は、もとよりいとまめ人にて、年ごろも、かのわたりに心をかけて、ほかざまに思ひ移ろふべくもはべらざりけるに、その思ひ叶ひては、いとど揺るぐ方はべらじ。
かの院こそ、なかなか、なほいかなるにつけても、人をゆかしく思したる心は、絶えずものせさせたまふなれ。その中にも、やむごとなき御願ひ深くて、前斎院などをも、今に忘れがたくこそ、聞こえたまふなれ」
と申す。
「いで、その旧りせぬあだけこそは、いとうしろめたけれ」
とはのたまはすれど、
「げに、あまたの中にかかづらひて、めざましかるべき思ひはありとも、なほやがて親ざまに定めたるにて、さもや譲りおききこえまし」
なども、思し召すべし。
「まことに、少しも世づきてあらせむと思はむ女子持たらば、同じくは、かの人のあたりにこそ、触ればはせまほしけれ。いくばくならぬこの世のあひだは、さばかり心ゆくありさまにてこそ、過ぐさまほしけれ。
われ女ならば、同じはらからなりとも、かならず睦び寄りなまし。若かりし時など、さなむおぼえし。まして、女の欺かれむは、いと、ことわりぞや」
とのたまはせて、御心のうちに、尚侍の君の御ことも、思し出でらるべし。 |
姫君のたいへんかわいらしく、幼くあどけない無心に振舞っている有様を見ていると、
「見てはやしたててくれて、また、至らないところは、見ないでそっと教えてくれるような人で、頼りになる人に預けたいものだ」
などと仰るのであった。
年かさの乳母たちを召されて、宮の裳着の儀式について話すついでの時にも、
「六条の大殿が、式部卿の宮の娘(紫上)を育てたように、この宮を預かって育ててくれる人がいないものか。臣籍の者にはいないだろう。内裏には、中宮などがいる。次々の女御も、とても高貴な身分の者ばかりで、しっかりした後見がなければ、その中で交際するのは、かえってつらいだろう。
この権中納言(夕霧)が独身だった時に、そっと打診しておくのだった。若いけれど、すごく優秀で、将来有望な人材だからな」
と(朱雀院が)仰せになる。
「中納言は、元来真面目な人で、長年思いをかけた方がいて、他に心を移すなど軽薄なこともなく、その思いが叶った後ですから、君の心が揺らぐことはないでしょう。
かえって、あの院ご自身こそどうでしょう、どんな身分の方でも新しい女君を求める気持ちは変わらないようですから。とりわけ深く思いを寄せている方が、前斎院(朝顔の君)であり、今も忘れがたく思っているようです」
と申し上げる。
「いや、その変わらぬ浮気っぽさが心配なのだ」
とは言うのだが、
「いかにも、多くの妻妾がいる中で、不愉快な思いもするだろうが、親の決めた定めたこととして、親代わりにお預けするか」
などとも思うのだった。
「まことに、多少なりと、世間並みに結婚させようと思う子女がいれば、どうせなら、あの人に縁組させたいと思うだろう。いくばくもないこの世に生きている間、あのように満足のいく思いをして、過ごしたいものだ。
わたしが女ならば、同じ兄弟姉妹でも、必ずついて行くだろうし。若いときなら、そう思っただろうし、まして、女がだまされるのも、無理はない」
と仰せになり、心のうちでは、尚侍の君(朧月夜)のこともあったようだ。 |
|
| 34.7 乳母と兄左中弁との相談 |
この御後見どもの中に、重々しき御乳母の兄、左中弁なる、かの院の親しき人にて、年ごろ仕うまつるありけり。この宮にも心寄せことにてさぶらへば、参りたるにあひて、物語するついでに、
「主上なむ、しかしか御けしきありて聞こえたまひしを、かの院に、折あらば漏らしきこえさせたまへ。皇女たちは、独りおはしますこそは例のことなれど、さまざまにつけて心寄せたてまつり、何ごとにつけても、御後見したまふ人あるは頼もしげなり。
主上をおきたてまつりて、また真心に思ひきこえたまふべき人もなければ、おのらは、仕うまつるとても、何ばかりの宮仕へにかあらむ。わが心一つにしもあらで、おのづから思ひの他のこともおはしまし、軽々しき聞こえもあらむ時には、いかさまにかは、わづらはしからむ。御覧ずる世に、ともかくも、この御こと定まりたらば、仕うまつりよくなむあるべき。
かしこき筋と聞こゆれど、女は、いと宿世定めがたくおはしますものなれば、よろづに嘆かしく、かくあまたの御中に、取り分ききこえさせたまふにつけても、人の嫉みあべかめるを、いかで塵も据ゑたてまつらじ」
と語らふに、弁、
「いかなるべき御ことにかあらむ。院は、あやしきまで御心長く、仮にても見そめたまへる人は、御心とまりたるをも、またさしも深からざりけるをも、かたがたにつけて尋ね取りたまひつつ、あまた集へきこえたまへれど、やむごとなく思したるは、限りありて、一方なめれば、それにことよりて、かひなげなる住まひしたまふ方々こそは多かめるを、御宿世ありて、もし、さやうにおはしますやうもあらば、いみじき人と聞こゆとも、立ち並びておしたちたまふことは、えあらじとこそは推し量らるれど、なほ、いかがと憚らるることありてなむおぼゆる。
さるは、『この世の栄え、末の世に過ぎて、身に心もとなきことはなきを、女の筋にてなむ、人のもどきをも負ひ、わが心にも飽かぬこともある』となむ、常にうちうちのすさびごとにも思しのたまはすなる。
げに、おのれらが見たてまつるにも、さなむおはします。かたがたにつけて、御蔭に隠したまへる人、皆その人ならず立ち下れる際にはものしたまはねど、限りあるただ人どもにて、院の御ありさまに並ぶべきおぼえ具したるやはおはすめる。
それに、同じくは、げにさもおはしまさば、いかにたぐひたる御あはひならむ」
と語らふを、 |
この世話役たちの中に、地位の高い乳母の兄で、左中弁の身分の者で、あの源氏の院に親しく長年出入りして仕えていたのがいた。この宮にも格別忠義を尽くしていたので、参上したときの話の中で、
「帝がこれこれの意向を持っていると聞いたので、源氏に折あればそっと申し上げるのはいかがでしょう。皇女たちはひとりでいるのが通例だが、あれこれにつけて心配りをして、何事につけても、世話を焼いてくれる人がいるのは、頼もしいものです。
帝のほかには、心からこの宮のことを思っくれる人もないので、わたしらは、お仕えするといっても、どれほどのことが出来ましょう。わたしひとりの思うままにもならず、成り行きで思っていないことが起きることもあるでしょうし、浮ついた噂が出たらどんなに迷惑なことでしょう。ご在世中に、ともかくも、このことが決まれば、お仕えしやすいです。
高貴なご身分と申しても、女は身の上が不安定なので、何事につけて心配ですが、こうして女宮がたくさんいる中で、特別扱いするのも、妬みが生じたりしますが、些細な疵も付けたくないものです」
と語り、それから弁は、
「どうすればよいのでしょう。院は不思議なほどお気持ちの変わらない方で、仮にも見初めた人は、深く思い至った人も、それほど深く思わなかった人も、それぞれに、引き取って、邸に集めるのですが、とりわけ大事にしている人はやはりひとりだから、そちらに片寄って、張り合いのない暮らしをしている方々も多くいるが、もしご縁があって、もし源氏に降嫁するようなことがあったら、どんなにご寵愛を受けているご婦人といえども、宮に張り合って振舞うことは、よもやあるまいと思われるが、それでもどうかなと懸念される点はあるように思われます。
とは申せ、『この世での栄達はこの上なく、末世に過ぎて、その身に不足はないのだが、女のことでは、人の非難もあり、自分でも満足できない』と常々、内輪の閑談のときにも仰るのであった。
いかにも、自分らが見ていても、そのように思いますから。それぞれの縁があって、世話している婦人方は皆、素性の分からぬ低い身分の人はおられないが、臣下の出で、院に肩を並べるられる人はいないのではないでしょうか。
もしそういうことがあれば、どんなにか似合いの夫婦になることでしょうか」
と語るのを、 |
|
| 34.8 乳母、左中弁の意見を朱雀院に言上 |
乳母、またことのついでに、
「しかしかくなむ、なにしの朝臣にほのめかしはべりしかば、『かの院には、かならずうけひき申させたまひてむ。年ごろの御本意かなひて思しぬべきことなるを、こなたの御許しまことにありぬべくは、伝へきこえむ』となむ申しはべりしを、いかなるべきことにかははべらむ。
ほどほどにつけて、人の際々思しわきまへつつ、ありがたき御心ざまにものしたまふなれど、ただ人だに、またかかづらひ思ふ人立ち並びたることは、人の飽かぬことにしはべめるを、めざましきこともやはべらむ。御後見望みたまふ人びとは、あまたものしたまふめり。
よく思し定めてこそよくはべらめ。限りなき人と聞こゆれど、今の世のやうとては、皆ほがらかに、あるべかしくて、世の中を御心と過ぐしたまひつべきもおはしますべかめるを、姫宮は、あさましくおぼつかなく、心もとなくのみ見えさせたまふに、さぶらふ人びとは、仕うまつる限りこそはべらめ。
おほかたの御心おきてに従ひきこえて、賢しき下人もなびきさぶらふこそ、頼りあることにはべらめ。取り立てたる御後見ものしたまはざらむは、なほ心細きわざになむはべるべき」
と聞こゆ。 |
乳母はまた別の機会に、帝に申し上げるには、
「しかじかかくかくと、某朝臣にそれとなく申しましたところ、『あの院は、必ずお受けすることでしょう。年来の宿願が叶うでしょうから、こちらの意向はほんとうかどうか、再度伝えて確かめてくれ』と申しておりすので、どのようにいたしたらよろしいでしょうか。
院は、女の身分に応じて、その人の違いをわきまえ、行き届いた心遣いをしておりますが、普通の身分の者でも、側に思い人が別にいれば、不愉快な思いをするでしょうから、嫌なこともあるでしょう。(女三宮の) 後見を願っている人々は、たくさんいるでしょう。/
よく考えてお決めになってください。身分の高い人と申しても、当世風では、はっきり自分の考えを持ち、世の中を自分の考え通りに過ごしている人もいるようですが、姫宮は、驚くほど世間知らずで、心もとなく見えますので、お側に仕える人々にも限度というものがございます。
ご主人の大筋の方針に従って、賢い下人たちがそれに倣って忠勤に励んでこそ、心丈夫というものです。これといった、ご後見がおられなければ、心細い限りでございます」
と申すのだった。 |
|
| 34.9 朱雀院、内親王の結婚を苦慮 |
「しか思ひたどるによりなむ。皇女たちの世づきたるありさまは、うたてあはあはしきやうにもあり、また高き際といへども、女は男に見ゆるにつけてこそ、悔しげなることも、めざましき思ひも、おのづからうちまじるわざなめれと、かつは心苦しく思ひ乱るるを、また、さるべき人に立ちおくれて、頼む蔭どもに別れぬる後、心を立てて世の中に過ぐさむことも、昔は、人の心たひらかにて、世に許さるまじきほどのことをば、思ひ及ばぬものとならひたりけむ、今の世には、好き好きしく乱りがはしきことも、類に触れて聞こゆめりかし。
昨日まで高き親の家にあがめられかしづかれし人の女の、今日は直々しく下れる際の好き者どもに名を立ち欺かれて、亡き親の面を伏せ、影を恥づかしむるたぐひ多く聞こゆる。言ひもてゆけば皆同じことなり。
ほどほどにつけて、宿世などいふなることは、知りがたきわざなれば、よろづにうしろめたくなむ。すべて、悪しくも善くも、さるべき人の心に許しおきたるままにて世の中を過ぐすは、宿世宿世にて、後の世に衰へある時も、みづからの過ちにはならず。
あり経て、こよなき幸ひあり、めやすきことになる折は、かくても悪しからざりけりと見ゆれど、なほ、たちまちふとうち聞きつけたるほどは、親に知られず、さるべき人も許さぬに、心づからの忍びわざし出でたるなむ、女の身にはますことなき疵とおぼゆるわざなる。
直々しきただ人の仲らひにてだに、あはつけく心づきなきことなり。みづからの心より離れてあるべきにもあらぬを、思ふ心よりほかに人にも見えず、宿世のほど定められむなむ、いと軽々しく、身のもてなし、ありさま推し量らるることなるを。
あやしくものはかなき心ざまにやと見ゆめる御さまなるを、これかれの心にまかせ、もてなしきこゆなる、さやうなることの世に漏り出でむこと、いと憂きことなり」
など、見捨てたてまつりたまはむ後の世を、うしろめたげに思ひきこえさせたまへれば、いよいよわづらはしく思ひあへり。 |
「わたしもそのように思いますが、皇女たちが結婚するのは軽薄だと思えることもあり、また、身分が高いといっても、女は結婚すれば、悔しいことも嫌なこともおのずからあるものですが、ひとつはそれで悩んでいるのだが、頼みの親に先立たれ、庇護者たちと別れてから、自分の思い通りに独身を通して、世の中を生きてゆくのも、昔は人心が穏やかで、世間に認められないような身分違いの結婚などは、考えてもいけないと思い込んでいたようだが、今の世では、色めいて風儀のよくないことも、縁につながる者を通して、聞こえてくる。
昨日まで身分の高い親の家であがめられて大事にされた女も、今日は、平凡な身分の低い浮気男どもに浮名を立てられだまされて、死後に親の名を汚す例が多く聞くが、煎じ詰めれば、どちらにしろ同じことだ。
それぞれの身分に応じて、前世の因縁など知り難ければ、万事につけて、心配なのだ。すべてにおいて、良くも悪くも、親兄弟が決めた通りに、世の中を過ごすのは、それぞれの運不運であって、将来落ちぶれたとしても、自分の過ちとはいえないだろう。
時を経て、非常な幸せがあり、うれしいことになるときは、こうして結果は悪くはなかったと思えるときでも、ちょっと耳にした当座は、親に知られず、頼りにする人も許さないで、自分勝手に浮気をして、女の身にはこの上ない汚点と思われることがある。
平凡な臣下の者同士でも軽薄で好もしくないことをして、本人の気持ちを離れてことが運ばれるはずもないものだが、わが意に反して夫に会い、身の上が決められてしまうのは、軽率で女として日頃の心構えや態度が推察されるものだ。
(三の宮は、)妙に頼りない性格ではないかと思われる様子なので、誰彼の一存で仲介すべきではない。そのようなことが、世間に漏れ出るのは、あってはならない」
などと、出家の後のことまで、心配そうに案じているので、乳母たちはいよいよ厄介なことになった、と思うのであった。 |
|
| 34.10 朱雀院、婿候補者を批評 |
「今すこしものをも思ひ知りたまふほどまで見過ぐさむとこそは、年ごろ念じつるを、深き本意も遂げずなりぬべき心地のするに思ひもよほされてなむ。
かの六条の大殿は、げに、さりともものの心得て、うしろやすき方はこよなかりなむを、方々にあまたものせらるべき人びとを知るべきにもあらずかし。とてもかくても、人の心からなり。のどかにおちゐて、おほかたの世のためしとも、うしろやすき方は並びなくものせらるる人なり。さらで良ろしかるべき人、誰ればかりかはあらむ。
兵部卿宮、人柄はめやすしかし。同じき筋にて、異人とわきまへおとしむべきにはあらねど、あまりいたくなよびよしめくほどに、重き方おくれて、すこし軽びたるおぼえや進みにたらむ。なほ、さる人はいと頼もしげなくなむある。
また、大納言の朝臣の家司望むなる、さる方に、ものまめやかなるべきことにはあなれど、さすがにいかにぞや。さやうにおしなべたる際は、なほめざましくなむあるべき。
昔も、かうやうなる選びには、何事も人に異なるおぼえあるに、ことよりてこそありけれ。ただひとへに、またなく持ちゐむ方ばかりを、かしこきことに思ひ定めむは、いと飽かず口惜しかるべきわざになむ。
右衛門督の下にわぶなるよし、尚侍のものせられし、その人ばかりなむ、位など今すこしものめかしきほどになりなば、などかは、とも思ひ寄りぬべきを、まだ年いと若くて、むげに軽びたるほどなり。
高き心ざし深くて、やもめにて過ぐしつつ、いたくしづまり思ひ上がれるけしき、人には抜けて、才などもこともなく、つひには世のかためとなるべき人なれば、行く末も頼もしけれど、なほまたこのためにと思ひ果てむには、限りぞあるや」
と、よろづに思しわづらひたり。
かうやうにも思し寄らぬ姉宮たちをば、かけても聞こえ悩ましたまふ人もなし。あやしく、うちうちにのたまはする御ささめき言どもの、おのづからひろごりて、心を尽くす人びと多かりけり。 |
「もう少し、世間のことを知るまで待とうかと、このところ我慢していたが、出家も出来なくなるのではという懸念がするので、気が急いてしまうのだ。
あの六条の大殿は、本当に、そうは言っても、物の心得があり、安心できる点では格別だし、あちこちにいる大勢の婦人たちのことは考えなくてもいいだろう。ともかくも、女自身の心がけ次第です。悠揚迫らず、広く世の模範ともいうべき人で、信頼できることでは、比類ない方でしょう。これよりいい人は、他に誰がおりましょうか。
兵部卿の宮、人柄は無難で、同じ兄弟だから、他人扱いをして軽んじたくないが、あまりになよなよして風流がかっていて、重々しいところが足りないせいか、少し軽薄な印象が強いです。やはりそんな人は、頼りない気がします。
また、大納言の朝臣で、家司をしている者が、三の宮を望んでいるというが、まじめなんだろうが、さすがにどんなもんだろう。そのような並みの身分の者は、やはり不都合だろう。
昔もこのような婿選びには、何事にも人に優れた声望のある者に、靡いていくものだが、ただ自分ひとりを大事にしてくれるのがいいと思って夫を決めるのは、十分ではないし残念なことです。
右衛門督(柏木)が思いを寄せている由、尚侍が話していましたが、その人程度なら、いま少し位が上がったら、何の不自由なことがあろう。まだ年も若く、まるで貫禄がない。
高い理想を持っていて、ずっと独身を通していて、少しもあせらず、志を高く持っている様子は、抜きんでて、漢学の才も申し分なく、将来は天下の柱石にもなる人物だから、行く末頼もしいが、やはり三の宮の婿と決めてしまうにのはどうか」
と、あれこれ思い悩むのであった。
朱雀院が、これほど愛情を寄せていない姉宮たちには、一向に求愛する人もない。どうゆうわけか、朱雀院が内輪で話す内緒の事が自然と広がって、三の宮に求愛する人が多いのだった。 |
|
| 34.11 婿候補者たちの動静 |
太政大臣も、
「この衛門督の、今までひとりのみありて、皇女たちならずは得じと思へるを、かかる御定めども出で来たなる折に、さやうにもおもむけたてまつりて、召し寄せられたらむ時、いかばかりわがためにも面目ありてうれしからむ」
と、思しのたまひて、尚侍の君には、かの姉北の方して、伝へ申したまふなりけり。よろづ限りなき言の葉を尽くして奏せさせ、御けしき賜はらせたまふ。
兵部卿宮は、左大将の北の方を聞こえ外したまひて、聞きたまふらむところもあり、かたほならむことはと、選り過ぐしたまふに、いかがは御心の動かざらむ。限りなく思し焦られたり。
藤大納言は、年ごろ院の別当にて、親しく仕うまつりてさぶらひ馴れにたるを、御山籠もりしたまひなむ後、寄り所なく心細かるべきに、この宮の御後見にことよせて、顧みさせたまふべく、御けしき切に賜はりたまふなるべし。 |
太政大臣も、
「この衛門督(柏木)が、今までひとりを通して、皇女でなければ結婚しないと決心していたのを、このような婿選びの段階になったので、希望する旨帝に申し上げました、親しく婿としてお召しいただけたら、どんなにか面目が立ってうれしいだろう」
と思い申して、尚侍(朧月夜)に、姉君の太政大臣の北の方を通して求婚の意向伝えたのだった。限りない言葉を尽くして奏上し、帝の内意をお伺いした。
兵部卿宮は、左大臣の北の方になった玉鬘を得られなかったので、いい加減な相手ではなく、選り好みしていたので、どうして心の動かぬことがあろろうか、この上もなくやきもきしていた。
藤大納言という者は、年来朱雀院の別当をしていて、身辺に出入りしていて馴れていたので、院が山籠りした後の、寄る辺なく心細いだろうから、姫の世話役にこと寄せて、(帝の)庇護がいただけるように、切にお願いするのだった。 |
|
| 34.12 夕霧の心中 |
権中納言も、かかることどもを聞きたまふに、
「人伝てにもあらず、さばかりおもむけさせたまへりし御けしきを見たてまつりてしかば、おのづから便りにつけて、漏らし、聞こし召さることもあらば、よももて離れてはあらじかし」
と、心ときめきもしつべけれど、
「女君の今はとうちとけて頼みたまへるを、年ごろ、つらきにもことつけつべかりしほどだに、他ざまの心もなくて過ぐしてしを、あやにくに、今さらに立ち返り、にはかに物をや思はせきこえむ。なのめならずやむごとなき方にかかづらひなば、何ごとも思ふままならで、左右に安からずは、わが身も苦しくこそはあらめ」
など、もとより好き好きしからぬ心なれば、思ひしづめつつうち出でねど、さすがに他ざまに定まり果てたまはむも、いかにぞやおぼえて、耳はとまりけり。 |
権中納言(夕霧)もこのようなことを聞いたので、
「人づてではなく、直接院の意向をお聞きしていたので、自然に何かのときに、ふと漏らして、朱雀院の耳に入れば、まさかぜんぜん問題にならないことはないだろう」
と胸がときめいたりするが、
「雲井の雁が今は打ち解けて、こちらを頼りにしているので、長い間、つらかったときもそれを口実にせず、他の女に心を移すこともせず過ごしてきたが、いまさら昔に戻り、女君をにわかに物思いさせてよいものだろうか。並々ならぬ高貴な方と縁組したら、何事も思いのままにならず、気を遣って、自分が苦しくなるだけだ」
など、元より浮気っぽい男ではないので、心を抑えて口にはださないが、さすがに他の男に決まってしまうのは、どんなものか、聞き捨てにはできなかった。 |
|
| 34.13 朱雀院、使者を源氏のもとに遣わす |
春宮にも、かかることども聞こし召して、
「さし当たりたるただ今のことよりも、後の世の例ともなるべきことなるを、よく思し召しめぐらすべきことなり。人柄よろしとても、ただ人は限りあるを、なほ、しか思し立つことならば、かの六条院にこそ、親ざまに譲りきこえさせたまはめ」
となむ、わざとの御消息とはあらねど、御けしきありけるを、待ち聞かせたまひても、
「げに、さることなり。いとよく思しのたまはせたり」
と、いよいよ御心立たせたまひて、まづ、かの弁してぞ、かつがつ案内伝へきこえさせたまひける。 |
春宮がこのような事情をお聞きになって、
「さし当った当面のことより、後の世の例ともなることなので、よく考えてするべきことです。人柄がいいといっても、臣下のひとは限界があるので、それでも、そうしたいと思うのなら、あの六条院こそ、親代わりに預けていいのでは」
とのことで、改まったお便りということではなく、このような春宮のご意向を伝え聞いて、
「そうだ、いかにもその通りだ。よく言ってくれた」
と、(朱雀院は)わが意を得たりとばかり、まづあの左中弁に仲介を頼んで、とりあえずこちらの意向を伝えさせた。 |
|
| 34.14 源氏、承諾の意向を示す |
この宮の御こと、かく思しわづらふさまは、さきざきも皆聞きおきたまへれば、
「心苦しきことにもあなるかな。さはありとも、院の御世残りすくなしとて、ここにはまた、いくばく立ちおくれたてまつるべしとてか、その御後見の事をば受けとりきこえむ。げに、次第を過たぬにて、今しばしのほども残りとまる限りあらば、 おほかたにつけては、いづれの皇女たちをも、よそに聞き放ちたてまつるべきにもあらねど、またかく取り分きて聞きおきたてまつりてむをば、ことにこそは後見きこえめと思ふを、それだにいと不定なる世の定めなさなりや」
とのたまひて、
「まして、ひとつに頼まれたてまつるべき筋に、むつび馴れきこえむことは、いとなかなかに、うち続き世を去らむきざみ心苦しく、みづからのためにも浅からぬほだしになむあるべき。
中納言などは、年若く軽々しきやうなれど、行く先遠くて、人柄も、つひに朝廷の御後見ともなりぬべき生ひ先なめれば、さも思し寄らむに、などかこよなからむ。
されど、いといたくまめだちて、思ふ人定まりにてぞあめれば、それに憚らせたまふにやあらむ」
などのたまひて、みづからは思し離れたるさまなるを、弁は、おぼろけの御定めにもあらぬを、かくのたまへば、いとほしく、口惜しくも思ひて、うちうちに思し立ちにたるさまなど、詳しく聞こゆれば、さすがに、うち笑みつつ、
†「いとかなしくしたてまつりたまふ皇女なめれば、あながちにかく来し方行く先のたどりも深きなめりかしな。 ただ、内裏にこそたてまつりたまはめ。やむごとなきまづの人びとおはすといふことは、よしなきことなり。それにさはるべきことにもあらず。かならずさりとて、末の人疎かなるやうもなし。
故院の御時に、大后の、坊の初めの女御にて、いきまきたまひしかど、むげの末に参りたまへりし入道宮に、しばしは圧されたまひにきかし。
この皇女の御母女御こそは、かの宮の御はらからにものしたまひけめ。容貌も、さしつぎには、いとよしと言はれたまひし人なりしかば、いづ方につけても、この姫宮おしなべての際にはよもおはせじを」
など、いぶかしくは思ひきこえたまふべし。 |
源氏は、院がこの宮のことを色々心配をされているのを、前から聞いていたので、
「お気の毒なことです。そうはいっても、院の余生は残り少ないから、 わたしもどれだけ院の後、生き残れるとして、後見を引き受けられるのか。現に、年の順を間違えないならば、わたしが今しばし生き残るとして、どの皇女にしても他人事にして聞き流して放置できるものでもないが、とりわけ、このように(帝ご自身が)特別のご心配をしている方は特に後見しようと思うが、それでもわたしの自身のこの身がどうなるか分からぬのが世の無常である」
と仰せになって、
「ましてひとえに頼まれた者としては、親しく馴れて夫婦の関係になることは、かえって、(朱雀院に)続いて世を去るときは心苦しく、自分が往生する妨げにもなるだろう。
中納言(夕霧)などは、年も若く身分も低いようだが、将来ある身で、人柄も、最終的には朝廷のご後見にもなれる身なので、その申し出にはふさわしいでしょう。
しかし、すごくまじめな性格で、思い決めた人がいるので、それで遠慮しているのでしょう」
などと仰せになって、自分は身を引くような様子なので、弁は、院のたってのお願いなので、源氏にそのように言われると、残念で、口惜しく思い、院が内々にお決めになった様子なども、詳しく申し上げると、源氏はさすがに、微笑んで、
「大そう可愛がっている皇女なれば、あながちに、過去の先例や将来の例になることを詳しく調べることもなかろう。迷わず(冷泉)帝に差し上げればいいのだ。高貴な古参の女御がいるということは、心配の種にはならないだろう。それにこだわるべきでもない。必ず末に来た人がおろそかにされるということでもない。
故桐壺帝のときも、大后が、春宮の最初の女御で、古参として権勢を振るったが、ずっと後で入内した入道藤壷の宮に、しばしば圧倒されていました。
この皇女の母女御こそは、あの宮(藤壺入道)の妹君であった。容貌もあの宮に次いでよいといわれた人だから、どちらにしても、女三の宮は、よもや、並の器量であろうはずがないだろう」
など(源氏は)関心はお持ちのようだ。 |
|
| 34.15 歳末、女三の宮の裳着催す |
年も暮れぬ。朱雀院には、御心地なほおこたるさまにもおはしまさねば、よろづあわたたしく思し立ちて、御裳着のことは、思しいそぐさま、来し方行く先ありがたげなるまで、いつくしくののしる。
御しつらひは、柏殿の西面に、御帳、御几帳よりはじめて、ここの綾錦混ぜさせたまはず、唐土の后の飾りを思しやりて、うるはしくことことしく、かかやくばかり調へさせたまへり。
御腰結には、太政大臣をかねてより聞こえさせたまへりければ、ことことしくおはする人にて、参りにくく思しけれど、院の御言を昔より背き申したまはねば、参りたまふ。
今二所の大臣たち、その残り上達部などは、わりなき障りあるも、あながちにためらひ助けつつ参りたまふ。親王たち八人、殿上人はたさらにもいはず、内裏、春宮の残らず参り集ひて、いかめしき御いそぎの響きなり。
院の御こと、このたびこそとぢめなれと、帝、春宮をはじめたてまつりて、心苦しく聞こし召しつつ、蔵人所、納殿の唐物ども、多く奉らせたまへり。
六条院よりも、御とぶらひいとこちたし。贈り物ども、人びとの禄、尊者の大臣の御引出物など、かの院よりぞ奉らせたまひける。 |
年が暮れた。朱雀院は、病気勝ちの気分が快方に向かうこともなく、万事につけてあわただしく思い立って、三の宮の裳着の儀式を、急いでいる様子は、後にも先にも例がないほどで、大騒ぎであった。
準備の様子は、柏殿の西面に、御帳、御几帳をはじめ、国内の綾綿を混ぜず、唐土の后の飾りにならって、おごそかで、豪華に、輝くばかりしに整えさせたのだった。
腰結いには、太政大臣にかねてからお願いしていたので、大げさな人だったので、大役を果たせないと思っていたが、院の言葉に昔から背いたことがなく、役を果たすことになった。
あと二人の大臣たちや、残りの上達部などは、どうにもならぬ障りがある人も、何とか手当して参上した。親王たち八人、殿上人は言うに及ばず、内裏、春宮の関係者は残らず参上し、盛大な儀式は評判だった。
院の行事は、今回が最後となるだろうこともあり、帝や、春宮をはじめとして、たいへんおいたわしく思われて、蔵人所、納殿に収蔵された唐物を多く献上された。
六条の院からも、お祝いの品々がたくさんあった。贈り物、参加者への禄、大臣の大饗の引き出物など、源氏からのものであった。 |
|
| 34.16 秋好中宮、櫛を贈る |
中宮よりも、御装束、櫛の筥、心ことに調ぜさせたまひて、かの昔の御髪上の具、ゆゑあるさまに改め加へて、さすがに元の心ばへも失はず、それと見せて、その日の夕つ方、奉れさせたまふ。宮の権の亮、院の殿上にもさぶらふを御使にて、姫宮の御方に参らすべくのたまはせつれど、かかる言ぞ、中にありける。
(秋好む中宮の歌)「さしながら昔を今に伝ふれば
玉の小櫛ぞ神さびにける」
院、御覧じつけて、あはれに思し出でらるることもありけり。あえ物けしうはあらじと譲りきこえたまへるほど、げに、おもだたしき簪なれば、御返りも、昔のあはれをばさしおきて、
(朱雀院の歌)「さしつぎに見るものにもが万世を
黄楊の小櫛の神さぶるまで」
とぞ祝ひきこえたまへる。 |
秋好む中宮からも、装束、櫛の箱、特に心を込めて選んで、あの昔の髪上げの道具、趣ある様に改め手を加えて、さすがに元の感じを失わず、それと分かるように、その日の夕方、献上した。中宮職の権の亮で、院の殿上にも奉仕しているのを使いに立て、姫君の元にやったが、このような歌が中に入っていた。
「髪に挿して、昔から今日まで使っていましたので、
古く神さびてしまいました」
院はご覧になって、昔懐かしい気持ちがして、あやかりものとして、不似合いではなかろうとお譲りしたのだが、現に名誉な櫛なので返事も自分の懐旧の情は差し置いて、
「あなたに続いて姫君の幸運を見たいものです
千秋万歳と教える黄楊の小櫛が古くなるまで」
と、院はお祝いするのだった。 |
|
| 34.17 朱雀院、出家す |
御心地いと苦しきを念じつつ、思し起こして、この御いそぎ果てぬれば、三日過ぐして、つひに御髪下ろしたまふ。よろしきほどの人の上にてだに、今はとてさま変はるは悲しげなるわざなれば、まして、いとあはれげに御方々も思し惑ふ。
尚侍の君は、つとさぶらひたまひて、いみじく思し入りたるを、こしらへかねたまひて、
「子を思ふ道は限りありけり。かく思ひしみたまへる別れの堪へがたくもあるかな」
とて、御心乱れぬべけれど、あながちに御脇息にかかりたまひて、山の座主よりはじめて、御忌むことの阿闍梨三人さぶらひて、法服などたてまつるほど、この世を別れたまふ御作法、いみじく悲し。
今日は、世を思ひ澄ましたる僧たちなどだに、涙もえとどめねば、まして女宮たち、女御、更衣、ここらの男女、上下ゆすり満ちて泣きとよむに、いと心あわたたしう、かからで、静やかなる所に、やがて籠もるべく思しまうけける本意違ひて思し召さるるも、「ただ、この幼き宮にひかされて」と思しのたまはす。
内裏よりはじめたてまつりて、御とぶらひのしげさ、いとさらなり。 |
体の具合がひどく悪いのを、元気をだして、この裳着の儀式を終わると、三日して、ついに髪をおろしてしまった。並みの身分の者の場合でも、出家の姿になるのは、悲しいことだが、ましてお付きの后たちも悲しく思うのであった。
朧月夜の尚侍の君は、側に来て、ひどく思い込んでいるのを、帝はたいそう感に堪えて、
「子を思う親の心は限りがあるが、こうして相思う者が別れるのは堪えがたい」
とて、決心が乱れそうになり、無理に脇息に寄りかかって、天台座主をはじめ、授戒の阿闍梨三人いて、法服などを用意するのであったが、この世に別れを告げる儀式は、悲しいものであった。
今日は、世を捨てた僧たちさえ、涙をとどめられないので、まして女宮たち、女御、更衣、大勢の男女、上下の者たちこぞって皆泣き出すに、院は心あわただしく、こんなはずではなく、静かな所に、やがては籠もるべく本意に異なっているのと思われたが、「これもただこの幼い宮のことを思えばこそ」と思うのであった。
内裏よりはじまって、お見舞いの多さは、今さら言うまでもない。 |
|
| 34.18 源氏、朱雀院を見舞う |
六条院も、すこし御心地よろしくと聞きたてまつらせたまひて、参りたまふ。 御賜 ばりの 御封などこそ、皆同じごと、下りゐの帝と等しく定まりたまへれど、まことの太上天皇の儀式にはうけばりたまはず。世のもてなし思ひきこえたるさまなどは、心ことなれど、ことさらに削ぎたまひて、例の、ことことしからぬ御車にたてまつりて、上達部など、さるべき限り、車にてぞ仕うまつりたまへる。
院には、いみじく待ちよろこびきこえさせたまひて、苦しき御心地を思し強りて、御対面あり。うるはしきさまならず、ただおはします方に、御座よそひ加へて、入れたてまつりたまふ。
変はりたまへる御ありさま見たてまつりたまふに、来し方行く先暮れて、悲しくとめがたく思さるれば、とみにもえためらひたまはず。
「故院におくれたてまつりしころほひより、世の常なく思うたまへられしかば、この方の本意深く進みはべりにしを、心弱く思うたまへたゆたふことのみはべりつつ、つひにかく見たてまつりなしはべるまで、おくれたてまつりはべりぬる心のぬるさを、恥づかしく思うたまへらるるかな。
身にとりては、ことにもあるまじく思うたまへたちはべる折々あるを、さらにいと忍びがたきこと多かりぬべきわざにこそはべりけれ」
と、慰めがたく思したり。 |
六条院も、(朱雀院が)少し気分がよろしいと聞いて、お見舞いに来た。源氏の御封は、太上天皇と同じだったが、太上天皇並にことごとしくして儀礼を盛大にはされない。世間の評判や敬意などは、格別であるけれども、あえて贅を尽くさずわざと簡略にして、例によって大げさにならない程度の車で、上達部なども、しかるべき最小限の人数に限って、車でお供するのだった。
院は待っていたので大そう喜んで、気分の悪いのを無理に元気を出して、対面した。改まったことはせず、ただ普段座しているところに、もうひとつ源氏の座を設けて、招じ入れた。
朱雀院のすっかり変わってしまった僧形を見て、来し方行く末を暗澹と感じて、自ずから悲しさがあふれるのを抑えがたかった。
「故桐壺院にお別れした頃から、世の無常を感じておりましたので、出家の願望は深まっていましたが、心弱く思い切った決心ができず躊躇しておりまし たが、ついにこのようなお姿でお会いすることになり先を越されたわたしの不甲斐なさが恥ずかしく思っております。
わたしとしては、出家などそれほどことでもないと思い立ったことがしばしばありましたが、いざとなると、耐え難いことが多くあるものです」
といかにも残念そうである。 |
|
| 34.19 朱雀院と源氏、親しく語り合う |
院も、もの心細く思さるるに、え心強からず、うちしほれたまひつつ、いにしへ、今の御物語、いと弱げに聞こえさせたまひて、
「今日か明日かとおぼえはべりつつ、さすがにほど経ぬるを、うちたゆみて、深き本意の端にても遂げずなりなむこと、と思ひ起こしてなむ。
かくても残りの齢なくは、行なひの心ざしも叶ふまじけれど、まづ仮にても、のどめおきて、念仏をだにと思ひはべる。はかばかしからぬ身にても、世にながらふること、ただこの心ざしにひきとどめられたると、思うたまへ知られぬにしもあらぬを、今まで勤めなき怠りをだに、安からずなむ」
とて、思しおきてたるさまなど、詳しくのたまはするついでに、
「女皇女たちを、あまたうち捨てはべるなむ心苦しき。中にも、また思ひ譲る人なきをば、取り分きうしろめたく、見わづらひはべる」
とて、まほにはあらぬ御けしき、心苦しく見たてまつりたまふ。 |
院も、心細く思っていたのだが、源氏の話を聞いて我慢できずに、涙にくれて、昔のこと今の物語を、いかにも弱々し気に話すのであった。
「この命が今日か明日かと思いながらも、月日がたってしまうと、決心が緩んで出家の本懐も遂げずに終わるのではないかと思いを新たにしました。
こうして出家したところで、余命がいくらもなければ、仏道修行も果たせないので、とりあえず一次的にも意を決して、念仏しようと思っています。病気がちなこの身でも、今まで生きながらえているのは、出家の志があったから、と思い知り、今までお勤めを怠っていたことも気になります」
と仰せになって、日頃思っていたことを、詳しく語るついでに、
「皇女たちを、たくさん捨ててゆくのは心苦しいが、中でも、他に世話を頼める人のない方が、特別に気がかりでどうしたものかと気にしていたす」
と言って、はっきり仰らぬ様子が、とてもお気の毒に思われた。 |
|
| 34.20 内親王の結婚の必要性を説く |
御心のうちにも、さすがにゆかしき御ありさまなれば、思し過ぐしがたくて、
†「げに、ただ人よりも、かかる筋には、私ざまの御後見なきは、口惜しげなるわざになむはべりける。春宮かくておはしませば、いとかしこき末の世の儲けの君と、天の下の頼みどころに仰ぎきこえさするを。
まして、このことと聞こえ置かせたまはむことは、一事として疎かに軽め申したまふべきにはべらねば、さらに行く先のこと思し悩むべきにもはべらねど、げに、こと限りあれば、公けとなりたまひ、世の政事御心にかなふべしとは言ひながら、女の御ために、何ばかりのけざやかなる御心寄せあるべきにもはべらざりけり。
すべて、女の御ためには、さまざま真の御後見とすべきものは、なほさるべき筋に契りを交はし、えさらぬことに、育みきこゆる御護りめはべるなむ、うしろやすかるべきことにはべるを、なほ、しひて後の世の御疑ひ残るべくは、よろしきに思し選びて、忍びて、さるべき御預かりを定めおかせたまふべきになむはべなる」
と、奏したまふ。 |
源氏は、さすがに気にかかる姫君のことなので、聞き過ごすことができずに、
「実際、臣下の者より、このようなご身分のかたは、後見がなくては、いかにも心もとないです。春宮がこうして安心していられますのも、末世に過ぎた立派なお世継ぎだ、と天下の人々に頼み仰ぎ見られるているからです。
まして院がこのことと是非にも言い置かれることは、ひとつとしておろそかに軽んじらるべきではないのですが、さらに行く先のこと思い悩むべくもあらざることですが、事には限りがありますので、春宮が即位して、世の政治は思いのままになるとはいいながら、姫君(女三宮)のために手厚く世話ができるとも限りません。
すべて女のためには、何かにつけて世話役といえる者は必要で、それはやはり夫婦の契りを交わして、万全の庇護者として守り育ててくれるというのが、先々安心なのです。どうしてもあとあとご心配が残るようでしたら、適当な人を選んで、内々に、しかるべき人を世話役に決めておくのがよろしいかろうとと思います」
と奏上した。 |
|
| 34.21 源氏、結婚を承諾 |
「さやうに思ひ寄る事はべれど、それも難きことになむありける。いにしへの例を聞きはべるにも、世をたもつ盛りの皇女にだに、人を選びて、さるさまのことをしたまへるたぐひ多かりけり。
ましてかく、今はとこの世を離るる際にて、ことことしく思ふべきにもあらねど、また、しか捨つる中にも、捨てがたきことありて、さまざまに思ひわづらひはべるほどに、病は重りゆく。また取り返すべきにもあらぬ月日の過ぎゆけば、心あわたたしくなむ。
かたはらいたき譲りなれど、このいはけなき内親王、一人、分きて育み思して、さるべきよすがをも、御心に思し定めて預けたまへ、と聞こえまほしきを。
権中納言などの独りものしつるほどに、進み寄るべくこそありけれ。大臣に先ぜられて、ねたくおぼえはべる」
と聞こえたまふ。
「中納言の朝臣、まめやかなる方は、いとよく仕うまつりぬべくはべるを、何ごともまだ浅くて、たどり少なくこそはべらめ。
かたじけなくとも、深き心にて後見きこえさせはべらむに、おはします御蔭に変りては思されじを、ただ行く先短くて、仕うまつりさすことやはべらむと、疑はしき方のみなむ、心苦しくはべるべき」
と、受け引き申したまひつ。 |
「そのように考えたことはありましたが、それも難しいことです。昔の例を聞きましても、在位中で全盛を誇った帝の皇女もしかべき人を選んで、そういったことをなさる例は多かったのです。
まして、今はこの世を去る際で、ことごとしく思うべきにではないが、また、世を捨てるといっても、捨てがたいこともあり、さまざまに思い乱れる中で、病は重くなってゆく。取り返せない月日がたってゆくと、心もあわたたしくなるのです。
恐縮なお願いなのですが、この幼い内親王を、ひとり、取り分け目をかけてくださって、そのような頼りになる人を、決めてくださってお預けしたい、とお願いしたいのですが、
権中納言(夕霧)などがひとりでいたころに、申し出るべきであったのですが、太政大臣に先をこされまして、残念です」
と仰せになるのだった。
「中納言の朝臣は、実務的な面では、十分ご奉公できるでしょうが、何分まだ、経験が浅く、分別も足りないでしょう。
恐れ多いですが、わたしが真心込めてお世話すれば、院が在俗中と変わらないと姫君も思われるでしょうが、いかんせん、行き先の齢が短く、途中でお仕えできなくなるのではないかと、懸念されるの気がかりです」
と源氏は引き受ける由、仰せになるだった。 |
|
| 34.22 朱雀院の饗宴 |
夜に入りぬれば、主人の院方も、客人の上達部たちも、皆御前にて、御饗のこと、精進物にて、うるはしからず、なまめかしくせさせたまへり。院の御前に、 浅香の懸盤に御鉢など、昔に変はりて参るを、人びと、涙おし拭ひたまふ。あはれなる筋のことどもあれど、うるさければ書かず。
夜更けて帰りたまふ。禄ども、次々に賜ふ。別当大納言も御送りに参りたまふ。主人の院は、今日の雪にいとど御風邪加はりて、かき乱り悩ましく思さるれど、この宮の御事、聞こえ定めつるを、心やすく思しけり。 |
夜になると、主人側の上達部たちも、客側の上達部たちも、皆御前に列し、饗設けに精進料理が出され、格式ばらず優雅に整えられた。 御前には、浅香の懸盤に御鉢など、昔とすっかり変わった様子に、人々は涙をぬぐった。あわれを誘うことは他にもあったが、煩雑なので、ここに書きません。
夜も更けて、帰った。禄を次々に賜る。別当大納言もお見送りに出てくる。主人の院は、今日の雪に風邪が加わって、体調が思わしくなかったが、三の宮のことが、決まったので、気が安らいだ。 |
|
| 34.23 源氏、結婚承諾を煩悶す |
六条院は、なま心苦しう、さまざま思し乱る。
紫の上も、かかる御定めなむと、かねてもほの聞きたまひけれど、
「さしもあらじ。前斎院をも、ねむごろに聞こえたまふやうなりしかど、わざとしも思し遂げずなりにしを」
など思して、「さることもやある」とも問ひきこえたまはず、何心もなくておはするに、いとほしく、
「この事をいかに思さむ。わが心はつゆも変はるまじく、さることあらむにつけては、なかなかいとど深さこそまさらめ、見定めたまはざらむほど、いかに思ひ疑ひたまはむ」
など安からず思さる。
今の年ごろとなりては、ましてかたみに隔てきこえたまふことなく、あはれなる御仲なれば、しばし心に隔て残したることあらむもいぶせきを、その夜はうち休みて明かしたまひつ。 |
源氏は、心苦しく、いろいろ思い悩むのだった。
紫の上も、このような話があるとは、かねてから聞いていたが、
「そうはならないだろう。朝顔の君の前斎院のときも、熱心だったが、ことさら思いを遂げようとされなかったのだから」
などと、思って、「そのようなことがあるのですか」と問うこともせず、何心もないふりをしているので、いとおしくなり、
「このことをどう思うだろう。自分の気持は少しも変わらない、そんなことがあった場合には、かえって愛情が深まるだろう、それが見極められない間は、どれほど疑うことだろう」
などと、不安に思うのだった。
この年頃は、お互いに隠し立てすることもなく、とても仲のよい夫婦なので、一時的にせよ隠し事があると、気になってしょうがないが、その夜はそのまま休んだのだった。 |
|
| 34.24 源氏、紫の上に打ち明ける |
またの日、雪うち降り、空のけしきもものあはれに、過ぎにし方行く先の御物語聞こえ交はしたまふ。
「院の頼もしげなくなりたまひにたる、御とぶらひに参りて、あはれなることどものありつるかな。女三の宮の御ことを、いと捨てがたげに思して、しかしかなむのたまはせつけしかば、心苦しくて、え聞こえ否びずなりにしを、ことことしくぞ人は言ひなさむかし。
今は、さやうのことも初ひ初ひしく、すさまじく思ひなりにたれば、人伝てにけしきばませたまひしには、とかく逃れきこえしを、対面のついでに、心深きさまなることどもを、のたまひ続けしには、えすくすくしくも返さひ申さでなむ。
深き御山住みに移ろひたまはむほどにこそは、渡したてまつらめ。あぢきなくや思さるべき。いみじきことありとも、御ため、あるより変はることはさらにあるまじきを、心なおきたまひそよ。
かの御ためこそ、心苦しからめ。それもかたはならずもてなしてむ。誰も誰も、のどかにて過ぐしたまはば」
など聞こえたまふ。
はかなき御すさびごとをだに、めざましきものに思して、心やすからぬ御心ざまなれば、「いかが思さむ」と思すに、いとつれなくて、
「あはれなる御譲りにこそはあなれ。ここには、いかなる心をおきたてまつるべきにか。めざましく、かくてなど、咎めらるまじくは、 心やすくてもはべなむを、かの母女御の御方ざまにても、疎からず思し数まへてむや」
と、卑下したまふを、
「あまり、かう、うちとけたまふ御ゆるしも、いかなればと、うしろめたくこそあれ。 まことは、さだに思しゆるいて、われも 人も心得て、なだらかにもてなし過ぐしたまはば、いよいよあはれになむ。
ひがこと聞こえなどせむ人の言、聞き入れたまふな。すべて、世の人の口といふものなむ、誰が言ひ出づることともなく、おのづから人の仲らひなど、うちほほゆがみ、思はずなること出で来るものなるを、心ひとつにしづめて、ありさまに従ふなむよき。まだきに騒ぎて、あいなきもの怨みしたまふな」
と、いとよく教へきこえたまふ。 |
翌日、雪がふり空模様もしみじみとした日、過ぎた昔のこと行く末の物語などを語り合った。
「朱雀院がすっかり弱気になり、お見舞いに参りましたところ、心動かされることがありました。女三の宮のことを、見捨てて出家できないと思われて、あれこれと仰せになるので、お気の毒になり、お断りできなくなりました。人は大げさに取りざたするでしょう。
今はそのようなことは、恥ずかしく、関心がもてなくなっていますので、人伝に言って来たときには、とにかくお断りしたのだが 直接お会いして、深い親心で心配されて、縷々仰せになったので、すげなくお断りすることはできなかった。
院が山寺にお移りする頃に、姫君を六条院にお迎えすることになります。面白くないとお思いでしょうが、どんなことがあっても、あなたへの気持ちは変わらないから、宮を厭わないでください。
あの三の宮こそ、お気の毒な立場です。見苦しくなくお世話しよう。どちらも、大らかな気持ちで過ごしてくれれば」
などと源氏は仰せになる、
紫の上は、源氏の何でもないお遊びでももっての外と思って、腹を立てる性格なので、「どう思うだろう」と心配するが、案外平静で、
「お気の毒なご依頼ですね。わたしなどが、どんな心よからぬ思いなど、抱きましょうか。目障りな、などと、咎められない限りは、心安くしております。あの方の母女御様も、近い関係と思いますので」
と卑下されるので、
「あまり簡単に、お許しが出るのも、どうしたのかと心配になります。実際のところ、お互いが思いやって、こちらも先方もそれを心得て、穏やかにお付き合いして過ごしてくださったら、大層ありがたいのです。
人の告げ口など、お聞き入れなさらないこと。世間の人の噂というものは、誰が言い出すということもなく、夫婦仲は歪んで伝えられ、思ってもいないことが、起きるものです。わが胸ひとつに納めて、事の成り行きを見定めて処するのがいいのです。早まって騒ぎ立てて、つまらない嫉妬などしないことです」
とよく説諭するのであった。 |
|
| 34.25 紫の上の心中 |
|
|
| 34.26 源氏に若菜を献ず |
年も返りぬ。朱雀院には、姫宮、六条院に移ろひたまはむ御いそぎをしたまふ。聞こえたまへる人びと、いと口惜しく思し嘆く。内裏にも御心ばへありて、聞こえたまひけるほどに、かかる御定めを聞こし召して、思し止まりにけり。
さるは、今年ぞ四十になりたまひければ、御賀のこと、朝廷にも聞こし召し過ぐさず、世の中の営みにて、かねてより響くを、ことのわづらひ多くいかめしきことは、昔より好みたまはぬ御心にて、皆かへさひ申したまふ。
正月二十三日、子の日なるに、左大将殿の北の方、若菜参りたまふ。かねてけしきも漏らしたまはで、いといたく忍びて思しまうけたりければ、にはかにて、えいさめ返しきこえたまはず。忍びたれど、さばかりの御勢ひなれば、渡りたまふ御儀式など、いと響きことなり。
南の御殿の西の放出に御座>よそふ。屏風、壁代よりはじめ、新しく払ひしつらはれたり。うるはしく倚子などは立てず、御地敷四十枚、御 茵、脇息など、すべてその御具ども、いときよらにせさせたまへり。
螺鈿の御厨子 二具に、御衣筥四つ据ゑて、夏冬の御装束。香壺、薬の筥、御硯、ゆする坏、掻上の筥などやうのもの、うちうちきよらを尽くしたまへり。御插頭の台には、沈、紫檀を作り、めづらしきあやめを尽くし、同じき金をも、色使ひなしたる、心ばへあり、今めかしく。
尚侍の君、もののみやび深く、かどめきたまへる人にて、目馴れぬさまにしなしたまへる、おほかたのことをば、ことさらにことことしからぬほどなり。 |
年も改まった。朱雀院は、姫宮を六条院に移すための準備に余念がない。結婚を申し出た人々は残念がって嘆くのであった。冷泉帝も入内の申し出をしていたので、このような決定を聞いて、思いとどまった。
ところで源氏は今年で四十歳になるので、お祝いの儀式を、朝廷にあっても聞き逃すはずもなく、世を挙げての儀式として、かねてから準備していたが、大げさな儀式ばったことは昔から好まなかったので、みな辞退した。
正月二十三日、子の日になると、左大将の北の方(玉鬘)が若菜を献上に訪問された。事前の話もなく、内密に用意されていたので、源氏はあまりに急だったので 辞退するすることもできない。内々のことであったが、実家も夫も勢いがあったので、六条院に移る儀式など格別だった。
南の御殿の西側を開け放って、御座を用意した。屏風、壁代など新しくしつらえられた。格式張って椅子などは立てず、敷物四十枚、座布、脇息など、すべての用具を新しく作って用意した。
螺鈿の御厨子二つ、衣を入れる箱四つそろえて、四季のお召し物、香壺の箱と薬の箱、などなど、目立たぬところに善美を尽くしている。插頭の台は、沈、紫檀で作り、またとない華美を尽くしている、同じく金銀の色使いにも気を使って、今めかしい。
玉鬘の君は、風雅の趣が深く、才気のある方なので、新しい趣向でしているが、全体としては、大げさにならぬようにしている。 |
|
| 34.27 源氏、玉鬘と対面 |
人びと参りなどしたまひて、御座に出でたまふとて、尚侍の君に御対面あり。御心のうちには、いにしへ思し出づることもさまざまなりけむかし。
いと若くきよらにて、かく御賀などいふことは、ひが数へにやと、おぼゆるさまの、なまめかしく、人の親げなくおはしますを、めづらしくて年月隔てて見たてまつりたまふは、いと恥づかしけれど、なほけざやかなる隔てもなくて、御物語聞こえ交はしたまふ。
幼き君も、いとうつくしくてものしたまふ。尚侍の君は、うち続きても御覧ぜられじとのたまひけるを、大将、かかるついでにだに御覧ぜさせむとて、二人同じやうに、振分髪の何心なき直衣姿どもにておはす。
「過ぐる齢も、みづからの心にはことに思ひとがめられず、ただ昔ながらの若々しきありさまにて、改むることもなきを、かかる末々のもよほしになむ、なまはしたなきまで思ひ知らるる折もはべりける。
中納言のいつしかとまうけたなるを、ことことしく思ひ隔てて、まだ見せずかし。人よりことに、数へ取りたまひける今日の子の日こそ、なほうれたけれ。しばしは老を忘れてもはべるべきを」
と聞こえたまふ。 |
お祝いの人々が次々とやってきて、源氏が姿を現して席に着くと、玉鬘と対面があった。源氏は心の内で、昔のことを様々に思い出すのだった。
源氏は非常に若く、こんなお祝いなどというのは、間違いではないか、と思えるほど、優雅で、子供がいるなどとは思えない様子で、玉鬘は久しぶりに、お会いするので、とても恥ずかしかったが、片ぐるしい隔てもなく、率直にお話に興じるのだった。
連れてきた幼い子も、かわいらしく、玉鬘は二人もお目にかけたくないと言ったが、大将はこんな機会だからぜひお目にかけなさいと言って、二人同じように振分髪で無邪気な直衣姿であった。
「年をとることも、自分ではことさら気が付くこともなく、昔のままに若ぶって日々を過ごしている有様で、こんな孫たちに促されて自分の年を思い知らされる有様です。
夕霧が早々と子をなしたとのことですが、大そうにしてまだ見ていないのだ。誰より先に私の年を数えて今日の子の日に祝ってくれるのはつらいものです。しばしは老いを忘れていたい」
と仰せになる。 |
|
| 34.28 源氏、玉鬘と和歌を唱和 |
尚侍の君も、いとよくねびまさり、ものものしきけさへ添ひて、見るかひあるさましたまへり。
「若葉さす野辺の小松を引き連れて
もとの岩根を祈る今日かな」
と、せめておとなび聞こえたまふ。沈の折敷四つして、御若菜さまばかり参れり。御土器取りたまひて、
「小松原末の齢に引かれてや
野辺の若菜も年を摘むべき」
など聞こえ交はしたまひて、上達部あまた南の廂に着きたまふ。
式部卿宮は、参りにくく思しけれど、御消息ありけるに、かく親しき御仲らひにて、心あるやうならむも便なくて、日たけてぞ渡りたまへる。
大将のしたり顔にて、かかる御仲らひに、うけばりてものしたまふも、げに心やましげなるわざなめれど、御孫の君たちは、いづ方につけても、おり立ちて雑役したまふ。籠物四十枝、折櫃物四十。中納言をはじめたてまつりて、さるべき限り取り続きたまへり。御土器くだり、若菜の御羹参る。御前には、沈の懸盤四つ、 御坏どもなつかしく、今めきたるほどにせられたり。 |
玉鬘も年を重ねて、成熟して、風格さえでてきて、素晴らしく見ごたえのある風情であった。
(玉鬘の歌)「若葉を摘んで、子を連れて、
親元の千歳を祈る今日このごろです」
と努めて大人びて歌を詠むのだった。沈の盆を四つ用意し、若葉の吸物を召し上がる。お盆をとって、
(源氏の歌) 「小松原の生い先長い命にひかれて
野辺の若菜も長生きするのでしょうか」
などと詠み交わしているうちに、上達部がたくさん南の廂に着いた。
兵部卿宮は、来ずらかったが、案内があったので、このように親しい間柄で、何か邪推されるのもいやで、日が高くなってから、やってきた。
髭黒の大将が、得意顔で、このような源氏との関係であってみれば、胸を張って座を仕切っているのも、不愉快であろうが、孫たちは、どちらの関係でにしても、いそいそと雑用をするのだった。籠物四十枝、折櫃物四十、の献上があった。夕霧をはじめ、しかるべき人々が続いた。盃が下され若葉の吸物が給じられた。源氏の御前には、沈のお盆が四つ、食器類も好ましく今風のものであった。 |
|
| 34.29 管弦の遊び催す |
朱雀院の御薬のこと、なほたひらぎ果てたまはぬにより、楽人などは召さず。御笛など、太政大臣の、その方は整へたまひて、
「世の中に、この御賀よりまためづらしくきよら尽くすべきことあらじ」
とのたまひて、すぐれたる音の限りを、かねてより思しまうけたりければ、忍びやかに御遊びあり。
とりどりにたてまつる中に、和琴は、かの大臣の第一に秘したまひける御琴なり。さるものの上手の、心をとどめて弾き馴らしたまへる音、いと並びなきを、異人は掻きたてにくくしたまへば、衛門督の固く否ぶるを責めたまへば、げにいとおもしろく、をさをさ劣るまじく弾く。
「何ごとも、上手の嗣といひながら、かくしもえ継がぬわざぞかし」と、心にくくあはれに人びと思す。調べに従ひて、跡ある手ども、定まれる唐土の伝へどもは、なかなか尋ね知るべき方あらはなるを、心にまかせて、ただ掻き合はせたるすが掻きに、よろづの物の音調へられたるは、妙におもしろく、あやしきまで響く。
父大臣は、琴の緒もいと緩に張りて、いたう下して調べ、響き多く合はせてぞ掻き鳴らしたまふ。これは、いとわららかに昇る音の、なつかしく愛敬づきたるを、「いとかうしもは聞こえざりしを」と、親王たちも驚きたまふ。
琴は、兵部卿宮弾きたまふ。この御琴は、宜陽殿の御物にて、代々に第一の名ありし御琴を、故院の末つ方、一品宮の好みたまふことにて、賜はりたまへりけるを、この折のきよらを尽くしたまはむとするため、大臣の申し賜はりたまへる御伝へ伝へを思すに、いとあはれに、昔のことも恋しく思し出でらる。
親王も、酔ひ泣きえとどめたまはず,御けしきとりたまひて、琴は御前に譲りきこえさせたまふ。もののあはれにえ過ぐしたまはで、めづらしきもの一つばかり弾きたまふに、ことことしからねど、限りなくおもしろき夜の御遊びなり。
唱歌の人びと御階に召して、すぐれたる声の限り出だして、返り声になる。夜の更け行くままに、物の調べども、なつかしく変はりて、「青柳」遊びたまふほど、げに、ねぐらの鴬おどろきぬべく、いみじくおもしろし。私事のさまにしなしたまひて、禄など、いと警策にまうけられたりけり。 |
朱雀院の病気がまだすっかり治っていないので、楽人などは呼んでいない。だが笛など、太政大臣はその方面のことは用意されていて、
「世の中にこのお祝いほど珍しく清らかな催しはまたとあるまい」
と仰せになって、優れた音色を出すべく練習をしていたので、内輪の管弦の遊びが始まった。
皆それぞれの楽器を演奏するなかで、和琴はあの太政大臣が第一に秘蔵している琴がある。上手な人が心をこめて弾けば、並ぶものがないので、他の人は遠慮するので、柏木が固く辞退するのを源氏が催促されると、なるほど大そう上手に、父太政大臣にも劣らぬほどに弾くのだった。
「何事も名人の子といってもその技をこれほど継ぐことがことができようかと思われるほど、ゆかしく殊勝に思われた。調子に合わせて、楽譜などはっきりしている唐土伝来の曲は、習得の方法もわかるが、興にまかせて弾き合わせるするすががきなどは、他の音が調って妙に面白く、あやしい響きがする。
父大臣は、琴の弦も緩めに張って、調べも低く奏し、余韻を多く響かせて調子を合わせる。柏木の方は、大そう明るく高い調子で、親しみがあって愛嬌のある弾き方で、「これほど上手と思わなかった」と親王たちも驚いた。
琴は兵部卿の宮が弾いた。この琴は、宜陽殿に収納のもので、代々名器と言われていたものだが、故桐壷院の晩年に女一の宮が音楽が好きで頂戴したものだった。この度の祝賀に善美を尽くすため、太政大臣が申し出て賜ったものであった。その伝承の経緯を思うに、源氏はしみじみと、昔を思い出した。.
蛍兵部卿の宮も酔って泣いていた。(源氏の)気持を汲み取って、琴は源氏に譲られた。源氏は、興を催すまま、このままに見過ごすことができず、普段弾かない珍しい曲をひとつ弾いた。大げさではなく、限りなくおもしろい夜の遊びであった。
合唱の人々も階段に呼んで、すぐれた声の限りに謡うのだった。夜の更け行くままに、物の調べも。砕けたものに変わり、「青柳」を謡う頃になると、実際、ねぐらの鶯も驚いただろう大変興がのってきた。私的な催しでやったのだが、禄など驚くほどのものを賜ったのだった。 |
|
| 34.30 暁に玉鬘帰る |
暁に、尚侍君帰りたまふ。御贈り物などありけり。
「かう世を捨つるやうにて明かし暮らすほどに、年月の行方も知らず顔なるを、かう数へ知らせたまへるにつけては、心細くなむ。
時々は、老いやまさると見たまひ比べよかし。かく古めかしき身の所狭さに、思ふに従ひて対面なきも、いと口惜しくなむ」
など聞こえたまひて、あはれにもをかしくも、思ひ出できこえたまふことなきにしもあらねば、なかなかほのかにて、かく急ぎ渡りたまふを、いと飽かず口惜しくぞ思されける。
尚侍の君も、 まことの親をばさるべき契りばかりに思ひきこえたまひて、ありがたくこまかなりし御心ばへを、年月に添へて、かく世に住み果てたまふにつけても、おろかならず思ひきこえたまひけり。 |
暁になって、玉鬘は帰った。源氏から贈り物があった。
「こうして世を捨てたようにして暮らしていると、年月の経つのが分からなくなるが、こうしてお祝いされて年を知らされると、心細くなります。
時々は、どんなに年をとったか会いに来てください。こんな不自由な年寄りが、思うままにお会いできないのは、残念だ」
などと(源氏は)仰せになって、あわれにも懐かしくも、思い出すことがないではないので、かえって、こんなふうにちょっと顔を見せて、 急いで帰ってしまうのも、ひどく残念に思うのだった。
玉鬘も,実の父はただの親子の血縁のみと思うだけで、源氏のように細やかな心遣いを、髭黒の北の方として落ち着いてくると、並々ならずありがたく思うのだった。 |
|
| 34.31 女三の宮、六条院に降嫁 |
かくて、如月の十余日に、朱雀院の姫宮、六条院へ渡りたまふ。この院にも、御心まうけ世の常ならず。若菜参りし西の放出に御帳立てて、そなたの一、二の対、渡殿かけて、女房の局々まで、こまかにしつらひ磨かせたまへり。内裏に参りたまふ人の作法をまねびて、かの院よりも御調度など運ばる。渡りたまふ儀式、言へばさらなり。
御送りに、上達部などあまた参りたまふ。かの家司望みたまひし大納言も、やすからず思ひながらさぶらひたまふ。御車寄せたる所に、院渡りたまひて、下ろしたてまつりたまふなども、例には違ひたることどもなり。
ただ人におはすれば、よろづのこと限りありて、内裏参りにも似ず、婿の大君といはむにもこと違ひて、めづらしき御仲のあはひどもになむ。 |
こうして二月十余日、朱雀院の姫君は、六条院へお輿入れになった。六条院にあっては、その準備に並々ならず用意した。若菜のときの西の放出に几帳を立て、あちらの一二の対に渡殿をかけて、女房のたちの局々を細かに用意して磨かせた。内裏に参上する人の作法に準じて、朱雀院からも調度類を運んだ。お輿入れの儀式の盛大さは言うに及ばない。
供奉には、上達部など大勢が参列した。あの家司を望んだ大納言も、おもしろからずおもいながら、参列した。車寄せの場所には、源氏が出迎えて、下りるのを見守った。例のないことであった。
源氏は臣下であるので、何をするにも限界があり、内裏に入内するのでもなく、婿入りするとも違って、珍しい夫婦の関係であった。 |
|
| 34.32 結婚の儀盛大に催さる |
三日がほど、かの院よりも、主人の院方よりも、いかめしくめづらしきみやびを尽くしたまふ。
対の上も、ことに触れてただにも思されぬ世のありさまなり。げに、かかるにつけて、こよなく人に劣り消たるることもあるまじけれど、また並ぶ人なくならひたまひて、はなやかに生ひ先遠く、あなづりにくきけはひにて移ろひたまへるに、なまはしたなく思さるれど、つれなくのみもてなして、御渡りのほども、もろ心にはかなきこともし出でたまひて、いとらうたげなる御ありさまを、いとどありがたしと思ひきこえたまふ。
姫宮は、げに、まだいと小さく、片なりにおはするうちにも、いといはけなきけしきして、ひたみちに若びたまへり。
かの紫のゆかり尋ね取りたまへりし折思し出づるに、
「かれはされていふかひありしを、これは、いといはけなくのみ見えたまへば、よかめり。憎げにおしたちたることなどはあるまじかめり」
と思すものから、「いとあまりものの栄なき御さまかな」と見たてまつりたまふ。 |
三日ほどは、朱雀院側からも、六条院の方からも、威儀を正し雅を尽くした往来があった。
紫の上も、何かにつけ落ち着いていられない身の回りであった。いかにもこんなことになったからと言って、姫君などに引け目を感じて気落ちするような方でもないが、今までは競争相手もいなかったので、今回は華やかで年も若く侮りがたい姫が降嫁して、何やらいたたまれない気がするが、何気なくよそおって、降嫁のときも、心を合わせてこまごました雑用もこなし、いじらしい様子に、本当にありがたいと源氏は思うのだった。
姫君は、本当にまだ幼くて、大人になっておらず、あどけなく、まるで子供であった。
あの紫の上を引き取った頃を思い出し、
「あちらは、気が利いていて手ごたえがあったが、こちらは、幼いだけで、よかろう。紫の上に憎らし気に立ち向かうこともないだろう」
と思って、「拍子抜けしそうで張り合いのない様子だな」と見るのであった。 |
|
| 34.33 源氏、結婚を後悔 |
三日がほどは、夜離れなく渡りたまふを、年ごろさもならひたまはぬ心地に、忍ぶれど、なほものあはれなり。御衣どもなど、いよいよ薫きしめさせたまふものから、うち眺めてものしたまふけしき、いみじくらうたげにをかし。
「などて、よろづのことありとも、また人をば並べて見るべきぞ。あだあだしく、心弱くなりおきにけるわがおこたりに、かかることも出で来るぞかし。若けれど、中納言をばえ思しかけずなりぬめりしを」
と、われながらつらく思し続くるに、涙ぐまれて、
「今宵ばかりは、ことわりと許したまひてむな。これより後のとだえあらむこそ、身ながらも心づきなかるべけれ。また、さりとて、かの院に聞こし召さむことよ」
と、思ひ乱れたまへる御心のうち、苦しげなり。すこしほほ笑みて、
「みづからの御心ながらだに、え定めたまふまじかなるを、ましてことわりも何も、いづこにとまるべきにか」
と、いふかひなげにとりなしたまへば、恥づかしうさへおぼえたまひて、つらづゑをつきたまひて、寄り臥したまへれば、硯を引き寄せたまひて、
「目に近く移れば変はる世の中を
行く末遠く頼みけるかな」
古言など書き交ぜたまふを、取りて見たまひて、はかなき言なれど、げにと、ことわりにて、
「命こそ絶ゆとも絶えめ定めなき
世の常ならぬ仲の契りを」
とみにもえ渡りたまはぬを、
「いとかたはらいたきわざかな」
と、そそのかしきこえたまへば、なよよかにをかしきほどに、えならず匂ひて渡りたまふを、見出だしたまふも、いとただにはあらずかし。 |
三日ほどは、毎夜通って行くのを、紫の上は、日ごろ馴れないことに、堪えていたが、やはり物悲しい。源氏の衣などを、女房たち念入りに薫きこんでいるのを、物思いに沈んで眺めている様子は、いじらしくすごく可憐で美しい。
「どうして、どんな事情があるにせよ、またほかに妻をもうけることがあるのだろう。浮気っぽく情にもろくなっている私の失態から、このようなことが起こったのだ。若いけれど、夕霧を婿にとは思わなかったのに」
とわれながら情けなく思い続けて、涙ぐんで、源氏が、
「今宵だけは、無理もないと許してください。これ以後途絶えると我が身に愛想が尽きるでしょう。そして姫君を疎かにしたら、院はどうお聞きあそばすだろう」
と思い乱れる心のうちは苦しそうだ。(紫上は)少し微笑んで、
「源氏の君ご自身でさえ決めかねているのに、その是非をわたしなどが、どうして決められましょう」
と言うと、言ってもしょうがないという風にとりなすので、源氏は恥ずかしいくなって頬杖をついて、寄りかかっていたが、紫の上は硯を引き寄せて、
(紫上の歌)「眼のあたりに、変われば変わる私たちの仲でしたのに、
末長くとあてにしていました」
古歌などを混ぜて書くのを、源氏は手に取って見て、何でもないことだけれど、いかにももっともだと思って、
(源氏の歌)「無常の世に命は絶えるだろうが、
わたしたちの仲は絶えることがないでしょう」
源氏がすぐ帰らないのを、紫の上は、気を使って、
「本当に困ります」
と早く帰るようにそそのかせるが、しなやかで感じの良い衣装で、えも言われずよい香りが匂って、お見送りするにも平気ではいられないのだった。 |
|
| 34.34 源氏、紫の上、眠れぬ夜を過ごす |
|
|
| 34.35 六条院の女たち、紫の上に同情 |
かう人のただならず言ひ思ひたるも、聞きにくしと思して、
「かく、これかれあまたものしたまふめれど、御心にかなひて、今めかしくすぐれたる際にもあらずと、目馴れてさうざうしく思したりつるに、この宮のかく渡りたまへるこそ、めやすけれ。
なほ、童心の失せぬにやあらむ、われも睦びきこえてあらまほしきを、あいなく隔てあるさまに人びとやとりなさむとすらむ。ひとしきほど、劣りざまなど思ふ人にこそ、ただならず耳たつことも、おのづから出で来るわざなれ、かたじけなく、心苦しき御ことなめれば、いかで心おかれたてまつらじとなむ思ふ」
などのたまへば、中務、中将の君などやうの人びと、目をくはせつつ、
「あまりなる御思ひやりかな」
など言ふべし。昔は、ただならぬさまに使ひならしたまひし人どもなれど、年ごろはこの御方にさぶらひて、皆心寄せきこえたるなめり。
異御方々よりも、
「いかに思すらむ。もとより思ひ離れたる人びとは、なかなか心安きを」
など、おもむけつつ、とぶらひきこえたまふもあるを、
「かく推し量る人こそ、なかなか苦しけれ。世の中もいと常なきものを、などてかさのみは思ひ悩まむ」
など思す。
あまり久しき宵居も、例ならず人やとがめむと、心の鬼に思して、入りたまひぬれば、御衾参りぬれど、げにかたはらさびしき夜な夜な経にけるも、なほ、ただならぬ心地すれど、かの須磨の御別れの折などを思し出づれば、
「今はと、かけ離れたまひても、ただ同じ世のうちに聞きたてまつらましかばと、わが身までのことはうち置き、あたらしく悲しかりしありさまぞかし。さて、その紛れに、われも人も命堪へずなりなましかば、いふかひあらまし世かは」
と思し直す。
風うち吹きたる夜のけはひ冷やかにて、ふとも寝入られたまはぬを、近くさぶらふ人びと、あやしとや聞かむと、うちも身じろきたまはぬも、なほいと苦しげなり。夜深き鶏の声の聞こえたるも、ものあはれなり。 |
こうして女房たちがただならぬことを言っているのも、聞き苦しいと思い、
「このようにたくさんの女房たちがいて、御心にかなって、身分は高くなくても華やかな女たちも、目馴れてしまって物足りなく思っているので、この宮がこうして移ってくるのは良いことかもしれない。
いまだに幼心がぬけないのでしょう、わたしも仲良くしたい、困ったことにわたしとの間に溝があるように気を回す者がいるやもしれぬ。身分が同じとか、向こうが劣っているとか、聞き逃せないことも、あるでしょう、恐れ多くも、いたわしいくも、なんとかして親しくしていただきたいと思っております」
などと(紫上が)仰ると、中務、中将の君などの人々が、目配せしながら、
「あまりのお心遣いですこと」
などと言うのであった。昔は普通の用だけではなく、召人として親しくしていた人たちだが、長い間、紫の上に仕えていて、皆この人の味方なのだ。
六條院に住む他の女君たちからも、
「どんなお気持ちでしょう。元々寵愛の薄いわたしたちは、気が楽ですが」
と水を向けて、お慰めする人もおり、
「こんな想像をしくれる人の方が、厄介なのだ。無常の世の中であれば、どうしてそんな執着することがあろう」
などと紫の上は思うのだった。
あまり夜遅く起きているのも、いつもと違って咎める人もあるだろうし、悪いと思いながら、衾に入って寝ようとすると、実に寂しく夜を過ごすことになり、やはり平静ではいられず、あの須磨の別れの時を思い出すので、
「今は、離れていても、同じ世の中に無事でいると分かれば、自分のことはさておいても、源氏の身を惜しみ悲しむだろう。その時のどさくさに紛れて、わたしも源氏も死んでしまっていたら、言う甲斐もないもない二人の仲だったな」
と気を取り直すのだった。
風が吹いて夜の気配は冷ややかで、すぐには寝られず、近くにいる女房たちに、あやしがられまいと、身じろぎもせず、やはりつらそうであった。夜深くなって、鶏の声が聞こえたのも、あわれを感じた。 |
|
| 34.36 源氏、夢に紫の上を見る |
わざとつらしとにはあらねど、かやうに思ひ乱れたまふけにや、かの御夢に見えたまひければ、うちおどろきたまひて、いかにと心騒がしたまふに、鶏の音待ち出でたまへれば、夜深きも知らず顔に、急ぎ出でたまふ。いといはけなき御ありさまなれば、乳母たち近くさぶらひけり。
妻戸押し開けて出でたまふを、見たてまつり送る。明けぐれの空に、雪の光見えておぼつかなし。名残までとまれる御匂ひ、
「闇はあやなし」
と独りごたる。
雪は所々消え残りたるが、いと白き庭の、ふとけぢめ見えわかれぬほどなるに、
「なほ残れる雪」
と忍びやかに口ずさびたまひつつ、御格子うち叩きたまふも、久しくかかることなかりつるならひに、人びとも空寝をしつつ、やや待たせたてまつりて、引き上げたり。
「こよなく久しかりつるに、身も冷えにけるは。懼ぢきこゆる心のおろかならぬにこそあめれ。さるは、罪もなしや」
とて、御衣ひきやりなどしたまふに、すこし濡れたる御単衣の袖をひき隠して、うらもなくなつかしきものから、うちとけてはたあらぬ御用意など、いと恥づかしげにをかし。
「限りなき人と聞こゆれど、難かめる世を」
と、思し比べらる。
よろづいにしへのことを思し出でつつ、とけがたき御けしきを怨みきこえたまひて、その日は暮らしたまひつれば、え渡りたまはで、寝殿には御消息を聞こえたまふ。
「今朝の雪に心地あやまりて、いと悩ましくはべれば、心安き方にためらひはべる」
とあり。御乳母、
「さ聞こえさせはべりぬ」
とばかり、言葉に聞こえたり。
「異なることなの御返りや」と思す。「院に聞こし召さむこともいとほし。このころばかりつくろはむ」と思せど、えさもあらぬを、「さは思ひしことぞかし。あな苦し」と、みづから思ひ続けたまふ。
女君も、「思ひやりなき御心かな」と、苦しがりたまふ。 |
源氏はことさらつらいとは思っていなかったが、それほど思い乱れていたのだろうか、紫の上が夢に現れたので、驚いて胸騒ぎがして、鶏の鳴き声が聞こえたので、夜深い刻も知らぬ顔に、急いで起きて出かけた。姫宮はまだ幼いので、乳母たちが近くに侍っていた。
妻戸を開けて源氏が出てゆくのを、乳母は見送った。まだすっかり明けない空に、雪の光が映えてまだよく見えない。衣に焚いた香の残りが漂い、
「闇はあやなし」
と乳母は独り言を言う。
雪は所々に消え残っているが、真っ白くなった庭に、その境が分からぬほどで、
「なお残れる雪」
と(源氏は)小さく口ずさみながら、格子を叩いたが、久しくこのようなことがなかったので、女房たちもゆっくり空寝していて、やや待たせてから、ゆっくりと格子を上げた。
「ずいぶん待たされたから、身体が冷えてしまった。早く帰って来たのは、あなたを怖がるきもちが並々ならぬからでしょう。私の罪ではないですよ」
と言って,衣を引き上げたりすると、紫の上は少し濡れた単衣の袖を隠して、すなおで優しいものの、決して打ち解けた気配は見せない様子に、とても気が引けるほど風情があった。
「これほどの身分が高い人は、いないだろう」
とつい姫宮と思い比べてみる。
源氏もいろいろと昔のことを思い出して、紫の上が仲直りしようとしないのを恨んで、その日は過ごしたので、出かけず、姫宮のいる寝殿に文を出すのだった。
「今朝の雪に気分がすぐれず、ひどく悩ましいので、気楽な所で養生します」
とあった。乳母は、
このように言ってきました。
とだけ口上で言ったきりだった。
「そっけない返事だな」と思うのだった。「院のお耳に入っても困るし、この時期だけはつくろわなければ」と思うが、そうもできないので、「そう思った通りだ。ああ困った」と思い続けるのだった。
紫の上を、「察しの悪い人だな」と苦々しく思うのだった。 |
|
| 34.37 源氏、女三の宮と和歌を贈答 |
今朝は、例のやうに大殿籠もり起きさせたまひて、宮の御方に御文たてまつれたまふ。ことに恥づかしげもなき御さまなれど、御筆などひきつくろひて、白き紙に、
「中道を隔つるほどはなけれども
心乱るる今朝のあは雪」
梅に付けたまへり。人召して、
「西の渡殿よりたてまつらせよ」
とのたまふ。やがて見出だして、端近くおはします。白き御衣どもを着たまひて、花をまさぐりたまひつつ、「友待つ雪」のほのかに残れる上に、うち散り添ふ空を眺めたまへり。鴬の若やかに、近き紅梅の末にうち鳴きたるを、
「袖こそ匂へ」
と花をひき隠して、御簾押し上げて眺めたまへるさま、夢にも、かかる人の親にて、重き位と見えたまはず、若うなまめかしき御さまなり。
御返り、すこしほど経る心地すれば、入りたまひて、女君に花見せたてまつりたまふ。
「花といはば、かくこそ匂はまほしけれな。桜に移しては、また塵ばかりも心分くる方なくやあらまし」
などのたまふ。
「これも、あまた移ろはぬほど、目とまるにやあらむ。花の盛りに並べて見ばや」
などのたまふに、御返りあり。紅の薄様に、あざやかにおし包まれたるを、胸つぶれて、御手のいと若きを、
「しばし見せたてまつらであらばや。隔つとはなけれど、あはあはしきやうならむは、人のほどかたじけなし」
と思すに、ひき隠したまはむも心おきたまふべければ、かたそば広げたまへるを、しりめに見おこせて添ひ臥したまへり。
「はかなくてうはの空にぞ消えぬべき
風にただよふ春のあは雪」
御手、げにいと若く幼げなり。「さばかりのほどになりぬる人は、いとかくはおはせぬものを」と、目とまれど、見ぬやうに紛らはして、止みたまひぬ。
異人の上ならば、「さこそあれ」などは、忍びて聞こえたまふべけれど、いとほしくて、ただ、
「心安くを、思ひなしたまへ」
とのみ聞こえたまふ。 |
今朝は、いつものように紫の上のところで朝寝して起きると、姫宮の所に文を送った。格別気をつかうような方ではないが、筆は十分選んで、白い紙に、
(源氏の歌)「わたしたちの間を邪魔するほどではありませんが
今朝の淡雪には心乱れ気分もすぐれない」
梅の枝につけて、人を呼び、
「西の渡殿に届けよ」
と仰せになり、そのまま外を眺めて、廂の端にいる。白い衣を重ね着して、梅の花に触って、「友待つ雪」にほのかに残る雪の上に降ってくる雪の空を眺めていた。鶯が近くの紅梅の枝の先に止まって鳴いているのを、
「袖こそ匂え」
と梅の花を袖に隠して、御簾を押し上げて眺めている姿は、夢にも、人の子の親で、高い位にある人とは見えず、若々しく魅力的であった。
返事は少しかかるだろうと思い、奥に入って、女君(紫上)に梅の花を見せるのだった。
「花というからには、これくらいは匂ってほしいものだ。この香を桜に移したら、もう誰も他の花は少しも見る気もしないだろう」
などと仰せになる。
「梅の花も、目移りしない時だから、目立つのだ。桜の盛りと比べて見たいものだ」
などと言っているうちに、返事があった。紅の薄様に、鮮やかに包まれているのを、ドキリとして、筆跡がいかにも幼いのを
「当分の間、紫の上には見せたくないものだ。隠し立てするつもりはないが、軽々しく人に見せては、恐れ多いご身分だから」
と思い、隠してしまえば、紫の上も気になるだろうし、ほんの片端を広げて見えるようにして、紫の上は、横目で見て横になっている。
(女三宮の歌)「お越しにならないので、頼りなく春の淡雪のように
空に消えてしまいそうです」
筆跡は、なるほど未熟で幼いのであった。「あの年頃になれば、これほどに幼くはないのだが」と、つい目がいってしまうが、見ないふりをしていた。
ほかの女なら、源氏も「こんな字だ」と、こっそり仰せになったろうが、お気の毒で、ただ、
「気の張らない方だとお思いください」
とだけ仰せになった。 |
|
| 34.38 源氏、昼に宮の方に出向く |
今日は、宮の御方に昼渡りたまふ。心ことにうち化粧じたまへる御ありさま、今見たてまつる女房などは、まして見るかひありと思ひきこゆらむかし。御乳母などやうの老いしらへる人びとぞ、
「いでや。この御ありさま一所こそめでたけれ、めざましきことはありなむかし」
と、うち混ぜて思ふもありける。
女宮は、いとらうたげに幼きさまにて、御しつらひなどのことことしく、よだけくうるはしきに、みづからは何心もなく、ものはかなき御ほどにて、いと御衣がちに、身もなく、あえかなり。ことに恥ぢなどもしたまはず、ただ稚児の面嫌ひせぬ心地して、心安くうつくしきさましたまへり。
「院の帝は、ををしくすくよかなる方の御才などこそ、心もとなくおはしますと、世人思ひためれ、をかしき筋、なまめきゆゑゆゑしき方は、人にまさりたまへるを、などて、かくおいらかに生ほしたてたまひけむ。さるは、いと御心とどめたまへる皇女と聞きしを」
と思ふも、なま口惜しけれど、憎からず見たてまつりたまふ。
ただ聞こえたまふままに、なよなよとなびきたまひて、御いらへなどをも、おぼえたまひけることは、いはけなくうちのたまひ出でて、え見放たず見えたまふ。
昔の心ならましかば、うたて心劣りせましを、今は、世の中を皆さまざまに思ひなだらめて、 「とあるもかかるも、際離るることは難きものなりけり。 とりどりにこそ多うはありけれ、よその思ひは、いとあらまほしきほどなりかし」
と思すに、差し並び目離れず見たてまつりたまへる年ごろよりも、対の上の御ありさまぞなほありがたく、「われながらも生ほしたてけり」と思す。一夜のほど、朝の間も、恋しくおぼつかなく、いとどしき御心ざしのまさるを、「などかくおぼゆらむ」と、ゆゆしきまでなむ。 |
今日は姫宮の所へ昼に行かれた。念入りに身づくろいをして、初めて見る女房たちは、素晴らしい見る甲斐があったと思うことだろう。乳母たちの中でも年取った者たちのなかには、
「さあどうだろう。このお方は、すばらしいが、困ったことが今に起きるだろう」
と中には心配する者もいた。
女宮は、とてもかわいらしく幼く、大層な飾り付けにかこまれて、事々しく麗しいのだが、ご自身は何心もなく、何もわからない様子で、衣装にうずまった小さな体が弱弱しい。源氏にも物おじせずただ稚児の人見知りしない様子が、気が張らずかわいい感じでいらっしゃる。
「院の帝は男らしく理屈っぽい学問は、弱いと世間では言われているが、風情のある方面、優雅で趣のある方面では人に勝っているので、どうしてこうおっとりとお育てになったのだろう。それにしても、ずいぶんかわいがってお育てしたとお聞きしたが」
と思うも、なんとなく残念だが、憎からず可愛いと思うのであった。
姫君はただ言われるままに、従順に従って、返事なども、ふと心に浮かんだことは、あどけなくそのまま言うので、とても見捨てられないと思うのだった。
昔の源氏だったら、嫌になっていたろうが、今は世の中は十人十色だと思い定めて、「いろいろな女がいるが、とび抜けて立派なのはいないものだ。それぞれ特徴のある女はいて、傍から見れば、正室として 立派なものだ、と見るだろう」
と思うと、二人一緒に離れず暮らしてきた年ごろは、紫の上の有様は立派で、「われながらよく育てたものだ」と思う。一夜隔てた朝も、恋しい逢いたいと思い、ひどく気持ちが傾くのも、「どうしてこんな気持ちになるのだろう」と、尋常な気持ではない。 |
|
| 34.39 朱雀院、紫の上に手紙を贈る |
院の帝は、月のうちに御寺に移ろひたまひぬ。この院に、あはれなる御消息ども聞こえたまふ。姫宮の御ことはさらなり。
わづらはしく、いかに聞くところやなど、憚りたまふことなくて、ともかくも、ただ御心にかけてもてなしたまふべくぞ、たびたび聞こえたまひける。されど、あはれにうしろめたく、幼くおはするを思ひきこえたまひけり。
紫の上にも、御消息ことにあり。
「幼き人の、心地なきさまにて移ろひものすらむを、罪なく思しゆるして、後見たまへ。尋ねたまふべきゆゑもやあらむとぞ。
背きにしこの世に残る心こそ
入る山路のほだしなりけれ
闇をえはるけで聞こゆるも、をこがましくや」
とあり。大殿も見たまひて、
「あはれなる御消息を。かしこまり聞こえたまへ」
とて、御使にも、女房して、土器さし出でさせたまひて、しひさせたまふ。「御返りはいかが」など、聞こえにくく思したれど、ことことしくおもしろかるべき折のことならねば、ただ心をのべて、
「背く世のうしろめたくはさりがたき
ほだしをしひてかけな離れそ」
などやうにぞあめりし。
女の装束に、細長添へてかづけたまふ。御手などのいとめでたきを、院御覧じて、何ごともいと恥づかしげなめるあたりに、いはけなくて見えたまふらむこと、いと心苦しう思したり。 |
院の帝は、二月中に寺にお移りになった。院は源氏に、情のこもった文を事細かに送ってきた。姫君のことはもちろんだ。
院がどんな風に思うだろうかなどと気にすることなく、源氏の気持ちのままに姫君をもてなしてくれることを、たびたび文を出すのだった。それでも、院は後ろ髪をひかれる思いで女三の宮の幼いことを心配されるのだった。
紫の上にも院から文があった。
「幼くて何のわきまえもなく参らせましたのを、罪なき者とお許しいただき、お世話してください。考慮されるべき血のつながりもあります。
(朱雀院の歌)世を背いたけれど、子を思う心こそ
出家の山路の妨げになります。
親の心の闇を晴らせずに申し上げるのも、おこがましいのですが」
とあり、源氏もそれを見て、
「お気の毒な文ですね。つつしんでお受けしますと、ご返事なさい」
とて、文遣いにも、女房に、盃をさし出させて、何杯もふるまわせた。「ご返事はどうしたものか」と書きづらく思ったが、大げさに趣向を凝らす時でもないので、ただ思ったことを述べて、
(紫上の歌)「背いた世にご心配がありましたら
それを強いて振り捨てないでくださいませ」
このように書いたのだった。
使者には、女の装束に細長を添えてかずけた。筆跡の見事なのを院はご覧になって、何事も大そう優れていらっしゃる方のそばに、ひどく幼く見えるのをやって、心苦しく思うのであった。 |
|
| 34.40 源氏、朧月夜に今なお執心 |
今はとて、女御、更衣たちなど、おのがじし別れたまふも、あはれなることなむ多かりける。
尚侍の君は、故后の宮のおはしましし二条の宮にぞ住みたまふ。姫宮の御ことをおきては、この御ことをなむかへりみがちに、帝も思したりける。尼になりなむと思したれど、
「かかるきほひには、慕ふやうに心あわたたしく」
と諌めたまひて、やうやう仏の御ことなどいそがせたまふ。
六条の大殿は、あはれに飽かずのみ思してやみにし御あたりなれば、年ごろも忘れがたく、
「いかならむ折に対面あらむ。今一たびあひ見て、その世のことも聞こえまほしく」のみ思しわたるを、かたみに世の聞き耳も憚りたまふべき身のほどに、いとほしげなりし世の騷ぎなども思し出でらるれば、よろづにつつみ過ぐしたまひけるを、かうのどやかになりたまひて、世の中を思ひしづまりたまふらむころほひの御ありさま、いよいよゆかしく、心もとなければ、あるまじきこととは思しながら、おほかたの御とぶらひにことつけて、あはれなるさまに常に聞こえたまふ。
若々しかるべき御あはひならねば、御返りも時々につけて聞こえ交はしたまふ。昔よりもこよなくうち具し、ととのひ果てにたる御けはひを見たまふにも、なほ忍びがたくて、昔の「中納言の君のもとにも、心深きことどもを常にのたまふ。 |
いよいよこれまでというので、上皇付きの女御、更衣たちは、それぞれ別れて実家に帰るのも、あわれなことが多い。
尚侍(朧月夜)の君は故后の宮が住んでいた二条の宮に住むことになった。姫宮はさておいて、このことを帝は後ろ髪が引かれるように思うのだった。尚侍は尼になろうと思ったが、
「競うように尼になるのは気ぜわしいから止めなさい」
と諫められて、ぼつぼつ持仏などの準備をするのだった。
六条の大殿(源氏)は、飽かぬ思いのまま別れた人なので、年来忘れることができず、
「どんな機会に会えるだろう。今一度逢って、過ぎ去った昔のことも話がしたいものだ」としきりと思っていたが、互いに世間の噂を気にする身であれば、世間を騒がせて気の毒だった頃を思い出し、万事につけ慎んで過ごしてきたのだが、こうして暇な時ができてくると、世の中の移り変わりに静かに思いを致すことが多くなり、いよいよ懐かしく会ってみたい思いがつのり、やってはいけないこととは思いながらも、通例のお見舞いにかこつけて、心をこめた文を頻繁に出すのであった。
若い恋仲のような間柄ではなかったのだが、返事もその時々に応じて交わしていた。朧月夜が昔よりも相応に成長し備わって円熟した様子を見るにつけ、我慢できず、昔の中納言の君の女房のもとに、切々たる思いを仰るのだった。 |
|
| 34.41 和泉前司に手引きを依頼 |
かの人の兄なる和泉の前の守を召し寄せて、若々しく、いにしへに返りて語らひたまふ。
「人伝てならで、物越しに聞こえ知らすべきことなむある。さりぬべく聞こえなびかして、いみじく忍びて参らむ。
今は、さやうのありきも所狭き身のほどに、おぼろけならず忍ぶれば、そこにもまた人には漏らしたまはじと思ふに、かたみにうしろやすくなむ」
とのたまふ。尚侍の君、
「いでや。世の中を思ひ知るにつけても、昔よりつらき御心を、ここら思ひつめつる年ごろの果てに、あはれに悲しき御ことをさし置きて、いかなる昔語りをか聞こえむ。
げに、人は漏り聞かぬやうありとも、心の問はむこそいと恥づかしかるべけれ」
とうち嘆きたまひつつ、なほ、さらにあるまじきよしをのみ聞こゆ。 |
中納言の君の兄の前の和泉の守を呼び寄せて、若々しく、昔に返って語り合った。
「人伝ではなく、物越しに直接言いたいことがある。そう先方に伝えて、忍んで参りたいのだ。
この節はそのような忍び歩きもむつかしい身分故、格別大事な秘密だから、あなたもまた人に漏らすことはないだろうし、お互いに安心だろう」
と仰せになる尚侍の君は、
「さあ、男女の仲を知るにつけて、昔からつれないみ心をさんざん味わってきましたので、朱雀院の出家という悲しいことをさしおいて、どんな昔話を語ろうというのでしょう。
実に、人は漏れ聞かぬとしても、自分の心に問うてみれば恥ずかしいではないか」
と嘆きつつ、やはり、逢うことはできないと、言ってくるのであった。 |
|
| 34.42 紫の上に虚偽を言って出かける |
「いにしへ、わりなかりし世にだに、心交はしたまはぬことにもあらざりしを。 げに、背きたまひぬる御ためうしろめたきやうにはあれど、 あらざりしことにもあらねば、今しもけざやかにきよまはりて、立ちにしわが名、今さらに取り返したまふべきにや」
と思し起こして、この信太の森を道のしるべにて参うでたまふ。女君には、
「東の院にものする常陸の君の、日ごろわづらひて久しくなりにけるを、もの騒がしき紛れに訪らはねば、いとほしくてなむ。昼など、けざやかに渡らむも便なきを、夜の間に忍びてとなむ、思ひはべる。人にもかくとも知らせじ」
と聞こえたまひて、いといたく心懸想したまふを、例はさしも見えたまはぬあたりを、あやし、と見たまひて、思ひ合はせたまふこともあれど、姫宮の御事の後は、何事も、いと過ぎぬる方のやうにはあらず、すこし隔つる心添ひて、見知らぬやうにておはす。 |
「昔、逢瀬も難しかった頃に、心を交わしたことがあったのだから。いかにも、出家された朱雀院に不実のようではあるが、昔なかったことでもないのだから、今更きっぱりと潔白にしたところで、いったん立った浮名を取り消したりすることができようか」
と思い直して、信田の森の和泉前司を案内にして行った。紫の上には、
「東の院にいる常陸の宮の君(末摘花)が、久しく患っていて、何かと忙しいのに紛れて見舞いに行っていないので、かわいそうで。昼など人目に立って出かけるのもよくないので、夜に忍んでおこうと思う。誰にも知らせないで」
と仰せになって、入念に身づくろいをするのを、いつもはそれ程気にする方ではないので、紫の上はあやしいと見て、思い当たることもあるので、姫君の後では、何事も昔のようではなく、少し隔たった気持ちがあって、素知らぬふりをするのであった。 |
|
| 34.43 源氏、朧月夜を訪問 |
その日は、寝殿へも渡りたまはで、御文書き交はしたまふ。薫き物などに心を入れて暮らしたまふ。
宵過ぐして、睦ましき人の限り、四、五人ばかり、網代車の、昔おぼえてやつれたるにて出でたまふ。和泉守して、御消息聞こえたまふ。かく渡りおはしましたるよし、ささめき聞こゆれば、驚きたまひて、
「あやしく。いかやうに聞こえたるにか」
とむつかりたまへど、
「をかしやかにて帰したてまつらむに、いと便なうはべらむ」
とて、あながちに思ひめぐらして、入れたてまつる。御とぶらひなど聞こえたまひて、
「ただここもとに、物越しにても。さらに昔のあるまじき心などは、残らずなりにけるを」
と、わりなく聞こえたまへば、いたく嘆く嘆くゐざり出でたまへり。
「さればよ。なほ、気近さは」
と、かつ思さる。かたみに、おぼろけならぬ御みじろきなれば、あはれも少なからず。東の対なりけり。辰巳の方の廂に据ゑたてまつりて、御障子のしりばかりは固めたれば、
「いと若やかなる心地もするかな。年月の積もりをも、紛れなく数へらるる心ならひに、かくおぼめかしきは、いみじうつらくこそ」
と怨みきこえたまふ。 |
当日は、姫君の寝殿にもゆかず、文をかわしただけであった。薫物に熱中して 暮らした。
夜の更けるのを待って、気心の知れた四、五人ばかり、網代車の、昔のようにやつれたのに乗って出かけた。和泉の守に案内を乞う。こうして来ています由、取り次ぎの女房がそっとお伝えすると、驚いて、
「おかしいこと。何とお伝えしたのか」
と機嫌を悪くしたが、
「対面せず、色めいたあしらいでお帰しするのは、具合が悪いでしょう」
と(女房が)少し無理な理由をこじつけて、招じ入れた。お見舞いなどの挨拶があって、
「もう少しここまで寄って来てください、物越しでもいいですから。昔のような乱暴なことはしませんから」
と(源氏が)切々とお願いすると、ため息をつきながら、いざり寄った。
「案の定だ、言うことをすぐ聞いてくれる」
と思うのだった。お互いに身体の動きは知っているので、感慨も浅からぬものがある。対面の場所は、東の対であった。辰巳の方の廂に座を設えて、障子の端は掛け金がかけてあので、
「若者のような気持ちがします。あれ以来の年月の数も、はっきり数えられる程に慕っていましたのに、このような他人行儀はつらいです」
と恨みがましく仰せになる。 |
|
| 34.44 朧月夜と一夜を過ごす |
夜いたく更けゆく。玉藻に遊ぶ鴛鴦の声々など、あはれに聞こえて、しめじめと人目少なき宮の内のありさまも、「 さも移りゆく世かな」と思し続くるに、平中がまねならねど、まことに涙もろになむ。昔に変はりて、おとなおとなしくは聞こえたまふものから、「これをかくてや」と、引き動かしたまふ。
「年月をなかに隔てて逢坂の
さも塞きがたく落つる涙か」
女、
「涙のみ塞きとめがたき清水にて
ゆき逢ふ道ははやく絶えにき」
などかけ離れきこえたまへど、いにしへを思し出づるも、
†「誰れにより、多うはさるいみじきこともありし世の騷ぎぞは」と思ひ出でたまふに、「げに、今一たびの対面はありもすべかりけり」
と、思し弱るも、もとよりづしやかなるところはおはせざりし人の、年ごろは、さまざまに世の中を思ひ知り、来し方を悔しく、公私のことに触れつつ、数もなく思し集めて、 いといたく過ぐしたまひにたれど、昔おぼえたる御対面に、その世のことも遠からぬ心地して、え心強くももてなしたまはず。
なほ、らうらうじく、若うなつかしくて、一方ならぬ世のつつましさをもあはれをも、思ひ乱れて、嘆きがちにてものしたまふけしきなど、今始めたらむよりもめづらしくあはれにて、明けゆくもいと口惜しくて、出でたまはむ空もなし。 |
夜がすっかり更けてゆく。玉藻に遊ぶ鴛鴦の声もあわれに聞こえて、しめやかな宮の邸の内の様子も、「往時と比べかくも移り行く世の中よ」と感慨を催し、平中のまねではないが、まことに涙がこぼれる。源氏は昔と違って年配者らしく話をするので、「この隔てをこうしよう」と障子を動かすのだった。
(源氏の歌)「年月を隔ててやっと逢うのに
こんな隔てがあっては涙が堰き止めがたくとまりません」
女、
「わたしも涙が堰き止められません
お逢いする道は途絶えました」
など受け付けないのだが、昔のことを思い出すと、
「誰のせいで、世間を大騒ぎさせたあんな大変なことがあったのか」と思い出すと、「今一度逢ってもいいか」
と決心が鈍るのだが、元来が重々しいところのない方なので、年来様々に世の中のことも知り、来し方を悔しく思い、公にも私ことにもいろいろな経験をし、たくさんのことを物思いもして、大そう自重して暮らしてきたが、昔の逢瀬も、その頃のことが遠からぬことに思えて、いつまでも強い態度でいられないかった。
昔に変わらず、朧月夜は、洗練された物越しで、若々しく愛嬌があり、ひとかたならぬ世間へのつつましさもあわれも、思い乱れて、嘆き勝ちな物腰も、今初めて逢った場合よりも新鮮で、夜が明けるのも惜しくて、帰る気配もない。 |
|
| 34.45 源氏、和歌を詠み交して出る |
朝ぼらけのただならぬ空に、百千鳥の声もいとうららかなり。花は皆散り過ぎて、名残かすめる梢の浅緑なる木立、「昔、藤の宴したまひし、このころのことなりけりかし」と思し出づる、年月の積もりにけるほども、その折のこと、かき続けあはれに思さる。
中納言の君、見たてまつり送るとて、妻戸押し開けたるに、立ち返りたまひて、
「この藤よ。いかに染めけむ色にか。なほ、えならぬ心添ふ匂ひにこそ。いかでか、この蔭をば立ち離るべき」
と、わりなく出でがてに思しやすらひたり。
山際よりさし出づる日のはなやかなるにさしあひ、目もかかやく心地する御さまの、こよなくねび加はりたまへる御けはひなどを、めづらしくほど経ても見たてまつるは、まして世の常ならずおぼゆれば、
†「さる方にても、などか見たてまつり過ぐしたまはざらむ。御宮仕へにも限りありて、際ことに離れたまふこともなかりしを。故宮の、よろづに心を尽くしたまひ、よからぬ世の騷ぎに、軽々しき御名さへ響きてやみにしよ」
など思ひ出でらる。名残多く残りぬらむ御物語のとぢめには、げに残りあらせまほしきわざなめるを、 御身、心にえまかせたまふまじく、ここらの人目もいと恐ろしくつつましければ、やうやうさし上がり行くに、心あわたたしくて、廊の戸に御車さし寄せたる人びとも、忍びて声づくりきこゆ。
人召して、かの咲きかかりたる花、一枝折らせたまへり。
「沈みしも忘れぬものをこりずまに
身も投げつべき宿の藤波」
いといたく思しわづらひて、寄りゐたまへるを、心苦しう見たてまつる。女君も、今さらにいとつつましく、さまざまに思ひ乱れたまへるに、花の蔭は、なほなつかしくて、
「身を投げむ淵もまことの淵ならで
かけじやさらにこりずまの波」
いと若やかなる御振る舞ひを、心ながらもゆるさぬことに思しながら、 関守の固からぬたゆみにや、いとよく語らひおきて出でたまふ。
そのかみも、人よりこよなく心とどめて思うたまへりし御心ざしながら、はつかにてやみにし御仲らひには、いかでかはあはれも少なからむ。 |
朝がほんのり明けてゆく得も言われぬ空に、百千鳥の声のさえずりもうららかだ。花は皆散ってしまって、名残りをかすかに残す梢の浅緑の木立、「昔、右大臣が藤の宴をしたのも、このころだった」と思い出すのも、年月が積もってそのころのことを次々に思い出される。
中納言の君が、お見送りするため、妻戸を開けると、(源氏は)振り返って、
「この藤の花よ。どうやって染めたものか。それに、得も言われぬこの匂い。どうしてこの花の蔭を立去ることができよう」
と帰りにくそうにしている。
山際からさし出る日のはなやかな光に照らされて、目もかがやく心地する源氏の姿の、程よく年齢を重ねた気配を、久しぶりに見るのは、いよいよ世の常の人とも思えない心地がして、
「どうして、あの方と結婚して、ご一緒にならなかったのか。宮仕えにも限りがあって、立后できたわけではなかった。亡き弘徽殿がなにかと心を砕いて、とんでもない騒動になって、軽々しく浮名を立てて終わってしまった」
などと(中納言の君は)思うのだった。名残りが尽きず語りつくせない物語の終わりはなく、ご身分柄心にまかせた振舞いができない身で、大勢の人目に触れるのも恐ろしく、用心しなければならない、日がようやく登り、あわただしく、廊下の戸に車を寄せてお供の者たちが、声を作って急がせた。
人を呼んで、あの咲きかけたは花を一枝折らせて、
(源氏の歌)「かって須磨の浦に沈んだ身が懲りもせず
この宿の見事な藤波に身を投げそうです」
源氏が大そう思い悩んで、高欄に寄りかかっているのを、中納言の君はお気の毒そうに見ている。女君も、今になってつつましく、様々に思い乱れ、美しい花の蔭には、なお身を寄せたくて、
(朧月夜の歌)「身をなげるのも本当の淵ではないから
しょう懲りもなく関わりたくない」
若者のような振舞いを、自分でも許さぬことに思いながらも、きびしい関守がいないためか、またの逢瀬を約束してお帰りになる。
あの当時も、誰よりも限りなくご執心だったのに、わずかばかりで途絶えた二人の仲だから、どうして恋の思いのつのらぬことがあろうか。 |
|
| 34.46 源氏、自邸に帰る |
いみじく忍び入りたまへる御寝くたれのさまを待ち受けて、女君、さばかりならむと心得たまへれど、おぼめかしくもてなしておはす。 なかなかうちふすべなどしたまへらむよりも、心苦しく、「など、かくしも見放ちたまへらむ」と思さるれば、ありしよりけに深き契りをのみ、長き世をかけて聞こえたまふ。
尚侍の君の御ことも、また漏らすべきならねど、いにしへのことも知りたまへれば、まほにはあらねど、
「物越しに、はつかなりつる対面なむ、残りある心地する。いかで人目咎めあるまじくもて隠しては、今一たびも」
と、語らひきこえたまふ。うち笑ひて、
「今めかしくもなり返る御ありさまかな。昔を今に改め加へたまふほど、中空なる身のため苦しく」
とて、さすがに涙ぐみたまへるまみの、いとらうたげに見ゆるに、
「かう心安からぬ御けしきこそ苦しけれ。ただおいらかに引き抓みなどして、教へたまへ。隔てあるべくも、ならはしきこえぬを、思はずにこそなりにける御心なれ」
とて、よろづに御心とりたまふほどに、何ごともえ残したまはずなりぬめり。
宮の御方にも、とみにえ渡りたまはず、こしらへきこえつつおはします。姫宮は、何とも思したらぬを、御後見どもぞ安からず聞こえける。 わづらはしうなど見えたまふけしきならば、そなたもまして心苦しかるべきを、おいらかにうつくしきもて遊びぐさに思ひきこえたまへり。 |
しっかり人目を忍んで自邸に帰ったが、寝乱れた髪をみて、待ち受けていた紫の上は、そんなことだろうと得心したが、気づかないふりをしていた。かえってやきもちをやいたりするよりも、つらくて、「どうしてかまってくれないのか」と思えば、前よりも一層深い約束を来世にかけてお仰せになるのだった。
尚侍の君のことも、漏らすべきではないが、昔のことも知っているので、ありのままではないが、
「物越しにほんの少し会いましたが、物足りない気がする。どうかして人目に立たないように隠れて、今一度お会いしたいのだが」
と語るのであった。紫の上は笑って、
「ずいぶん若返ったようですね。昔の恋を今にむし返すのですから、どっちつかずの寄る辺ないわたしはつらいです」
とて、さすがに涙ぐんでいる目元が、可愛らしい、
「これ程ご機嫌が悪いのでは困ります。ただ素直に、抓ったりして、教えてください。他人行儀に思ったことも言わないのは、今までなかったことで、心外ですね」
とて、何やかやとご機嫌をとっているうちに、すっかり白状したようである。
姫宮の方にも、すぐにも出かけられないで、紫の上をあれこれとなだめるのだった。姫宮は何とも思っていなかったが、付き添いの乳母たちが不平がましく言うのだった。三の宮が面倒な方であったら、そちらも気を遣わなければならならなかったが、素直で可愛らしい人形のように思った。 |
|
| 34.47 明石姫君、懐妊して退出 |
桐壺の御方はうちはへえまかでたまはず。御暇のありがたければ、心安くならひたまへる若き御心に、いと苦しくのみ思したり。
夏ごろ、悩ましくしたまふを、とみにも許しきこえたまはねば、いとわりなしと思す。めづらしきさまの御心地にぞありける。まだいとあえかなる御ほどに、いとゆゆしくぞ、誰れも誰れも思すらむかし。からうしてまかでたまへり。
姫宮のおはします御殿の東面に、御方はしつらひたり。明石の御方、今は御身に添ひて、出で入りたまふも、あらまほしき御宿世なりかし。 |
桐壷の御方(明石の女御)は、里帰りが許されず、暇をとれそうもないので、今まで気軽に過ごしていた若い心には、大そうつらかった。
夏ごろ、気分が悪くなったのだが、東宮からすぐにはお許しがでず、仕方ないとあきらめていた。しかしそれはおめでたであった。まだごく幼いので、大へんなことになったと、まわりは誰もが心配した。このようにして内裏を罷り出た。
姫宮(女三宮)のいる御殿の東面に、お部屋を設えた。明石の君は、娘の女御に付き添って出入りするのであった。理想的な宿世であった。 |
|
| 34.48 紫の上、女三の宮に挨拶を申し出る |
対の上、こなたに渡りて対面したまふついでに、
「姫宮にも、中の戸開けて聞こえむ。かねてよりもさやうに思ひしかど、ついでなきにはつつましきを、かかる折に聞こえ馴れなば、心安くなむあるべき」
と、大殿に聞こえたまへば、うち笑みて、
「思ふやうなるべき御語らひにこそはあなれ。いと幼げにものしたまふめるを、うしろやすく教へなしたまへかし」
と、許しきこえたまふ。宮よりも、明石の君の恥づかしげにて交じらむを思せば、御髪すましひきつくろひておはする、たぐひあらじと見えたまへり。
大殿は、宮の御方に渡りたまひて、
「夕方、かの対にはべる人の、淑景舎に対面せむとて出で立つ。そのついでに、近づききこえさせまほしげにものすめるを、許して語らひたまへ。心などはいとよき人なり。まだ若々しくて、御遊びがたきにもつきなからずなむ」
など、聞こえたまふ。
「恥づかしうこそはあらめ。何ごとをか聞こえむ」
と、おいらかにのたまふ。
「人のいらへは、ことにしたがひてこそは思し出でめ。隔て置きてなもてなしたまひそ」
と、こまかに教へきこえたまふ。「御仲うるはしくて過ぐしたまへ」と思す。
あまりに何心もなき御ありさまを見あらはされむも、恥づかしくあぢきなけれど、さのたまはむを、「心隔てむもあいなし」と、思すなりけり。 |
紫の上は、明石の女御にお会いする折りに、
「姫宮(女三宮)にも、中の戸を開けてご挨拶しよう。かねてからそう思っていましたが、その機会がなかったので遠慮していました。親しくなれば、安心ですから」
と源氏に申し上げると、笑って、
「そうあってほしいものだ。大へん子供ぽいので、後の心配がないように教えてやってくれ」
と許可が出る。宮よりも、明石の君がこちらが恥ずかしくなるような立派な様子を思えば、御髪を洗い身づくろいをした姿は、類なきものと見えた。
源氏は、宮の方に行かれて、
「夕方、あちらの対にいる紫の上が、明石の女御にお会いするので、その折にこちらにお近づきの挨拶をしたいといっておりますので、お許しくださって語らってください。気持ちのよい方です。まだ若いのでお相手としても不似合いではないです」
などと仰せになる。
「恥ずかしいですね。何を話したらいいのでしょう」
と姫宮がおっとりして言う。
「お返事は、相手の言うことに応じてなさるとよいのです。他人行事なおあしらいはなさいますな」
と細かに教えて、仰せになるのだった。「二人は仲良くしてほしい」と思う。
あまりに無邪気な姫宮の有様を、紫の上に見られるのも、恥ずかしいが、申し出に対して、「止めたりして、隔てを作るのもよくない」と思った。 |
|
| 34.49 紫の上の手習い歌 |
対には、かく出で立ちなどしたまふものから、
「我より上の人やはあるべき。身のほどなるものはかなきさまを、見えおきたてまつりたるばかりこそあらめ」
など、思ひ続けられて、うち眺めたまふ。手習などするにも、おのづから古言も、もの思はしき筋にのみ書かるるを、「さらば、わが身には思ふことありけり」と、身ながらぞ思し知らるる。
院、渡りたまひて、宮、女御の君などの御さまどもを、「うつくしうもおはするかな」と、さまざま見たてまつりたまへる御目うつしには、年ごろ目馴れたまへる人の、おぼろけならむが、いとかくおどろかるべきにもあらぬを、「なほ、たぐひなくこそは」と見たまふ。ありがたきことなりかし。
あるべき限り、気高う恥づかしげにととのひたるに添ひて、はなやかに今めかしく、にほひなまめきたるさまざまの香りも、取りあつめ、めでたき盛りに見えたまふ。去年より今年はまさり、昨日より今日はめづらしく、常に目馴れぬさまのしたまへるを、「いかでかくしもありけむ」と思す。
うちとけたりつる御手習を、硯の下にさし入れたまへれど、見つけたまひて、引き返し見たまふ。手などの、 いとわざとも上手と見えで、らうらうじくうつくしげに書きたまへり。
「身に近く秋や来ぬらむ見るままに
青葉の山も移ろひにけり」
とある所に、目とどめたまひて、
「水鳥の青羽は色も変はらぬを
萩の下こそけしきことなれ」
など書き添へつつすさびたまふ。ことに触れて、心苦しき御けしきの、下にはおのづから漏りつつ見ゆるを、ことなく消ちたまへるも、ありがたくあはれに思さる 。
今宵は、いづ方にも御暇ありぬべければ、かの忍び所に、いとわりなくて、出でたまひにけり。「いとあるまじきこと」と、いみじく思し返すにも、かなはざりけり。 |
(紫の上は)対面の準備をしながら、
「わたしより、寵愛をより受けている人があるだろうか、自分の頼りない境遇を知るだけのことではないか」
などと、思い続けられ、物思いに沈んでいる。手習いをするにも、おのずから、古い歌も、もの思わしい歌のみ書いているのを、「そうだ、わたしには、思い悩むことがあったのだ」と自分の身ながら思い知る。
源氏が行かれて、宮や女御の君などの有様を、「それぞれに可愛らしくていらっしゃる」と、さまざま見たてるその目から見て、年頃見慣れている方が、並みの器量であったなら、これほども心を打つこともないだろうが、「やはり比類ない美しさだ」と見る。世間にめったにない美しさだ。
この上なく気高くこちらが気が引けるほど美しく整って、華やかで今風で、なまめかしい色香があり、総じて素晴らしい女盛りであった。去年より今年が勝り、昨日より今日がよりいっそう美しく常に真新しく、「どうしてこうも美しいのだろう」と思うのだった。
思いのままに書いた手習いを、硯の下に差し入れたが、源氏が見つけて、繰り返しご覧になる。格別上手な筆跡でというわけではないが、巧みで美しく書いている。
(紫上の歌)「秋が近くにきたのかしら、
青葉の山も紅葉に変わってしまった、わたしも飽きられるのかしら」
とある歌に目を止めて、
(源氏の歌)「水鳥の青い羽根の色は変わりませんよ、
萩の下葉のように変わるのはあなたでは」
などと書き添えた。(紫上は)何かにつけておいたわしい気色なのが、自ずからわかるのだが、それを事も無げに振舞っているのも、実に立派であった。
今宵は、どちらの方も行かなくてよさそうなので、あの朧月夜の処へ出かけた。「決して、あってはならないこと」と重々思うのだが、思い返すことはできなかった。 |
|
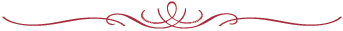
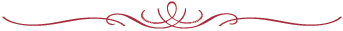
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)