| 【30、藤袴(ふじばかま)11節】 |
| 2-1 |
長雨の時節 |
| 2-2 |
宮中の宿直所、光る源氏と頭中将 |
| 2-3 |
左馬頭、藤式部丞ら女性談義に加わる |
| 2-4 |
女性論、左馬頭の結論 |
| 2-5 |
女性体験談(左馬頭、嫉妬深い女の物語) |
| 2-6 |
左馬頭の体験談(浮気な女の物語) |
| 2-7 |
頭中将の体験談(常夏の女の物語) |
| 2-8 |
式部丞の体験談(畏れ多い女の物語) |
| 2-9 |
天気晴れる |
| 2-10 |
紀伊守邸への方違へ |
| 2-11 |
空蝉の寝所に忍び込む |
| 2-12 |
それから数日後 |
|
| あらすじは次の通り。 |
入内を前にして玉鬘はひとり悩んでいた。源氏の懸想はやまず、また、入内したとしても帝寵の厚い秋好中宮と弘徽殿の女御と争うことは考えられなかった。父、内大臣は源氏の顔色を窺うばかりで、誰ひとり悩みを打ち明ける相手もいない。そんな折、親切心を装った夕霧にまで言い寄られる。
源氏の元に立ち寄った夕霧は玉鬘との関係を追及する。なんとかかわす源氏だが、玉鬘への思いを断つ時が来たことを悟る。
玉鬘の入内が十月と決まり、内大臣の使者として柏木が訪れる。かつての懸想人である実の弟柏木を玉鬘はそっけなくあしらう。多くの求婚者から手紙が届くが、玉鬘は蛍の宮にだけ短い返事を書いた。 |
| 30.1 玉鬘、内侍出仕前の不安 |
尚侍()の御宮仕へのことを、誰れも誰れもそそのかしたまふも、いかならむ、親と思ひきこゆる人の御心だに、うちとくまじき世なりければ、ましてさやうの交じらひにつけて、心よりほかに便なきこともあらば、 中宮も女御も、方がたにつけて心おきたまはば、はしたなからむに、わが身はかくはかなきさまにて、いづ方にも深く思ひとどめられたてまつれるほどもなく、浅きおぼえにて、ただならず思ひ言ひ、いかで人笑へなるさまに見聞きなさむと、うけひたまふ人びとも多く、とかくにつけて、やすからぬことのみありぬべきを、もの思し知るまじきほどにしあらねば、さまざまに思ほし乱れ、人知れずもの嘆かし。
「さりとて、かかるありさまも悪しきことはなけれど、この大臣の御心ばへの、むつかしく心づきなきも、いかなるついでにかは、もて離れて、人の推し量るべかめる筋を、心きよくもあり果つべき。
まことの父大臣も、この殿の思さむところ、憚りたまひて、うけばりてとり放ち、けざやぎたまふべきことにもあらねば、なほとてもかくても、見苦しう、かけかけしきありさまにて、心を悩まし、人にもて騒がるべき身なめり」
と、なかなかこの親尋ねきこえたまひて後は、ことに憚りたまふけしきもなき大臣の君の御もてなしを取り加へつつ、人知れずなむ嘆かしかりける。
思ふことを、まほならずとも、片端にてもうちかすめつべき女親もおはせず、いづ方もいづ方も、いと恥づかしげに、いとうるはしき御さまどもには、何ごとをかは、さなむ、かくなむとも聞こえ分きたまはむ。世の人に似ぬ身のありさまを、うち眺めつつ、夕暮の空のあはれげなるけしきを、端近うて見出だしたまへるさま、いとをかし。 |
尚侍()への宮仕えを、どちらの親もが勧めるのだが、どうしたものか、親と頼む人さえ気を許せない状態で、まして宮中に出仕するにつけても、意に反してやむをえないことが生じて、中宮も弘徽殿女御にも、それぞれの機嫌を損じることになったりしたら、宮中にはいられなくなるだろうし、わたしの弱い立場では、どちらの親にも深い縁がある訳でもなく、世間からも軽く見られて、大きく取り沙汰され、どうかして物笑いの種にしようと恨んでいる人も多くいるだろうから、何かにつけ、不愉快なことばかり起こるに違いなく、分別のない年頃でもないので、様々に思い乱れ人知れず嘆くのであった。
「そうかといって、このままでいるのも悪くはないが、源氏の御心ばえは、煩わしいく厭わしいので、どんな機会に、関係を断ち切って、世間の邪推に対して、潔白を示すことができようか。
実の父大臣も、源氏の思惑を憚って、堂々と引き取ってきちんと自分の娘として扱うことはないであろうから、やはりいずれにするにしても、見苦しく、男に思いを掛けられて、心を悩まし、世間にも騒がれることになるのだろう」
と、かえって実の親に晴れて面会してからは、取り分け遠慮する様子もない源氏の態度も加わって、玉鬘は人知れず嘆くのであった。
悩みを、全部ではなくても少しでも相談できる女親もいなくて、どちらの親御にしたって、実に立派で近づきにくい方々ゆえ、何をああだこうだと話したりすることができようか。世間の人にはあまりないない身のありさまを、思い嘆きながら、夕暮れの空が迫ってくるなかで、廂の間の端近くに座って眺めている姿はなんとも美しい。 |
|
| 30.2 夕霧、源氏の使者として玉鬘を訪問 |
薄き鈍色の御衣、なつかしきほどにやつれて、例に変はりたる色あひにしも、容貌はいとはなやかにもてはやされておはするを、御前なる人びとは、うち笑みて見たてまつるに、宰相中将、同じ色の、今すこしこまやかなる直衣姿にて、纓巻きたまへる姿しも、またいとなまめかしくきよらにておはしたり。
初めより、ものまめやかに心寄せきこえたまへば、もて離れて疎々しきさまには、もてなしたまはざりしならひに、今、あらざりけりとて、こよなく変はらむもうたてあれば、なほ御簾に几帳添へたる御対面は、人伝てならでありけり。殿の御消息にて、内裏より仰せ言あるさま、やがてこの君のうけたまはりたまへるなりけり。
†御返り、おほどかなるものから、いとめやすく聞こえなしたまふけはひの、 らうらうじくなつかしきにつけても、かの野分の朝の御朝顔は、心にかかりて恋しきを、うたてある筋に思ひし、聞き明らめて後は、なほもあらぬ心地添ひて、
「この宮仕ひを、おほかたにしも思し放たじかし。 さばかり見所ある御あはひどもにて、をかしきさまなることのわづらはしき、はた、かならず出で来なむかし」
と思ふに、ただならず、胸ふたがる心地すれど、つれなくすくよかにて、
「人に聞かすまじとはべりつることを聞こえさせむに、いかがはべるべき」
とけしき立てば、近くさぶらふ人も、すこし退きつつ、御几帳のうしろなどにそばみあへり。 |
(玉鬘は、)薄い鈍色の衣(祖母大宮の喪に服する)を、人懐かしい風に質素にまとって、いつもと違う色合いにも、容貌はじつにはなやかに引き立っていて、御前に仕える女房たちは、微笑んで見ているのだが、宰相中将(夕霧)が、同じ色の、少し濃い色の直衣姿で纓を巻いた姿で、なまめかしく清らかに、お見えになった。
初めから、率直に好意を寄せていたので、他人行儀な扱いをしてなかったのだが、今さら実の姉弟でなかったからと言って、急に態度を変えるのも変なので、御簾に几帳を添えた対面には、取次ぎの女房はいなかった。源氏の文使いで、内裏からの仰せがあって、それを伝えに夕霧が遣わされたのだった。
文の返事は、おおらかで感じの良い様子で申し上げるので、品があって心引かれる心地がするが、あの野分の朝に垣間見た顔が、心にかかって忘れられず、親子で嫌な関係にあると思ったが、親子でないと分かった後では、恋心がつのり、
「この宮仕えがあっても、おそらくあきらめないであろう。あのように(六條の院の) すばらしい夫人方の間にあって、色恋沙汰の面倒なことが必ず起きるであろう」
と思うと、気が気でなく心配で胸がつまるが、知らぬ風でさり気なく、
「誰にも聞かれないようにしなさいと言われましたので、どうしましょう」
と仔細ありげに言うので、近くにいる女房たちも、少し退いて、几帳の後で横を向くのだった。 |
|
| 30.3 夕霧、玉鬘に言い寄る |
そら消息をつきづきしくとり続けて、こまやかに聞こえたまふ。主上の御けしきのただならぬ筋を、さる御心したまへ、などやうの筋なり。いらへたまはむ言もなくて、ただうち嘆きたまへるほど、忍びやかに、うつくしくいとなつかしきに、なほえ忍ぶまじく、
「御服も、この月には脱がせたまふべきを、日ついでなむ吉ろしからざりける。十三日に、河原へ出でさせたまふべきよしのたまはせつ。なにがしも御供にさぶらふべくなむ思ひたまふる」
と聞こえたまへば、
「たぐひたまはむもことことしきやうにやはべらむ。忍びやかにてこそよくはべらめ」
とのたまふ。この御服なんどの詳しきさまを、人にあまねく知らせじとおもむけたまへるけしき、いと労あり。中将も、
「漏らさじと、つつませたまふらむこそ、心憂けれ。忍びがたく思ひたまへらるる形見なれば、脱ぎ捨てはべらむことも、いともの憂くはべるものを。さても、あやしうもて離れぬことの、また心得がたきにこそはべれ。この御あらはし衣の色なくは、えこそ思ひたまへ分くまじかりけれ」
とのたまへば、
「何ごとも思ひ分かぬ心には、ましてともかくも思ひたまへたどられはべらねど、かかる色こそ、あやしくものあはれなるわざにはべりけれ」
とて、例よりもしめりたる御けしき、いとらうたげにをかし。 |
(夕霧は、)とっさに作り話をつぎつぎと作って、仔細に申し上げる。帝のご執心がただならぬので、ご用心なさいなどとかである。返事のしようもなく、玉鬘はただ嘆いているのだが、ひっそりとして愛らしくたいそう女らしいので、我慢することができずに、
「喪服もこの月には脱ぐはずでしたが、陰陽士の占いで日が悪かったのです。十三日に賀茂の河原に出て(徐服する)と(源氏が)仰せになっております。わたしもお供に参ずるべく思っております」
と(夕霧が)言えば、
「皆がお供するのは、大げさになるでしょう。目立たぬようにしたいものです」
と(玉鬘が)言う。玉鬘が喪に服している事情を、世間に知られないように配慮しているのは、大そう気を使う。中将も、
「世間に知られまいと、わたしにまで気を使うのは心外です。大宮の形見の喪服を脱ぐのも堪え難く思われます。それにしても、どんなご縁があってここにご一緒されているのか、腑に落ちません。この喪服がなければ、大宮の孫とは分からないでしょう」
と(夕霧が)言うと、
「何の分別もないわたしなどには、何があったのか想像もつきませんが、このような喪服の色こそ妙にしみじみとした気持ちになります」
とて、いつもよりしんみりした様子は、可愛らしく風情があった。 |
|
| 30.4 夕霧、玉鬘と和歌を詠み交す |
かかるついでにとや思ひ寄りけむ、蘭の花のいとおもしろきを持たまへりけるを、御簾のつまよりさし入れて、
「これも御覧ずべきゆゑはありけり」
とて、とみにも許さで持たまへれば、うつたへに思ひ寄らで取りたまふ御袖を、引き動かしたり。
「同じ野の露にやつるる藤袴
あはれはかけよかことばかりも」
「道の果てなる」とかや、いと心づきなくうたてなりぬれど、見知らぬさまに、やをら引き入りて、
「尋ぬるにはるけき野辺の露ならば
薄紫やかことならまし
かやうにて聞こゆるより、深きゆゑはいかが」
とのたまへば、すこしうち笑ひて、
「浅きも深きも、思し分く方ははべりなむと思ひたまふる。 まめやかには、いとかたじけなき筋を思ひ知りながら、えしづめはべらぬ心のうちを、いかでかしろしめさるべき。なかなか思し疎まむがわびしさに、いみじく籠めはべるを、 今はた同じと、思ひたまへわびてなむ。
頭中将のけしきは御覧じ知りきや。人の上に、なんど思ひはべりけむ。身にてこそ、いとをこがましく、かつは思ひたまへ知られけれ。なかなか、かの君は思ひさまして、つひに、御あたり離るまじき頼みに、思ひ慰めたるけしきなど見はべるも、いとうらやましくねたきに、あはれとだに思しおけよ」
など、こまかに聞こえ知らせたまふこと多かれど、かたはらいたければ書かぬなり。
尚侍の君、やうやう引き入りつつ、むつかしと思したれば、
「心憂き御けしきかな。過ちすまじき心のほどは、おのづから御覧じ知らるるやうもはべらむものを」
とて、かかるついでに、今すこし漏らさまほしけれど、
「あやしくなやましくなむ」
とて、入り果てたまひぬれば、いといたくうち嘆きて立ちたまひぬ。 |
このついでにと思いついたのだろう、夕霧が美しく咲いた藤袴を持って、御簾の端から差し入れて、
「これもご覧になる理由はあるでしょう」
と言って、すぐには手放さず持っていると、真意に気づかず手に取った玉鬘の袖を、夕霧が引いた。
(夕霧の歌)「同じ喪に服してやつれている藤袴です
あわれな言葉の一つもかけてください」、
「夕霧は思いを寄せていたのか」と思って、玉鬘はとても不愉快で嫌な感じがしたが、そ知らぬふりをして、そっと身を引いて、
(玉鬘の歌)「元を尋ねれば遠く離れて血筋は違いますので
縁があるというのは口実でしょう
こう親しく話をしているより深い縁はあるのでしょうか」
と言えば、夕霧は、
「縁が浅いか深いか、お分かりのことと思います。本当は、恐れ多い宮仕えのことを知りながら、静められない自分の心のうちを、どうしてして分かっていただけましょうか。口に出せば、かえって疎まれるのがつらくて、心に秘めていましたが、身を尽くしてもと思い込んでいます。
頭中将の柏木の執心ぶりはご存知でしょう。他人事だと、思っておりました。わが身になって、たいそう愚かなことだと思い知った次第です。かえってかの君は、姉弟と知ってからは、あきらめて、血筋は切れることはないと、諦めたのをうらやましく思う、このわたしをあわれんでください」
など細々とたくさん言うことはありますが、どうかと思われるのでくだくだしくは書きません。
尚侍の君(玉鬘)は、奥へ引っ込みながら、厄介なことになった思い、
「冷たい仕打ちですね。過ちをしそうにないわたしのことは、すでにご存知でしょうが」
と(夕霧は)言って、このついでにもう少し言いたかったけれど、
「何だか気分が悪いので」
とて、(玉鬘が)引っ込んでしまったので、夕霧はひどく嘆いて立った。 |
|
| 30.5 夕霧、源氏に復命 |
「なかなかにもうち出でてけるかな」と、口惜しきにつけても、かの、今すこし身にしみておぼえし御けはひを、かばかりの物越しにても、「ほのかに御声をだに、いかならむついでにか聞かむ」と、やすからず思ひつつ、御前に参りたまへれば、出でたまひて、御返りなど聞こえたまふ。
「この宮仕へを、しぶげにこそ思ひたまへれ。宮などの、練じたまへる人にて、いと心深きあはれを尽くし、言ひ悩ましたまふになむ、心やしみたまふらむと思ふになむ、心苦しき。
されど、大原野の行幸に、主上を見たてまつりたまひては、いとめでたくおはしけり、と思ひたまへりき。若き人は、ほのかにも見たてまつりて、えしも宮仕への筋もて離れじ。さ思ひてなむ、このこともかくものせし」
などのたまへば、
「さても、人ざまは、いづ方につけてかは、たぐひてものしたまふらむ。中宮、かく並びなき筋にておはしまし、また、弘徽殿、やむごとなく、おぼえことにてものしたまへば、いみじき御思ひありとも、立ち並びたまふこと、かたくこそはべらめ。
宮は、いとねむごろに思したなるを、わざと、さる筋の御宮仕へにもあらぬものから、 ひき違へたらむさまに御心おきたまはむも、 さる御仲らひにては、いといとほしくなむ聞きたまふる」
と、おとなおとなしく申したまふ。 |
「いっそのこと、言わなければよかった」と夕霧は口惜しかったが、もっと身にしみて恋しく思うあの御方(紫上)を、この程度の物越しで、「少しでも声だけでも何かの折に聞いてみたい」と切に思いつつ、源氏の御前に参じて、出てきた源氏に(玉鬘の)返事を報告するのだった。
「この宮仕えは乗り気でないのだ。蛍兵部卿などは、女の扱いになれていて、深く情けの限りをつくして、口説いたであろうから、すっかり心にしみたのだろうか、お気の毒だ。
しかし、大原野の行幸で、帝を見ているので、実に美しいと感動したはずだと、思っている。若い女なら帝をちょっとでも見れば、宮仕えが嫌だとは思うまい。そう思って、この度の宮仕えを薦めたのだ」
などと(源氏が)仰せになれば、
「それにしても、玉鬘のお人柄は、どちらにお似合いでしょうか。中宮は並ぶ者なき地位にいらっしゃるし、また、弘徽殿の女御にしても家柄もよく世の評判もいいので、いかに帝の思いが強くても、肩を並べるのは難しいでしょう。
宮(蛍兵部卿宮)は大そう熱心に思っているので、格別に女御としての宮仕えでないにしても、自分の希望と違うので、不快な思いするでしょうし、仲の良い兄弟なので、困ったことだと存じられます」
と大人びたことを(夕霧は)言うのだった。 |
|
| 30.6 源氏の考え方 |
「かたしや。わが心ひとつなる人の上にもあらぬを、大将さへ、我をこそ恨むなれ。すべて、かかることの心苦しさを見過ぐさで、あやなき人の恨み負ふ、かへりては軽々しきわざなりけり。かの母君の、あはれに言ひおきしことの忘れざりしかば、心細き山里になど聞きしを、かの大臣、はた、聞き入れたまふべくもあらずと愁へしに、いとほしくて、かく渡しはじめたるなり。ここにかくものめかすとて、かの大臣も人めかいたまふなめり」
と、つきづきしくのたまひなす。
「人柄は、宮の御人にていとよかるべし。今めかしく、いとなまめきたるさまして、さすがにかしこく、過ちすまじくなどして、あはひはめやすからむ。さてまた、宮仕へにも、いとよく足らひたらむかし。容貌よく、らうらうじきものの、公事などにもおぼめかしからず、はかばかしくて、主上の常に願はせたまふ御心には、違ふまじ」
などのたまふけしきの見まほしければ、
「年ごろかくて育みきこえたまひける御心ざしを、ひがざまにこそ人は申すなれ。かの大臣も、さやうになむおもむけて、大将の、あなたざまのたよりにけしきばみたりけるにも、応へける」
と聞こえたまへば、うち笑ひて、
「かたがたいと似げなきことかな。なほ、宮仕へをも、御心許して、かくなむと思されむさまにぞ従ふべき。女は三つに従ふものにこそあなれど、ついでを違へて、おのが心にまかせむことは、あるまじきことなり」
とのたまふ。 |
「むつかしいもんだね。わたしの一存でどうなるものでもないのに、髯黒の大将さえわたしを恨んでいる。何ごとにつけこうした気の毒な境遇を見過ごせないので、わけもなく恨まれ、かえって軽率だった。あの母君の、あわれに言い残したことが忘れられず、寂しい山里と聞いていましたが、あの内大臣には、申し出ても聞いてもらえず、困っていたので不憫に思い、引き取ったのです。ここで姫君扱いするので、あの大臣もならったのでしょう」
とて、源氏はまことしやかに仰せになった。
「玉鬘の人柄は、宮の北の方としてふさわしいだろう。今風で、優雅なところがあり、それでいて賢く、間違いをしないだろうし、宮とはうまくゆくだろう。その上、宮仕えにしても、十分やる力量はあるでしょう。容貌よく、才気があり、公の儀式などにも暗くはなく、てきぱきしているので、帝が普段から望んでいる御心に叶うだろう」
と仰せになる源氏の真意が知りたかったので、
「何年もこうして育てた心ざしを、世間の人は枉げて言うのです。あの大臣も、そのような意を含んで、髯黒の大将があちらのつてを通じて申し込んだときも、そのように返事をしてます」
と(夕霧が)言うと、源氏は微笑んで、
「それもこれも見当違いですね。なお、宮仕えのことも、内大臣の許しをえて、大臣がこうしようと思う様に、従うのがよろしい。女には三従の義があるが、順序を違えて、わたしの意見に従うなど、あってはならないです」
と仰せになるのだった。 |
|
| 30.7 玉鬘の出仕を十月と決定 |
「うちうちにも、やむごとなきこれかれ、年ごろを経てものしたまへば、えその筋の人数にはものしたまはで、捨てがてらにかく譲りつけ、おほぞうの宮仕への筋に、領ぜむと思しおきつる、いとかしこくかどあることなりとなむ、よろこび申されけると、たしかに人の語り申しはべりしなり」
と、いとうるはしきさまに語り申したまへば、「げに、さは思ひたまふらむかし」と思すに、いとほしくて、
「いとまがまがしき筋にも思ひ寄りたまひけるかな。いたり深き御心ならひならむかし。今おのづから、いづ方につけても、あらはなることありなむ。思ひ隈なしや」
と笑ひたまふ。御けしきはけざやかなれど、なほ、疑ひは置かる。大臣も、
「さりや。かく人の推し量る、案に落つることもあらましかば、いと口惜しくねぢけたらまし。かの大臣に、いかで、かく心清きさまを知らせたてまつらむ」
と思すにぞ、「げに、宮仕への筋にて、けざやかなるまじく紛れたるおぼえを、かしこくも思ひ寄りたまひけるかな」と、むくつけく思さる。
かくて御服など脱ぎたまひて、
「月立たば、なほ参りたまはむこと忌あるべし。十月ばかりに」
と思しのたまふを、内裏にも心もとなく聞こし召し、聞こえたまふ人びとは、誰も誰も、いと口惜しくて、この御参りの先にと、心寄せのよすがよすがに責めわびたまへど、
「吉野の滝を堰せかむよりも難きことなれば、いとわりなし」
と、おのおの応ふ。
中将も、なかなかなることをうち出でて、「いかに思すらむ」と苦しきままに、駆けりありきて、いとねむごろに、おほかたの御後見を思ひあつかひたるさまにて、追従しありきたまふ。たはやすく、軽らかにうち出でては聞こえかかりたまはず、めやすくもてしづめたまへり。 |
「内大臣は内心では、六条の院には立派なご夫人がたが長年いらっしゃるのに、その人数に入れることをせず、半ば捨てるつもりでわたしに譲って、通りいっぺんの宮仕えをさせて、自分の物にすると考えたのだろう、はなはだうまい頭の良いやり方だと感嘆していたと、ある人が話してくれました」
と正面きって夕霧が話をすると、源氏は「まったくそう思われても仕方ない」と思い、玉鬘が気の毒になって、
「ずいぶん持って回ってひねくれて考えたものだね。何でも裏にまわって考える性分の人だからね。そのうち皆に分かるようになるだろう。片寄った考え方だね」
と笑う。口調はきっぱりしているが、夕霧にはなお疑いが残る。源氏も、
「そうか。皆があれこれと想像する、その思惑通りになったら、さぞ口惜しく思うことだろう。内大臣にどうかしてわたしの清い心を知らせたいものだ」
と思うにつけても、「実に、宮仕えということにして、うまく目立たぬように紛れ込ませているなどと、よくも見抜いたものだ」と気味悪く思った。
こうして、喪服を脱いで、
「来月になっても、出仕は慎しむべきでしょう。十月になれば」
と仰せになるが、帝は待ち遠しいとお思いになり、言い寄ってくる人々は、誰もが口惜しく思い、入内の前に何とかしてほしいと仲介の女房たちを責め立てているが、
「吉野の滝を堰き止めるよりも難しいので、どうしょうもない」
とそれぞれの女房が返事をする。
夕霧も、言わでもがなのことを口に出してしまって、「どう思っているだろう」と苦しい思いのままに、駆け回って、たいそう細々と、何か後見役のようなふりをして、ご機嫌伺いをしていた。夕霧は、あっさり軽々しく口に出したりはしないで、気持ちを抑えていた。 |
|
| 30.8 柏木、内大臣の使者として玉鬘を訪問 |
まことの御はらからの君たちは、え寄り来ず、「宮仕へのほどの御後見を」と、おのおの心もとなくぞ思ひける。
頭中将、心を尽くしわびしことは、かき絶えにたるを、「うちつけなりける御心かな」と、人びとはをかしがるに、殿の御使にておはしたり。なほもて出でず、忍びやかに御消息なども聞こえ交はしたまひければ、月の明かき夜、桂の蔭に隠れてものしたまへり。見聞き入るべくもあらざりしを、名残なく南の御簾の前に据ゑたてまつる。
みづから聞こえたまはむことはしも、なほつつましければ、宰相の君して応へ聞こえたまふ。
「なにがしらを選びてたてまつりたまへるは、人伝てならぬ御消息にこそはべらめ。かくもの遠くては、いかが聞こえさすべからむ。みづからこそ、数にもはべらねど、絶えぬたとひもはべなるは。いかにぞや、古代のことなれど、頼もしくぞ思ひたまへける」
とて、ものしと思ひたまへり。
「げに、年ごろの積もりも取り添へて、聞こえまほしけれど、日ごろあやしく悩ましくはべれば、起き上がりなどもえしはべらでなむ。かくまでとがめたまふも、なかなか疎々しき心地なむしはべりける」
と、いとまめだちて聞こえ出だしたまへり。
「悩ましく思さるらむ御几帳のもとをば、許させたまふまじくや。よしよし。げに、聞こえさするも、心地なかりけり」
とて、大臣の御消息ども忍びやかに聞こえたまふ用意など、人には劣りたまはず、いとめやすし。 |
実の兄弟たちは、寄って来ず、「宮仕えになったらお世話しよう」と、それぞれ待ち遠しい気持ちだった。
頭中将(柏木)は、心底恋いこがれ嘆いていたが、音沙汰もなくなり、「突然変わるのですね」と女房たちはおかしがっていたが、内大臣の使いとして来訪した。未だに目立たぬように、ひそかに文などをやり取りしていたが、月の明るい夜、桂の陰に隠れて立っていた。見向きもされなかったのが、すっかり変わって南の御簾の前に招じられた。
玉鬘は、取次ぎなしで話すことは、やはり気が引けるので、宰相の君を通して応えた。
「わたしを使者に立てるのは、じかに申し上げろということです。こう隔てがありましては、どうして申し上げられましょう。自分は数ならぬ身ですが、姉弟の絆は切れないたとえもあります。いかがと思われましょうが、昔風ですが、頼みにしておりましたのに」
とて、少し不愉快な気持ちだ。
「おっしゃるとおり、年頃の積もる話も添えて、お話したいのですが、この日頃なんだか気分がすぐれず、寝込んでおります。こうして責められるのも、かえって疎まれているのかという気がいたします」
と、玉鬘は生真面目に言った。
「気分がすぐれないので、御簾の中へは入れてもらえないのですか。いやいや、こう申し上げるのも気が利かぬことでした」
とて、内大臣の伝言をひそかに申し上げる態度など、さすがに誰にも負けない、申し分ないものだった。 |
|
| 30.9 柏木、玉鬘と和歌を詠み交す |
「参りたまはむほどの案内、詳しきさまもえ聞かぬを、うちうちにのたまはむなむよからむ。何ごとも人目に憚りて、え参り来ず、聞こえぬことをなむ、なかなかいぶせく思したる」
など、語りきこえたまふついでに、
「いでや、をこがましきことも、えぞ聞こえさせぬや。いづ方につけても、あはれをば御覧じ過ぐすべくやはありけると、いよいよ恨めしさも添ひはべるかな。まづは、今宵などの御もてなしよ。北面だつ方に召し入れて、君達こそめざましくも思し召さめ、下仕へなどやうの人びととだに、うち語らはばや。またかかるやうはあらじかし。さまざまにめづらしき世なりかし」
と、うち傾きつつ、恨み続けたるもをかしければ、かくなむと聞こゆ。
「げに、人聞きを、うちつけなるやうにやと憚りはべるほどに、年ごろの埋れいたさをも、あきらめはべらぬは、いとなかなかなること多くなむ」
と、ただすくよかに聞こえなしたまふに、まばゆくて、よろづおしこめたり。
「妹背山深き道をば尋ねずて
緒絶の橋に踏み迷ひける
よ」
と恨むるも、人やりならず。
「惑ひける道をば知らず妹背山
たどたどしくぞ誰も踏み見し」
「いづ方のゆゑとなむ、え思し分かざめりし。何ごとも、わりなきまで、おほかたの世を憚らせたまふめれば、え聞こえさせたまはぬになむ。おのづからかくのみもはべらじ」
と聞こゆるも、さることなれば、
「よし、長居しはべらむも、すさまじきほどなり。やうやう労積もりてこそは、かことをも」
とて、立ちたまふ。
月隈なくさし上がりて、空のけしきも艶なるに、いとあてやかにきよげなる容貌して、御直衣の姿、好ましくはなやかにて、いとをかし。
宰相中将のけはひありさまには、え並びたまはねど、これもをかしかめるは、「いかでかかる御仲らひなりけむ」と、若き人びとは、例の、さるまじきことをも取り立ててめであへり。 |
「参内の仔細は、詳しく聞いておりませんが、 内々に打合せてご相談されのがよろしいでしょう。何ごとも人目を憚って、来訪できず話もできないのが気になっております」
など、内大臣の伝言を伝えるついでに、
「いやはや、恥ずかしい文も、もう差し上げようもない。どちらであっても、わたしの真心を見過ごすなど、なんとも恨めしいです。まずは今宵のもてなしですね。他人行儀な南面ではなく、非公式な北面から招じて、宰相の君は嫌っておられるにしても、下仕えなどの人びとに、親しくお話したかった。こんな扱いはないでしょう。それぞれに珍しい間柄ですね」
と(柏木の)恨み言を、(宰相の君は)このように玉鬘に報告する。
「まことに、姉弟と知って急に態度を変えるのも、外聞が悪いのですし、長年引き籠もっていた胸の内を、明かしませんのも、とてもつらいものです」
と率直に言ったので、まばゆく感じ、柏木は気恥ずかしくなり何も言えなかった。
(柏木)「実の兄妹とは知らずに
成らぬ恋の道に踏み込んでしまった
よ」
と恨んでも、誰のせいでもない。
(玉鬘の歌)「事情をご存じなく迷い込んだのですね
妙なお手紙と拝見していました」
「どういうお立場のものなのか、分からなかったのでしょう。何ごとにしても、たいへん世間体を気にする方なので、ご返事をさし上げなかったのでしょう。まさかこのままではございますまい」
と(宰相の君が)申し上げると、そういうことなら、
「いや、長居をしすぎたようです。少しずつお世話の労が積み重なってから、恨み言も申しましょう」
とて立ち上がった。
月が隈なく照って、空の様子もまことに風情があり、柏木は大そう気品があって美しい容貌で、直衣の姿も好ましくはなやかで、趣があった。
夕霧の気配には、とても及ばないが、柏木もこれほど美しいのは、「どうしてこのような一族なのであろう」と若い女房たちは、例によって、並のことでも取り立ててほめるのであった。 |
|
| 30.10 鬚黒大将、熱心に言い寄る |
大将は、この中将は同じ右の次将なれば、常に呼び取りつつ、ねむごろに語らひ、大臣にも申させたまひけり。人柄もいとよく、朝廷の御後見となるべかめる下形なるを、「などかはあらむ」と思しながら、「かの大臣のかくしたまへることを、いかがは聞こえ返すべからむ。さるやうあることにこそ」と、心得たまへる筋さへあれば、任せきこえたまへり。
この大将は、春宮の女御の御はらからにぞおはしける。大臣たちをおきたてまつりて、さしつぎの御おぼえ、いとやむごとなき君なり。年三十二三のほどにものしたまふ。
北の方は、紫の上の御姉ぞかし。式部卿宮の御大君よ。年のほど三つ四つがこのかみは、ことなるかたはにもあらぬを、人柄やいかがおはしけむ、「嫗」とつけて心にも入れず、いかで背きなむと思へり。
その筋により、六条の大臣は、大将の御ことは、「似げなくいとほしからむ」と思したるなめり。色めかしくうち乱れたるところなきさまながら、いみじくぞ心を尽くしありきたまひける。
「かの大臣も、もて離れても思したらざなり。女は、宮仕へをもの憂げに思いたなり」と、うちうちのけしきも、さる詳しきたよりあれば、漏り聞きて、
「ただ大殿の御おもむけの異なるにこそはあなれ。まことの親の御心だに違はずは」
と、この弁の御許にも責ためたまふ。 |
髯黒の大将は近衛府の長官で、柏木の中将はその次官であってみば、常に呼び寄せて、親しく話をし、内大臣にも伝えさせた。人柄もよく、朝廷の後見となる予定の人なので、「何の難があろう」と内大臣は思うのであるが、「かの大臣がこうときめたことを、どうして反対できようか。それだけの理由があるのだ」と心得ているので、源氏に任せているのだった。
この髯黒の大将は、春宮の女御の兄妹の血縁であった。二人の大臣(源氏と内大臣)を措いては、その次ぎに帝の信任が厚いお方である。年の頃三十二三であった。
北の方は、紫の上の異母姉であった。式部卿の宮の長女であった。三つ四つ年上であるのは、大した欠点でもないが、人柄がどうだったのだろう、「おばあさん」と仇名をつけて、大事にせず、なんとか別れようとしていた。
その関係から源氏は、髯黒の大将は、「相応しくないし困ったことになる」と思っていた。色恋にうつつを抜かすような方ではなかったが、まことに熱心に奔走していたのだった。
「あの内大臣も、まったく問題外と思っておられない。女は宮仕えは、気は進まないと思っている」と、内幕の事情に詳しい伝があるので、漏れ聞いていて、
「ただ、源氏の大臣の意向に異なっているだけなだろう。まことの親の心に違わなければ」
と、お付きの弁(玉鬘付き女房)を急かせるのだった。 |
|
| 30.11 九月、多数の恋文が集まる |
九月にもなりぬ。初霜むすぼほれ、艶なる朝に、例の、とりどりなる御後見どもの、引きそばみつつ持て参る御文どもを、見たまふこともなくて、読みきこゆるばかりを聞きたまふ。大将殿のには、
「なほ頼み来しも、過ぎゆく空のけしきこそ、心尽くしに、
数ならば厭ひもせまし長月に
命をかくるほどぞはかなき」
「月たたば」とある定めを、いとよく聞きたまふなめり。
兵部卿宮は、
「いふかひなき世は、聞こえむ方なきを、
朝日さす光を見ても玉笹の
葉分けの霜を消たずもあらなむ
思しだに知らば、慰む方もありぬべくなむ」
とて、いとかしけたる下折れの霜も落とさず持て参れる御使さへぞ、うちあひたるや。
式部卿宮の左兵衛督は、殿の上の御はらからぞかし。親しく参りなどしたまふ君なれば、おのづからいとよくものの案内も聞きて、いみじくぞ思ひわびける。いと多く怨み続けて、
「忘れなむと思ふもものの悲しきを
いかさまにしていかさまにせむ」
紙の色、墨つき、しめたる匂ひも、さまざまなるを、人びとも皆、
「思し絶えぬべかめるこそ、さうざうしけれ」
など言ふ。
宮の御返りをぞ、いかが思すらむ、ただいささかにて、
「心もて光に向かふ葵だに
朝おく霜をおのれやは消つ」
とほのかなるを、いとめづらしと見たまふに、みづからはあはれを知りぬべき御けしきにかけたまひつれば、つゆばかりなれど、いとうれしかりけり。
かやうに何となけれど、さまざまなる人びとの、御わびごとも多かり。
女の御心ばへは、この君をなむ本にすべきと、大臣たち定めきこえたまひけりとや。 |
九月になった。初霜がおりて、趣きある朝、例のそれぞれの取次ぎの女房たちが、わきに隠して持って来る文を、玉鬘は見ることはなく、女房たちが読むのを聞いている。髯黒の大将の文には、
「頼みにしていた月も、過ぎてゆく空の気色に、気はそぞろで
(髭黒の歌)人並みだったら結婚を避ける月なのに
わたしは命がけで九月にかけて生きています」
「月が改まったら」との予定を、よく知っているのだ。
兵部卿の宮は、
「言っても仕方がないので、言い様がありませんが。
(兵部卿の歌)帝のご寵愛を得ても分け入った玉笹の
下葉の霜のようなわたしを忘れないでください
分かっていただけたら、慰めようもあるでしょう」
と言って、ひどくしおれて下が折れた枝に露を落とさず持ってきた使いも、相応しい。
式部卿宮の子息の左兵衛督は、紫の上の異母兄弟であった。親しく邸に出入りしていたので、邸の事情もよく知っていて、たいそう心を痛めていた。 恨み言を長々書き綴って、
(左兵衛督の歌)「忘れようとしていますがそれが悲しく
いったいどうしたものでしょうか」
紙の色、墨つき、含めた匂いも、されぞれに良く、女房たちも皆、「こんな方があきらめてしまったら、寂しくなりますね」
など言うのだった。
兵部卿の宮へ返事は、どう思っているのか、少し書いて、
(玉鬘の歌)「自分から望んで光に向かう葵でも
朝露を自分で消したりしますでしょうか」
と薄墨でさらりと書いたのを、趣きあると見るが、玉鬘自身は宮の愛情を感じているような詠みぶりなので、ほんの一言の文だが宮は嬉しかった。
このように、特にどうということはないが、様々の人の恋文が多かった。
女の心ばえは、この君を手本とするのがよい、とそれぞれの大臣は判定なさったとか。 |
|
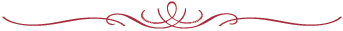
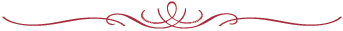
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)