| 手だれ |
|
優れた技を持っている。「名人」「達人」など漢語でも表現できるが、「手だれ」「腕利き」など、体の名称を使った大和言葉のほうが、技を繰り出す巧みな姿が生き生きと伝わってくる。 |
| きざはし |
|
階段。「きざ」は刻む、「はし」は橋。その昔、橋は「2カ所をつなぐもの」という意味で使われ、「はしご」もそこから来た言葉。きざはしは、2つの地点をギザギザと刻む道という意味。 |
| まろうど |
|
客。語源は「まれ(稀)ひと」。たまに来る人、つまり客人を指す。枕草子にも、急用があるときに来て「長言(長話)するまらうと」にはイラッとする、と使われている。 |
| しもたや |
|
普通の民家。「仕舞(しも)うた屋」が語源。つまり今は商いをやめた家、の意。店じまいという言葉は今もよく使うが、廃業するなら「店を畳む」と言ったほうが誤解を生まない。 |
| 目もあや |
|
きらびやか。「あや」は「怪しい」。身に着けた衣服や飾りがあまりにきらびやかで、目がクラクラするほど、という意味。「派手」よりも激しい表現だ。 |
| ゆくりなく |
|
思いがけず。どことなくのどかな響きがあるが、実は「突然のことで」と驚きや戸惑いを表す言葉。パーティーの席などで「ゆくりなくもスピーチのご指名を受け…」などと使う。 |
| 誼(よしみ)を結ぶ |
|
親しくする。「誼」は親しく思う気持ちや、そこから生まれる交流・交遊を指す。目上の人と付き合いがあることを、「○○様と誼を結ばせていただいております」などと使う。 |
| 敷居が高い |
|
心苦しくて訪問しづらい。よく使われる慣用句だが、「あのレストランは高級で、どうも~」は誤用。恩師など世話になった人に不義理や失礼をしたままで心苦しい、顔向けできないというときに使う。 |
| むべなるかな |
|
なるほどと思う。「むべ」は「なるほど」という意味。驚いたり感心したりしたことの背景を聞き、「ああ、なるほど!」と納得したときに「それは“むべなるかな”です」などと使う。 |
| ほんのお口汚しですが… |
|
量が少ないですが。おしなべて食べ物は口を汚すもの。量が十分なら腹は満ちるが、口を汚すだけで腹の足しにならないほど少し、という意味。お茶菓子や酒肴(しゅこう)を出すときに謙遜して使う。 |
| お手すきのときに |
|
「手が空いているとき…」「お暇なとき…」という表現は直接的なのでNG!「お手すきのときに」を使用することで、快くお願いを聞いてくれる。 |
| しばし |
|
「もう少し時間がかかります」という表現よりも、「しばし」を使うことで、相手の焦る気持ちを静めることが期待できる。 |
| 心待ち |
|
「ご返信を、首を長くして待っております」という気持ちを伝える言い回しに使われる。「早急な返信をお願いします」よりも、「ご返信を心待ちにしております」の方が、返信に対する期待感を相手に伝えることができる。 |
| 不躾(ぶしつけ) |
|
「失礼なのは十分承知のうえですが…」の言い回しに使われる。「不躾」を使うことにより、相手に敬意、自分を卑下した表現により効果が期待できる。 |
| 致しかねます |
|
「〜できません」という言い方よりも、「致しかねます」を使うことにより丁寧に断ることができる。 |
| 恐れ入ります |
|
「恐れ入りますが、会社名を教えていただけないでしょうか」のように使われ、柔らかい表現になる。 |
| おおむね |
|
会議資料は「おおむね」作成しました 。「だいたい」や「ほとんど」ではなく、「おおむね」、「あらまし」に言い換えることにより知的な表現になる。 |
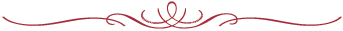
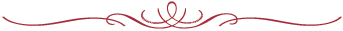
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)