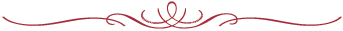
| 大和文読み |
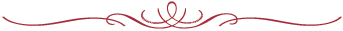
更新日/2017.3.30日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、大和言葉、熟字考をしておく。 2006.8.31日 れんだいこ拝 |
![]()
「女性に人気「大和言葉」…しとやかな雰囲気を醸す」を転載しておく。
|
|
| 【熟字訓】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は「熟字訓」、「ウィキペディア熟字訓」、「熟字訓 」を参照
熟語(古い日本語、現在でも使われる中国語の場合がある)を訓読みする場合がある。これを熟字訓という。例えば、梅雨(つゆ)、五月雨(さみだれ)、大人(おとな)、昨日(きのう)等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熟字訓(じゅくじくん)は、日本語において漢字の単字単位ではなく熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの。単字に分解してもそれぞれに熟字訓の要素は現れない。また、読みの方でも分節不可能なものが多い。
例えば、「明日」に「あす」。単字の「明」や「日」に「あす」の要素はない。また読みの「あす」を「あ」と「す」に分けることもできない。漢語においては「明」と「日」を修飾-被修飾の関係で組み合わせて新たな意味を作り出しているのであり、これを単字それぞれのもつ字訓を使わずに、二字まとめて一訓を当てたものである。単字訓で読めば「あくるひ」になる。よく使われる言葉が熟字訓になっている場合が多い。訓には和語ばかりでなく外来語が使われることがある。例えば「煙草」を「たばこ」と訓読みする。熟字が漢語文法に則って作られていることが前提であり、字音や字訓を利用しつつも漢字本来の意味や熟字構造を無視して和語や外来語に漢字を当てる当て字とは異なる。 また、熟字訓と音読みで意味が異なる場合がある。「今日」は、「きょう」と読む場合はある特定の日(本日)を指し、「こんにち」と読む場合には特定の長い期間(最近)を指す。一般に二三字で特殊な読みをするものをすべて熟字訓と考える人がいるが、それは誤りである。例えば「玄人」「素人」を「くろうと」「しろうと」と読むが、これは「玄」が「くろ」、「素」が「しろ」、「人」が「ひと」と分解でき、その「くろ」+「ひと」のウ音便に過ぎない。熟字訓も通常の訓読みと同様、最初は個人的な使用(義訓)から生じている。それが慣用的なものとして定着したものが今見る熟字訓である。江戸時代に「閑話休題」を「それはさておき」と訓んでいたことが知られるが、現代には定着していない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の地名
日本の地名や人名には熟字訓であるものが少なからずある。その場合、「大和(やまと)」や「飛鳥(あすか)」のように熟字の語義と訓とがかなりかけ離れているものも多い。これは律令制の整備に際し、日本の地名に中国風に漢字2字の名称をつけたとき、もとの和名からかけ離れた漢字熟語を用いたためであり、訓が語義を説明するものというよりも地名に対して漢風の漢字で表記したものと言える。「近江」のように「ちかつあはうみ」から漢字がつけられていても、「おうみ」とだけ読むために元々の関係性が明確でなくなっているものも多い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暦・季節・時間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動植物
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食べ物
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活用品
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「泡沫」と書いて「うたかた」。ホウマツと音読みすることもあるように、もともとは中国製の熟語です。「泡」の訓読みは「あわ」、「沫」も同じく「あわ」を意味する漢字ですから、「泡沫」の意味は「あわあわ」、ではなくて、単純に「あわ」ということになります。つまり、古代中国語の「泡沫」と、古代日本語の「うたかた」とは同じ意味なのです。そこで、「泡沫」を「うたかた」へと翻訳することが可能だということになります。訓読みとは、本来、中国語としての漢字を日本語に翻訳したものです。中国語「泡」は日本語「あわ」に翻訳できるから、漢字「泡」を「あわ」と訓読みするというわけです。そこで、「泡沫」が「うたかた」に翻訳できるとなると、「泡沫」の2文字をまとめて「うたかた」と訓読みしてしまおう、ということにもなってきます。このように、漢字2文字以上をまとめて訓読みすることを、熟字訓(じゅくじくん)と呼んでいます。「熟字」とは「熟語」と同じ意味で、「熟字訓」とはつまり、熟語の訓読みという意味です。世間一般に「当て字」と呼ばれているものの中には、多くの熟字訓が含まれています。ところが、1946年に当用漢字が制定されたとき、当て字はかな書きにする、という方針が打ち出されました。その結果、熟字訓はあまり用いられなくなってしまったのです。とはいえ、「泡沫(うたかた)」のように、今でも愛され続けている熟字訓も数多くあります。読み方がむずかしいという難点はありますが、熟字訓には熟字訓のよさもあります。よい部分は、これからも受け継いでいきたいものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢字二字以上の熟字全体に,日本語の訓をあてて読むこと。また,その読み。「昨日(きのう)」「紅葉(もみじ)」「杜鵑(ほととぎす)」「羊歯(しだ)」の類。本辞典では常用漢字表付表記載の熟字訓は「《昨日》」「《紅葉》」,それ以外のものは「〈杜鵑〉」「〈羊歯〉」のように,《 》と〈 〉を使って表記欄に指示してある。
【当て字】より…また言葉(ことば),出来(でき)などを,それぞれの文字の正当な意義用法によらぬとして,当て字にふくめることがある。さらに,土産(みやげ),銀杏(いちよう),今日(きよう),三和土(たたき),煙草(たばこ),麦酒(ビール),天鵞絨(ビロード)など,漢字2,3字の結合を一々の字の音訓によらずに,全体として一つの単語にあてる(熟字訓という)場合をも,当て字という人が近来はある。常用漢字表および同音訓表の適用にあたってはこれらの当て字は一括して排斥されつつあるが,一方,常用漢字表以外の漢字を使わないようにするために行われる,銓衡→選考,落伍→落後,繃帯→包帯のような書きかえは,主として漢語についてであって,当て字とはよばれていないが,新たに作られつつある当て字といえよう しかし、そういった議論は置いておいて、現代日本語の世界で考えたときには、「当て字」には大きく分けて以下の2種類があるのではないかと思います。 1「滅茶苦茶」(めちゃくちゃ)、「倫敦」(ロンドン)などのように、漢字の本来の意味とは関係なく、ある漢字 を用いるもの。 さて、一方の「熟字訓」は、本来、「熟字(=熟語)に対する訓読み」のことです。訓読みとは、中国語としての漢字の意味を日本語で翻訳したものですが、同じ作業を熟語に対して行ったものなのです。結果として、漢字2字以上からなる熟語に対して、日本語1語を当てたものが熟字訓であるということになります。 今回は、日本の情緒を感じる2字熟字訓について461名の読者に聞きました。 Q.日本の情緒を感じる2字熟字訓を教えてください(複数回答) 1位 もみじ→紅葉 34.7% 2位 いちょう→銀杏 22.1% 3位 たなばた→七夕 21.5% 4位 かや→蚊帳 19.7% 5位 せんす→扇子 17.4% ■もみじ→紅葉 ・「もみじって日本らしい、とても美しい光景だから、漢字まで良く見える」(35歳男性/機械・精密機器/営業職) ・「文字の向こうに色が見えて情緒を感じる」(27歳男性/マスコミ・広告) ・「赤じゃなくて紅を使うところが繊細な日本人ぽいから」(37歳女性/団体・公益法人・官公庁/秘書・アシスタント職) ■いちょう→銀杏 ・「実のことは『ぎんなん』と呼び、木や葉のことは『いちょう』と呼ぶのは面白いと思うから」(35歳男性/情報・IT/技術職) ・「日本には良い漢字がいっぱいあるなと思う」(26歳女性/アパレル・繊維/事務系専門職) ・「四季、季節にかかわるものは、情緒を感じます」(38歳女性/情報・IT/事務系専門職) ■たなばた→七夕 ・「言葉に涼しさを感じる」(27歳男性/建設・土木/技術職) ・「字面と響きがいいなと思うので」(27歳女性/情報・IT) ・「日本人なら誰でも読めるのに、少し日本語を勉強した外国の人では絶対読めないだろうなと思うから」(25歳女性/不動産/事務系専門職) ■かや→蚊帳 ・「夏の暑さを和らげてくれるから」(39歳男性/人材派遣・人材紹介/営業職) ・「蚊なんて全世界どこでもいるだろうに、不思議なもので蚊帳と聞くと日本の文化だなあと思う。音が柔らかくていい」(28歳女性/印刷・紙パルプ/クリエイティブ職) ・「蚊帳は今の家では見ることはないだろうけれど、田舎の景色や雰囲気が思い出されて日本という感じがします」(31歳女性/自動車関連/事務系専門職) ■せんす→扇子 ・「センスありますね」(24歳男性/機械・精密機器/技術職) ・「可憐さを感じるから」(26歳女性/機械・精密機器/事務系専門職) ・「優雅な感じがする」(29歳女性/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職) ■番外編:後世に伝えるべき伝統文化 ・ぞうり→草履「ぞうりは、風情がある感じで特にいいですね」(54歳男性/電機/技術職) ・あま→海女「ちゃんとその漢字をみるとどんなものか想像しやすいようにできているなと思う」(33歳女性/学校・教育関連/事務系専門職) ・そろばん→算盤「隣町はそろばん作りで有名な町。だからか、しょっちゅう……というか、毎日算盤という漢字を見てます。でも算盤はできない」(29歳女性/団体・公益法人・官公庁/専門職) |
| 義訓 |
| 義訓(ぎくん)とは、漢字に固定化した訓ではなく、文脈に合わせて個人的にその場限りの訓を当てることをいう。表記の面から言えば、当て字である。特に『万葉集』など上代文献での漢字の使い方をいう。「暖(はる)」「寒(ふゆ)」「金(あき)」「未通女(おとめ)」「数多(あまねし)」「間置而(へだたりて)」など。
また「天皇」を「すめらみこと」、「大臣」を「おとど」、「一寸」を「ちょっと」と読んだり、「閑話休題」を「それはさておき」と読んだりもする。訓読みと言うよりも、漢語(中国語)を日本語に意訳して訓むものといえる。現代において漫画などで「本気」と書いて「マジ」と振り仮名をつけるのも義訓の一種といえる。 義訓がのちに固定的に使われるようになって正訓となることがある。 |
| 国訓 |
| 漢字が本来表す中国語の意味ではなく日本独自の訓を当てるものを国訓(こっくん)という。たとえば、「鮎」は中国語では「なまず」であるが、訓は「あゆ」であり、「沖」は中国では「つく」(衝→簡化: 冲)などの意味であるが、訓は「おき」である。これらは漢字で日本語を表記できるようになったためにできたものである。 |
| 外来語による訓読み |
漢字の訓読みに用いるのは和語とは限らず、外来語である場合もある。この場合はカタカナで表記されることが多い。
訓読みの例熟字訓の例 |
「手が空いているとき…」「お暇なとき…」という表現は相手に失礼なのでNGです!そこで。「お手すきのときに」を使用することで、快くお願いを聞いてくれるはずです。
「もう少し時間がかかります」という表現よりも、「しばし」を使うことで、相手の焦る気持ちを静めることが期待できます。
「ご返信を、首を長くして待っております」という気持ちを伝える言い回しに使われます。「早急な返信をお願いします」と圧迫感を与えるよりも、「ご返信を、心待ちにしております」と言い換えることで、返信に対する期待感を相手に伝えることができます。
「失礼なのは十分承知のうえですが…」の言い回しに使われます。「不躾」を使うことにより、相手に敬意を示すために、自分を下においた表現にすることができます。
「〜できません」という言い方よりも、「致しかねます」を使うことにより、丁寧に断ることができます。
「恐れ入りますが、会社名を教えていただけないでしょうか」のように相手に迷惑をかけてしまったり、骨折りに対して申し訳ない気持ちを伝える際にも用います。
「だいたい」や「ほとんど」ではなく、「おおむね」「あらまし」に言い換えることにより、知的な表現になります。
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)