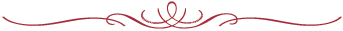
| れんだいこの語彙の適切和訳読本 |
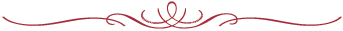
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.8日
| れんだいこのカンテラ時評206 | れんだいこ | 2006/08/31 |
| 【れんだいこの語彙の適切和訳考】 気になっていた事を書きつけておく。旅行やマスコミを通じて世界諸国民とのコミュニケーションが否応なく増し、その分言語交通が大事な時代に入っているが、過去の不適切な和訳をそのままにしておいて良いものか、と思うようになった。誤訳であろうと、既に歴史的地位を獲得しているので、こだわる必要はないと思えばそれまでだが、やはり気になることは気になる。 その第一は、「哲学」という翻訳についてである。これは、英語の「フィロソフィー」(philosophy)の和訳であるが、原義は、「愛」を意味する「フィロ」(philo)と「知」を意味する「sophy」の結合語であると聞く。直訳すれば「愛知学」ということになる。 或る時誰かが(学がなくて申し訳ない、どこかで読んだ気がするが忘れた)、それを「哲学」と表現した。それが通用して今日まで至っている。ところが、漢字にも表意文字としての意味があるからして、「哲学」の意味を詮索せねばならない。その結果、漢字としての意味と洋文字としての意味が一致していれば合格である。よって、「哲学」の「哲」と「学」の意味を問わねばならない。 れんだいこは、「哲」の意味を知らない。漠然と分かるのは、「哲」の上の造りが「折」で、下の造りが「口」であることである。これをれんだいこが解せば、「口を折る」ということになる。例えば、減らず口を叩くとか、相手を言い負かすとかの意味合いが浮かんでくる。「学」はそのまま受け取るとして、よって「哲学」とは、「相手の意見を打ち負かす為の学問ないしはへらず口学問」と云うようなニュアンスがでてくる。これでは学ぶ事を嫌う者が出てきても致し方ない。 英語の「愛知」的意味のフィロソフィー(philosophy)と漢字の「相手の意見を打ち負かす為の学問」との間にはかなり隔てがあると云うことになる。そこで、れんだいこは適訳を考えた。ズバリ「学問」と訳すべきではなかろうか。既に「学問」は幅広く使われているが、それは間違いで単に何々学と表現すれば良いのにわざわざ学問としているのではなかろうか。「学問」というのは元々西欧語の「フィロソフィー」と釣り合っているのではなかろうか。 どこまで正しいのか分からないが、以降、れんだいこ式和訳表記では「フィロソフィー」を「学問」と訳すことにする。ちなみに「stydy」は勉強するでよく、「knowledge」は知識でよく、「institute」は研究するで良いだろう。「フィロソフィー」は「学問」の意である。即ち学び問うのだ。その精神を愛知と云うのであり、真意は「特に学び問う学問」というところにあるのではなかろうか。御意の士よ、得心したら続け。 れんだいこが云いたかったのはそのことではない。「フィロソフィー論」は前置きである。本当に論じたかったのは、ドイツ語の「アオフヘーベン」(Aufheben)についてである。従来これを「止揚」と訳している。マルクス主義学の泰斗、福本和夫氏は異議を唱え「揚棄」と訳している。 れんだいこは、どちらも今ひとつだと思っている。ドイツ語の「アオフヘーベン」(Aufheben)の「アオフ」(Auf)とは英語の何に当るのだろうか。ひょっとして「オフ」(of)ではなかろうか。「ヘーベン」(heben)とは「ハブ」(have)の名詞形ないしは動詞なのだろうか。いずれにせよ、直訳すれば「持ち上げて脱する、又は脱して持ち上げる」とかの意味を持っているのではなかろうか。 その原意に対して「止揚」や「揚棄」訳は適切だろうか。れんだいこは、「止揚」の「止」が決定的に意味が違うと思っている。「揚棄」の方がまだしも適訳と思うが、「棄」が幾分筋違いではなかろうかと思っている。マルクス主義用語で多用される「アオフヘーベン」であるが、れんだいこが察するのに、「否定の否定弁証法」を通じて「或る段階のものが革命的質変換により次の高次な段階に向うという螺旋(らせん)的発展の経緯に於ける質的転換」を指摘した用語ではなかろうか。 そうすると、平板な「持ち上げて脱する、脱して持ち上げる」では意味をなさない。そこで、「止揚」とか「揚棄」という簡潔二文字訳が生まれているのであるが、既に述べたように不適切訳かないしはそれに近い誤訳であろう。何しろ、マルクス主義にとっては、「アオフヘーベン論」は重要な意味を持っているので、この辺りを不適切訳や誤訳で済ますのは良くない。誰も指摘していないようであるが、あるいは誰かが指摘しているのかも知れないが、「止揚」ないしは「揚棄」が罷り通っているのはいただけない。 ならば、どう訳すべきか。れんだいこはふと閃いた。それを記そうと思うが、勿体ないので今は明らかにしない。本掲示板を見ている関心のある者の意見を求めたい。その上で、れんだいこ訳を開陳したいと思う。出来の良いのを造案したので忘れないうちに書き付けてみた。 そうそうこれを書くのを忘れてた。この種の遣り取りを為すに際して、現代著作権論者の営為の何と妨害敵対的なことか。お前たちは、学問的営為の反面教師であるということを弁えて世間に蟄居しつつ世渡りせよ。大手を振って闊歩するなぞ厚かましいにもほどがあろう。これに追従する者も右同じだ。ウンよう云った。 2006.8.31日 れんだいこ拝 |
||
| Re:れんだいこのカンテラ時評231 | れんだいこ | 2006/11/06 |
| 【「アオフヘーベン」の適訳としての「出藍」考】
2006.8.31日付け「れんだいこのカンテラ時評206、語彙の適切和訳考」で触れたが、マルクス主義用語で重要な意味を持ち多用されているにも拘わらず、その割にはしっくりしない「アオフヘーベン」(Aufheben)の適正訳に決着をつけたい。 これまで一般的には「止揚」と訳されてきている。戦前戦後の稀代の理論家・福本和夫氏が異議を唱え、「揚棄」と言い換えている。しかし、れんだいこ的には「止揚」も「揚棄」の両訳ともしっくりしない。そう感覚しているのはれんだいこ一人であろうか。とにかく今ひとつと云う感じがしており、こたびれんだいこが新たに造語する。これを世に発表し、賛否を賜りたいと思う。 ドイツ語の「アオフヘーベン」(Aufheben)は、「auf」と「heben」の結合語である。辞書で確認すればそれぞれの意味合いは分かる。「auf」を仮にネット検索の「アクセス独和辞典」で引けば、次のように記されている。「何々の上に(へ、で)」、「何々を期して」等々。なお、動詞の前綴りに付けられ色々な意味を持つとある。「heben」は、「(持ち)上げる(がる)」等々とある。 問題は、これを結合させた時化学反応が生じ、新たな意味を持って登場していることにある。だから、「auf」と「heben」のそれぞれの意味を単に結合させただけでは役に立たない。結合語を一挙的にどう理解するのかが問われていることにある。この認識の下に「止揚」ないし「揚棄」と訳されているのであるが、この和訳語が適切かどうか。 思うに、「アオフヘーベン」の原意には、「持ち上げて脱する、又は入り込んで抜け出す」とかの意味が込められているのではなかろうか。マルクス主義的「アオフヘーベン」は、「否定の否定弁証法を通じての革命的質変換でらせん的発展していく、或る段階のものがより高次の段階に向う突然変異的経緯の表現用語」ではなかろうか。その意を汲んで「止揚」とか「揚棄」という簡潔二文字訳が為されているのであるが適切であろうか。 思うに、「止揚」の場合、「止」が決定的に意味が違う。「アオフヘーベン」の原意は止めはしない。「揚棄」の場合、「棄」が幾分筋違いではなかろうか。「アオフヘーベン」には母斑を包摂してままの脱皮的意味が有り、完全純粋に棄てやしない。「揚棄」の方が「止揚」よりは原意に近いとは思うが。 だとすれば、「アオフヘーベン」はマルクス主義にとって重要な意味を持っているのであるからして、このまま不適切訳や誤訳で済ますのは良くない。この辺りをエエ加減にしたままで推移してきているマルクス主義は、未熟なのではなかろうか。そういう状態であるのに難解に説いてきたマルクス主義学説は、難解に説くほどお笑いなのではなかろうか。 ならば、どう訳すべきか。れんだいこは、「れんだいこのカンテラ時評206、語彙の適切和訳考」で次のように記した。「れんだいこはふと閃いた。それを記そうと思うが、勿体ないので今は明らかにしない。本掲示板を見ている関心のある者の意見を求めたい。その上で、れんだいこ訳を開陳したいと思う。出来の良いのを造案したので忘れないうちに書き付けてみた」。 かく意見を求めたが、我ならこう訳すという提案はいただけなかった。つまり、反応はなかった。勿体ぶらずにこの辺りで開陳しよう思う。さて結論である。れんだいこは、「アオフヘーベン」を「出藍」と訳したい。「出藍の誉れ」の「出藍」である。「出藍の誉れ」の故事来歴については辞典で確認していただくとして(「故事来歴」参照)、「アオフヘーベン」の語義は、「止揚」、「揚棄」よりも「出藍の誉れ」の意の「出藍」に近いのではなかろうか。 マルクス主義的な事象又は認識に冠する「弁証法的らせん発展」とは、「出藍の誉れ」的にもたらされる認識の高次化過程を云うのではなかろうか。それは、内在的に理解せねばならないという意味を付与している。とするならば、外在的な解釈の余地を残す「止揚」、「揚棄」でなく、「出藍」と訳すべきではなかろうか。そういう訳で、よりまし訳として、れんだいこは以降この訳及び理解に従うことにする。 思えば、マルクス主義用語で生命とも云うべき「アオフヘーベン」を安逸に理解していることからして、既成マルクス主義運動は幼稚なものでしかなかったのではなかろうか。もっとも、マルクス主義の最新研究は、マルクス主義を高みに置くのではなく、マルクス主義から出藍せねばならないところへ来ているのであるが。 2006.10.6日 れんだいこ拝 |
||
| 【イエスの山上の垂訓「心の貧しい人々は、幸いである」考】 | |
イエスの山上の垂訓冒頭の「心の貧しい人々は、幸いである」も一考に値する。果たして適正訳なのだろうか。通説は反語的に理解して大過なきを得ているようであるが、やはり思考停止していると思わざるを得ない。私説は、「心の貧しい」は誤訳ではなかろうかと思っている。正しくは、「貧しい」を欠乏とか貧乏の意味で「貧」として捉えるのではなく、「未だ至っていない未熟域にある状態」を指しているのではなかろうかと考えている。これにどういう違いがあるのかと云うと、「心の貧しい」を「貧」で捉えると裏説教的に捉える必要があってややこしくなるのに比して、「未だ至っていない未熟域にある状態」として捉えるといわば未熟者である故の謙虚さが生まれると云うか釣り合いになる。よって、「心の貧しい人々は、幸いである」の真意は、「未だ至っていない未熟さを自覚している謙虚な人たちは、幸いである」と云う意味になる。この拝し方が、神殿本部派特にパリサイ派の「真理に到達したとする自覚者」認識による傲慢な人達との鮮やかな対比になっている。かく理解して、正しくは、「自分が未熟であることを自覚している人々は、幸いである」と訳すことになる。そうすると、山上の垂訓の冒頭はイエスの次のような御教えになる。よほど分かりやすいであろう。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)