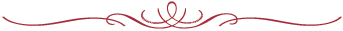
| れんだいこの翻訳テーゼ(翻訳の要諦)考 |
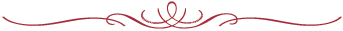
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.8.14日
関連サイト、「和訳読本」
| 【れんだいこの翻訳責務】 |
| れんだいこはなぜ翻訳に手をつけねばならないのか、それも慣れない手つきで。それは、既成市井品に満足していないからである。それも翻訳側の能力の不足によってそうであるのならまだしも、時に故意過失的な誤訳が為されていると思うからである。 思えば、れんだいが若い頃、本を手にして読み耽るもどこか釈然としない個所に何度も遭遇していた。主としてマルクス主義関係の洋書翻訳ものに多かったが。マルクス主義とは難解晦渋なものだなという感慨を覚えつつ読み進めた記憶がある。しかし、その後にれんだいこの知恵が増すに応じて、「難解晦渋」さが曲者であることに気づくようになった。果たして、マルクス、エンゲルスは「難解晦渋」に語っていたのであろうか、という疑問が湧くようになった。 確かに、マルクス、エンゲルスは、高度な見解を披瀝している。しかし、「難解晦渋」には書きつけてはいないのではなかろうか、という疑問が湧くようになった。労働者階級の知の向上、哲学的及び社会的認識の深化に向けての啓発書を著わしているが、それを読む対象が労働者階級であることを常に意識しており、必要以上に「難解晦渋」に書いてはいないはずではないか、と思うようになった。 しかし、れんだいこには、それを確かめる術がなかった。ところが面白い。インターネットの普及がれんだいこに証明機会を与えてくれることになった。まだまだ不十分とはいえ、マルクス、エンゲルス本の訳出本が公開されるようになっており、用語の英和翻訳、文章の英和翻訳も無料でできるようになっており、その気になれば「れんだいこ和訳本」ができない訳ではないという時代になっている。 こうして、2004.1.10日頃よりその最初として「フォイエルバッハ・テーゼ」を手掛け、次に「共産党宣言(「共産主義者の宣言」)」に向いつつある((「共産主義者の宣言」考))。ここまでやって判明したことは、やはりれんだいこが想像していた通り、マルクス、エンゲルスの文章は精密ではあるが何ら「難解晦渋」なものではなく、むしろ論理的であるだけ却って理解しやすいということであった。その翻訳に当って、雑に意訳されたり「難解晦渋」に訳されたり、要するに翻訳側の能力が追いついていない又は故意過失的にミスリードしているということが分かった。 そういう意味で、「れんだいこ和訳本」を世にどんどん送り出したいと思う。れんだいこにとっての問題は、それを為す時間と機会にどれだけ恵まれるだろうか、ということだけである。恨めしいが仕方がない。大幅にゆっくりになるだろうが為しえるところまでやってみたい。そして、誰かの、後世の方も含めてお役に立てれば無上の幸いというべきだろう。 締めとして云いたいことは、実際のマルクス、エンゲルスの語りを会得して初めてその見解の是非を問うべきではないのか。目下の翻訳は全体にぼやけ過ぎている。この段階で、マルクス理論を早分かりして、その上に悪乗りして批判を声高にするものはお調子もんと云わざるを得ないのではかろうか。そういうなのはれんだいこの性に合わない。 2004.1.11日 れんだいこ拝 |
| Re:れんだいこの和訳癖が止らない | れんだいこ | 2004/01/14 | |
| れんだいこは目下、マルクス、エンゲルスの「共産党宣言」を和訳している。もう少しで完訳しそうだ。分かったことは、既成の訳本をいくら読んでも理解できないだろう、それほど滅茶苦茶に翻訳されているということである。これは、訳者の能力不足が原因だろうか。普通はそう考えられるが、れんだいこは意図的に誤訳、滅茶苦茶訳されていると思っている。それほどに投降主義的合法主義党として純化している公認左派党派は汚い手を使っていると思っている。 それはともかく、れんだいこは若い頃、「共産党宣言」始めマルクス関係本を何度か読んでも意味が分からなかったことに対して、自身の能力不足を訝っていたが、そうではなくて分からないほうが賢者であったことが分かって可笑しくなった。それにしても、市井の賢者の読解力には舌を巻く。よくぞ分かってこれたもんだとふふふ。 それはそうと、興味深い次の一文に出くわした。2004.1.13日付け日経新聞「私の履歴書」にJ・K・ガルブレイスの12回目の手記には次のように書かれている。
2004.1.14日 れんだいこ拝 |
|||
| 【れんだいこの翻訳テーゼ(翻訳の要諦)考】 | ||||||||||||||||
独語を原書としてこれを英訳する際には案外楽に翻訳できるのではなかろうかと思われる。なぜなら、文法が同じだから、独語用語を英語に翻訳すれば良いだけではないかと。これに比べて、和訳の場合には文法が全く違うので困難が伴う。その際の重要な事は次の点にあるように思われる。
以上を「翻訳の三生命線」とすれば、次の注意が「翻訳の補助的留意事項」ということになる。
以上のことは、マルクス、エンゲルスの英訳板かられんだいこ和訳本を生む過程で体得した翻訳の知恵である。備忘的に書きつけておく。時間があれば、れんだいこ訳と市販訳と比較対照的に検討してみたいと思うが、今はできない。どなたか並べて確認してみて欲しい。 2022年夏頃、ふと源氏物語を読みたくなり、市井品で確認したところ、「翻訳の要諦考」に記した通りの悪訳、拙訳が相場になっていることが判明した。これでは、源氏物語に好奇心を持って近づこうとする者がいなくなるだろう。恐らく原文は現代に通じる恋愛物語になっており、それを通しての時代風刺になっており、その出来栄えは世界史上の傑作品になっているのではないのか。これを知らないのは勿体なさすぎる。かくいう私が70歳過ぎての読書であるからして、あたら惜しいことをしたという思いをひしひしと感じている。こうなるとしゃぁない、いつもの癖でれんだいこ訳を目指すことにする。 2022.8.14日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)