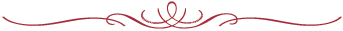
| 衝撃の誤訳指摘 |
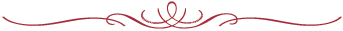
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.8日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 広西元信氏の「資本論の誤訳」(こぶし書房、2002.3.30日再初版)は非常に刺激的である。初版は1966.12.1日らしいが、2002.3.30日再出版され、れんだいこも読む機会に恵まれた。内容は、題名「資本論の誤訳」とあるが、資本論にとどまらずマルクス主義全体のいわば通念化している常識に対して、異議を唱えているところに値打ちがある。その通念常識がどうでも良いようなところのものであれば影響は無いのだが、マルクス主義の根本理解に関わるところに異議を唱えているから、衝撃は重い。主として、「誤訳」でアプローチしているが、それは手法であって、本質はマルクス主義の理解を廻っての論戦となっているところに意義がある。 非常に幸運だったことは、広西元信氏の「資本論の誤訳」が、れんだいこのモヤモヤを晴らしてくれたことである。れんだいこも、マルクス主義の理解を廻って至るところで齟齬し始めている。もはやマルクス自身の教説、その信徒の教説、流布されているマルクス主義を峻別し、今一度再整理し直さなければならないと思い立っているところであるが、広西元信氏の「資本論の誤訳」はそのモヤモヤに根拠があることを示唆してくれた。そういう意味で有り難かった。思わず読み耽った。その成果を以下記しておこうと思う。 2003.1.3日 れんだいこ拝 |
| 「資本論の誤訳」感想記 | れんだいこ | 2003/01/04 |
| 今年の正月は、広西元信氏の「資本論の誤訳」(こぶし書房)を読み進めることになった。縁あってインターネットで取り寄せた。まだ読了してないが、早くもこうして感想を記そうというほどに衝撃的であった。れんだいこは、公認マルクス主義に数々の疑問を生みつつあり、それに対置すべくいくつかの仮説を用意している。この場合、ならばマルクスの原典に当たり確認すれば良いのだが、やぶ用というかオマンマ稼業でなかなかそれもできない。そういう悩みの中で年が明け、暮れ、また明けてきた。 こたび「資本論の誤訳」を読んで、「目からうろこが落ちるほど洗われた」というより「ハタと膝を打った」という感じの方が近い。その一つ。所有と占有概念の違いを識別すること。マルクスが、占有概念で社会主義社会を透視していたという指摘に対してなるほどと思った。その二。マルクスの言説の中に国有化概念はなく、むしろ資本主義的株式会社を労働者の生産管理的方向(アソシエーション)へ発展させる必要を遠望していたこと。その限りで、ロシアのスターリニズム的国有化政策指導は何らマルクス主義的でないどころか、反対物であったこと。その三。プロレタリア独裁という概念は、共産党の独裁に道を拓く指針ではなく、社会の支配権総体に対してブルジョア独裁に対置される用語であること、等々が特に共感できた。 著者曰く、そういう読み誤りが全て「誤訳」から発している。「誤訳」の由来はまた別の考察として、世界中のマルクス主義文献の特徴となっている。数多くの著者を異にする翻訳本が出ているが、共通して「誤訳」している。無知からくるものならともかく頑迷なまでに意図的な「誤訳」もある。その「誤訳」版マルクス主義を前提にして、社会を批判し得々としている知識人が多い、との指摘もなるほどと思った。 一番為になったことは、れんだいこがこのところ関心を寄せているマルクスとルネサンス精神との絡みであった。本書は正面から問うてはいないが、マルクスがルネサンス精神の空気を吸っておりその雰囲気の中で著作している、その継承者としての立場に有ったことを示唆している。ところが、マルクス主義の後継者はここのところをすっぽり欠落させてしまう。この観点からの研究をもっとしておきたいと思った。 最後に。マルクスの資本論、その他著作での教説は、意外というか予想以上に具体的な言及をしているのではないのか。当時の社会を踏まえて極めて的確な青写真を用意し、ないし指摘していたのではないのか、そこら辺りを読み直してみたいと思った。 この理解の仕方に異論があれば、指摘して欲しいと思います。以上感想記と致します。しかしなんだな、本書に拠れば、史上のマルキストというのはみんな偽者ということになってしまう。そういう衝撃本的重みがありますね。 |
||
![]()
| 【村岡 到:書評・広西元信『資本論の誤訳』 (こぶし書房)、摂取すべき先駆的な諸提起】 | |
「カオスとロゴス」編集長・村岡 到・氏の書評「広西元信『資本論の誤訳』
(こぶし書房)、摂取すべき先駆的な諸提起」(「QUEST」第19号、2002.5月掲載)を転載しておく。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)