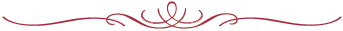
| イソップ履歴考 |
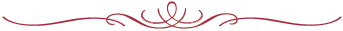
(最新見直し2010.11.05日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、イソップの人となりを確認する。「ウィキペディアアイソーポス」その他を参照する。 2010.11.5日 れんだいこ拝 |
| 関連サイト | |||
| イソップ履歴考 |
| イソップは、紀元前619年 - 紀元前564年ごろの人で古代ギリシアの寓話作家。日本では英語読みのイソップ (Æsop, Aesop) という名でイソップ寓話の作者として知られる。れんだいこ的にはもう少し知りたいが、以下の程度しか分からない。 イソップのギリシア名はアイソーポス(古希: Αἴσωπος)で、紀元前619年頃、古代ギリシア時代のトラキアあるいは小アジアのどこかで生まれている。当時の記録がなく半ば伝説の人物であるが実在したのは確からしい。紀元前5世紀のヘロドトスの「歴史」に登場しており、これがアイソーポスに関する最初の記述となっている。その生涯はよくわからない。一般に伝えられる話では、元はサモスの市民イアドモンの奴隷だったと云う。語りに長けており、後に解放されたという。その後は寓話の語り手として各地を巡ることになる。しかし、それを妬まれデルポイの市民に殺されたとされる。彼にまつわる有名な逸話に、主人の旅行の荷物持ちをした時のエピソードがある。かさばる為に他の奴隷達が持つのを嫌がった食料を進んで持ち、旅の終わりには他の奴隷達が疲れ果てながら荷物を運ぶ傍らで、中身が減って軽くなった袋を口笛を拭きながら運んでいたと云われる。イソップ物語は、紀元前300年頃、アレクサンドリアで集成されたらしい。 この解説では奴隷になった経緯、奴隷以前の身分が不祥である。イソップ物語に秘められている高度の知性を思えば、元々は高貴な身分の知識人であったと思われる。イソップ物語が如何に愛唱され、紀元前300年頃、アレクサンドリアで集成されたらしい経緯も分からない。それなりの意味が有った筈であろう。 イソップ寓話(イソップぐうわ、古希: Αισώπου Μύθοι )は、アイソーポス(イソップ)が作ったとされる動物寓話を中心とする寓話集。日本ではイソップ物語・イソップ童話と呼ばれることが多い。すべての寓話に教訓が含まれており、現在でも童話、絵本などの形で広く読まれている。イソップは多くの寓話を残したが、現在伝わっている「イソップ寓話」すべてがアイソーポスの創作ではない。それ以前から伝えられていた寓話、後に創作された寓話があとからイソップ寓話とされたりしたほか、アイソーポスの出身地(恐らく、小アジアのどこかだろうといわれている)の民話を基にしたものも多数含まれているとされる。 イソップ寓話の原文はギリシア語で書かれている。原典は失われており、現存するのは古代及び中世にバブリウス、ファエドルス、アヴィアヌス、ル・ピュイのアデマールなどによってまとめられたラテン語のものである。英語のテクストで最初に出版されたのは、ウィリアム・カクストンによる1484年の中英語のもので、その後1692年にロジャー・レストランジェがより現代英語に近い近代英語で改版した。ほぼ同じ頃、ジャン・ド・ラ・フォンテーヌがフランス語に翻案し、これが非常に有名である。 日本では、1593(文禄2)年に「イソポのハブラス(ESOPO NO FABVLAS)」として紹介されたのが始まりで、これはイエズス会の宣教師がラテン語から翻訳したものと考えられており、天草にあったコレジオ(イエズス会の学校)で印刷されたローマ字のものである。これに基づき「天草本伊曾保《いそぽ》物語」が刊行されているが、若干の記述の違いが認められる。その後、江戸時代初期から「伊曾保物語」として各種出版され、普及し、その過程で「兎と亀」などのように日本の昔話へと変化するものもあらわれた。内容は現在のイソップ寓話集と異なる話も収録されている。明治になって幕臣出身の学者で沼津兵学校校長だった渡部温が英訳からの翻訳による「通俗伊蘇普物語」(現在、東洋文庫にて入手可能)を著しベストセラーとなった。やがて修身教科書にも取り入れられたことから広く親しまれるようになった。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
2)聖書とイソップ寓話の相関関係について
1)ギリシャ語本文に関して
イソップ寓話は起源前6世紀にに実在した人物が起源である。(ヘロドドス2巻134章)彼はサモス人イアドモンの奴隷であった。その生涯は不明な点が多く最後は彼の話術に対する逆恨みを得てデルポイで処刑された。その寓話は口伝として世界に広まり、同時に様々な改編や誤訳に贋作が混在して流布したと思われる。最初にイソップの寓話を記述したのはアテネで処刑される直前のソクラテス(BC399 : プラトン「パイドン60E 」)によるものと言われるが今日にまで、その所在は確認されていない。
次に、イソップ寓話を収集したのはバレロンのデメトリオスで(BC350-280頃)当時の口伝や各種寓話の中でイソップによるものを採集しその写本はAD10世紀頃まで実在していたが今日ではその所在は確認されていない。
現存する写本で最古のものはパエドルス(BC18) によるものでラテン訳のものが5巻95話が現存している。
さて、最も信頼できるギリシャ語写本はAD1世紀の後半に記されたバブリオスによるもので143話が存在しパエドルスの95話と共にB.E.ペリーによって編纂されローブクラシカルライブラリー436番に収録されている。
今日、最も信頼できるテキストとしてはエミール・シャンブレーによる358話が最も標準的テキストとして評価さているのて是を参考のため添付する。
2.聖書とイソップの相関箇所について
前記の如く、イソップ寓話は多くの人の口と筆を通して編纂されたためどの言葉がイソップ本人の物であるのか、或いは全く無関係の作者の寓話か、さらにそれぞれが編集されたときに、どれが編集者の加筆なのかを判別することは大変困難な問題を提起する。しかし、実際その流布の年代や当時の交易範囲から考えて聖書とイソップ寓話に相関関係があり得ることは否定できないと思われる。実際後記の17か所には何らかの影響があったと推測される。しかし、聖書がイソップ寓話に影響したのか、またイソップ寓話が聖書に影響したのかは今後の解明を待たなけれはならない。
特に、今日の形にイソップ寓話が纏められる過程で聖書を伝える人々が介在したことは否定できないからである。それは日本に最初にイソップ寓話を紹介した「イソホ物語」がイエスズ会宣教師によるものであり。教父アウグスチノスもイソップに親しんだ事などからも容易にうかがいしれる。
聖書とイソップ寓話の相関関係箇所
番号 題名 共通主題 聖書箇所
No 11 エテイオピヤ人 肌の色 エレミヤ13章23節
No 19 造船所のイソップ 土と水 黙示録12章16節
No 20 2羽の雄鳥と鷲 へりくだり Iペテロ5章5節
No 24 笛を吹く漁師 笛と踊り マタイ11章17節他
No 37 狐と豹 豹の斑点 エレミヤ13章23節
No 58 人間と狐 麦畠の火事 士師15:1-8, IIサムエル14:30-32
No 59 人と獅子 獅子を殺す 士師14章5節~9節
No 66 王を求める蛙 木々にそよぐ王 士師9章1節~21節
No 69 医者蛙と狐 医者よ自分を治せ ルカ4章23節
No159 胃袋と足 肢体の自慢 Iコリント12章18節~22節
No198 惚れた獅子と百姓 自らを滅ぼす 創世記34章1節~31節
No252 木どもとオリーブ 木々にそよぐ王 士師9章1節~21節
No259 旅人と真理 捨てられた真理 箴言3章3節
No288 蛇の尻尾の導き 盲人の導き穴に マタイ15章14節他
No296 盗みをした子と母 子どもを懲らせ 箴言19章18節
No331 黄蜂と蛇 自分の死で復讐 士師16章21節~31節
No343 禿頭の騎手 裸で生まれ死ぬ ヨブ1章21節
3)相関関係箇所の考察
以上代表的17か所を上げたが、この中には明白な関係を示唆するものがある。例を上げると、
No 24 笛を吹く漁師 笛と踊り マタイ11章17節他
No 37 狐と豹 豹の斑点 エレミヤ13章23節
No 66 王を求める蛙 木々にそよぐ王 士師9章1節~21節
No 69 医者蛙と狐 医者よ自分を治せ ルカ4章23節
No252 木どもとオリーブ 木々にそよぐ王 士師9章1節~21節
No343 禿頭の騎手 裸で生まれ死ぬ ヨブ1章21節
である。それ以外は単なる偶然と思う事が可能である、しかし、上記6箇所に関しては何らかの関係があると思われる。しかし、実際にその関係を究明するためには残念な事にイソップ寓話に関する本文経歴が不明確であり、その相似点がどの時代に存在したのかを明確にする事が出来なかった。先述のペリーの編纂したバブリウスの物は紀元1世紀後半頃を参考にしてもやはりその時代には旧約聖書も新約聖書もほぼ現在の大勢が定まっていたと思われるため参考に出来ない。
従ってこの点に関しては残念な事だが、より優れたイソップテキストの入手を抜きにしては考察が出来ない。イソップ寓話が聖書と同じ言語で記されている。