75年3・14
(***しかし、やはり党の指導者であったH書記長の死は大きかったと思う。□◯派のテロで暗殺されたのであるが、そのニュースを聞いたのは党本部の書記局の部屋であった。それはもうかつて味わったことのないようなショックを受けた。党本部は3階建てのビルであったけれど、建物全体が静まり返って重苦しい雰囲気に包まれたようだった。歯をくいしばって眼に涙をうかべる者もいた。
本多さんの人物像
H氏はみんなから親しまれ尊敬されていたのだ。H氏はその当時の他派やガクセイ運動の指導者と比べてもけたちがいの人物であったと思う。彼の人物感を表する多くのエピソードがある。例えば、サンリズカ闘争の初期の頃、彼は農民の指導者の家を訪ねた時、神棚に手を合わせたという。彼にとっては唯物論者としての立場などよりも、農村の慣習をふまえ人間と人間の信頼関係を得ることこそが大事であったのであろうか。こんなことをさらっとできる人はその当時ほとんどいなかったと思う。また、彼は、機関紙やビラなどでは難解な言葉使いをことさら批判し平易な文章を心掛けろと口をすっぱくして言っていた。ほかのサヨクと言えば難解な言葉を書き連ねてそれが知的であるかのような時代にである。
70年闘争で組織破防法が発動されいよいよ危ないかという時でも党の主要な政治局メンバーがさっさと地下に移動したのにほんとは一番危ない彼が最後まで残った。また党が彼に最強の防衛隊をつけようとした時拒否されたとも聞いた。遠く離れて防衛上も安全なところから指導すべきだという意見にもがんとして拒否されたとも聞いた。そのあたりも敵の情報網にひっかかる原因があったのかもしれない。なにか当時”義理と人情の**派”と一部で言われていたけれど、これはH氏の人柄に大いに関係していたにちがいない。つくづく惜しい人をなくしたと思った。もちろん残ったS氏などもりっぱな指導者ではあるけれど、やはりH氏あってのことではないだろうか。やはりH氏ならばついていこうという面はあったと思う。いわば例えは悪いがH氏は「仁侠」にも通ずるものがあった。
【注】S氏、清水丈夫政治局員。後の「議長」
「神棚に手を合わせた云々」は60年代当時としてはさほど意外では無い気もするが、実態はどうだったろう? 筆者との世代・年代の差、70年以降の時代の空気の差、みたいなものも感じるが?
「決戦主義」と本多さんの持論
**派は当時「決戦主義」などと揶揄されたものだが、しかしそんな他派の低レベルの批判などおかど違いであり、それこそはH氏の思想そのものであった。「革命党は負けがわかっていても(たとえ局面における戦術的勝利がほど遠い場合であっても)戦わなければならない時がある」というのがH氏の持論である。奴隷根性に堕ち、敗北主義にそまるよりも階級と人民に希望を与えるために党と活動家は犠牲になって戦え、ということであった。だからこそすべての党員がどんな時であろうと「H氏なら必ずやる」という確信をもっていた。敗北主義におちいることなど一度もなかった。どんな苦しい時でも楽観主義であった。「やる時はやるんだ」という気概をすべての党員が持っていたのだ。彼についていけばまちがいないという心情すらおれにもあった。
「等価報復」「完全せん滅」
だからこそ彼が亡くなった時の悲しみは例えようもなかった。党内も激高していた。党内でも最左派でならしていたB戦闘同志会などは「□◯派本部とD労会館に突入しよう!」とか叫んでいた。H氏がテロに遇ってから1週間後、6人の□◯派戦闘員がアジトで完全××されている。党のすべての人間がそれを長いこと(たった1週間であったのに)待ち望んでいた。みんながようやく半分くらい溜飲をさげたような気がしたと思う。それは史上に残るもっとも激烈な戦闘であったようだ。新聞各紙のトップをかざり、社会面は半分以上をさいて報道していたと思う。その後の「自民党本部火炎放射焼き討ち事件」に匹敵する扱いであった。周囲の電話何万回線も切断し、敵のアジトの鉄のドアをガソリンカッターで切断し、中のバリケードを打ち壊して突入し、一方の隊は隣の部屋からスレートを巨大なハンマーでたたき壊して突入したらしい。××された6人はH氏が受けたのと同じ打撃を全員が強制されたという。部隊は全員真っ赤な返り血をあびたらしい。
この当時から「等価報復」という言葉が使用されている。(H氏の暗殺者の凶器はまさかりであったらしい。それに対して1mもあるバールで報復したらしい。その後の政治集会で60年アンポゼンガクレンイインチョウで有名なK氏は「ファシストの脳天にバールを!」とアジっていた。)その事件の報道を聞いてすべての党員が手に手をとりあって「やった、ついにやった!」と叫んでいた。それからその後の1年近くはまさしく嵐のようなテロ合戦であった。銃火器だけは使わなかったけれど、何百人もの死傷者を出した戦争以外のなにものでもなかった。
あえて言いたい。革マルは「左翼」ではない。「内ゲバ」ではない
戦争以外のなにものでもない多くの戦闘行動に俺も数多く臨戦している。歴史的事実を風化させないために俺はあえていまだ生々しい記憶を掘り起こしている。ひとつことわっておくが□◯派はもはや決してサ翼ではない。敵対党派や文化人らににわとりの生首や猫の死体を宅急便で送ったりするのはサ翼ではない。敵対的な労組の幹部らを尾行し電話を盗聴しプライベートな醜聞をさがしまくりそれをネタに恫喝するのはサ翼ではない。他派をつぶすためにのみ軍事組織をつくり、他派の戦闘はすべて「権力の謀略」であるなどとうそでぬりかためるのもまたけっしてサ翼のやることではない。他派をウジ虫とか青虫とか公然と機関紙で言ってるのもまた□◯派の本質を表している。したがってこの戦争をひとくるめに「内ゲバ」と称するのは決して正しくない。サ翼の仮面を被った、史上もっとも暴力的な新興宗教団体と言った方がいいかもしれない。事実、党首の「くろカン」としょうする人物は彼等の集会では録音テープで登場する!彼等は総立ちになって拍手するらしい。
|
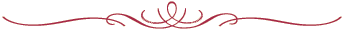
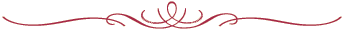
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)