| 42852 | 真珠湾攻撃秘史 |
んで、東郷外相は野村大使宛対米覚書を発電、内容は「7日貴地時刻午後1時を期し米側に 貴大使より直接御手交ありたし」と指令した。しか〜し、ワシントン大使館でタイプに手間取り野村大使がハル長官に渡したのは、何と真珠湾攻撃開始30分前の予定が、午後2時20分になってしまった。この結果、真珠湾攻撃は無通告攻撃となってしまった。これが歴史の汚点になってしまったわけです。
戦後、戦争挑発者はルーズベルトと知り、米国民は腰がぬけるほど驚く
開戦して間もなく米国では真珠湾事件審査委員会が設けられ、終戦後は上下両院議員によるロバーツ委員会が設けられて真相が究明されました。その報告書によれば戦争を企画し、戦争を準備し、遂行するための共同謀議を行ったのは・・・ワシントンのホワイトハウスの中であったのです。「戦争の張本人は日本の軍閥であった」とするルーズベルトの宣伝の根底から覆され、「捕らえてみれば我が子なり」であり、米国中驚天動地の驚きであったのです。
ゴードン・W・プランゲ著『真珠湾は眠っていたか』にまず第一に「アメリカが攻撃されない限りアメリカ人を戦線に送らない」とルーズベルトは選挙公約をしていた為、アメリカが攻撃されることが必要であった。第二にルーズベルトはハワイ攻撃が妨害されることなく行われるように、キンメルとショート(ハワイの防衛責任者)に日本のハワイ攻撃電報から入手した情報を与えないようにした。第三にルーズベルトはショートに警告しなかったことの隠蔽工作を行った」。
題名:No.356 ルーズベルトと
![]() 真珠湾攻撃に関する真実
真珠湾攻撃に関する真実
今回は、昨年出版されたロバート・B・スティネット著、『Day of Deceit』(フリープレス刊)の書評をお送りします。本書は真珠湾攻撃について、当時の米大統領フランクリン・D・ルーズベルトがそれを事前に知っていただけでなく、最初に日本が米国を攻撃するよう仕向けたのは大統領自身とその側近達であったと、機密扱いを解かれた国家安全保障公文書からの引用やその他の証拠をもとに立証しています。以下に本書の概要を紹介した書評をお送りしますので、是非お読み下さい。皆様からのご意見をお待ちしております。(ビル・トッテン)
ルーズベルトと真珠湾攻撃に関する真実
ルーズベルト元大統領が、1941年12月7日の真珠湾攻撃を事前に知っていたかどうかについては、歴史家の間で長い間議論されてきた。ロバート・B・スティネットは「情報の自由法」の下で機密扱いを解かれた公文書を17年間にわたり丹念に調べ上げ、その著書『Day
of Deceit』の中で、ルーズベルトとその最高顧問たちが真珠湾攻撃の前に日本の戦艦がハワイに向かっていると知っていたことを示す、確固たる証拠を提示している。そしてスティネットは、本書の核心として、ルーズベルトは当時第二次世界大戦への参戦に否定的だった米国世論を戦争支持に変えるために日本を挑発する政策をとったと主張している。
米国がまだ大恐慌の後遺症に苦しんでいる頃、ルーズベルトはすでに、ヨーロッパでの戦争に米国が最終的には巻き込まれると予見していた。そしてイギリスが日独伊枢軸国に敗れることになれば、世界が危険な状況に直面すると恐れ、参戦はせずとも可能な限りイギリスを助けていた。イギリスに必要物資を提供するため武器貸与法を成立させ、カリブ海の海軍基地と引き換えに50艘の駆逐艦をイギリスに提供し、また米国の「中立」という立場の解釈を最大限に拡大して大西洋の巡視も開始した。
米国の世論調査では、88%の国民が海外派兵に反対しており、ルーズベルトはこれ以上戦争に肩入れすれば初の3期目の再選が危ぶまれることを承知していた。さらにルーズベルトは米軍を海外派兵しないことを公約にしていたのである。
そこへ願ってもないチャンスが訪れた。1940年10月7日、アーサー・H・マクカラム少佐が海軍諜報部の長官に、米国の参戦を容易にかつ正当化するための8つの行動からなる計画を送ったのである。その計画とは日本との戦争開始を最優先にしたものであり、米国を軍事攻撃せざるを得ない状況に日本政府を追い込むための一連の方策が盛り込まれたものだった。そして、日本領海内への米国の戦艦配備や、日本経済の圧迫を狙った完全な経済封鎖を含むこのマクカラム少佐の8つの提案を、ルーズベルト大統領は即座に実行に移し始めたのであった。
ルーズベルトはどうしても日本に奇襲攻撃をさせる必要があった。そうなれば、米国は自己防衛のために行動しているのであり、海外派兵は行っていないと有権者に説明できる。日本の奇襲攻撃により米国民が一致団結し、孤立主義は終わるとルーズベルトは見込んだのであった。
著者のスティネットは、ジョージ・ブッシュ大尉の下で第二次世界大戦に参戦し受勲した海軍退役軍人である。彼は、様々な政府および軍の覚書や記録から、説得力のある証拠文献を豊富に引用し、自らの主張を実証した。日本艦隊の無線は決して傍受されなかったという神話を覆し、12月7日の10日前に、米国の暗号解読者が日本海軍の無線をいくつか傍受し、日本が真珠湾を攻撃することを米側は事前に掴んでいたことを明らかにしている。ハワイの高級将校たち(太平洋艦隊司令官のハズバンド・キンメル海軍大将とウォルター・ショート陸軍中将)は、政府の指令に関する連絡網から外され、さらに日本の真珠湾攻撃を事前に察知できなかった責任を被せられ、解任されている(米上院は1999年5月、彼らの容疑を晴らした)。実際には、キンメル海軍大将は艦隊を北太平洋に移動させ、日本の部隊集結地を積極的に探していたが、海軍本部はキンメルに戻ってくるように命令していた。
さらにスティネットは、真珠湾攻撃が終わるやいなや、どのように証拠隠滅が始められたかについても触れ、海軍将官がすべての覚書や書類を破棄するよう命令したとし、さらに本書の最後では、今も、ルーズベルト元大統領がこの陰謀に荷担していなかったことを証明しようとするいい逃れやごまかし、偽証が行われていると記している。
スティネットは、ルーズベルトが日本を騙すためにとった策略は憎むべき行動だと信じてはいるものの、「ルーズベルト大統領が直面した、苦痛を伴うジレンマは理解できる。彼は、孤立主義をとっていた米国に自由のための戦いへの参加を納得させるため、間接的な方法を見つけなければならなかったのである」と語っている。ただし、これは単に理解できるということに過ぎず、決して容認しているわけではない。
もしスティネットの主張が正しければ、ルーズベルトは真珠湾の犠牲となった米国人の英霊に対して多くの責任を負っている。スティネットは本書において、米海軍が日本の真珠湾攻撃を少なくとも予期はしていたと、ほぼ確実に立証している。ルーズベルト大統領自身がその攻撃を意図的に挑発したという見方は情況証拠でしかないが、今後米国内においてかなりの論議を呼び起こす説得力を持っているといえるだろう。
アメリカ側は単に襲撃を察知していただけでなく、むしろ意図的に日本をそこへ導いたというのが、本書の主張である。にわかには信じがたいような話だが、「情報の自由法」(FOIA)により近年ようやく日の目を見た未公開資料の山が、圧倒的な説得力で迫ってくる。なかでも中心となるのは、真珠湾の前年、海軍情報部極東課長マッカラムが起草した、日本への戦争挑発行動覚え書だろう。以後の対日政策は、まさにこの覚え書どおり進行している。また、開戦直前の日本艦隊には「無線封止」が行われたというのが定説だが、実際はきわめて無造作に通信が交わされており、その大半が傍受解読されて作戦は筒抜けだった。これまた驚くべき話だが、130通にも及ぶ傍受記録をつき突き付けられては納得するしかない。
著者は執拗なまでの粘り強さで資料を博捜し、これまでの常識や偽られた史実を次々と覆してゆく。情報重視の姿勢は、収集した資料を公開するほどの徹底ぶりで、有無を言わさぬ信憑性がある。むろん、いまだ閲覧を許されない極秘文書は数知れず、各方面からの反論も多々想定されるが、本書によって真珠湾研究が次の段階へ入ったことは間違いない。今後、この著作を経ずして真珠湾を語ることはできないだろう。それだけの重みをもつ本である。(大滝浩太郎)
http://www1.linkclub.or.jp/~frank/history/pearl.html
|
|
なぜ、宣戦布告がなされなかったか。 |
|
|
アメリカ海軍は、暗号を解読していながらなぜハワイ艦隊に警戒命令を下さなかったか。 |
|
|
アメリカのルーズベルト大統領は、日本の真珠湾攻撃を事前に知らされていたか。 |
|
|
日本の連合艦隊機動部隊は真珠湾攻撃の際なぜ第二次攻撃をしなかったか。 |
|
|
山本長官は、この攻撃の真の目的をなぜもっと部下に下達・徹底しなかったのか。 |
|
|
日米関係が緊迫しているこの時期に、外務省はなぜアメリカ大使館員の転勤を実施したのか。 |
| 昭和 | 西暦 | 月・日 | 日米間の出来事 | その他の国際情勢 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1940 | 1月14日 | 阿部信行内閣総辞職 | |
| 1月16日 | 米内光政内閣成立 | |||
| 1月26日 | 日米通商航海条約期限切れ、無条約時代に入る | マレー沖海戦 | ||
| 3月上旬 | 臼井大佐(参謀本部主務課)と鈴木中佐が重慶政府代表の宋子良と香港で会談(桐工作) | |||
| 3月12日 | 汪兆銘、和平建国宣言を発表 | |||
| 3月30日 | ハル国務長官、南京政府否認声明 | 汪兆銘を主席とする南京政府樹立 | ||
| 5月上旬 | 重慶爆撃開始 | |||
| 5月11日 | 有田外相、蘭印現状維持を各国駐日大使に申し入れる | |||
| 5月18日 | 御前会議で対支処理方策を決定 | |||
| 5月25日 | 有田外相、バブスト駐日蘭大使に対蘭印13項目の要求を送る | |||
| 6月3日 | 工作機械の対日輸出禁止 | |||
| 6月9日 | ノモンハン国境確定交渉成立 | |||
| 6月12日 | 日タイ友好条約締結 | |||
| 6月18日 | 米下院海軍委員会で海軍拡張案(両洋艦隊法案)が可決 | |||
| 6月24日 | ビルマおよび香港経由による蒋介石政権援助物資輸送停止をイギリスに申し入れる | |||
| 7月16日 | 米内内閣総辞職 | |||
| 7月22日 | 第二次近衛内閣成立 | |||
| 7月25日 | ルーズベルト大統領、石油と屑鉄を対日輸出許可品目に加える | |||
| 7月26日 | 閣議で大東亜新秩序と「基本国策要綱」を決定 | |||
| 7月27日 | 政府・大本営連絡会議で「時局処理要綱」が決定 | |||
| 9月3日 | 米英防衛協定調印 | |||
| 9月16日 | 米で選抜徴兵制公布 | |||
| 9月19日 | 支那派遣軍総司令部、桐工作(対重慶和平工作)の一時打ち切りを決定 | |||
| 9月22日 | 日・仏印軍事協定成立 | |||
| 9月23日 | 北部仏印進駐 | |||
| 9月25日 | 米陸軍通信隊、日本海軍の暗号解読に成功 | 米、重慶政府に2500万ドルの借款供与 | ||
| 9月27日 | 日独伊三国同盟調印 | |||
| 10月8日 | 極東の米国人の引き揚げ勧告 | |||
| 10月14日 | ルーズベルト大統領、レインボー計画(陸海軍統合戦争計画)を承認 | |||
| 10月15日 | 松岡外相、グルー駐日米大使と会談 | |||
| 10月16日 | 米国、屑鉄と鋼鉄の対日輸出禁止 | |||
| 10月30日 | 日ソ交渉開始 | |||
| 11月6日 | ルーズベルト、大統領に三選される | |||
| 11月30日 | 南京政府(汪兆銘政権)承認 日華基本条約調印 |
|||
| 12月5日 | ウォルシュ司教、ドラウト神父、松岡外相を訪問 | |||
| 12月28日 | ウォルシュ、ドラウト帰米 | |||
| 16 | 1941 | 1月8日 | 米全艦隊を太平洋・大西洋・アジアの三地域に編成替え | |
| 1月30日 | 日本の調停によりタイ仏印停戦協定調印 | |||
| 2月3日 | 対独伊ソ交渉案要綱を決定 | |||
| 2月11日 | 野村吉三郎駐米大使ワシントンに着任、日米交渉が本格化 | |||
| 3月8日 | 第一回目の野村・ハル会談 | |||
| 3月11日 | 米で武器貸与法成立(英国援助を強化) | |||
| 3月12日 | 松岡外相、ソ連経由で独伊訪問に出発 | |||
| 3月14日 | 第二回目の野村・ハル会談 | |||
| 3月17日 | 「日米協定草案」起草 | |||
| 3月23日 | 松岡外相、スタインハート駐ソ米大使と会談 | |||
| 4月9日 | 野村大使、日米交渉のための第一次日本案を提出 | |||
| 4月13日 | 日ソ中立条約調印 | |||
| 4月14日 | 野村・ハル会談、米の対中国三原則が示される | |||
| 4月16日 | ハル国務長官、野村大使に日米交渉の四原則「日米了解案」を提示 | |||
| 5月12日 | 野村大使、ハル国務長官に修正案を提出 | |||
| 5月27日 | ルーズベルト大統領、国家非常事態・臨戦態勢を宣言 | |||
| 5月31日 | 米側「中間案」を提示 | |||
| 6月12日 | 日ソ通商協定・貿易協定成立 | |||
| 6月14日 | ルーズベルト大統領、独伊の在米資産凍結を命令 | |||
| 6月21日 | ハル国務長官、5月31日の米側「中間案」の修正と松岡外相を避難するオーラルステートメントを野村大使に手渡す | |||
| 6月22日 | 独ソ戦開始 | |||
| 7月1日 | 独伊、汪兆銘政府承認 | |||
| 7月2日 | 重慶政府、独伊と国交断絶 | |||
| 7月12日 | 英ソ相互援助協定調印 | |||
| 7月15日 | 日米了解案をめぐり松岡外相と近衛首相が対立 | |||
| 7月16日 | 閣内不統一で第二次近衛内閣総辞職 | |||
| 7月18日 | 第三次近衛内閣成立、豊田海軍大将が外相に就任 | |||
| 7月21日 | 日・仏印防衛協定成立 | |||
| 7月25日 | ルーズベルト大統領、米国内の日本資産を凍結 | ガソリンの対日輸出禁止・日本への石油製品売却を禁止 | ||
| 7月26日 | 英、国内の日本資産凍結および日英通商航海条約、日・印通商条約、日本ビルマ間通商条約破棄。蘭印政権が在留邦人の資産凍結を布告 | |||
| 7月28日 | 南部仏印進駐 | |||
| 8月1日 | 米、対日石油輸出を全面禁止 | |||
| 8月2日 | 米、ソ連へ計107億ドルの武器、経済援助を決定 | |||
| 8月8日 | 野村大使、ハル国務長官に日米首脳会談(ハワイ会談)開催を提案 | |||
| 8月12日 | ルーズベルト大統領とチャーチル首相が共同で大西洋憲章を発表 | |||
| 8月17日 | 野村、ルーズベルト大統領会談。対日警告文と首脳会談に対する回答が伝えられる | |||
| 8月18日 | 豊田外相、グルー会談 | |||
| 8月28日 | 野村大使、ルーズベルト大統領に日米首脳会談を申し入れる | |||
| 9月2日 | 陸海軍部局長会議で「帝国国策遂行要領」の陸海軍案を策定 | |||
| 9月3日 | 米側が日米首脳会談について事前討議の必要を回答 | |||
| 9月4日 | 野村大使、新たな「共同声明」を申し入れる | |||
| 9月6日 | 御前会議で「帝国国策遂行要領」決定 | |||
| 9月13日 | 政府・大本営連絡会議で「日・支和平基本条件」を決定 | |||
| 10月1日 | 対ソ援助のための米英ソ議定書調印 | |||
| 10月2日 | 米側、強硬な「覚書」を提示 | |||
| 10月12日 | 対米和戦の会議が近衛別邸で開かれるが、陸相(東條英機)の不同意で未決 | |||
| 10月15日 | ゾルゲ事件発覚、ノモンハン国境協定調印 | |||
| 10月16日 | 近衛内閣総辞職 | |||
| 10月18日 | 東條内閣成立 | |||
| 11月5日 | 御前会議で対米交渉案(甲・乙案)と12月1日午前零時までに対米交渉成立の場合は開戦中止を決定、大本営は対米英蘭作戦準備を命令 | |||
| 11月6日 | 米、10億ドルの対ソ武器貸与借款を決定 | |||
| 11月7日 | 野村大使、甲案を米側へ提示 | |||
| 11月13日 | 米下院で中立法修正案通過(実質的に中立政策を放棄) | |||
| 11月15日 | 来栖三郎特命全権大使ワシントンに着任、大本営陸軍部が、南方軍に作戦命令を下令 | |||
| 11月20日 | 野村、来栖両大使、米側に乙案を提示 | |||
| 11月22日 | ワシントンで米・英・蘭・華会議開催。英国艦隊(プリンス・オブ・ウェールズ、レパルスほか)極東派遣 | |||
| 11月26日 | 米側から提案(ハル・ノート)が示される。ハワイ作戦機動部隊が択捉島の単冠湾をハワイに向けて出航 | |||
| 11月27日 | 政府・大本営連絡会議でハル・ノートを最後通牒と結論する | |||
| 12月1日 | 御前会議で対米英蘭開戦決定 | |||
| 12月5日 | 野村・来栖両大使、日本側回答をハル国務長官に手交 | |||
| 12月6日 | 野村大使宛、対米最終覚書を打電 | |||
| 12月8日 | ホノルル時間7日午前6時45分、米駆逐艦ウォードが真珠湾港外で特殊潜航艇を撃沈 | |||
| ホノルル時間午前7時55分、第一次攻撃隊が真珠湾攻撃を開始 | ||||
| ワシントン時間午後2時20分(ホノルル時間午前8時50分)野村、来栖両大使、ハル国務長官に日本政府の最後通牒を渡す | ||||
| 日本時間午後4時、米英に宣戦布告の詔勅を発表 | ||||
| 米議会で対日宣戦布告決議を可決 | ||||
| 12月11日 | 独伊、対米宣戦布告 |
| Column of the History |
| 86.「真珠湾奇襲」は嘘だった!! ── アメリカの対日先制攻撃 (2001.2.21) |
|---|
[トップページ] [前のページ] [次のページ] [コラム目次] [歴史用語解説集] [歴史関連書籍案内]
昭和16(1941)年12月7日午後1時30分(現地時間 日本の日付では12月8日)、択捉
"Remember Pearl Harbor!!"
(真珠湾を忘れるな!!)
と言っては、軍を鼓舞してきました。しかし、日本軍による「真珠湾攻撃」は、果たして、本当にアメリカが主張する様な「奇襲」だったのでしょうか? 実は、「奇襲」を掛けてきたのは、むしろ、アメリカの方だったのです。と言う訳で、今回は、アメリカによる「奇襲」
── 対日先制攻撃を通して、「騙し討ち」の汚名を払拭したいと思います。
何故、「真珠湾攻撃」は、アメリカから「真珠湾奇襲」
── 「騙し討ち」と言われなくてはならないのか? 実は、開戦当日、ワシントンの日本大使館が「大失態」を犯したからなのです。日本が真珠湾を攻撃したのが、12月7日の午後1時30分(現地時間)。しかし、ワシントンの日本大使館がアメリカ側に「国交断絶通告」
── 「宣戦布告」を届けたのは、何と真珠湾攻撃から30分後の午後2時(現地時間)だったのです。つまり、「真珠湾攻撃」が先で「宣戦布告」が後となってしまった訳で、これが後々迄、「騙し討ち」と言われる事となった所以(ゆえん)だったのです。(ちなみに、「大失態」を犯して日本の名に泥を塗った「国賊」大使館員達は、何の裁きも受けず、戦後、高級外務官僚となった) つまり、昭和天皇・日本政府・大本営・連合艦隊司令長官(山本五十六)共に、アメリカに対して「騙し討ち」をしよう等とは、露とも思ってはいなかったのです。本来、「国交断絶通告」は、12月7日午後1時(現地時間)に届けられる筈でした。日本から無電で送られた暗号電報を解読し、成文化した上で、アメリカ側に届ける。この重要な任務を、ワシントンの大使館員達は、赴任する同僚の送別会を優先した結果、処理に遅れを来たし、攻撃よりも後に届ける羽目となったのです。致命的です。これでは、アメリカから「騙し討ち」と言われても仕方がありません。し・か・し、敢えて言います。「騙し討ち」を掛けてきたのは、アメリカの方だと。
12月7日午後0時10分(現地時間)、アメリカ海軍司令部に一つの暗号電報が入電しました。
「ワレ、日本潜水艦ヲ撃沈セリ。」
それは米軍艦が、公海上 ── アメリカの領海外において、日本海軍の潜水艦を攻撃、撃沈した事を報告する暗号電報だったのです。(米国海軍ヒューウィット調査機関提出書類75(1945年6月7日),みすず書房『現代史資料
35巻』)
つまり、アメリカは、日本による「真珠湾攻撃」の1時間20分も前に、「宣戦布告」もなしに、日本の潜水艦を攻撃、撃沈した事になる訳で、これこそ、正に「騙し討ち」と言えるのです。それにしても、日本の「真珠湾攻撃」をもって「騙し討ち」と言わしめたのですから、ルーズヴェルトも相当の極悪人です。
| 12:10 | 米軍、「宣戦布告」無きまま、日本潜水艦を攻撃し撃沈(対日開戦) |
| 13:00 | 本来、日本側が「国交断絶通告」をアメリカ側に通達すべきだった時間 |
| 13:30 | 日本軍、ハワイ・真珠湾を攻撃(対米開戦) |
| 14:00 | 在ワシントン日本大使館、「国交断絶通告」をアメリカ側に通達 |
「攻撃を受けた場合を除いて、国民を戦場に送る事は決してあり得ない。」 こう公約していたルーズヴェルトでしたが、内心は戦争がしたくて、戦争がしたくて、堪らなかったのです。そんなルーズヴェルトでしたから、日本に先制攻撃をさせる事に腐心したのは言う迄もありません。ラニカイ号を含む老朽船3隻に星条旗を掲揚させた上で、日本軍艦に接近させ、日本軍艦から先に砲撃してくるよう、挑発をしたりもしています。しかし、攻撃命令を受けていない日本軍艦は静観するに留まり、遂に先制攻撃を掛けなかったのです。(米国アナポリス海軍研究所『ラニカイ号の巡洋航海
── 戦争への挑発』)
「いかに日本を操り、我々の損害は少なくし、いかにして最初の一発を撃たせる様にし向けるかが問題だ、とルーズヴェルト大統領は語った。」(スチムソン・米国陸軍長官の日記より)
そんなルーズヴェルトでしたから、「真珠湾攻撃」の一報が入った時には、さぞかし狂喜乱舞した事でしょう。しかし、それは「糠(ぬか)喜び」でした。「真珠湾攻撃」の1時間20分も前に、「宣戦布告」無きまま、米軍が日本潜水艦に対して「先制攻撃」をしていたのですから・・・。
暦
[トップページ] [前のページ] [次のページ] [コラム目次] [歴史用語解説集] [歴史関連書籍案内]
・歴史に名高い
真珠湾攻撃ミッション
1941年12月8日 ワレ、奇襲ニ成功セリ。
日本軍は、空母6隻を真珠湾攻撃の拠点とし、フォード等周辺に在泊する米太平洋艦隊の艦艇・施設への攻撃を開始。あなたの任務は爆撃機を援護し攻撃を成功させ、無事帰還することだ・・・あの真珠湾攻撃がミッションとして登場。日本軍からの攻撃に応戦する、米軍側のミッションもあり、2つの視点から楽しむことが出来ます。

|
歴史上に残る魚雷攻撃をはじめとする全10のミッションを収録。
|
|
|
ミッション一覧
■鹿児島湾浅海面雷撃訓練
真珠湾攻撃に先立ち、雷撃訓練を行う。鹿児島鴨池基地から離陸し、海面スレスレまで降下して目標を雷撃せよ。
■第一次攻撃隊水平爆撃隊 淵田美津雄中佐
九七式艦上攻撃機隊を率い、米戦艦アリゾナを爆撃せよ。
■第一次攻撃隊雷撃隊 村田重治少佐
九七式艦上攻撃機隊を率い、米戦艦ウェストヴァージニアを雷撃せよ。
■第一次攻撃隊降下爆撃隊 高橋赫一少佐
九九式艦上爆撃機隊を率い、ヒッカム飛行場に駐機中の米機を爆撃せよ。
■第一次攻撃隊制空隊 板谷茂少佐
零式艦上戦闘機隊を率い、敵迎撃機を一掃せよ。
■第ニ次攻撃隊水平爆撃隊 嶋崎重和少佐
九七式艦上攻撃機隊を率い、フォード島基地に駐機中の米機を爆撃せよ。
■第ニ次攻撃隊降下爆撃隊 江草隆繁少佐
九九式艦上爆撃機隊を率い、米戦艦ネヴァダを爆撃せよ。
■第ニ次攻撃隊制空隊 進藤三郎大尉
零式艦上戦闘機隊を率い、敵迎撃機を一掃せよ。
■アメリカ陸軍 P-36Aホーク戦闘機
日本軍の来襲だ。直ちに離陸し日本軍機を撃墜できるだけ撃墜し、帰還せよ。
■アメリカ海軍 PBYカタリナ飛行艇
(架空戦記)日本軍攻撃隊が帰還する。彼らを密かに追尾し、日本軍機動部隊を攻撃せよ。
|
|
終戦前後2年間の新聞切り抜き帳(21)
真珠湾攻撃・風船爆弾・人間魚雷
真珠湾攻撃と九軍神

この写真は、開戦の頃を風靡した有名な写真です。
真珠湾攻撃の時、潜航艇に乗り組んで湾内に入り込み
海中から米艦隊を攻撃した九人の勇士です。
(雑誌から拝借したコピーです)
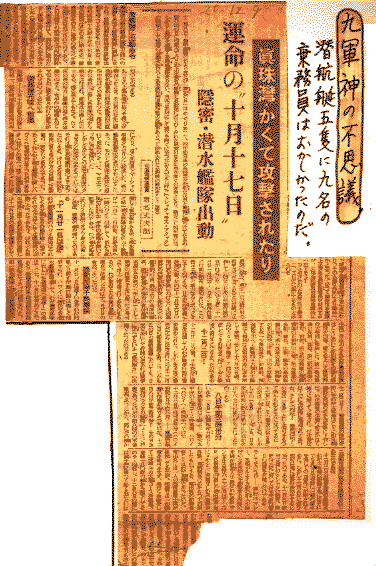
この記事は、いかにして真珠湾を攻撃したか、その経過
を書いてあるもの。戦略的な文面なので、一般向きとしては
それほど興味は湧かない。然し、当時は初めて知った事実
だけに驚きの目で見つめていた。

九軍神の不思議!
五隻の潜航艇に九名の
乗務員はおかしかったのだ!
新聞記事全文(すぐ上の記事のみ)
(20年12月9日付け)
生きていた[真珠湾の勇士]
大本営発表の欺瞞白日の下に
無謀なる対米宣戦の日、今を去る四年前の12月8日、オアフ島米軍軍事施設に奇襲をかけたわが航空部隊のあとを受けて月青き真珠湾に隠密潜入、深傷を蒙った米大平洋艦隊に第二回目の攻撃を敢行した日本特殊潜航艇五隻の乗組員九名は軍神として全国民崇敬の的となったが、この艇五隻に乗組員九名という大本営発表に当時国民は割り切れぬものを抱きながらも日本側では攻撃に参加せる者は最初から九名であったと宣伝、国民一般にそう思い込ませてしまった。今回マニラから引き揚げた一邦人によって初めてその真相が伝えられ、一名は生き残って最初の日本軍捕虜として現在米本国に収容されていることが明らかにされた。同邦人はマニラにあって捕らえられ永い米軍捕虜収容所生活中に米人将校から得た確実な消息を齎したものであるが、同氏の語るところによると真珠湾攻撃に参加した五隻の特殊潜航艇は奇襲敢行直後出動した米海軍の爆雷攻撃によって全滅し、その一隻が岸近く打上げられた、米軍側では直ちにこれを陸揚げして艇内を検分すると一名は戦死、他の一名は爆雷の衝撃によってひん曲がった同艇内に挟まれ瀕死の状態に陥っていた。
直ちに救出、手厚い看護によって一命を取止め日米開戦初の捕虜となったのである。その後の彼は捕虜番号「第一号」ということが悪気のない米国人気質に投ずるに十分であったのであろう。「真珠湾を忘れるな」と全米人を激怒せしめたにも拘わらず交戦国捕虜としては全く不相応の厚遇を受けているのである。今米本国の基地に移されているが、全く不自由のない生活を送り、一度は生還を期せず殉国の若き血潮を燃やして豆粒の艇に乗り組み、九名の同僚とともに真珠湾の海底に運命をともにしたなら武人最高の栄誉たる「軍神」に祭り上げられた彼であるが、今更のように非人道的日本の軍閥に愛想をつかし、日本へは気持ちはないと称しているといわれる。なおこの事実に関しては当時米側当局より中立国を通じて詳細日本側に通達の手続きがあったといわれるが大本営は国民に対して何等発表しなかったものである。右につき第二復員省(元海軍省)当局者は次のごとく語った。
当局としては捕虜となった軍人の名前を公表したことは未だ嘗てその例を見ないし日本人の立場として、また捕虜となった家族の心情を推察して当局から直接の公表を避けている。いずれにしてもこの問題は一度世界に出なければならない問題あるだけに当局にしても一応家族との連絡を終えた後に何等かの形で近いうちに発表されることになろう。
(仮名遣いは現代仮名遣いに直してあります)
-------------------------------------------------------------------
真珠湾攻撃はアメリカ側の「罠」にはまっただけの事ではないのか---このことについては随分と論議されてきています。
確かにおかしいと思う点が多々あります。湾内に並べられていた艦船は旧式の型が多く、特に戦艦は中古品に近いものでした。
どうせ新しく作るのなら中古品は戦術的に利用した方が得策だったと考えたとしても不自然ではありません。特に変なのは空母が一隻も並べられていなかった点、これは絶対におかしいと言い続けられています。
戦時中「ハワイ・マレー沖海戦」という映画がやってきて、学校で見に行った覚えがあります。内容はすべて忘れてしまっていますが、たった一箇所、文字通りワンシーンだけ覚えています。
湾内に潜入し、無事所定の攻撃を終えた潜航艇が余裕を以て海上に浮かび上がり、ハッチが開き、中から美男子の海兵さんが出て来て、彼方の燃え盛る敵艦船をキリリとした表情で、満足そうに見つめている光景でした。現地は真暗な海上の筈なのに、何故か、海兵さんの姿は煌々とスポットライトを浴びたように明るく眩しく見えていました。------それが記憶の断片として残っている一箇所のシーンです。
米軍の発表では、それらの豆潜水艦は、現地では、戦闘に参入する前に駆逐艦や水雷艇などの爆雷攻撃の標的になり全く為すすべもなく自滅した、と報ぜられています。そのどちらが正しいのか知る由はありませんが、彼我の戦闘能力の差があまりにも大きいので、どうやら米軍の報告の方が的を得てるような感じです。
スポットライトを浴びて輝いていた海兵さんは、すでにその時はバラバラになって海中の藻屑と消えていたのです。 ----それが軍神の姿でした。
------------------------------------
風船爆弾

新聞記事全文
AP東京特派員はわが風船爆弾について次のように語っている。日本軍の高価なV-1号兵器「紙風船爆弾」はドウリットルの東京空襲の復讐として企画されたが、日米両国の黙殺にあって、簡単に放棄された。日本陸軍技術本部将校は二日特にAP記者に説明した。
ドウリットルが東京の空を騒がしてから三年間、今年四月二十までに放射された風船爆弾は九千個に達し、いずれも東京に近い三拠点から行われた。この第一弾が完成し放射されるまでには二ケ年以上の歳月が費やされ、九百万円以上の費用が投ぜられた。実際に米大陸に到着したものはワイオミング州に着いたその第一弾のみであった。爆弾の効果に就いて重慶放送によるアメリカの情報を絶えず注意していたが、この爆弾についてその後何等の情報もなくついに風船爆弾の使用は無意味であるとの結論に達した。この爆弾の狙ったところは日米両国民に対する心理的効果であった。
日本国内においてこの秘密兵器についての宣伝は特にされなかった。それはアメリカにおける実際の効果について確証を握っていなかったからだ。日本国民は新聞紙上で僅かに知った程度であった。山火事をおこしあるいは都市に落下せしめて民心の動揺を狙ったものであるが、爆弾はあまりにも小さく操縦の方法がないので、軍事施設の破壊が可能であるとは予期しなかった。爆弾には目玉がなく、爆発地点を選ぶ能力はないが米大陸の広さからいって、どこかに落下するであろうと思っていた。
直径三十フイート以上
日本の帝国主義者も一般国民も空襲の範囲からアメリカ人はずっと離れているから、直ちにアメリカ人のところまで到達できる武器を発見するための努力がはじめられた。同じような方法でこれより十年前にすでに知られていた風船爆弾の原理最高空の天気の状況を知る為に利用された。爆弾にも同じような考え方が用いられるという提案が軍の士官と民間の種々な方面から提出された。陸軍省では絶えず民間からも手紙を受け取っていた。その方面の技術部の士官達はその詳がを纏めていた。いろいろな実験の後これらの武器の製造が千九百四十四年の夏に始まった。その最初のものはその年の十一月に現われた。日本は風船に紙を使わなければならなかった程窮状にあった。
その風船は直径が三十フイート以上であったが、非常に薄いものであった。そのため五枚の紙を膠で張り合わせてあったと士官達はいっていた。この部分は日本の一般人によって作られた。
爆弾は造兵廠で特別に企画されたが、最大搭載量は六十ポンド、一発の重量は三十ポンドであった。使用された爆弾の三分の二は焼夷弾でその他は人名殺傷弾であった。これら爆弾の放射地点は東京の東北約六十マイルの大津及び勿生の海岸と東京の東方約二十マイルの一の宮の三ケ所であった。風船は海岸に広げられてガスを充填し爆弾を装置したのちに係留ロープ切断とともに空中高く舞い上がっていった。
地上部隊が時計仕掛で
科学者達は既に創造してしまった風船爆弾は空に向かって一万ヤード上がり、強い東風に乗ってアメリカの西海岸まで直線距離五千マイル以上を時速百二十五マイルから百九十マイルで到達するものと考えられた。風船爆弾は上げられてから四十時間から五十時間たつと空中に向かって爆発するようになっていた。
風船爆弾を打ち上げる時は地上部隊が時計仕掛をする時附近の漁村の僅かな日本人がそれを見ていた。士官達のいうところによれば風船爆弾を打ち上げるには冬が一番よい時季でもあり、かつ天気の良い方がよいということである。それで五ケ月間に三つの打ち上げる場所で一日平均二十個の風船爆弾が打ち上げられた。天候の悪い時には時間を延ばしても打ち上げていた。士官達は悲しげに海軍の神風、または人間ロケット砲などに相応するところの名前をこの武器につけられなかったと説明していた。
(※仮名使いは現代仮名にしてあります)
---------------------------------------------------------
このAP電の記者の記述は、日本の当事者から聞いた話として書かれていますが、実際はどうであったか、米国側のコメントを加えた形で書かないと正確な記事とはなりません。その範囲ではこのレポートは間違っています。
後年、それに関する米国の雑誌記事を読んだのですが、米本土に到達した風船爆弾の數は数百個はあったような記憶があります。アメリカ本土に到達した地点を黒丸で表していた地図が載っていたのですが、ほぼ全土にわたって黒丸がついていました。風船爆弾は大変な脅威をアメリカに与えたのです。ただ、軍によって徹底した情報制限と管理がなされ極力情報漏失を防いだので、被害は勿論、住民達の不安動揺などについては日本軍に伝えられる事なしに終わったとのことでした。
かって私は福島県小名浜町に住んだことがあります。そこは風船爆弾の打ち上げ地点である勿生(なこそ)の近くでした。そこで聞いた範囲では、風船爆弾の打ち上げは連日行われていたとの事です。立ち入り禁止区域があるわけでなし、誰でも邪魔にならぬ範囲の遠くからであれば自由に見物は出来たと言っていました。[--附近の漁村の僅かな日本人がそれを見ていた...]とする記述も何かしら作為を感じさせるような悲観的な記述の仕方です。
風船爆弾は両国の国技館の中で作られました。昭和20年3月10日の東京大空襲の[前後]にわたってその建物が利用された、とあるので、際どい場所でありながらそれに代わる代替地はなかったのだと思われます。
なお、それに携わった労働者は専ら[学徒動員]で集められた女子学生であったと聞いています。
現在、両国にある[江戸東京博物館]に残された本物の風船爆弾が飾られてあります(間違いはないと思いますが)。ただ、見た限りでは直径30フイート(約10メートル)はなく、目見当では数メートルと小振りだったような気がします。
---------------------------------------------------------------
朝日新聞に載った風船爆弾の著書[吉野興一著]紹介--2000年11月12日(朝刊)評者・中野翠 氏
苦肉の策と思ったら周到な研究が背景に
風船爆弾 純国産兵器「ふ号」の記録
実は、先月中旬のNHK「ニュース10」での特集を見て以来、風船爆弾には興味をかき立てられていた。
風船爆弾とは言うまでもなく、太平洋戦争末期に日本軍がアメリカに向けて飛ばした奇妙な爆弾のことである。原爆を持つ国に対して風船爆弾。「竹槍で本土決戦」というのと同じようなもの。敗色濃厚の日本軍はそんな荒唐無稽な思いつきにすがるほど追い詰められていたのだ----とばかり思い込んでいたのだが、意外にも風船爆弾は偏西風を巧妙に利用した兵器で、一発はオレゴン州で爆発し、六人の死者を出すという「戦果」も上げていたというのだ。
私が最も興味をひかれたのは、風船の素材が和紙とコンニャク糊だったという事だ。今テストしてみても「引っ張られても裂けない強さ」において和紙はアルミ以上に優れていると言う。爆弾を積み込み、高度一万メートル以上の所を敵国へと向かう巨大風船----。なんと風雅でむごい怪兵器!と私は唸ったのだった。
タイミングよく出版された本書は、期待を裏切らない、実に興味深いリポートだった。
風船爆弾(暗号名は「ふ号」)はとっぴな思いつきではなく、そこに至るまで、十八世紀以来の偵察用気球の長い前史があったこと。日本にはアメリカよりも二十年も早く偏西風を発見した科学者がいたこと。当時の軍人と技師によって開発されたラジオゾンデ(高層気象観測用の電波発信器)は世界最先端のものだったこと----。まさに著者が言う通り、風船爆弾は「1944年当時の日本の国力の粋を集めた、巨大プロジェクトと言えるのである」。
結局、風船爆弾は計9.300発が飛ばされ、そのうちの約1.000個がアメリカ大陸に飛来。西海岸だけでなく深く内陸部(五大湖周辺)にまで到達していたという。
最後には重要な恐ろしい指摘も。当時の日本軍では、爆弾ではなく生物兵器を搭載さる作戦が少なくともも準備段階まで進められていたというのだ。入念な論証で、説得力があった。
-----------------------------------------------------------
人間魚雷

真珠湾攻撃に出撃した特殊潜航艇は、その後、いろいろと変遷を重ねながら、戦争激化とともに、最後は人間が乗ったまま敵艦に体当たりを敢行するという神風潜航艇までに発展?しました。それが「人間魚雷 回天」でした。
最初は魚雷に人間が乗れるようにしただけのもの、という物騒なシロモノ。然し、最後の頃はかなり高度な構造に作られていました。いずれにしても、人間が乗って体当たりをする基本構想は変わりませんでした。
飛行機を使った「神風航空機」にも共通しているのですが、基地を飛び立つまでは、周囲の激励の声に揉まれてその気になって飛び立つのはいいが、洋上で一人だけの空間に身を置いた時の特攻隊の兵士はどのような心境に陥るか、それが問題であったと聞いた事がありました。基地では、自らの死に疑念を覚え翻意して戻って来る兵士の処遇に頭を痛めたとか、そんなウワサがあった事も耳にしました。
そんなこともあって、人間魚雷の場合は、戻ってきてもムダなように、棺桶を封するがごとく、釘を使って蓋を打ちつけた、とか、又は溶接をして密封した、とか、常識では考えられない方法がとられたと言われていました。(真偽の程は分かりませんが)
集団のために自分の生命を捧げる風潮は「農耕民族(草食)」に多く「狩猟民族(肉食)」には少ない、こんな論調にも出会った覚えがあります。その論拠については残念ながら覚えていませんが。
|
|
真珠湾攻撃について |
||||||
|
||||||
|
||||||
|