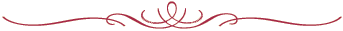
| 財政投融資問題 |
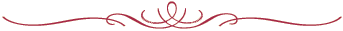
(最新見直し2009.2.9日)
| 「財政投融資」とは、日本では、「資金運用部資金、産業資金、産業特別会計、簡易生命保険、郵便年金積立金などを資金源として、国家によって為される投資及び融資のことを云い、政府事業の建設投資、各種金融公庫への出資、日本開発銀行等に対する融資を云う」。 |
| その財投の残高は、****年現在約三百五十兆円にのぼる。財務省は、年金、郵便貯金、簡易保険など国民から集めた資金を半ば強制的に借り上げ、特殊法人や自治体に貸し付けてきた。ところが、借り手の特殊法人では収支を無視した乱脈経営が常態化している。特殊法人がお金を返済できなければ、焦げ付いた分は税金で穴埋めしなければならない。財政破綻が加速し、国民が背負い込む損失がいまも拡大しているのに、財投の実態解明や借り手の責任追及には手をつけていない。改革の本質とはその病巣に大胆にメスを入れることだったのではないのか。 郵貯と簡保は、年金と並ぶ財投資金の大口貸し手だ。三年前の改革で、郵政の資金は原則自主運用に転換したが、現在も国債を購入するという形で巨額の財投資金を提供している。国債漬けの財政運営が温存させられているのだ。郵政民営化後の郵貯、簡保には貸し付けの拡大を認めることになっているが、資金運用の大半はやはり国債への投資になるだろう。郵政民営化された会社が資金集めに頑張れば頑張るほど、国債の安定消化が進むというのでは、何が財政改革かということになる。政府が打ち出した「郵政民営化の基本方針」は、極言すれば民営化ができれば大成功と言っているに過ぎない。なぜ郵政事業を改革するのかの原点から大きく外れてしまっている。 基本方針の閣議決定にいたる過程では、これまでの小泉手法が踏襲された。自民党内の抵抗勢力を挑発し、その摩擦熱を利用して国民の支持を得るというやり口だ。ところが、今回は首相の思惑通りに運ばなかった。 国民も自民党も「学習」したのかもしれない。「なぜ民営化なのか」の説明は一切なく、形だけを先行させる。スローガンが連呼されるばかりで、改革の良し悪しを評価する基準が必ずしも明確でない。内閣改造、党人事の駆け引き道具として郵政民営化問題を強引に取り込んだ印象がぬぐえないのだ。政局の主導権確保には多少とも利することにはなったが、国民的共感を喚起して抵抗勢力との対決を演出するという首相の狙いは不発に終わった。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)