岩井議員は、「中曽根内閣以降の財政再建」を評価せんとして次のように述べている。「赤字国債の発行は先ほどお述べになりましたように三木内閣のときに始まりました。そして、福田内閣、大平内閣、鈴木内閣と赤字国債の発行が続いたんですね。まあ、私に言わせればそれらの内閣の財政規律はむちゃくちゃとは言わないけれどもやっぱり乱れていたと言わざるを得ない、そう思います。中曽根内閣になってやっとこれではいかぬという反省が生じたのであります」。
そういう認識を披瀝した後で、「中曽根内閣以降、財政再建はどのように行われてきたのか御説明願いたいと思います。赤字国債の累積拡大というものを何とか食い止めようとしたのではございませんか」と質問している。国務大臣(塩川正十郎)は、次のように答弁している。「中曽根内閣になりましてから、一つは、一番大きい変化が起こってまいりましたのは、民間活力の活用ということ、これでございました。それと同時に、このときにいろんな面におきまして規制の緩和が行われまして、したがいまして、公共事業等によるところの言わば経済活性化への方向を民間活力に切り替えた、これが大きい財政上の一つの転換であったと、私はその当時を思い出しまして感じております」。この政府答弁に対して、岩井議員は次のように追従している。、「そうなんですね。民間活力というふうな新しい政策を打ち出しながら財政再建に努められたと。で、中曽根内閣のときになって初めて財政規律が回復する、こういうことだと思います」。 |
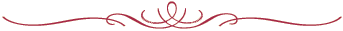
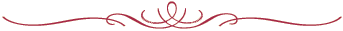
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)