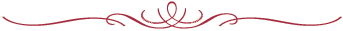
| 白拍子考 |
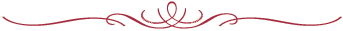
更新日/2021(平成31→5.1栄和改元/栄和3).7.3日
| (吉備太郎のショートメッセージ) |
| ここで、「白拍子考」をものしておく。「」、「」その他参照。 2016.2.22日 吉備太郎拝 |
![]()
| 【白拍子考】 |
| 「源義経との恋を引き裂かれた悲劇のヒロイン・静御前。その職業「白拍子」とは?」。 |
| しづやしづ しづの苧(を)だまき くり返し 昔を今に なすよしもがな |
| 【意訳】静、静と何度も私を呼んでくれた、彼と一緒のあの頃に戻れたなら……。 |
| ※しづ、は倭文(しづ。麻布)にかけ、苧だまきとは麻糸の玉。そこから糸を繰り出す様子に喩えています。 |
| 時は平安末期、謀叛人となってしまった恋人・源義経(みなもとの よしつね)を慕う歌を詠んで、源頼朝(よりとも)公の不興を買った静御前(しずかごぜん)のエピソードは、今も多くの人々に愛されています。 そんな静御前は、母の磯禅師(いそのぜんじ)ともども白拍子(しらびょうし)を生業としており、静御前によってその存在を知った方も多いと思いますが、白拍子とは一体どんな職業なのでしょうか。 今回はそれを調べたので、紹介したいと思います。 |
| 白拍子とは歌舞の1ジャンルで、素拍子とも書くように伴奏なしの即興で踊るスタイルを指しました。 その起源は平安時代中期の第74代・鳥羽天皇(在位:嘉承2・1107年~保安4・1123年)のころ、島の千歳(しまのせんざい)と和歌の前(わかのまえ)という遊女が舞ったことによるそうです。 彼女たちは水干(すいかん。男性装束)に立て烏帽子(えぼし)、白鞘巻の太刀を佩いた男装スタイルで注目を集めます。現代で言う宝塚歌劇団の走りみたいなものでしょうか。 やがて舞うのに邪魔な烏帽子と太刀を除いた水干のみで舞うようになり、それまで男女関係なく愛好されていた白拍子は、男装した女性が舞う「男舞(おとこまい)」となっていきました。 これは異性装によって舞手が「神がかった状態」を表現しており、座の昂揚感をより高めるためとも考えられます(もちろん男性の女装でもいいのですが、そういう舞は別にあります)。かくして白拍子が普及するにつれ、より歌舞の巧みな遊女の代名詞となり、時代が下ると猿楽(さるがく。後の能、狂言)、曲舞(くせまい。後の幸若舞)などに発展していったのでした。 |
| 吉野山 峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき |
| 【意訳】吉野山に積もる雪を踏み分けながら行ってしまった彼を追って行きたい……。 |
| さて、冒頭の静御前に話を戻すと、謀叛人を慕う唄で宴席は白けてしまい、頼朝公はカンカンです。 「おのれ、我が面と向かって謀叛人を慕うとは、その方も一味として処断してくれようぞ!」。 「元より覚悟……かくなる上は、先に九郎(義経)様をお待ちしとうございまする」 。「よぅ吐(ぬ)かした、覚悟せぃ!」 。さぁ叩っ斬られるぞ……誰もがそう思ったところへ、割って入ったのは頼朝公の正室・北条政子(ほうじょう まさこ)。 「お待ち下され……静どのの想いは貞女(貞節な女性)の鑑(かがみ)。もしも一時の咎を恐れて伴侶を見捨てるようなことがあれば、心ある女子(おなご)どもの笑い者となりましょう」 。「……むぅ」。「かく言うわたくしにしても、かつて一介の流罪人に過ぎなかったあなたの元へ、吹き荒れる雨風の中を駆けつけたのをお忘れでしょうか。それともあなたは、わたくしがあなたを見捨てるべきであったと仰せなのでしょうか?」。「むむむ……」。「何がむむむですか。我が意に染まぬ者が面白くない気持ちも解らなくはありませぬが、ここは私情をおいて静どのをご称讃あそばすべきです」。「……相分かった。追って褒美をとらせる故、下がれ!」。「ははぁ。しからばこれにて」。その後、静御前は歴史の表舞台から姿を消し(身ごもっていた義経の男児は殺され)、この世で義経と再会することはありませんでしたが、せめてあちらでは親子三人で幸せになって欲しいものです。 |
| ※参考文献: 永原慶二 監修『新版 全譯 吾妻鏡』新人物往来社、2011年11月 杉本圭三郎 訳『新版 平家物語 全訳注』講談社学術文庫、2017年4月 谷川健一『賤民の異神と芸能』河出書房新社、2009年6月 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)