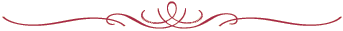
| 特権官僚の出現考 |
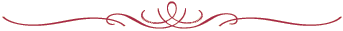
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
奪われた権力
ソ連における統治者と被統治者
エレーヌ・カレール=ダンコース
(著者)、エレーヌ・カレール=ダンコース ソルボンヌ大学教授とパリ政治学院のソ連研究課程主任を兼ねている。また、シカゴ大学のソ連民族間題研究グループにも属し、中央アジアを担当している。その研究分野は、ロシアおよびソ連史、中央アジア史、ソ連の外交政策ときわめて広範囲に及び、さらに、一般に現代世界における民族間題に特別な開心を寄せている。邦訳書に、『崩壊した帝国』(1981年)、『奪われた権力』(1982年)、『ソ連邦の歴史』(1985年)、『パックス・ソビエチカ』(1987年)(以上、新評論刊)がある。
「ロシアを治めるものは、誰に対しても責任を負う必要はない。彼らは思いのままに臣民の賞罰を行なうことができる」
ロシアでの権力に関するこの定義は、ピョートル大帝のものだが、奇妙に現代的な響きを持っている。わずか数語でそれは、ソビエト権力の性質と、その対社会関係のけわしい歴史を要約していないだろうか。
(第一章P.15〜20の冒頭部分略。P.21より)
ところで、職業的能力には金銭的な面で報いておきながら、一方ではこれまた増加してきている政治家、官僚群をこうした給与序列化から遠ざけておけるものだろうか。平等が経済的必要の前に犠牲にされた以上、政治関係者も同様の恩恵を手にするだろうことは明白であった。それに彼らもまた、体制にとっては絶対的必要物ではないか。
この点、レーニンはできる限り不平等への復帰を抑えようと努めた。一九二一年六月二十三日の政令は、政治的幹部の給与が、彼らの配属されている企業の平均賃金の一五〇%を越えてはならないと規定している。しかしこのような規定は、これら幹部らの活動量がふえ、手当が増大したこともあって引き起こされた予想以上に大きな幹部給与の伸びの前にたちまち空文になってしまう。一九二五年三月二十一日に出た新たな政令はこうした事態の教訓を汲み、政治活動に対する報酬の枠をひろげたが、すでに実際にはそれが平均的労働者賃金の三倍から四倍の間を動いていることはよく知られていた。ただしここでは肝腎の問題は給与ではない。
このようにソビエト政権が一方で平等主義、一方で経験主義的な問題の取り組み方のいずれをとるか迷っていたこのころからすでに、平等主義をうたいあげた声明や、政治的責任を持つ者に課された給与制限などは限られた意味しか持たなくなっていた。金銭とか俸給とかは、決して唯一の生活手段ではないからである。欠乏状況は、つねに独自の律法を生み出すものである。特別な流通回路が生まれ、人がモノを手に入れられるのは、使えるカネがあるからではなく、それを入手できる立場にあるからだ、という事態となる。革命直後のロシアで何よりも問題だったのは、食べることと住むことだった。一九一七年に採択され、その後補足された食料配給制度は、不足がちな物資を社会的な、また公益性の基準にしたがい配分する使命を帯びていた。労働者の国家では労働者が王さまであり、一番多い配給量を手にした。一方、旧体制の生き残りである雑多なカテゴリー、たとえば貴族、ブルジョア、聖職者、無職の連中などは、社会的階層の最下段に追いやられ、しばしば配給量決定に当たって考慮に入れられることさえなかった。ただ、公益性という基準はやがて事態をひどく複雑なものにしてしまう。
体制側は当初、国家の機能に欠くことのできない専門家に特典を与えることを決定した。一九一九年のロシアは流行病とたたかわねばならない状況にあったため、一九一九年四月十日の政令は医師、看護婦に対する食料の特配を決めた。一九二〇年四月三十日、こんどは経済的に特別な重要性をもつ企業の労働者・職員、危険な作業をしている労働者、並みはずれて高度の技能をもつ非肉体労働者らが同様の特典を手に入れた。同様にして、公的職務を行使するもの、権力中枢周辺で働くものにも特典を与えてよいのではないだろうか。
ただ政治的分野へのこうした特権拡大は、余りにも平等主義イデオロギーに抵触することが明らかなので、権力側は、すでに戦時共産主義期から公式の平等主義と内密の特典供与慣行を組み合わせる道を選んでおり、それは時とともに増幅されていった。政府メンバーとその家族、党メンバー、警察、軍隊、さまざまな官僚たちは、まさしく一つのウラ経済体系全体を作りあげることにより、彼らの物質的問題も解決したのである。それは彼らメンバーだけに対し、酒保、レストラン、部門別特定商店など、外部世界に対しては門戸を閉ざし、ほとんど知られてさえいない場所への出入を開放するもので、成文化してはいないものの、完璧に機能するルールにより社会を序列化するものであった。こうしてすでに一九一八年から軍隊の中で特別なパイヨーク(配給)が供与され、しかもその量が普通の基準に比べてひどく豊富なので、軍人でない連中まで数多く不正手段で軍籍に登録し、おこぼれにあずかろうとする光景が見られたのである。
欠乏状況のおかげで、建て前上の平等の陰に事実上の不平等がこうして発達していったが、この不平等を、受益者側集団の方はいずれも覆い隠すことに専念した。それがソ連国家は労働者国家であるという、あれだけ声高に、絶えず繰り返されてきた主張と完全に矛盾するものだったからである。専門家たちの享受する特典だけは大っぴらに扱われたが、それも平等主義のテーゼを根拠づけるのに役立つからであった。専門家たちは、全体的にみて旧特権階級の出身者が多く、当面必要とされる彼らへの特典も、消えゆく世界への最後の供物にすぎなかった。専門家たち自身も消え去る運命にあった。
公式の、あるいは覆い隠された経済的不平等に、政治的不平等も加わった。
すでに見たように、レーニンは一九一七年に抑圧機構を復活させていた。内戦や体制反対派との闘いの歳月は、警察を極度の権力をもつ機構に肥大させ、その権限(抑圧的、司法的)は全社会をカバーした。ただしこの権限にも、レーニンが最初から定めておいた限界があった。すなわち「党」はこうした警察のせんさくの眼を免かれることができたのである。党のまわりにこのような保護ネットを張りめぐらすことにより、レーニンは党に対し、一般社会ではとても考えられぬような安全性を付与した。それはまた免責性を与えることでもあり、おかげで党は、法律では必ずしも認められていないような物質的利得を重ねることができた。このように政治権力層を一般法や民衆共通の運命から引き離すことにより、レーニンは一般社会とこの生まれつつある政治的階級との間に溝を掘ることに貢献する。とりわけ彼は、同質的な社会集団――ソ連官僚機構を作りあげるのに貢献したのである。
不平等慣行が発達し、特権的集団が確立される一方で、イデオロギーは革命の熱望にかなった社会モデルを掲げ続けた。公式の演説が競って繰り返し、新聞が書きたて、小説家たちが描写するよう求められていたもの、それは貧しい人たちの叙事詩であり、同じ運命を分かち合う男たちの友愛の世界だった。言葉でも態度でも、ソ連権力はいま生まれつつある社会的現実を否定した。権力側は、ロシアの地で勝利を収めた労働者階級が、国際的な舞台での孤立の代価を払っているのだという、困難な時代の神話に依然すがりついていた。ただしすでに、ソ連で始まったこの新たな階層分化を今後合法化してゆくための説明の素描が、ここには浮かび出している。ただ一国で勝利してしまった革命は、この予見されなかった状況に対する適応の努力を払わねばならないのだ。
レーニンの個性に色どられたソビエト国家創建の時代は、結局のところ(それが望まれたものだったかどうかは別として)、ソ連体制を一つの明確な方向――本来のユートピア的構想や革命で描き出された目標とは無縁の方向へ導こうとするさまざまな選択によって特徴づけられている。権力(政治的、あるいは技術的な)は底辺から遠ざかった。それは専門家の仕事だった。レーニンは今世紀初め、『何をなすべきか』を書いて革命の手段を規定しょうとした際、革命がアマチュア主義や自然発生的イニシアチブなどに耐えられるものではなく、職業的専門家や厳密な組織化を必要とするものだ、とあっさり結論を下している。一九一七年に権力を握ったレーニンは、その権力の行使に当たって、彼が革命実行のために作りあげたルールを適用しようとするのだ。プロフェッショナル化と(革命的ユートピアとは無縁な)権力の厳密な組織化とは、レーニン主義思想の中の、いわば定数である。一九一七年から二三年にかけて、レーニンがソ連の政治舞台を支配する中で形成されていった権力は、たちまち官僚主義的、専制的、守旧的になってしまう。こうした展開は、そもそも誕生の時からこの権力が社会の管理外におかれていただけに、一層容易だった。一九一七年の帝国国家の廃墟の上に、ほとんど踵を接して出現した新しい国家は、革命家たちが非難してやまなかった諸国家と同様、みずからが独占管理権を握る抑圧横構の上に基盤をおいた国家だった。しかもこれら抑圧機構の勢力と管轄範囲は、その後も増大してやまなかったのである。
権力も、それを管理する手段も取りあげられてしまった社会は、またすでにこの当時から、指導党の外部での表現手段を持つこともできなかった。権力との間を分かつ溝を埋める唯一の可能性は、全面的に党と一体化し、自分がその申し子であると認めることだった。しかし、たとえ社会が権力と一体化したとしても、現実を覆い隠すことはできなかった。指導階層は、入手可能な物質的特典の保有を序列化し、さまざまな特権を組織することにより、短い年月の間に社会共同体を、特典への接近権(アクセス)によって分離されたさまざまなカテゴリーに分割してしまった。こうして彼らは、権力に物質的基盤を与えたのである。確かに諸特権は、それを入手することが可能なすべてのカテゴリーに平等に与えられたわけではなく、各カテゴリーの間で身分的な相違が現われた。こうしてわれわれは四つの身分タイブを識別することができる。それは少なくとも四つの、それぞれ固有の特典の周りに結集した社会集団を生むのだが、彼らはいずれもすでに二〇年代初頭から社会全体とは切り離された存在となっていった。まず専門家集団である。その社会的出身環境のため、公然と特典を与えても差し支えないもので、彼らは高い給与を手に入れた。つぎに(党、国家、警察の)政治責任者らで、その特典は公に認めるわけにいかないし、その給与は労働者賃金を基準に算定され、厳重に管理されている。ただし、給与面での制限は行政面での飛び切りの特典や珍重すべき特権(食品、住宅、交通)で埋め合わされた。軍隊は早くから物質的特典(特殊商店、酒保、住宅)に加え、平均水準より高い給与とおまけにそれをウラ活動による副収入で改善する権利、とりわけ有利な年金システム、軍人の子のための教育上の特典(優先的な高等教育機関入学と授業料免除)などをしっかり抱えこんだ。最後に創造的インテリゲンチヤ(アカデミー会員、作家、芸術家、弁護士、医師、科学研究者など)は、権力と協力することを受け入れているだけに、特別な配慮の対象となった。たとえば二〇年代初めに決まった食料特別配給、住宅面の特典(一九二二年一月十六日の法令は、研究者の仕事のためにそれぞれ一室を追加割当しており、この規定は一九二四年に、“適当な場所の供与を必要とするような”知的活動を行なうものすべてに拡大された)、流行、そしてとりわけ一九二五年以後になると、創造的活動に報いる賞の授与がある。こうした賞は相当な金額のほかに威信面、身分面でのさまざまな特典をもたらすものであった。
こうして短かい歳月のうちに、労働者の社会の外側に、特権者の社会が作りあげられた。それはある時は自己の特権を見せびらかし、またある時は(これは政治的責任をもつものの場合だが)給与のつつましさという虚構(フィクション)のかげにそれらを隠した。公表されたものであろうとなかろうと、こうした社会的分化は重い影響を及ぼすことになった。それが高等教育への接近の横会という面を通じて、差別の永続化の可能性に結びついていたからである。
以上(P.38まで)
以下、第二章から第八章で、スターリン体制からブレジネフ体制までの分析がされています。(注)は、ほとんどフランス語か英語の原典なので、省略しました。
(関連ファイル) 健一MENUに戻る
ロイ・メドヴェージェフ 『1917年のロシア革命』
梶川伸一 『飢餓の革命 ロシア十月革命と農民』
中野徹三 『社会主義像の転回』 制憲議会解散論理
ソルジェニーツィン『収容所群島』…第二章、わが下水道の歴史
大藪龍介『国家と民主主義』 個人独裁、党独裁の容認